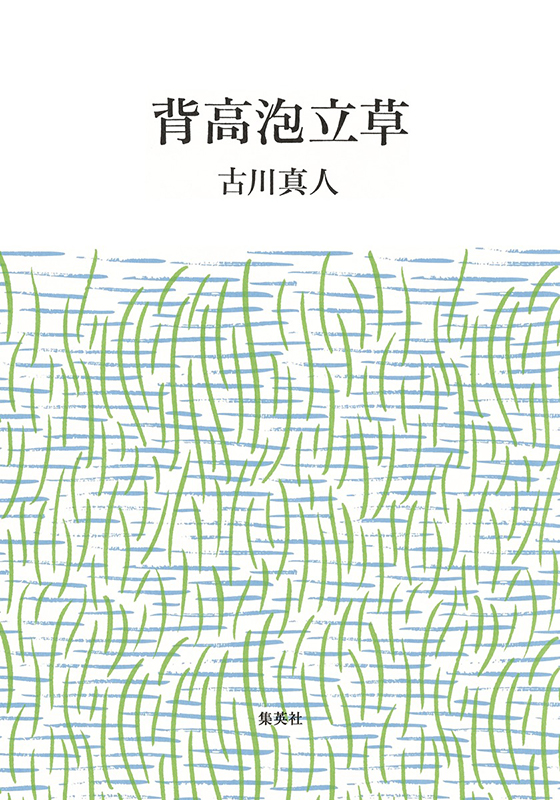プロフィール
-
古川 真人 (ふるかわ・まこと)
1988年福岡県福岡市生まれ。國學院大學文学部中退。2016年「縫わんばならん」で第48回新潮新人賞を受賞しデビュー。2020年「背高泡立草」で第162回芥川龍之介賞受賞。その他の著書に『四時過ぎの船』『ラッコの家』『ギフトライフ』がある。
第162回 芥川賞受賞インタビュー 古川 真人『背高泡立草』
◆島を書き続けて
──芥川賞を受賞されて一週間、受賞のご実感は湧いてこられましたか? 今のお気持ちをお聞かせください。
親戚や友人が、自分のために喜んでくれるのがとてもありがたいです。ただ、自分自身は、嬉しいとか、しみじみくるという感じはまだないですね。
──『背高泡立草』の舞台は長崎県の島です。古川さんは新潮新人賞を受賞されたデビュー作「縫わんばならん」から本作まで続けて四作、この島を舞台にした小説を書いてこられました。島は古川さんにとって、どのような場所ですか?
母方の親族が多く住んでいる島で、子供の頃から、盆と正月は島に行っていました。幼い頃ですが兄が入院している時、祖父母の家に預けられていて、島でできた友人もいます。こういう思い出深い場所、自分にとって近しい人たちの話や言葉なら書けるかもしれないと思ったのが、書き始めたきっかけです。島に行くと、僕自身は覚えていない僕の子供の頃の逸話を、婆さんたちが聞かせてくれて、それを小説的だなと思ったこともありました。
──本作がこれまでの作品と大きく異なるのは、古い納屋の草刈りをする現在の話と、島にまつわる時空を超えた物語が、交互に展開される点です。選考委員の島田雅彦さんは「土地に根付いている歴史の重層性を巧みにすくい上げている」と評価されました。この構成はどのように生まれたのでしょう。
今回は短編連作を書きたいと思ったんです。これまでと違う形式に着手してみたいという意識がありました。
──満州(現・中国東北部)に入植した家族の話や、カヌーで島に流れ着いた若者の話など、島の歴史的なエピソードはどのように考えられていきましたか?
何もかもが小説の通りではないのですが、島に鯨組があって択捉探検隊に選ばれた人がいたとか、朝鮮半島の人たちの船が難破したとき、土間で芋粥をたいたとか、そういう話を実際に島で聞いたんです。それらを元に膨らませていきました。
◆嘘っぽくない会話を
── 一方、現在では、一族が荒れ果てた古い納屋の草刈りに出かけます。古川さんも草刈りをされていたんですか?
親族はやっていたらしいですが、帰省する時期でもないので、僕は参加したことはないですね。前作の『ラッコの家』(文藝春秋)で、最後のほうにえんえんと海の中を書いたんです。海の獣がくねくねと海の中を泳ぎまわるようなテクストにしたかったから。それで、次は草だろうと、草刈りを書いた。安直な考えです(笑)。自分自身が草むらに入ってしまうような文章、うっそうとしてくるような文章を書きたいと思いました。
──美穂と奈美の親子はじめ、登場人物たちの方言での会話が魅力的です。
標準語圏でないところで育ったせいか、中高生の頃、テレビドラマや漫画の会話を嘘っぽいと感じていました。それもあって、こういう気分だったら、絶対にこういう会話になるだろうという会話を書こうと。そうすると、自然と方言になる。それ以外の口調だと、借りてきた言い回しになるんです。
ただ、会話の多くを方言が占める分、地の文はなるべくわかりやすい文章にしようと思いました。カギカッコ内は自分にとっていちばん気持ちのいいリズムで書くんですが、地の文はあまりトリッキーな書き方はしないようにと。そういう使い分けは意識しています。
──古川さんも方言を話されますか?
実家に帰ると、ちょっと方言が入りますね。僕は福岡育ちですが、僕の言葉はおそらく、近隣地域で生まれ育った同世代の男性と比べると、軟弱といわれるような言葉の選択があると思います。これは確実に、男がわりと早死にする家系だったので、お婆さんとか伯母さんに囲まれて育ってきた影響です。
◆芥川賞は「パスポート」
──本作を含め、特定の島と家族を書かれてきた古川さんの小説は、「サーガ」と称されます。「サーガ」を書こうという意識はおありだったのでしょうか?
二作目(『四時過ぎの船』)を書き終えたくらいのタイミングで、編集の方から、最近、サーガ形式の作家はめずらしいですよと言われて、あ、そうなの? と。びっくりしたのを覚えています。サーガを書こうとか、書きたいという自覚や意識はなかったですね。確かに登場人物は前作と同じですが、前の作品を読んだことがない人でも読めるものを書いていますし、自分にとって掘り下げたい、発展させたいテーマが、島や家族だったという感じです。
──「サーガ」を書いた作家といえば中上健次がいますが、特にお好きということは?
中上健次の小説には、ノックアウトされるような文章の圧力は感じますが、男くささがみちみちていますよね。本来、子は母親から生まれてきますが、中上健次の小説は、人間が男から生まれているような、男が出産しているような、そんな印象を受けます。それは、先ほど述べたような、どちらかというと女の親族に囲まれて育ってきた僕の家族の歴史とは何か違うなと。影響という意味では、津島佑子さんの小説の影響を受けています。
──デビュー後のインタビューではトルストイもお好きと仰っていました。
トルストイは大好きです。学生時代に惑溺した『戦争と平和』は、最初十代だったヒロインが、最終巻では子を持つ母親になっている。人間が歳をとるのは当たり前なのですが、小説は長い年月を書けることをトルストイから学びました。そしてトルストイが何よりすごいのは、それでもまだ書いてないことがあることをほのめかす書き方をしているところです。どれだけ枚数を費やしても、人間は書き切れるものでないことが伝わってきて、小説はここまで書けるのかと痺れました。
──芥川賞受賞は古川さんにとって大きな転機になりそうですか?
選考委員のお一人からは「パスポート」という言葉をいただきましたし、友人にはメールで「やっとスタート地点に立てたね」と言ってもらいました。そうした言葉などから、たとえ自分は変わりたくないと思っていても、変わってしまうものだと思っています。
──これからも島は書かれるのでしょうか? 今後の展望を教えてください。
いつかまた島を書くことはあるかもしれませんが、次は、違うものを書いてみたいですね。これまで島の永遠のような時間の中から生まれてくるものを書いてきましたが、それとは違う語り口やスピードを求めてくるようなもの、自分にとって未知なる他者が現れるようなものを書いてみたいです。それから、これまで書いてこなかった一人称の小説や、方言でない言葉にもチャレンジしていきたいです。
(聞き手・構成=砂田明子)
(「青春と読書」2020年3月号転載)
担当編集より
第162回芥川賞を受賞した古川真人さんの『背高泡立草』が1月24日に発売になりました。
主人公の大村奈美は、母の実家・吉川家の納屋の草刈りをするために、母、伯母、従姉妹とともに福岡から長崎の島に向かいます。
行きの車の中で、奈美が「別に良いやん、草が生えてたって。誰も使わんっちゃけん」とこぼしても、母は「良いやないね、兄ちゃんも手伝ってくれるって言いよるけん、すぐ終わるよ」と受け流すばかり。
吉川家には<古か家>と<新しい方の家>があるものの、祖母が亡くなり、いずれも今は空き家に。
奈美はふと気になって、島に着いてから、伯父や祖母の姉に、いつから吉川家は<古か家>に住んでいたのかを聞きます。
そして、吉川家は<新しい方の家>が建っている場所で戦前は酒屋をしていたこと、戦中に統制が厳しくなって廃業し、満州に行く同じ集落の者から家を買って移り住んだのが<古か家>だったことなどを知ります。
初めて聞く、一族のさまざまなエピソード。
実はそれらの出来事には、島から海の向こうに出ていった者や、海から島にやってきた者が関わっていたことが、読者に明かされます。
江戸時代、捕鯨の腕を買われて蝦夷に派遣された漁師。
戦後、故郷の朝鮮に帰ろうとして船が難破し島の漁師に救助された労働者たち。
時代が下って現代、カヌーに乗って現れた、鹿児島からやってきたという少年。
草刈りをする奈美の一日の物語に、これらの違う時代の人々の物語が交錯します。
その人々の人生を知る由もない奈美ですが、まるでその気配を感じ取ったかのように、草に埋もれた納屋を見ながら、吉川の者たちと二つの家に流れた時間、これから流れるだろう時間を思うのです。
「短編連作を書いてみたかった」という著者が挑んだ、記憶と歴史が結びついた新境地。
些末なことを言い合う家族の会話のその方言の響きと共に、ぜひお楽しみください。
(編集H)
新着コンテンツ
-
連載2025年07月15日
 連載2025年07月15日
連載2025年07月15日【ネガティブ読書案内】
第44回 ホリコシさん
「10分遅刻して卒論を出せなかった時」
-
インタビュー・対談2025年07月08日
 インタビュー・対談2025年07月08日
インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」
著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。
-
お知らせ2025年07月04日
 お知らせ2025年07月04日
お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!
演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。
-
インタビュー・対談2025年07月04日
 インタビュー・対談2025年07月04日
インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」
ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は
窪美澄
2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日青の純度
篠田節子
煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!