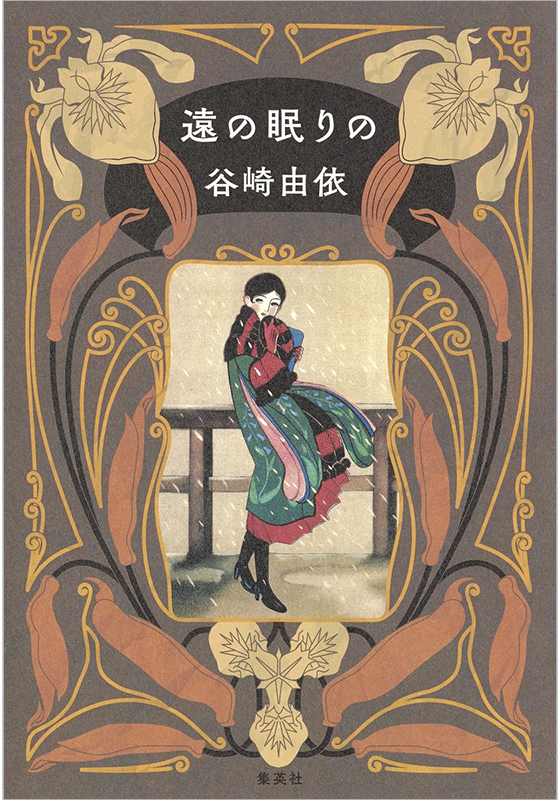内容紹介
“ここではないどこか”を求めつづけ、最後には日本で「移民作家・小泉八雲」となった男ラフカディオ・ハーン。
彼の人生に深く関わった3人の女性が、胸に秘めた長年の思いを語りだす。
生みの母ローザ・アントニア・カシマチは、1854年、アイリッシュ海を渡る船上で、手放した我が子パトリシオの未来を思いながら。
最初の妻で解放奴隷のアリシア・フォーリーは、夫パットとの別離を乗り越えたのち、1906年のシンシナティで、新聞記者の取材を受けながら。
2番目の妻で武士の娘小泉セツは、八雲との永遠の別れのあと、1909年の東京で、亡き夫に呼びかけながら。
あなたを語ることは、あなたを蘇らせること――
ジョン・ドス・パソス賞受賞の注目作家が、女性たちの「声」を繊細かつ鮮やかに描いた話題作
プロフィール
-

モニク・トゥルン (Monique Truong)
1968年南ベトナム・サイゴン(現ベトナム・ホーチミン市)生まれ。6歳のときに戦争難民としてアメリカに移住。イェール大学卒業(文学専攻)、コロンビア大学法学大学院修了(法学博士)。2003年刊行のデビュー作『ブック・オブ・ソルト』がニューヨーク公共図書館若獅子小説賞、PEN/ロバート・W・ビンガム賞などを受賞、14ヶ国で出版される。“Bitter in the Mouth”に続く第三長編となる本書は、ジョン・ガードナー小説賞を受賞、パブリッシャーズウィークリーの2019年ベストフィクションにも選ばれる。2021年ジョン・ドス・パソス賞受賞。現在ニューヨーク在住。
-
吉田 恭子 (よしだ・きょうこ)
1969年福岡県生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科修士課程修了。ウィスコンシン大学ミルウォーキー校英文科創作専攻博士課程修了。現在、立命館大学教授。著書に“Disorientalism”、共著書に『現代アメリカ文学ポップコーン大盛』、訳書にジェイムズ・M・ケイン『ミルドレッド・ピアース 未必の故意』、共訳書にレベッカ・L・ウォルコウィッツ『生まれつき翻訳 世界文学時代の現代小説』などがある。
インタビュー
推薦のことば
ディテールの中から豊かに湧き起こってくる女たちの生の香り、味、響き。
ラフカディオ∙ハーンは謎の真空地帯のように彼女らの心を惹きつけ続ける。
――多和田葉子氏(作家)
書評
女たちの言葉が浮かびあがらせるハーンの面影
西成彦
イオニア海に浮かぶレフカダ島(現在はギリシャ領)で一八五〇年に生まれたラフカディオ・ハーンが、いつしか西へ西へと海を渡り、四十歳直前に来日、一八九六年に英国籍を棄てて日本に帰化したことは、皆さんもご存じだろう。こうして彼は「小泉八雲」となった。
来日後のハーンに関しては、良人を亡くした妻のセツが遠戚にあたる三成重敬を聴き手として語った「回想」が何度か英訳されて出まわり、日本でも日本語版がハーンの教え子の田部隆次が書いた評伝『小泉八雲』に「思ひ出の記」の題で収録されて以来、広く愛され、読まれてきた。
この前史を踏まえつつ、ベトナム生まれの英語作家、モニク・トゥルンが、セツが八雲の面影に向かって語りかけるという装いで「再話」を試みた。それが本作である。
本人を前にしての語りだから、良人をめぐる証言というより、しんみりとした親密な語り口調になっている。生前のハーンはセツから「八雲」の名で呼ばれるのを嫌ったようだが、ここでのセツは「八雲よ」と声をかけ力強い。
そして、本作の何よりの面白さは、セツによる回想に先立って、ハーンの生母(ローザ・カシマチ)の息子への呼びかけ、そしてハーンが文章家としての修業を積んだオハイオ州シンシナティ時代に事実婚の関係を結んでいた下宿の料理番の女性(アリシア)が新聞記者に向かってした打ち明け話が、ひとつひとつ色合いを変えながら巧みに配置されていることにある。
たがいに面識のない三人の女(語る言語も異なる)に共通するのは、彼女らがそれぞれのやり方でハーンを愛し、その食欲だけでなく、おとぎ話をせがむ子供っぽさにも快く応じてやったという点だ。
ガートルード・スタインのパリでの生活を、その料理番を務めたベトナム人のコックの眼を通して描いた『ブック・オブ・ソルト』で彗星のように登場したモニクであればこそ、ハーンがどのような欲望の主であったかをさぐりあてる能力にもたけていた。
今まで知られなかったハーンが、女たちの語りを通して新しく生まれかわる。
にし・まさひこ●文学研究者
「青春と読書」2022年4月号転載
わたしだって語ることはできる
鈴木みのり
三つの場所、三つの時間においてそれぞれの人生を生きた三人の女性たちが、それぞれ出会ったある人物との関わりのなかから、語る。その人物を、母ローザ・アントニア・カシマチはパトリシオと呼び、さらに〈パトリックと呼ばないでください、後生ですから〉と述べる。出生時「パトリック・ラフカディオ・ハーン」と名づけられ、後に日本国籍を取得し、「小泉八雲」として知られる人物について、出生名の英語読みは父親の使う言葉で、〈わたしの言葉ではないの〉とローザは続ける。これは、言語と歴史の価値づけとの深い関わりを示唆している。
本作は、「歴史上」名の知れた人物と深い関わりを持ち影響を与えながらも、大文字の歴史からは注目されずにきた三人の女性の視点から、その「歴史」を読み直す試みでもある。しかしより重要なのは「わたしの言葉」による語りに耳を傾けるよう促す点だ。
当時英国支配下のイオニア諸島・サンタマウラ島で出産後、イギリス軍医の夫チャールズの故郷アイルランドに渡り、義叔母によって息子を取り上げられたローザ。奴隷の料理人として勤めるアメリカの下宿で、ジャーナリストとなるハーンと出会い、妻として支えたアリシア・フォーリー。そして、日本を探訪し執筆する、英語教師のハーンと伴に旅し、看取った小泉セツ。この三章が小説の大きな柱だ。そのあいだに、エリザベス・ビスランドによる評伝からの抜粋が挿入される。この構成は、語り、書き、批評し、読む主体が常に当たり前に、西欧(あるいは欧米)・白人・(非クィアな)男性を中心とする歴史、文学、ジャーナリズムの世界の「美」や「優劣」の価値基準を問い直す効果をもたらす。
三人がそれぞれ、「ラフカディオ・ハーン/小泉八雲」として知られる人物をパトリシオ、パット、八雲と違う名で呼びかけるように、小説はわかりやすく直線的ではない。記憶を辿って仔細に分け入るとき、別の時間や経験と接続しもするため、読んでいて統一感がないように感じられ、読み手にとってなじみのない時代や土地や風習に依拠する情報の空白が停滞するような感覚を生み、手間もかかるし混乱もするだろう。しかし、言いまちがいをくりかえすアリシアが〈わたしだって話を語ることはできる〉と言うように、力を奪われたマイノリティの経験を軽視し、価値がないかのように扱う言語表現の形式や評価基準に抵抗し、生き延びる力を与える物語がこの小説には息づいている。
アリシアが、〈自分にない技術について教えることはできないから〉パットの〈書きものについて〉アドバイスはしないとわきまえる一方で、パットは〈料理のことはあまり知らなかった〉のにアリシアの〈料理に意見をする〉と語る。この批評的な視点は、ラフカディオ・ハーンが料理本を出したと聞いたアリシアの〈あのひとが丸々本を一冊書けるぐらい台所のことを知っていると誰かが信用したことに面食らってます〉という言葉にも通じる。この箇所は、アリシアと別れた後に妻となったセツが、和食が合わない八雲にイギリス式の料理を用意したり、晩年過ごした大久保の家を準備したりと、まさに女性が家・生活をめぐる諸々をお膳立てしてあげた点とも共鳴する。稼得者が主に男性で、女性はその営みをバックアップする家事労働を無償で行う、という現代にも続く性別役割分業の形式だ。
アリシア〈から台所を取り上げたのです。もう何ヶ月も、あれやこれやの言葉で〉というパットのエピソードは、言葉という政治的な道具を通して他者を抑圧し、支配する構図の告発だ。そのハーン自身も、大叔母ブレナン夫人が厳格なカトリック教の規範に従わせるために送った、ダブリンの寄宿学校で〈自分の代わりに教師や生徒に暴力を振るわせた〉という経験をしており、皮肉だ。この系譜は、ローザがその父親から、〈男がいて、何が書かれていて、何をわきまえておくべきか告げてくれるから、文字はいらぬと〉読み書きの教育を受けられなかったことや、東方正教の規範によって異端視された経験から続くため、痛ましくもある。
モニク・トゥルンは六歳のとき、戦争難民としてアメリカに渡った。本書以外で日本語に翻訳された唯一のトゥルンの小説『ブック・オブ・ソルト』がそうであるように、自身の経験を創作と積極的に結びつけてこなかったといえる。しかし、生まれ故郷の(それ以前も歴史的に複数のヨーロッパ諸国の支配下に置かれてきた)サンタマウラ島がレフカダ島に名を変えたことにふれて、〈自分が生まれたときはイギリスの手にあったものが、今ではギリシャという国の手に移った〉というパットからアリシアへの語りは、被支配側が支配側によって振り回される不当な経験を敷衍させるかたちで、世界での覇権を握ろうとするアメリカの帝国主義によるベトナムへの侵略という面への批判的な意識を推測させる。アラブ系にもルーツを持つ肌の色をしたローザ、黒人としてアメリカの奴隷制のもとに置かれたアリシア、英語で読む欧米の一般読者を想定したとき地理・文化になじみのない層にとって決して「受け入れやすい物語」とは言えない日本のセツ。この三人を主な語り手に選んだトゥルンがきっと、植民地主義や人種主義の支配構造をも射程に入れていると考えるのは、妥当だろう。
トゥルンはローザ、アリシア、セツと、ハーンの史料にあたりながら、史実や自身が想像力でふくらませた箇所から、象徴的なエピソードを巧みにちりばめる(そのどれが史実で、どれがそうではないかがわたしには判別はつかないし、事実を知ることが一義的な目的ではないため検証はしていない)手腕には、舌を巻く。さらにその技巧は、作家自身の思想や経験を語るための目的という恣意的なかたちではない。歴史の整理された説明のなかに位置づけられなくても、確かに存在した誰か固有の、他の誰かに分かつことはできないはずの生きられた人生・生活に根ざした言葉・視点で綴られる。読み手ひとりひとりのなかに、かすかな気配ほどでも確かにある、普段はかたちにならない自分の言葉や物語に応答する声が、きっと見つかるはずだ。
「すばる」2022年7月号転載
新着コンテンツ
-
インタビュー・対談2025年07月08日
 インタビュー・対談2025年07月08日
インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」
著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。
-
お知らせ2025年07月04日
 お知らせ2025年07月04日
お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!
演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。
-
インタビュー・対談2025年07月04日
 インタビュー・対談2025年07月04日
インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」
ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は
窪美澄
2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日青の純度
篠田節子
煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日情熱
桜木柴乃
直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。