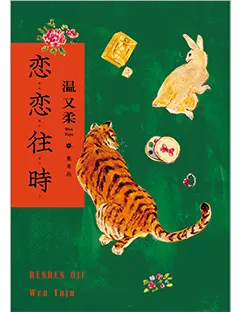内容紹介
大人気詩人・最果タヒが32人の〈キャラクター〉に贈る、最大熱量のラブレター!
コミックから宝塚、アニメ、ドラマに童話まで、
古今東西の〈キャラクター〉への「愛」を磨き上げた、
きらめく宝石箱のような最新エッセイです。
【目次】
誰より私が私を信じている――『ガラスの仮面』姫川亜弓
自分を好きな人に、優しくしたい――『らんま1/2』シャンプー
弱さを嫌悪してるのは誰――『呪術廻戦』禪院真希
心って詩のこと――『銀河鉄道の夜』ジョバンニ
あなただけがわからない――『エリザベート』ルキーニ
社会のための「心」を持たない――『チェンソーマン』デンジ
友達を「ばか」と思うことについて――『クマのプーさん』クリストファー・ロビンとプー
人が人と生きるのは不自然で、自然で。――『A子さんの恋人』A 子
己の価値を見つける――『HiGH&LOW』村山良樹
あなたは太宰治ではない――「桜桃」太宰治
いい人である前に――『ドラえもん』のび太
死に損ないの人の地獄――『ゴールデンカムイ』月島軍曹
天才もただの人――『のだめカンタービレ』千秋真一
愛こそギャグ――『ルナティック雑技団』天湖ゆり子
追悼・葛城ミサト――「エヴァンゲリオンシリーズ」葛城ミサト
きみがぼくに愛をくれたから――『ユニコ』ユニコ
器のない指導者――『NEVER SAY GOODBYE』アギラール
友情は愛じゃない――『天使なんかじゃない』麻宮裕子
血の匂いのするヒーロー――『鬼滅の刃』竈門炭治郎
傷ついた人生を抱きしめるには――「夢の音色」さくらももこ
神は人を愛せない。――『封神演義』太公望
正しさのために強くならなくてもいいよ――『クレヨンしんちゃん』風間トオル
頭脳はスペックではない――『DEATH NOTE』L
私があなたを救いたい――『宝石の国』ルチル
誰かの機嫌を誰も取らない――『動物のお医者さん』菱沼聖子
恋は一人の中で咲く――『人魚姫』人魚姫
大人がきみを生贄にする前に――『星の王子さま』星の王子さま
強い人ほど傷だらけになる――『大奥』和宮
愛情と侮り――『それでも町は廻っている』嵐山歩鳥
ぼくはぼくだという、当たり前のこと。――『トーマの心臓』エーリク
青春に切なくならないで。――『けいおん!』田井中律
ルーシーに優しくしたい。――『PEANUTS』ルーシー・ヴァンペルト
プロフィール
-
最果 タヒ (さいはて・たひ)
詩人。1986年生まれ。2006年に現代詩手帖賞、07年に『グッドモーニング』で第13回中原中也賞、15年に『死んでしまう系のぼくらに』で第33回現代詩花椿賞、24年に『恋と誤解された夕焼け』で第32回萩原朔太郎賞を受賞。最新刊に小説『恋の収穫期』、エッセイ『ファンになる。きみへの愛にリボンをつける。』等。
エッセイ
きみの信じている星が見える
最果タヒ
人が真剣に信じているものを、真剣に信じながら聞くことが人にはなかなかうまくできない。そこには愛が必要だったり友情が必要だったり崇拝が必要だったりする。人は信じていればそこにない星が見えたりもするが、それを同じように見るのはとても難しくて、でも、それは信じている本人からすれば真実なのだ。その人の人生はそこから始まったりする、するのに、たとえその人の隣にいても、その人と同じ強度でその人の見ているものを信じ抜くことはなかなかできない。
人間は噓をつくし、いまは本気でも未来はわからないから。その人の「信じる」に自分の心を懸けて、全てを注いで飛び込んでいくことがまず難しい。それは、愛していたって難しい。
けれどそういうところに、美しい意志は宿るのだ。自分が決めたことを貫くとき、自分が選んだ道を突き進むとき、人は自分だけに見える星を、いつまでも瞳の真ん中に映して、まっすぐに歩む。その星を信じぬいて、だからこそ、風が吹いても雨が降ってもそのまま突き進んでいける。それは第三者には訳のわからない熱量だろう。客観的に「こうであるべきなんです」と説明できるようなものではなく全てを自分が信じて、選んだものに向けて注ぐとき、人は彗星のように飛べるが、でもそれを、その途中で、第三者が理解し共感することって難しい。
その人が彗星になった後ならたくさんの人が理解できるだろうけど。その人の人生の結末が見えてきて、何を目指していたのかが、その人の熱量として伝わってくるから。けれどそうやって、結果が出せるくらいには貫けなかった人だって、星を見ていた。何かを信じていた。そのうち星を見失っても、目移りをしても、忘れてしまっても、その時にその人の心にあった確信は消えない。走り抜けた事実は消えない。生きることは正しい答えを選んでいくことではないから、自分にしかわからない「こうだ」という確信に頼って進むしかない瞬間はいくどもあって、その度に人は孤独になる。確信を積み重ねて、他の誰にもわからない道を歩む。他者には、簡単に共感できない存在になる。でもそうやって「私だけの私」が始まるとも言える。
そんな人を愛したいとき、理解なんてしなくていいと私は思う。共感とか理解とか、そういうものがコミュニケーションの重要なもののように語られがちだが、本当は、その人が見ている星について、「そこには何もないよ」なんて言わずに、その人が見ている方角を一緒に見上げて、その人の瞳の強さを感じて、あるような気がする、と心の中でそっと思うくらいでいいとも思う。私にも確信をしたことがあり、それは別のことだけど、でもだから、きみがきみ一人で見ているものを、見えなくても、信じてみようって思える。その瞳の強さだけは身に覚えがあるから。そしてそんなふうに「身に覚えがある」と思うために、私は今まで一人で何かを信じてきたようにも思う。きみが彗星になろうとする時、私も彗星になろうとしていた一瞬のことを思い出して、そして二人で遠くで彗星と彗星としてすれ違うのだ。そんなふうに、その人のそばにいることは、どんな理解より美しいと思う。
私は物語が好きで、そこにいるキャラクターが、何かを信じて突き進むのを追えることを愛している。彼らには私が見えないから、彼らのじっと信じているものを近すぎるくらい心で接近して、見ようとして見ようとして、そうやって私にも一瞬星が見えることがあるから。彼らは、生きている人よりずっと内面の思考を読み手に知らせてくれるから。その人の瞳にしか見えない星が、ずっとリアルに私にも見える。それが理屈としてはおかしな星でもいい、共感などできなくてもいい、物語は共感ではない方法で、人の心の熱量そのものにシンクロする形で、愛したり憎んだりするその感覚を思い出させる。悪役が好きです、人を殺した人物も好きです、美しい心の持ち主も好き、身勝手な人間も好き、一人の人間にしか見えないものを、追い続けて、ついに見えたと思った時の、他者がいるからこそついた火が私の心の中に燃え広がる瞬間がたまらない。人を愛することの喜びはここにもあると私は思う、キャラクターを通じて、私は人を愛そうと伸ばし続ける手に、花束をいくつもいくつも受け取ってきている。それは物語が終われば溶けて消えるものだけれど、でも私はその手を物語が終わってもずっと伸ばし続けていられる。無数の花束の香りに包まれながら、私は物語でもなんでもない、結末もない、こんなになんでも貫けるわけでもない人のところにいく。考えていることがモノローグで伝わるわけでもない、どこまでも「知らない人」でい続ける他者の前に行く。
私は、いつも誰かに出会う準備をして、誰かの中に生まれようとする彗星に対していつも誠実でいたくて、そんなにみんな、私に心を開いてくれるわけではないとわかっていても、それでもそうやって、エネルギーとエネルギーで交わる瞬間があると信じて生きている。そのことをずっと諦めずにいる。そうやって走り抜ける私の、軌道に残る光の尾のように、読んだ物語からついた火が、キャラクターから受け取った星のまたたきが、いくつも光って見えている。現実に誰かを愛し抜く代用のようにキャラクターを愛しているのではないよ。あの光の尾は、「私は誰かを愛したいよ」というそれだけの、それだけの彗星の跡なのだ。いつまでも人の心の高熱に接近するのを諦められず、自らも高熱であり続ける私の心の軌道として、キャラクターへの愛の痕跡はある。私は、こんなふうにまっすぐに熱を放ちながら、未来なんて何にもわからない中で、きみが見ているものが私にも一瞬見えたと、伝えたくなる人に出会いにいく。これからもきっと。物語でも現実でも。絶対に、そうなんだ。それもまた、一つの私の人生の確信なのだろう。私は誰かを愛したいし、そしてきっと、愛せる。という。
「すばる」2025年10月号転載
インタビュー
新着コンテンツ
-
インタビュー・対談2026年02月19日
 インタビュー・対談2026年02月19日
インタビュー・対談2026年02月19日奥泉光×更地郊「他人に合わせるなんてことはできない。自分が読んで面白いと思うものを書く」
選考会で評価が真っ二つに割れた、すばる文学賞受賞作の著者の更地郊さんと選考委員の奥泉光さん。新人と大先輩の初対談が実現した。
-
インタビュー・対談2026年02月17日
 インタビュー・対談2026年02月17日
インタビュー・対談2026年02月17日北方謙三×美村里江(俳優)「海が紡ぐ物語」
『チンギス紀』の文庫解説でも北方作品について熱く語ってくださった俳優・美村里江さんが読み解く『森羅記』の魅力とは――?
-
インタビュー・対談2026年02月17日
 インタビュー・対談2026年02月17日
インタビュー・対談2026年02月17日連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」 北方謙三×織田裕二(俳優)「小説と映像、唯一無二の表現」
待望のドラマ化を記念して、原作者・北方謙三さんと主演・織田裕二さんに小説と映像、表現者としての醍醐味を語り合っていただきました。
-
お知らせ2026年02月17日
 お知らせ2026年02月17日
お知らせ2026年02月17日小説すばる3月号、好評発売中です!
平石さなぎさんの読切や村山由佳さんの新連載など小すば新人賞出身作家の作品が目白押し。北方謙三さんと織田裕二さん、美村里江さんとの対談2本も。
-
連載2026年02月16日
 連載2026年02月16日
連載2026年02月16日【ネガティブ読書案内】
第51回 古賀及子さん
ふられた時
-
インタビュー・対談2026年02月06日
 インタビュー・対談2026年02月06日
インタビュー・対談2026年02月06日ピンク地底人3号×鳥山まこと「言葉と物語が立ち上がるまで」
選考委員も「好対照」と評した作品で第47回野間文芸新人賞を同時受賞したお二人。贈賞式から間もない高揚感のままに、語り合っていただきました。