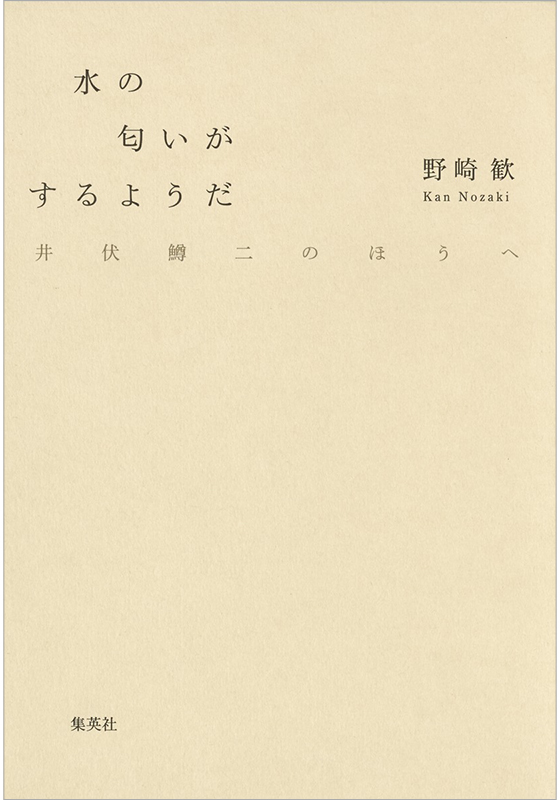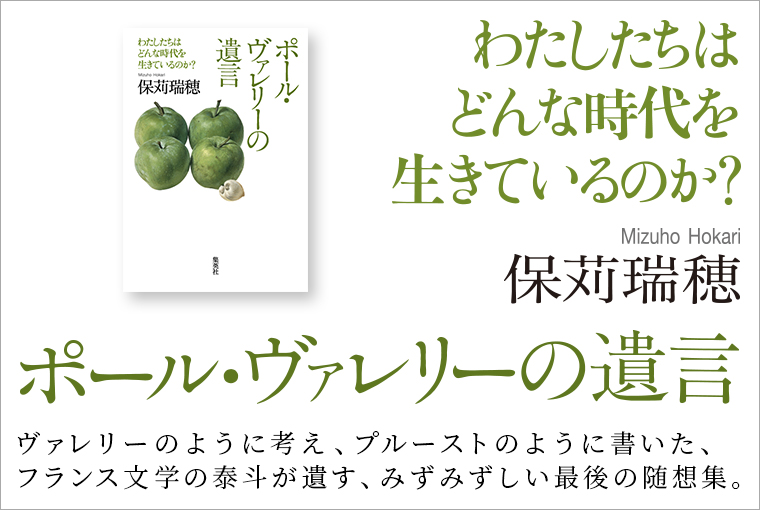
内容紹介
《二度の戦乱を生き、精神の危機を見すえていた詩人の声に耳を傾けながら、著者はそこに諦念ではなく希望を上塗りして、二十一世紀に生きる人間への信頼を言葉で回復しようとつとめた。稀有なユマニストの思索の跡がここにある。》──堀江敏幸氏(作家)
《筆致は隅々まで明澄で、弾むようにみずみずしい。プルースト的な心のふるえに満ちたこの至上の一冊をとおして、保苅さんの精神はわれわれ読者に優しく、そして熱く語りかけ続けることだろう。》──野崎歓氏(フランス文学)
「わたしはおよそ四十年ぶりにパリにもどって来た」。一生をパリに捧げた仏文学の泰斗が出会う、様々な時代の記憶の中の人々。激動の時代を生きたポール・ヴァレリーの思索を導きの糸に綴る、瑞々しい最後の随想集。
プロフィール
-
保苅 瑞穂 (ほかり・みずほ)
1937年12月23日、東京神田生まれ。1961年、東京大学文学部フランス文学科卒業。1968年、東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得満期退学(1964年〜67年にパリ留学、エコル・ノルマル・シュペリウールに在籍)。東京大学名誉教授、獨協大学名誉教授。専門はフランス文学。
主な著書に『プルースト・印象と隠喩』(筑摩書房、1982年)、『プルースト・夢の方法』(筑摩書房、1997年)、『モンテーニュ私記 よく生き、よく死ぬために』(筑摩書房、2003年)、『ヴォルテールの世紀 精神の自由への軌跡』(岩波書店、2009年)、『プルースト 読書の喜び 私の好きな名場面』(筑摩書房、2010年)、『恋文 パリの名花レスピナス嬢悲話』(筑摩書房、2014年)、『モンテーニュの書斎 『エセー』を読む』(講談社、2017年/第69回読売文学賞〔随筆・紀行賞〕)、主な訳編著に『プルースト全集』第12巻〜18巻(筑摩書房、1985年〜97年)、『プルースト評論選』全2冊(筑摩書房、2002年)、ロラン・バルト『批評と真実』(みすず書房、2006年)など。監修にフィリップ・ミシェル=チリエ『事典 プルースト博物館』(筑摩書房、2002年)。
2021年7月10日、パリにて逝去。
書評
パリへの想い、自由への情熱
野崎歓
保苅瑞穂さんは大学入学時、英文学を志していたという。情熱的な教授の授業に触れて「滾々(こんこん)とわきでる湧き水のような文学の汲み尽くせない清新な喜び」(第八章)を味わった。しかしその後、プルーストと出会い、専攻を仏文に決めたのだ。
文学の「汲み尽くせない清新な喜び」を教えてくれる外国文学者として、まっさきにぼくの頭に浮かぶのがほかならぬ保苅瑞穂さんなのである。プルーストを始めとして、モンテーニュ、さらにはヴォルテールと、フランス文学史上の巨人たちについて書かれたその著作の数々は、自分が❝フランス文学に興味をもつ日本語読者❞であることの幸福に浸らせてくれるものばかりだ。
本書で保苅さんは、二十世紀前半のフランスを代表する詩人・思想家ヴァレリーを取り上げ、反=戦争の人としての側面を描き出している。文明の危機に深く動揺しつつ、「どこまでも理性だけに従いましょう」と訴えたヴァレリーの「遺言」は今、まさにアクチュアルに響く。そのメッセージを鮮やかに聴き取り得たのは、保苅さんが現代世界に走る亀裂を鋭く察知していたからだ。「精神の自由に対する情熱」(ヴァレリー「ヴォルテール」)の尊さが、何とよく伝わってくることか。
本書刊行を待たずして、昨年、保苅さんは亡くなられた。だが遺作となったこの本でも、筆致は隅々まで明澄で、弾むようにみずみずしい。青春の一時期を過ごし、退職後ふたたび暮らす巡り合わせとなったパリの街と、そこに住む人たちに対する想いが全巻に脈打っている。とりわけ最終章に記された一老婦人との交流の回想には、フランス文化への限りない愛惜があふれ出すかのようで、繰り返し読んではそのたびごとに目頭が熱くなる。著者の白鳥の歌というほかはない。まさしくプルースト的な心のふるえに満ちたこの至上の一冊をとおして、保苅さんの精神はわれわれ読者に優しく、そして熱く語りかけ続けることだろう。
「青春と読書」2022年8月号転載
「存在の深みにある本質的な静かさ」を文章にする
宮下志朗
保苅さんは「駒場」という職場の同僚であったが、私が母校に戻ったのは遅く、いっしょの時期は長くはない。その頃、キャンパスは新たな脱皮の最中で、私も否応なしにその動きに巻き込まれていった。「フランス語教室」という名の大部屋の仲間たちは、大学院の専攻という個別の部屋に分かれていき、「フランス語教室」は連絡調整機関となった。それでも会議は続いた。穏やかな表情を崩すことなく、どこか遠くを見つめるような眼差しで、黙って坐っていた保苅さん。自分はまもなくキャンパスを去る身だから好きにどうぞ、ぼくも好きにします、といった風情だった。
定年で「駒場」を去った保苅さんから、やがて『モンテーニュ私記』という美しい思索の本が届いた。『エセー』を愛読していたので、驚きはなかった。驚きは、それ以後にやってきた。保苅さんがパリに行った、パリに住んでいるという。奥さまとの死別という悲しみの後、パリで新しい女性と出会って再婚、幸せに暮らしているとのこと。この間、雑誌の対談や会食で保苅さんと会ったりしたが、パリに骨を埋める話は出なかった(と思う)。昔から縁の深い一六区に住んだらしいが、いつからパリに移り住んだのか、正確なことは知らない。
「もし幸運にも、若者の頃、パリで暮らすことができたなら、その後の人生をどこですごそうとも、パリはついてくる」という、ヘミングウェイ『移動祝祭日』の名高いエピグラフが、本書でも引かれている。わたしの周辺にも、若き日のパリ経験が決定的で、常に「パリがついてくる」仲間は多い。定年退職して、係累も、引き止めるものもなくて、青春の地パリに戻る条件が揃っている人もかなりいる。でも、古希を目の前にして、本当に「パリの懐」に戻る人など稀だ。彼は本当に戻った――四十年の歳月を経て。それが驚きだった。
老いた身をパリの空気に浸すことで、「官能的な肉体の目覚め」を、気力の充実を感じて、プルースト論はいうに及ばず、一八世紀のサロンを主宰したレスピナス嬢が、社交界の寵児に宛てた熱烈な手紙を読み込み、心の奥底に分け入った傑作『恋文』、『モンテーニュの書斎』と題された『エセー』再読の名品(読売文学賞)等、美しい文章を次々と書いた。わたしは『エセー』の訳者だが、彼の読みのしなやかさに及ばないと感じることも多い。好きな作品をこよなく愛し、何度でも読む、深く読んで考えるのが彼の流儀。「ぼくは論文は書いたことないんだ」と明言していた。謙遜も混じりとはいえ、ほぼ当たっている。
パリの家の近くで偶然、その内側に「みなぎる力に耐えてひたすらひっそり咲いている」、満開間近の八重桜を発見した幸運を喜び、老齢をかえりみず異国の地に戻って、「静かな生活の単調なリズムの反復のなかで」、「八重の桜」の「内部の充実」さながらに、「精神の飛躍」がもたらされる時を待ち、「根気よく」暮らしているわが身に思いを馳せた。その「充実」はみごとはじけて、豊穣の晩年となった。ヴァレリーの言葉を借りるならば、彼は「存在の深みにある本質的な静かさ」(「知性の決算書」)の内に、パリでの日々の暮らしを通して、文学の営みを極めたのだ。
その詩人ヴァレリーは、きわめて鋭く、多大の予感にみちた文明批評で知られている。たとえば「精神の危機」は、第一次大戦後の廃墟の上に立って、「ヨーロッパ」近代の無秩序化と精神の危機とを、右の「本質的な静かさ」の喪失と重ね合わせた評論で、批評家ヴァレリーの誕生を告げるエッセイとなった。本書は、ヨーロッパの知性でもあったこの詩人の、ある種ペシミズムに満ちた文明批評を読むことをテーマとしている。そして、かつて同じく一六区に住んでいたという、この知性の人・精神の人の日々の思考を追いかけるところから始めて、その文明論に迫っていく。
そこには、「ヨーロッパ」という名の文明の崩壊や、「精神の自由」の危機を訴えるべく書かれた文章や講演は、今こそ読み直されるべきだとの直感が確実にある。たとえば、(フランスのような)混血による複合民族ではなく、単一民族を標榜する国家は「受け身の姿勢」に、「集団的な従属」に陥りやすいという指摘(「フランスの多様性」)。あるいは、「平和が約束事のシステム(中略)信用に基づく構築物(中略)金がすべてのものを代行する。(中略)最後に戦争がこうした貸借状況を決済し、(中略)観念には事実を(中略)ただの言葉には死を突きつける」(「東洋と西洋」)といった分析は、今こそアクチュアリテを発揮する。平和とはフィクション、二つの大戦を経験して、戦争という暴力を見せつけられたヴァレリーの絶望は深い。だから、高校生たちに向けた講演でも、歴史に学ぶという安易な姿勢への疑問を提示、われわれの世界は今や予測不能な局面に突入しているのに、「後ずさりしながら未来へ入ってゆく」のは、むしろ危険なことなのだと、警鐘を鳴らしてもいた。
ヴァレリーの用語にからませて、保苅さんの生き方を述べるならば、「終焉の始まり」という「甘美な時」の内に「生きる歓び」を見出している「ヨーロッパ」なるもの、これがまだ息づいている「パリ」に暮らして、思考するということだ。あくまでも、パリにいたからこそ書けた本、パリでの暮らしや経験とヴァレリーの文明評論との交錯を、現場で描いた本なのだ。
終章「ヨハン・シュトラウスが聞こえてくる部屋」は、人生の「珠玉」の時間を過ごしたアパルトマンの家主である貴婦人――二つの大戦という悲劇を経てきた老婦人――の追憶。「ヨーロッパ」の「終焉の始まり」が、老婦人の姿に重ね合わされていることは明らかだ。この章を書き終えた保苅さんは病を得て他界した。永遠の文学青年のくりくりした瞳の奥には、今の時代への深い悲しみが横たわっていたのか。その悲しみを秘めながら、「生きる歓び」を求めてパリに戻り、文事をなしとげた。「文人」保苅瑞穗の遺作である。
「すばる」2022年8月号転載
新着コンテンツ
-
新刊案内2024年07月26日
 新刊案内2024年07月26日
新刊案内2024年07月26日地面師たち ファイナル・ベッツ
新庄耕
不動産詐欺の組織犯罪の闇に迫る、新時代のクライムノベル『地面師たち』の待望の続編!!
-
インタビュー・対談2024年07月26日
 インタビュー・対談2024年07月26日
インタビュー・対談2024年07月26日新庄耕「釧路がシンガポールになる、というあり得なさで「いける!」と」
今夏Netflixでドラマシリーズ化された前作と、その待望の続編である本作への思いを著者に伺いました。
-
インタビュー・対談2024年07月19日
 インタビュー・対談2024年07月19日
インタビュー・対談2024年07月19日青波杏「「語れない」をテーマに描く、女性同士の繫がりと植民地の歴史」
現代の台湾に生きる女性二人が、古い日記に隠された真実を探る物語。謎と日常、過去の歴史と現在が交わる中で見えてくるものとは。
-
インタビュー・対談2024年07月19日
 インタビュー・対談2024年07月19日
インタビュー・対談2024年07月19日ファン・ボルム「休めない社会だからこそ、休む人たちの物語を描きたいと思った」
本屋大賞翻訳小説部門第1位に輝き、ロングセラーを続けている本作への思いを、著者のファン・ボルムさんに伺いました。
-
お知らせ2024年07月17日
 お知らせ2024年07月17日
お知らせ2024年07月17日小説すばる8月号、好評発売中です!
奥田英朗さん「家」シリーズの待望の新作読切を始めとした大特集のテーマは”家族”。新川帆立さん、遠田潤子さんの対談も必読です!
-
連載2024年07月12日
 連載2024年07月12日
連載2024年07月12日【ネガティブ読書案内】
第32回 浅倉秋成さん
「ポジティブ思考が羨ましくて仕方がない時」