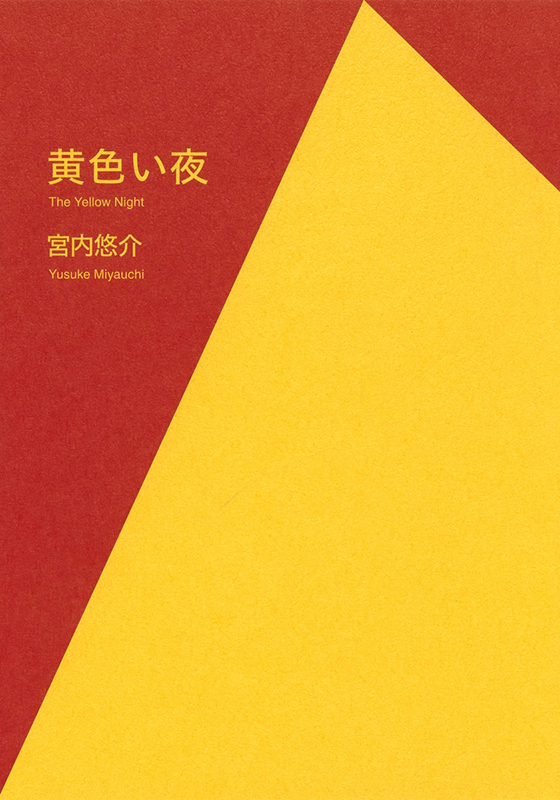内容紹介
酉島伝法『るん(笑)』には全3話収録です。
真弓さんを中心に、その夫、母、甥っ子が、各話のメインキャラクターになります。
それぞれ、だいたいこんな内容です。
第1話「三十八度通り」
結婚式場に勤める土屋は、38度の熱が続いていた。
解熱剤を飲もうとすると妻の真弓に「免疫力の気持ち、なぜ考えてあげない」と責められる。
第2話「千羽びらき」
真弓の母は、全身が末期の蟠【わだかま】りで病院のベッドに横になっていた。
すぐに退院させられ、今後はそれを「るん(笑)」と呼ぶ治療法を始めることになる。
第3話「猫の舌と宇宙耳」
真弓の甥の真【まこと】は、近くの山が昔の地図にはないと知り、登りはじめた。
山頂付近で、かわいい新生物を発見する。それは、いまは存在しないネコかもしれなかった。
プロフィール
-
酉島 伝法 (とりしま・でんぽう)
1970年、大阪府生まれ。作家、イラストレーター。
2011年、「皆勤の徒」で第2回創元SF短編賞を受賞し、
13年刊行の作品集『皆勤の徒』で第34回日本SF大賞を受賞。
19年刊行の第一長編『宿借りの星』で第40回日本SF大賞を受賞。
他の著書に『オクトローグ 酉島伝法作品集成』がある。
『るん(笑)』刊行記念エッセイ
「千の羽根をもつ生き物」
酉島伝法
これまで発表した小説は、遠未来や他の惑星を舞台にした、あまり人間の姿をしていない登場人物たちの物語が多い。でも作家になる前はSFらしい小説すら書いたことがなかった。デビュー短編となった「皆勤の徒」(2011年)では、大量の造語を使う凝縮文体を試みたが、あまりに時間がかかるため、もしこの作品で世に出たらその後はどうしたらいいのかと思っていたら受賞し、うろたえつつも同じ作風で書き続けることになった。2年がかりで単著が出た後で初めてSF以外の文芸誌から依頼をいただき、『るん(笑)』の最初の話となる「三十八度通り」に取り掛かると、今度は普通の人間の書き方がわからなくなっていて、二本足でどう歩くのかを確かめるようにして書いた。
SFでは殆ど隠れてしまうが、自分の体験に由来する足場を幾つも据えて書くことが多い。実話だから面白いとかリアルということではなく(そもそも物語と現実のリアリティにはずれがある)、わたしの場合、想像だけでは足元がぐらつきやすく、より遠くへ飛ぶには力を込めるための足場が必要であるらしい。『るん(笑)』の三つの収録作は、どれも舞台が現代の日本に近い分、土台となった足場が透けて見えやすい。
「三十八度通り」では子供の頃から現在に到るまで感じ続けてきた違和感が元になっている。親戚に買わされ家に積み重なっていく健康食品、血液型で二重人格だと決めつけられ続けたこと、周囲であたりまえに語られるスピリチュアルの数々 そういったものが主流になった世界を書いたことになっているが、実のところ、すこし角度を変えて見た現実社会そのもののつもりだった。
職場として出てくる結婚式場の場面は、学生時代のアルバイト経験が元になっている。初日に複雑な操作を30分ほどレクチャーされただけでいきなり披露宴の本番をさせられ、他人の人生にとってかけがえのない日を台無しにしてしまうのではないかという恐怖に膝が震えた。台無しにしかねない事態も度々起きた。作中に書いたように、本来新郎新婦の入場で回るはずのミラーボールが、招待客の入る段階から派手に回りだして止まらなくなったり、作中には書かなかったが新婦の叔父がカラオケで熱唱しはじめたらなぜか歌声がユニゾンで、歌入りのカセットテープだとわかって青くなったりした。なぜか客席に支配人が座っていて、緊張して仕事をしていたら、会場の外を支配人が歩いているのが見え混乱したこともあった。後で双子だと知った。
2作目の「千羽びらき」は、「三十八度通り」と対をなす作品として構想した。今回の語り手となるのは、1作目の語り手の妻の母親だ。大病を患うが、この世界では死が別の概念に言い換えられ、病院も病気を作る場所として危険視されており、代わりに主流となった擬似医療になすがままにされる。その一環として出てくるのが、タイトルにもなった〈るん(笑)〉という言葉だ。意味がわからず戸惑われた方もいるかもしれない。わたしも提案されたときには意表を突かれて戸惑った。考えさせて欲しいと言って、他にもっと良い案はないかと頭を巡らせたが、出てくるのは『次元上昇〔アセンション〕プリーズ』という駄洒落くらいだ。けれど、改めて『るん(笑)』を見直してみれば、祈願と詭弁の撞着するこの世界が象徴されており、これしかないと思うようになった。
この話を書き進めるうちに、エミリー・ディキンソンの言葉が自然と重なってきて、その名前を一度も出さずにこの詩人にまつわるあれこれを作中に鏤めた。ディキンソンは「「希望」は羽根をつけた生き物」という詩を書いているが、「千羽びらき」とは、作中で千羽鶴を使って行われる祈願のことだ。千羽鶴は、小学生の頃からずっとわたしの心の片隅に重くぶら下がり続けてきたものでもある。何にも邪魔されず本を読みたいがために、水銀体温計を擦って38度まで熱を上げ、学校を休んで没頭した。味をしめて同じことを繰り返し、とうとう警察病院に検査入院させられた。病院だけでも恐ろしいというのに警察。様々な検査にも恐怖を覚えたが、ある日、クラス全員で作ったという千羽鶴が送られてきて卒倒しそうになった。
3作目の「猫の舌と宇宙耳」は、「千羽びらき」の語り手の孫を中心とする、子供たちの物語だ。この世界では、猫が排除されており、子供たちはその姿を見たこともなければ、どのような漢字を書くのかも知らない。
数年前から川辺に坐って小説を書いているが、「猫の舌と宇宙耳」の執筆中になぜか猫が目の前を通るようになり、ときにはわたしの足元や背後に寝そべって心地よさげにくつろぐこともあった。まるで福音のようで忘れられない。
(初出「青春と読書」2020年12月号)
新着コンテンツ
-
インタビュー・対談2025年07月08日
 インタビュー・対談2025年07月08日
インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」
著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。
-
お知らせ2025年07月04日
 お知らせ2025年07月04日
お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!
演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。
-
インタビュー・対談2025年07月04日
 インタビュー・対談2025年07月04日
インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」
ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は
窪美澄
2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日青の純度
篠田節子
煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日情熱
桜木柴乃
直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。