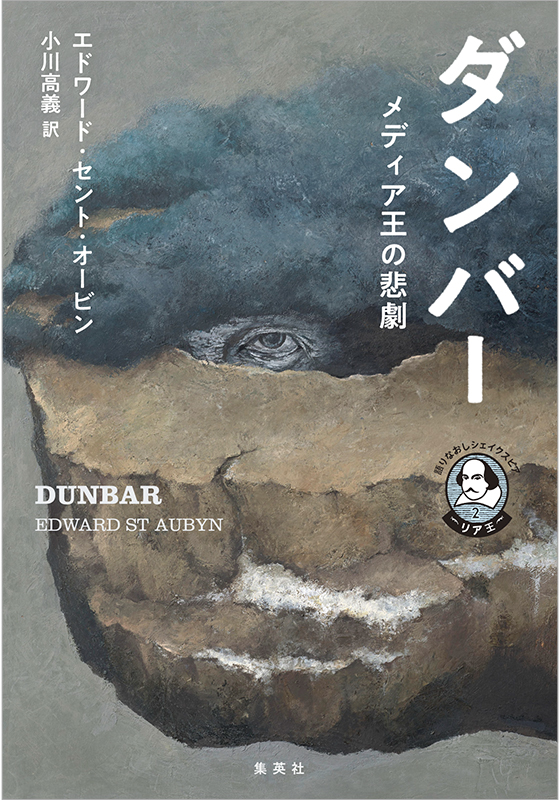内容紹介
ケイトは、率直な物言いが世間に受けない29歳。エキセントリックな科学者の父と、15歳の妹の三人暮らし。植物学者を目指していたこともあったが、今はプレスクール教員のアシスタントをしながら家事を切り盛りしている。ブロンド美人で夢見るような表情を浮かべている妹は男子にもてるが、ケイトにはいまだに恋人がいない。そんなある日、父が、外国人の優秀な研究助手ピョートルの永住権を獲得するために、とんでもない提案をもちかけてきた――。
プロフィール
-
アン・タイラー (Anne Tyler)
1941年米国ミネソタ州ミネアポリス生まれ。『ここがホームシック・レストラン』で1983年のピューリッツァー賞とPEN/フォークナー賞の最終候補に。『アクシデンタル・ツーリスト』は1985年全米批評家協会賞を受賞し、1986年ピューリッツァー賞最終候補作に(ローレンス・カスダン監督により映画化。邦題『偶然の旅行者』)。『ブリージング・レッスン』で1989年ピューリッツァー賞を受賞。2015年『A Spool of Blue Thread』でブッカー賞最終候補に。ボルティモア在住
-
鈴木 潤 (すずき・じゅん)
翻訳家。フリーランスで翻訳書の企画編集に携わる。訳書にショーン・ステュアート『モッキンバードの娘たち』(東京創元社)、シオドラ・ゴス『メアリ・ジキルとマッド・サイエンティストの娘たち』(共訳・早川書房)など。神戸市外国語大学英米学科卒。
【書評】不器用さを抱えた人びとの姿にとびきりの愛とユーモアを込めて
評者 倉本さおり
じゃじゃ馬。おてんば。はねっかえり。
子供の頃はそうした言葉が自分に対して使われると誇らしかった。だからシェイクスピアのその題目を知った際は当然のごとくイラっとし、なぜだかひどく塞ぎこんだ。
この本を読んだ今ならわかる。当時の私は「ならす」という言葉から垣間見えてしまった社会のありように傷ついていたのだ。
本作は、シェイクスピアの名作を当代のベストセラー作家たちが「語りなおす」シリーズの第三弾にあたる。下敷きにしているのは『じゃじゃ馬ならし』だ。気性が荒いせいで行き遅れ、父親の悩みの種だった娘が、資産目当てに近づいた求婚者の調教によって飼い慣らされ、従順な妻へと変貌する(!)――現代の常識では「性差別的」だと指摘される点も多いシェイクスピア作品の中でもきっての問題作といえるだろう。
一方、本作の「じゃじゃ馬」にあたる主人公・ケイトはというと――植物学者を志していたものの、率直すぎる性格が災いして大学を中退。二十九歳となった今は実家でくすぶっている。そんな彼女のもとに、科学者の父が縁談を持ち込んだことで物語が動き出す。海を越えてアメリカにやってきた優秀な研究助手・ピョートルに永住権を与えるため、自分の娘と結婚させてしまおうというわけだ。
ケイトは見かけこそ男性並みの高身長でデニムばかり穿いているものの、無自覚にへまをやらかしては落ち込んでいるし、伯母のシルマには常に頭が上がらない。なによりケイトは十四歳のときに母を喪って以来、研究以外はまるでダメな父親と、ひと回り以上歳の離れた妹のためにずっと家庭内でケア労働に従事してきた。一方、ピョートルも屈託がなさそうに見えるが、実際は自分の人生をコントロールすることに四苦八苦している。
作者のアン・タイラーは、誰かが誰かに「飼い慣らされる」過程を描くのではなく、むしろケイトやピョートルのような不器用さを抱えた人びとの姿にとびきりの愛とユーモアを込めて物語を立ち上げていく。翻って、それは人びとの生き方を都合よく「均そう」とする社会に対する痛快で真っ当な反駁なのだ。
くらもと・さおり●書評家
(『青春と読書』2021年10月号より)
新着コンテンツ
-
お知らせ2025年07月04日
 お知らせ2025年07月04日
お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!
演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。
-
インタビュー・対談2025年07月04日
 インタビュー・対談2025年07月04日
インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」
ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は
窪美澄
2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日青の純度
篠田節子
煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日情熱
桜木柴乃
直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。
-
インタビュー・対談2025年07月04日
 インタビュー・対談2025年07月04日
インタビュー・対談2025年07月04日篠田節子「創作する側の気持ちってどういうものなのか、突き詰めて書いてみたかった」
バブル期に一世を風靡するも「終わった」と言われ、近年になり復活した外国人画家の正体を追うミステリーの根底にあるテーマとは。