『リバー』刊行記念インタビュー 奥田英朗 「「テーマパーク」ではなく「自然の森」を書きたい」

未解決で終わった婦女暴行殺人事件から十年後、同じ手口で若い女性が殺された。果たして、同一犯か模倣犯か。冒頭から緊迫感あるシーンで始まる壮大な犯罪小説『リバー』。著者の奥田英朗氏に作品について聞いてみた。小説とは何か、目指すのはどこか……奥田流小説論にも迫る!
撮影/藤澤由加 聞き手・構成/タカザワケンジ
北関東で起きる連続殺人事件を追う
――『リバー』は北関東で起きた連続殺人事件の捜査に絡む刑事、被害者家族、新聞記者、そして容疑者たちにそれぞれフォーカスしたスケールの大きな群像劇になっています。どのようなところから構想されたのでしょうか。
奥田 僕は映画からヒントを得ることが多いのですが、今回はデヴィッド・フィンチャーの『ゾディアック』と、ポン・ジュノの『殺人の追憶』、この二作が頭の中にずっとあって、こういうテイストのものを書きたいなと。どちらも犯人捜しがメインじゃなくて、事件に絡んでくる人間模様がリアルで面白い。
――たしかにどちらの映画も連続殺人事件が描かれていて、『リバー』の冒頭も『殺人の追憶』と同様に死体が発見されるところから始まりますね。しかし『リバー』で死体が発見されたのは県境の渡良瀬川の両岸で、群馬側、栃木側という順で婦女暴行殺人事件が起きます。しかも十年前に連続殺人があったということで話がさらに複雑になっていきます。川を挟んで起きる連続殺人事件という展開は、どういうところから来たんでしょうか。
奥田 群馬、栃木にまたがる女児連続殺人事件がありましたよね。一九七〇年代初頭には群馬で起きた大久保清の連続婦女暴行殺人事件もあったから、そのイメージがあったのかもしれない。それに警視庁や大阪府警はいろんな作家が書いているから、都市部ではなく地方の警察を書いてみたかったということもありますね。群馬県警は以前、取材経験があったので、記者クラブがどこにあるとか、細々したことを知っていたので書きやすいということもありました。
――取材されたのは『沈黙の町で』のときですか。
奥田 そうそう。県警本部長室に呼ばれて、本部長とちょっと会談したりもしました。「警察官僚ってこういう人なのか」と思ったり。それで何となくなじみがあったんですね。
――『リバー』の連載前に舞台となった場所に足を運ばれたそうですね。
奥田 行きました。行って、そこの風にあたってくれば何となくわかるかなと。渡良瀬川の河川敷には野球部の子たちがいて挨拶してくれたり、小説に出てくる通りですよ。
――のんびりとした河川敷の風景が殺人事件で一変し、地域に緊張が走ります。連続殺人という大事件だけにたくさんの人物が登場しますが、奥田さんは群像劇の名手でもあり、今回も事件に関わる人たちの多視点で書いていますね。
奥田 多視点で重層的に描くことで物語の全体が見えるということもあるし、チャップリンの「人生は近くで見ると悲劇だが、遠くから見ると喜劇だ」という言葉が好きなんです。近くで見ると当事者は泣いているけれど、遠くから客観的に見るとその出来事は喜劇に思える。小説はその中間にいるべきなんじゃないかっていう気持ちがずっとあって。とくに今回は主人公を一人に絞らずに、誰にも肩入れしないようにしたかった。全員と同距離を保つ。被害者とも、容疑者とも。
登場人物を善悪で裁くようなことは僕にはできないし、する気もない。そういう考え方で書くなら群像劇が都合がいいわけです。

新旧世代の刑事と三人の容疑者
――事件を追う警察の関係者だけでも、群馬、栃木の両県警から参加する刑事たちがいて、現場の若手からベテランと幅広い。さらには十年前の事件を捜査したOB、元栃木県警の滝本誠司の執念が印象に残ります。
奥田 昔の刑事って暴走しやすかったと思いますね。今のようにガバナンスとかコンプライアンスとかうるさくなかったから。警察OBの話を聞いても、かつては暴力団と付き合ったり、容疑者を殴ったりすることが平気であったそうだし、社会の目もそんなに厳しくなかった。逆に人情刑事みたいな人もいたそうだし。今はもう失点が怖いから、はみ出すようなことはやらないだろうけど。
――新旧の刑事気質の描写も印象的でした。二十代~三十代の刑事たちは仕事にまじめに取り組みながら、家族とも良好な関係を築こうと腐心している。一方で、旧世代の滝本は妻からなかば見捨てられているという自覚がある。また、容疑者気質も描き分けられていて、滝本が十年前から追い続けている池田などは、警察を挑発し続ける人物です。
奥田 昔から日本中どこにでもああいう人物はいるんですよ。これも警察OBに聞いたことですが、東京でオリンピックの開会式のような大きなイベントがあると、地方の警察は一カ月くらい前から警備のために特定の人物をマークするわけです。ずっと行確(行動確認)するわけですよ。その時期に東京に行って事件を起こさないように。
――池田のほかに二人、つまり容疑者が三人浮上します。四十代の池田と、三十代前半の平塚健太郎と刈谷文彦というそれぞれ個性的な男が出てきます。
奥田 容疑者が三人というのは、書き手としては犯人をわからなくする、捜査を混乱させる目的ですよね。読者にも混乱してほしい。でも設計図を引いてこういうキャラクターを三人出そうと決めたわけではなくて偶然です。捜査線上に当然何人か容疑者が浮かぶだろうなと思いながら書いて、書いているうちに出てきたっていう感じですね。
――奥田さんは細かくプロットを立てるわけではないとうかがっています。
奥田 立てられないですね。容疑者三人に関しても、書いているうちにだんだん自由になっていって、これだけ書いたんだからもっと事件に絡ませようって考えていったという感じですね。
――読者も刑事たちと一緒に捜査の進展に一喜一憂するわけですが、三人それぞれに怪しいところがあり、犯人像とズレるところもある。とくに平塚健太郎は解離性人格障害(多重人格)かもしれないという仰天の展開があるわけですが。
奥田 混乱させるだけさせて、最後にどう落とし前をつけるかということを自分に課すわけですよ。どんどん混乱させて、どうすりゃいいのか自分も刑事と一緒に考えるわけです。
書いていて、都合のいいほうと悪いほうがあったら、悪いほうを選ぶわけ。そうすると作家も否応なく考えるから。言ってみれば自分で考えてもいなかったことをどんどん書いているんですよ。そうやって読者の興味をつないでいくっていうやり方ですね。



「ブルース・スプリングスティーンやチャック・ベリーなど、自分の好きなレコードジャケットのイメージだったり、スティーブ・マックイーンなどの映画スターの姿を模写して楽しんでいます」(奥田)
視点人物は下の名前で書く
――平塚健太郎絡みで、篠田という犯罪心理学者が登場します。風変わりな人物で面白かったのですが、彼は下の名前が出てきませんよね。姓で書かれる人物と下の名前で書かれる人物とがいるのは。
奥田 下の名前で書いているのは、その人物の視点で書いているときですね。群馬県警の若手刑事で斎藤一馬という人物が出てくるけど、「斎藤一馬」と登場時に書いて、斎藤一馬の視点で書くときは、「一馬は」と書く。ほかの人の視点で書くときに出てきたら「斎藤は」にする。原則としてはそうですね。例外もあるけど。
『リバー』には主な視点人物が六人出てきます。斎藤一馬と栃木県警の野島昌弘、元栃木県警の滝本誠司、中央新聞の千野今日子、十年前の事件の被害者遺族の松岡芳邦、スナック「リオ」の吉田明菜。六人くらい出すと、読者が追い切れなくなって、もっとたくさん視点人物がいるように見えてくる。篠田の視点では書いていないから下の名前もとくに書かなかったというわけです。
――たしかに下の名前で書かれると登場人物との距離がぐっと縮まって、事件に向けるまなざしも変化しますね。視点人物の中では松岡芳邦も強烈な印象を残します。十年前の事件で娘を亡くしていて、遺体発見現場の不審人物を見張り続けています。十年ぶりに起きた事件にも自ら関わっていって並外れた情熱を注ぎ込みます。
奥田 かなり前ですが、池袋駅で立教大生が殺された痛ましい事件がありましたよね。駅のホームで殴られて亡くなってしまって、犯人が逃亡したまま捕まっていない。被害者のお父さんがそのあとも犯人を捜し続けているというルポルタージュ番組をテレビで見て、ずっと頭に残っていたんです。
――松岡の場合は目の病気があって、視力を失う恐怖とも戦いながら犯人を追う。その切実さに胸を打たれました。書いているうちに、もともとイメージしていた登場人物みたいなものが違う顔を見せていくこともあるんですか。
奥田 ありますね。書いているうちにだんだんそれぞれのキャラクターがひとり立ちしていくというかね。自分の都合のいいようには動かさないから。「この人、この次何やるんだろう」と思いながら書いていますよ。
――今回、意外な動きをした登場人物はいますか。
奥田 滝本をあんなふうに書くつもりはなかったですね。頑固おやじみたいな昔気質の元刑事のつもりで考えていたんだけど、どんどん自分で動いていって。まあでもやっちゃうだろうなっていう予感はあったかな。
――すごい展開でしたね。池田みたいな狂気に対しては、追う側も狂気にならないと対抗できないんだと感じるくらい。警察は権力ですから暴走されては困りますが、捜査している刑事の実感としては、「あいつを野放しにしておけない」という思いもあるんだろうなと。池田以外にも有力な容疑者が浮上しますが、本当に彼が犯人なのか。刑事も読者も最後まで翻弄されますよね。何より動機が見えてこない。
奥田 よく「犯行の動機解明にあたる」って言うけど、そんなのわかるわけがないっていう思いが僕の中にあるんですよ。思い描いた人生を送れなかった人間が世の中に対して何かやってしまうっていうのは世間にたくさんありますよね。アメリカの銃乱射事件もそうでしょう。そういった犯罪に対して動機自体の解明って意味がないと思う。できるのは、誰も孤独にさせてはならない、社会の援助をどうするかというのが重要なんじゃないかというくらいで。だから今回も犯人の内面に関してはほとんど描写していません。犯罪に関してわかったようなこと書くのが嫌だったからあえて書かなかったんです。
――作中でも書かれていますね。「マスコミはいつも、動機の解明が待たれますという常套句で犯人像を探ろうとするが、理屈で説明できる人間なら人など殺さないのである」。なるほどと思いました。でも、納得できないと不安だからマスコミに動機を決めてもらって物語に落とし込んで安心したい。事実を報道するはずのマスコミが物語化を志向して、小説家の奥田さんがそれを否定するんだなと思うと、面白く感じます。


「何を書くかわからない」は既得権
――群像劇ということで、脇の登場人物の印象が濃いのも奥田さんの作品の魅力です。今回、個人的に長野の八木というラーメン屋店主が好きでした。元ヤンキーで地元でやたらと顔が広い。警察の捜査にも積極的に協力します。
奥田 僕は岐阜出身なんだけど、故郷に帰ると昔ヤンチャしてたのが顔になっていたりするんですよ。顔になってるっていうのは別に悪いことをしているわけじゃなくて、地元で会社を経営してて羽振りがいい。「何でもやってやるぞ」みたいな景気のいいことを言ったりね(笑)。
――人物像に心あたりがあるんですね。では、一方、池田みたいな犯罪者気質の人間はどうですか。
奥田 いない、いない。映画からヒントを得ていますよね。犯罪者が出てくるような映画、リアルな人間を描いた人間ドラマが好きだから。テレビドラマでいうと、僕はずっと山田太一さんが好きなんだけど、ああいう市井の人を一人の人間として描いたものが好きなんです。自分でもそういうものを書きたい。市井の人の中には池田みたいにはみ出してしまう人も当然いるわけです。
でも今、そういうリアルな人間を描くって少数派でしょう。日本人の七割がアニメとアイドルとゲームで育ってるというのが僕の実感で、そうするともうリアリズムって用がない。舞台設定とプロットとキャラが大事。それはつまり、テーマパークのアトラクションですよね。僕はそういうものにまったく関心がない。自然なものをやりたいんですね。
つまり、「テーマパーク」に対して「自然の森」を僕は書きたいと思っているんです。自然の森に読者を案内している。だからそこに人工的なアトラクションはないわけですよ。風とか小鳥のさえずりとかをただ楽しんでいただければと思うんだけど。
僕も完全なオールドスクールで分が悪いなとは思いますけど、少数派には少数派の矜持があるしね。
――奥田さんの場合は、『リバー』のように犯罪を扱ったものもあれば、日常寄りのユーモラスなものやちょっとファンタジックなものもある。その幅広さも興味深いところです。
奥田 同じようなものを書かないのはルーティーンが苦手だっていうのと、あと、読者の期待に応えたくないっていうのがあるかな。
ヒット作って、作家にとって諸刃の剣なんです。それと似たものを読者も編集者も求めてくるから、応えていたら疲弊するし自己模倣が始まる。そうなる前に別のことをやるわけです。だからデビューしてすぐの段階でいろんなことやっちゃったほうがいいんですよね。そうすれば既得権になるわけです。「奥田は何書くかわからない作家だ」っていう。そうなれば楽ですよ。若い作家の人にぜひ言いたい。「読者と編集者の要望に応えてはならない」って(笑)。
――私は最初に『最悪』を読んですごいと思って、次にさかのぼってデビュー作の『ウランバーナの森』を読んだんですが、『最悪』とはまるで違う作品なので驚きました。しかも『最悪』『邪魔』の次が『イン・ザ・プール』。たしかに次に何が来るかわからないですね。
奥田 自分の中のルールみたいなのがあって、それに従ってやっていれば、読者はついてきてくれるんじゃないかって思っていますね。


開いた見開きだけで世界がわかる小説を
――『リバー』のような犯罪を扱った作品はミステリとして読む読者もいると思うんですが、個人的にはあまりミステリだと思えなくて。ご自身としてはどうですか。
奥田 ミステリじゃないですね。これまでの僕の作品に関しても、ミステリのランキングにたまに上がると場違い感があります。
――あくまで犯罪にまつわる人間ドラマ、ということですね。では犯罪を書くことについてはどうですか。
奥田 犯罪って人間の一番弱い部分が出ちゃうものだと思うんです。誰だって平和で満たされていれば何もやらないと思うんだけど、追い詰められてやってしまうわけですよね。それまでの人生で満たされないものがあったり、苦しめられてどうしようもなかったりして。ほとんどの人間は犯罪なんかしないじゃないですか。僕のまわりにも犯罪者は一人もいないし、ほとんどの人はそうですよね。ただ社会には確実にいるわけですよ。
――たしかに今回の容疑者は三人とも育ってきた環境や生育歴に追い詰められている部分がありますね。奥田さんが『罪の轍』でお書きになった犯罪者とも共通するところがあると思いました。『罪の轍』は一九六〇年代初頭が舞台ですが、奥田さんはほかにも昭和の犯罪小説を書かれています。現代とどちらが書きやすいというのはあるんですか。
奥田 現代のほうが嫌ですよ。ネットの犯罪がどうのこうのって言われてもわからないし、どこで何をやっても監視カメラで追跡されちゃうしね。昭和のほうが楽ですよ。携帯電話もないしインターネットもないから刑事は歩くしかない。
――それでも今回、現代を舞台にお書きになったのはなぜでしょう。
奥田 なぜということもないけど、これで最後かもしれないですね。あまりにもヘビーだから。書くとなると大体三年がかりの長編になっちゃうんですよ。『リバー』も取材に行ったのが二〇一九年だもの。
――とはいえ、時代に関係なく、奥田さんの場合、犯罪が絡んだ作品は全部大長編ですよね。『罪の轍』も『オリンピックの身代金』も。
奥田 そうですね。五百枚ぐらいでさっと書こうと思うんだけど、千枚いっちゃうんだよね。
単純な勧善懲悪物にしたくないのと、事件の背景を描きたいのと、謎解きとかトリックに関心がないから必然的に犯人が捕まるまでか、事件が起きるまでの物語になるから、どうしても長くなっちゃうんですよ。
――先ほどのミステリではないという話とも通じますが、奥田さんの作品はどんでん返しとか読んでスッキリするオチとは違う方向で書かれていますよね。
奥田 自然の森は別に何のオチもないし、そもそも入口も出口もないわけだからそうなりますよね。髙村薫さんが、本をパッと適当にめくって、そのページを読んだだけで世界がわかるっていうのが文学だ、ということをおっしゃっていて。自分もそれを目指しているところはあります。どこを切り取ってもちゃんと、そこを読んだだけでも読ませる小説。前後は関係なく。そういう小説を書きたいですね。
特別企画 奥田英朗セレクト
『リバー』 Original Soundtrack プレイリスト
1 Shhh/Peaceful ・・・・・・・・・・マイルス・デイヴィス
2 Nobody’s Fault but Mine ・・・・・・・・・・ニーナ・シモン
3 Brazil ・・・・・・・・・・アントニオ・カルロス・ジョビン
4 If I Had A Boat ・・・・・・・・・・Lyle Lovett
5 Oscar Said ・・・・・・・・・・Till Brönner, David Friedman
6 Stop This Train ・・・・・・・・・・ジョン・メイヤー
7 コーヴァリス ・・・・・・・・・・増尾 好秋
8 Quizas, Quizas, Quizas ・・・・・・・・・・Laura Fygi
9 Bamboo ・・・・・・・・・・Mike Mainieri
10 Thorn of a White Rose ・・・・・・・・・・Elvin Jones
11 I Want You ・・・・・・・・・・Gary Burton and Friends Near, Friends Far
12 Compare to What-Live at Montreux Jazz Festival ・・・・・・・・・・Les McCann, Eddie Harris
13 Medley: In the Garden/You Send Me/Real Real Gone/Allegheny-Live ・・・・・・・・・・ヴァン・モリソン
14 Looking Up ・・・・・・・・・・Michel Petrucciani
わたしはリスナー歴50年の音楽ファンである。デスメタルとアニソン以外なら何でも聴く。美空ひばりからスティーヴ・ライヒまで。ニーノ・ロータからモグワイまで。しかも深掘りをする。某ホテルのラウンジに流れるアンビエントな環境音楽があまりに素晴らしいので、「これは誰の作曲ですか」と支配人をつかまえて詰問し、本社に問い合わせもらってその作曲家の名前を聞き出し、作品を片っ端から聴き漁ったという前科もある。これ誰の曲? と気になると夜も眠れない。典型的な“No Life. No Music”の人間と思っていただいていい。
そんなわたしの嗜好を日頃から観察する編集者から、「新刊『リバー』のサウンドトラックを作りませんか?」との提案があった。もちろん、わたしが「やる、やる」と犬が餌をねだるがごとく即答したことは言うまでもない。こういう仕事ならいくらでも引き受ける。他人の小説のサントラだって選曲してやってもよいが、まあ来ないか。

マイルス・デイヴィス
のっけから長尺曲(18分超)で申し訳ない。①はエレクトリック・マイルスの代表作『In A Silent Way』のA面丸々。いろいろ考えたが、オープニングを飾る曲はこれしかないのと、小説全体の通奏低音ともいえるサウンドだと思ったので選んだ。早くもエゴ全開ですな。通して聴いて欲しいが、気が短い人は五分でスキップしてもいいよ。許す。

ニーナ・シモン
②はブルース・ナンバーの古典。いろいろカヴァーはあるが、ここでは黒人シンガーで公民権運動家でもあったニーナ・シモンに歌ってもらおう。「全部わたしのせいよ」と、聴く方がたじろぐ迫力の懺悔をしている。

アントニオ・カルロス・ジョビン
③は一転してブライトなボサノバの名曲。アリ・バホーゾが作ったこの曲もカヴァーは目白押しだが、ボサノバの本家のジョビン師匠にお任せしたい。ここで奏でられるフェンダー・ローズは、エレピ史上最高の気持ちよさ。何時間でも聴いていられる。
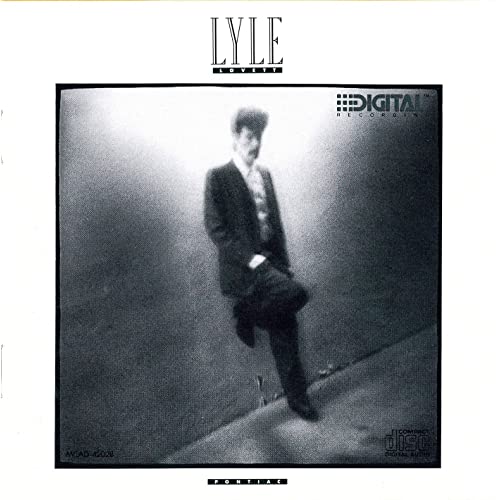
Lyle Lovett
④は俳優としても知られるアメリカのシンガー・ソング・ライター、ライル・ラヴェット(ジュリア・ロバーツの元旦那と言った方がわかりやすいか)の隠れた名曲。「もしもボートを持っていたら……」。あなたなら何をしますか?

Till Brönner, David Friedman
⑤はドイツのジャズ・トランペット奏者、ティル・ブレナーのミッドナイトな一曲。いわゆるクラブ・ジャズだがダンスには向いていない。ウイスキーのお伴に。

ジョン・メイヤー
⑥はジョン・メイヤーの切ない一曲。「列車を止めて。降りて家に帰りたい」と繰り返し歌う。そんなときが、わたくし同様、みなさまの人生にも何度かあったであろうと推察いたします。

増尾 好秋
⑦は日本のジャズ・ギターの第一人者、増尾好秋の軽快なインストゥルメンタル・ナンバー。晴れた日のドライブに最適の伴奏曲だと、ずっと思っていた。印象的なフルートは渡辺貞夫。それとユニゾンでメロディ・ラインを弾くベースは❝チンさん❞こと鈴木良雄。70年代のいわゆる「和ジャズ」には名曲・名演がいっぱいある。

Laura Fygi
⑧はキューバの古い歌謡曲。スペイン語の「Quizas」は英語だと「Perhaps」の意味。恋人に何を聞いても「たぶん、たぶん、たぶん」としか答えが返ってこない、という歌詞です。歌手のローラ・フィジィはよく知らない人だが、カヴァーを聞き比べたら、この人が一番よかった。
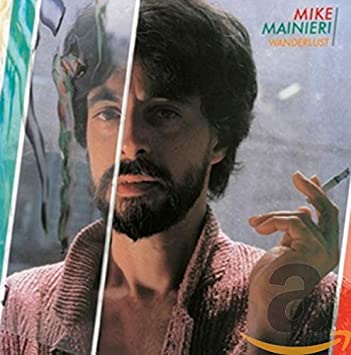
Mike Mainieri
⑨はジャズ・ヴィブラフォン奏者、マイク・マイニエリが80年代初めに発表したフージョン期の一曲。ブリヂストン・タイヤのテレビCFに使われたので、憶えている人もいるだろう。歳がばれるが。

Elvin Jones
⑩はジャズ・ドラマー、エルヴィン・ジョーンズ名義だが、実質はキーボードを担当したヤン・ハマーのリーダー作と言って差し支えないと思う。’75年の作品『On the Mountain』の1曲目で、ジェフ・ベックはこれを聴いて衝撃を受け、’76年の『Wired』のセッションにハマーを招いたにちがいないと、当時リアルタイムで聴いたわたし(高校生でしたよ)は確信している。

Gary Burton and Friends Near, Friends Far
⑪はボブ・ディランの曲をジャズのゲイリー・バートンがカヴァーしたもの。ディランのカヴァーは数あれど、わたしはこれが一番好き。ホーン・アレンジも楽しく、おじさんでもスキップしたくなる。

Les McCann, Eddie Harris
⑫はレス・マッキャンが弾いて歌って説教するゴスペル・ソウル・ジャズの大名曲。「お前さんはいったい何と比較して、それをリアルにしようと企んでいるんだ?」とみんなが叱られる。マーティン・スコセッシ監督の『カジノ』でもこのナンバーが挿入曲として使われていて、映画館でしびれた記憶がありますな。
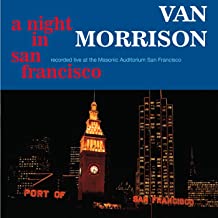
ヴァン・モリソン
⑬はヴァン・モリソンの素晴らし過ぎるライヴ盤『A Night In San Francisco』から、ハイライトのメドレー・ナンバーを。「no guru, no method, no teacher」とモリソン御大が吠えまくる。わたしも基本的には、グルも、メソッドも、先生も必要としない人間なんだと思う。我流が性にあっている。

Michel Petrucciani
⑭はペトルチアーニの代表曲。この美しいピアノの調べを聴きながら、映画のエンドロールのように本を閉じていただければ幸いかと存じます。
以上、約90分。昔のLPレコードならぎりぎり二枚組。最初にリストアップしたときは軽く2時間を超え、これでは読者に相手にしてもらえないと思い、絞りに絞った結果である。とくに作品内でのシーンは説明しないが、もし『リバー』を読んでいただけたのなら、このサウンドトラックを聴いて、「あの場面の曲かな」と想像していただけるとうれしい。お付き合いいただき、ただ感謝。
「小説すばる」2022年10月号転載
※「Spotify」プレイリスト配信サービスの利用はSpotify社の利用基準に準じ、小社が動作等を保証するものではありません。Spotify社の事由による配信終了で、予告なく楽曲が聴取できなくなる場合があります。
※オリジナルサウンドトラック3曲目の「Brazil」はSpotify配信サービスの対象外(2022年9月22日現在)のため、上記プレイリストには未収録です。
プロフィール
-
奥田 英朗 (おくだ・ひでお)
1959年岐阜県生まれ。雑誌編集者、プランナー、コピーライターを経て、
1997年『ウランバーナの森』で作家デビュー。
2002年『邪魔』で大藪春彦賞、2004年『空中ブランコ』で直木賞、
2007年『家日和』で柴田錬三郎賞、
2009年『オリンピックの身代金』で吉川英治文学賞を受賞。
『ナオミとカナコ』『向田理髪店』『ヴァラエティ』『罪の轍』『コロナと潜水服』など著書多数。
新着コンテンツ
-
インタビュー・対談2025年07月18日
 インタビュー・対談2025年07月18日
インタビュー・対談2025年07月18日窪 美澄×藤野千夜「団地を書くふたり」
団地を書き続けてきたおふたりに、団地に対する思いや互いの作品の印象、執筆の背景などを語っていただきました。
-
お知らせ2025年07月17日
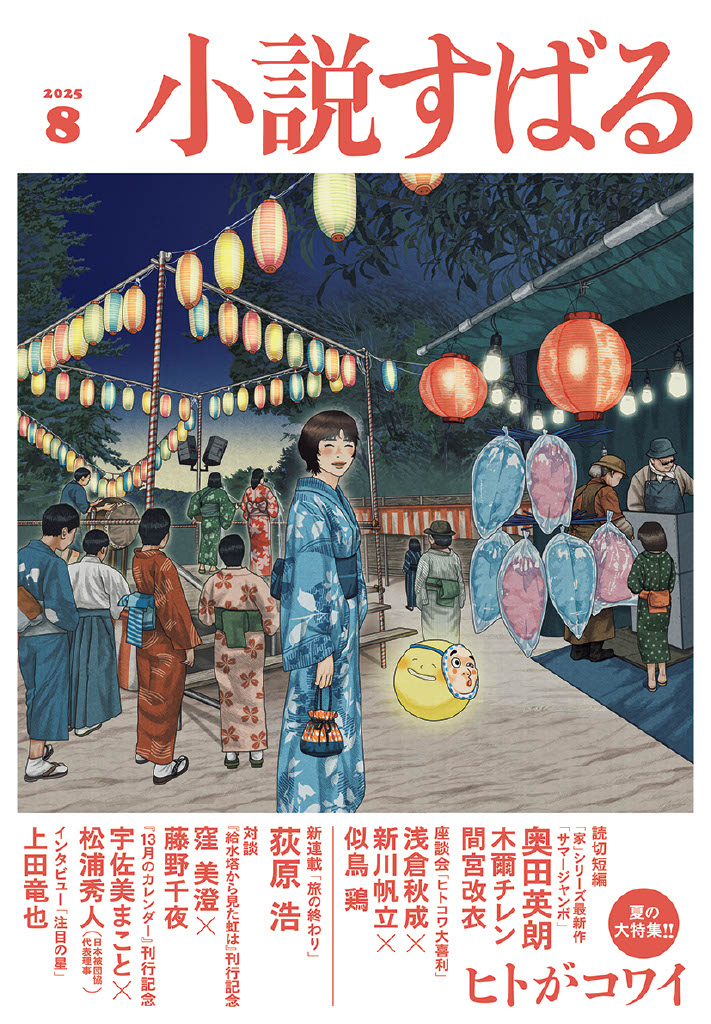 お知らせ2025年07月17日
お知らせ2025年07月17日小説すばる8月号、好評発売中です!
巻頭は荻原浩さんの新連載。特集〈ヒトがコワい〉では奥田英朗さん「家」シリーズ最新作の読切短編も!
-
連載2025年07月15日
 連載2025年07月15日
連載2025年07月15日【ネガティブ読書案内】
第44回 ホリコシさん
「10分遅刻して卒論を出せなかった時」
-
インタビュー・対談2025年07月08日
 インタビュー・対談2025年07月08日
インタビュー・対談2025年07月08日桜木紫乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」
著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。
-
お知らせ2025年07月04日
 お知らせ2025年07月04日
お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!
演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。
-
インタビュー・対談2025年07月04日
 インタビュー・対談2025年07月04日
インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」
ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。





