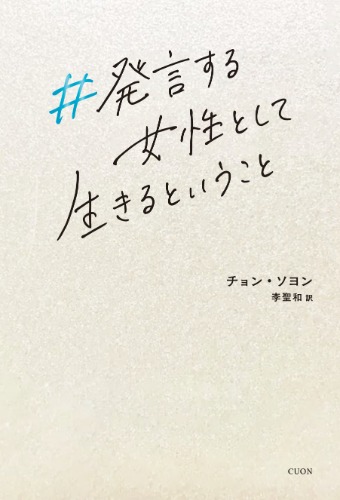今いちばん会いたい人に、作家が直撃インタビュー! 職人、役者、ミュージシャン、アスリート……さまざまな分野の方々に、作家の洞察力が切り込みます。ひと味違ったインタビューをお楽しみください。
第8回 松田青子さん(作家)が、チョン・ソヨンさん(SF作家)に会いに行く【前編】
2023年05月30日
韓国SF作家、チョン・ソヨンさんが来日しました。チョンさんに会いに行くのは、女性の多様な生き様を模索しつづけてきた作家・翻訳家の松田青子さん。三年前、二人が対談する予定だった短編集『となりのヨンヒさん』の刊行記念イベントは、猛威を振るった新型コロナウイルス感染症によって無期延期となりました。
その間にも、松田さんの『持続可能な魂の利用』が韓国で翻訳され、チョン・ソヨンさんのエッセイ集『#発言する女性として生きるということ』が日本で翻訳されるなど、作品での交流は活発に行われています。
三年を待ってついに叶った対談。生きること、書くことへの新しい可能性を探っていきます。
撮影/神ノ川智早 構成/すんみ 通訳/李希京 (2023年4月15日 神保町にて収録)

終わりの先に続く人生の気配を残す
松田 三年前にSF短編集『となりのヨンヒさん』刊行記念の書店イベントにゲストとして呼んでいただきましたが、ちょうどコロナ禍が始まり、お会いすることが叶わなくなってしまいました。当時お聞きしたいことがたくさんあったので、こうして改めてお会いすることができてうれしいです。
チョン ようやくお会いできましたね。
松田 『となりのヨンヒさん』を三年ぶりに読み直しながら思ったのですが、この本ではシステムというものに対して無力な人間が、システムの犠牲になってしまったり、犠牲にならないために抗ったりする姿がいろいろな形で描かれています。
特に象徴的だったのは、「再会」のスミです。この女性は宇宙飛行士になれるかどうかが決まる卒業試験で、遭難した飛行船に遭遇します。マニュアル通りならそのまま素通りすべきですが、彼女は優先して遭難船を助けたことによって試験に落ちてしまい、それによって夢見ていた未来は閉ざされます。このときに、「評価項目に含まれていない動作です」というアラームが何回も鳴り響きます。彼女はそれを無視してでも遭難した人たちを助ける。この場面がとても印象的だったのですが、というのは、〈これは評価項目に含まれていない動作です〉という警告を、我々は常に社会に問われ続けながら生きていると思うんです。
その警告に従わないと、今の社会の‟普通”から逸脱してしまったり、キャリアを築いたりすることができなくなるけれど、それでもやるんですか、と。そのような問いの前で、果たして人間はどう行動するのか。とても普遍的で現代的なテーマでもありますし、痛みをともないながらも、それでもやる姿に胸が熱くなりました。また、スミが夢を閉ざされる一方、宇宙飛行士になる夢を叶えた側もまともな生活を送れなくなるわけで、人生というものの多義性も感じさせます。
チョン そう読んでいただき、ありがとうございます。
松田 「再会」などが入っている第二部の「カドゥケウスの物語」は、カドゥケウスという大きな企業によって支配されている世界を描いています。チョンさんは今も「カドゥケウスの物語」を書き続けられていると聞きました。その理由をお聞かせ願えますか。
チョン そもそもの始まりは、これまでの作品よりもう少し大きな世界を感じさせる物語を書きたいと思ったことです。SFは、世界がいかに動いているかということを示すためのジャンルです。もし自分が世界を創ろうとしたらどんなものが出来上がるだろうか。そんなことを考えながらSFを書いているのですが、それを形にしたのがカドゥケウスの連作です。
私が見ている世界は、個人がシステムを変えることも、システムに抵抗することもできない場所です。しかしそれでも人間は、それぞれの立場で自分にできることをやり続けなければなりません。「再会」はまさにそういった観点から話を紡いでいこうと思いました。私たちは小さい頃に、例えば童話なんかを読んでいいことをすればそれなりの報いがあるということを学びます。ですが、実際はいいことをしたからといって、必ずしも何かが返ってくるわけではありませんし、いくらいいことをしても、結果が伴わないこともあるわけです。しかしそれとは関係なく、私たちはやるべきことをやり続けなければなりません。
私は、人間は正しい選択をする存在で、人のためになることをする存在だと信じています。しかし、こうした選択には喪失や失敗が伴うこともあるし、その結果が必ずしもいいわけではありません。ですが、結末がきれいでなくても、その人の人生は続きます。カドゥケウスの連作では、そのような話を書いていきたいと思っています。
松田 SFやファンタジー、ホラーといったジャンルは、自分たちの現実とは遠い世界のことが書かれているようで、実は時代時代の社会そのものを照射する存在だと私は思っているのですが、チョンさんの作品もまさに、我々が恒常的に感じている、この社会の中で生きている上での理不尽さや喪失というものが描かれていて、だから日本の読者の心を打っていると思います。
結末といえば、チョンさんの短編は、話の終わり方がすごく納得できるんです。私もここで終わらせるだろうな、と思える。例えば「宇宙流」だと、主人公が実際に宇宙に行った後の物語を書こうとする人もいると思います。ですが、チョンさんはその手前で終わらせていますよね。そのような肌感覚が、自分はすごくすんなり腑に落ちたのですが、チョンさんは作品を書く際に終わりのタイミングをどのように決めていますか。
チョン ほとんどの場合は、どこでどんなふうに終わらせるかを最初から決めて書きはじめます。先ほどお話ししたように、人生はずっと続いていくわけです。一方で、物語はどこかで終わらなければならない。「宇宙流」の場合は、宇宙に行く前に幕を閉じますよね。それから「引っ越し」の場合も、引っ越しをする前に話が終わります。
松田 そうですね。
チョン でも、登場人物の人生はそこで完結するわけではありません。私は、その先に続く人生の気配を残しておきたいんです。向上していく感覚、と言えばいいでしょうか。
松田 向上していく感覚?
チョン 物語に決着をつけて「落とす」のではなくて、その先の人生を想像させることで、次のステップをイメージしてもらいたいんです。
松田 なるほど。チョンさんの小説を読んでいると、自分も小説を書きたくなるし、アイデアが次々と浮かぶような不思議な感覚があるんです。何でなんだろうと思っていたのですが、チョンさんが描かれているのが、誰かの可能性の物語だから、その物語を読んだ人の可能性の扉も開く効果があるのかもしれません。チョンさんの作品を知ることができて本当にうれしく思っています。

未来をつくる社会活動、人を癒す小説
松田 『となりのヨンヒさん』には、よりよい未来を信じて社会をよくするための戦いを、自分の個人的な営みとしてやり続ける人々の姿が描かれていますが、新刊のエッセイ集『#発言する女性として生きるということ』を読んで、チョンさんの小説に通じる問題意識を感じることができました。
松田 チョンさんご自身も、個人的な戦いとして、さまざまな活動をされていますね。国際結婚のために韓国に移住してきた女性たちのサポートや、ベトナム、カンボジア、ネパールの女子学生向けの高等教育支援事業などをされている。エッセイにも書かれていますが、どういう活動かをもう少し詳しく教えていただけますか。
チョン まず移住女性をサポートしはじめたのは、私が弁護士になる前からです。住んでいた町に小さな文化センターがあって、そこで韓国語を教えていたのがきっかけです。それから弁護士になってからは、そこの生徒さんの離婚などを支援していました。
国際結婚で韓国に移住するようになったそういう女性がとても大勢いるので、彼女たちの自立を支援するNGOも今増えています。ここ一、二年は、そのようなNGOが設立した相談センターで働いている女性の就業規則や労働契約などを精査しています。
それから女子高生への支援は、彼女たちを大学に行かせるという目的でやっていまして、現在は十人に奨学金を給付しています。私がカンボジアのとある大学に講演に行ったことがきっかけでした。その大学には女子学生がとても多かったんです。私が「随分女子学生が多いんですね」と言うと、カンボジアも昔の韓国と同じで、優秀な男子学生はみんな首都プノンペンに行ってしまうと言われました。一方で女子学生は、優秀であっても地元の学校に通わざるを得ないと。大学に行きたいけれど、行けない女の子も多いという話を現地のNGO関係者から聞きました。オーストラリアのNGOが優秀な学生を支援しているが、全員に奨学金を渡すことができないからそこから取りこぼされる女の子も多いと。それじゃあ、私がその子たちをサポートします、ということで支援を始めることになりました。
松田 すばらしいです。
チョン その後、ネパール人の人権弁護士から頼まれてネパールでも同じ支援をしていますし、ロースクールで知り合ったベトナムの友だちと一緒にベトナムの高校生も支援しています。
松田 大忙しですね!
チョン こうしたサポートをしていて感じたことですが、あまりにもタイミングが遅いとそのチャンスを生かせないので、やはり高校一年か二年のときからサポートをしてあげたいと思っています。
あと、国によってそれぞれ環境や状況が違うので、その国に合ったサポートも必要です。例えばネパールでは、いまでも一部の地域や文化圏において、女の子が生理をすると学校に行ったり外出したりするのが難しい状況になります。それで奨学金をもらって学校に行けるようになっても、生理による欠席や早退のために教育が途絶えてしまうという話を聞きました。そこで私は生理用ナプキンなどを支援したり、ネパールの女性の運動家の方に生理教育を依頼したりしました。
また、カンボジアの場合は、国内の政治社会的な事情により、教育レベルがあまり高くないという現状があります。それで選んだ奨学生たちに英作文をして送ってもらい、添削して返すなどの学習サポートも行いました。
松田 細かくいろいろ手を尽くされていて、チョンさんは未来をつくる活動をされているんだなと心から思います。チョンさんの問題意識が弁護士のお仕事でも、小説でもすべてつながって、一つの希望をつくられているということを、お話を聞いていて感じることができました。
『#発言する女性として生きるということ』の中のエッセイ「起こってしまうこと」に、「私は、起こってしまったことの前で立ち上がった人たちを見つめる」という一文がありますが、『となりのヨンヒさん』に収録されている短編も、実際の出来事や事件を下敷きにされているものが多いですね。私はちょっと影響を受けやすいというか、くらいやすいところがあって、ひどい事件や事故のニュースを見ると、調子が悪くなってしまったり、その後もずっとそのことが忘れられなかったりします。それで、時にはニュースを見ないようにして自分を保護しないといけないことがあります。消化することも、口に出すこともできなくて、そのことについて書くこともできないときがあります。そういう恐ろしいことが現実に起こってしまうなかで、自分の小説は誰かを救えるのだろうかと考えてしまいます。特に今は、家で仕事をしながら育児をしていて、身近な範囲でしか暮らせていなくて、できることは署名や募金くらいだったり。
そこで、先ほどうかがった活動のほかにも、弁護士として、実際にたくさんの方を助けていらっしゃるチョンさんにお聞きしたいのですが、それでも小説でしかできないと思えることはありますか。
チョン あります。時空間を超えることができるというのは、小説だけが持っている強みだと思います。何年も前に『となりのヨンヒさん』が日本で出たおかげで今こうして松田さんと対談しているわけですし、作品を書きながら期待した範囲をはるかに超える何かが可能になることもあります。これは、やはり小説を書いているから経験できる幸運だと思うんです。
実は、私がロースクールに行ったのは、松田さんと同じように考えていたときでした。作家デビューを果たしたときに、私は「これで死んでも世に名は残る」と考えました。ですが、三年後に本は絶版になり、私も世の中も何一つ変わりませんでした。「ああ、このままじゃいけない。何かやれることをやろう」。そう思ったのが、弁護士になったきっかけです。
松田 え、そうだったんですね。先に弁護士さんだったのかと思っていました。
チョン でも今になってみると、小説を書くことだけが可能にしてくれる何か、つまり、自分がいなくても何かもっと大きなものにつながれる力が小説にはあるんだなと痛感しています。小説家になって三年後のあのときのあの悩みは、おそらくスランプだったのでしょう。
松田 小説がスランプのときに弁護士になるというのは超人的というか、すごすぎますね。
これまでで作品を書くことによって癒されたり、何かにつながったと感じられたりした瞬間はありますか。
チョン 『となりのヨンヒさん』の「馬山沖」は、極めて個人的な作品なんです。中学まで暮らした馬山という小さな都市で感じた混乱のようなものを書きたかった。正常と異常の狭間で感じるある種のアイデンティティーの混乱というものです。それで作品が完成するまでかなり時間がかかりました。そして書き上げたとき、自分の心の痛みや傷といったものが私から離れていくような感覚を受けたんです。しかし、それが読者にもちゃんと伝わるだろうか、と内心不安がありました。
それから数年後に、SF小説の創作について講演をすることになったのですが、講演が終わったあとバス停でバスを待っていたら、参加者の一人が私のところに近寄ってきてこう言いました。自分はSFの創作には全く関心ないが、高校のときに「馬山沖」を読んだおかげで、自殺を思いとどまることができたと。それで今こうして生きていると。そのことを伝えたくて、講演に駆けつけてくれたそうです。思いがけず自分の癒しと読者の癒しがつながったなと思いました。
松田 すごくいい話ですね。
チョン 私が作家として最も価値を置いているのは、自分が書いた作品で読者を慰めたり癒したりすることです。個人では到底防ぎようのないことが世の中で起きてしまう、ということを小説を通して受け入れたり、確認したりすることで可能になる癒しというものがあると思うんです。

プロフィール
-
松田 青子 (まつだ・あおこ)
2013年、デビュー作『スタッキング可能』が三島由紀夫賞及び野間文芸新人賞候補に。19年、短編「女が死ぬ」がシャーリィ・ジャクスン賞短編部門の候補となる。2021年、『おばちゃんたちのいるところ』が、BBC、ガーディアン、NYタイムズ、ニューヨーカーなどで絶賛され、TIME誌の2020年の小説ベスト10に選出。LAタイムス主催のレイ•ブラッドベリ賞の候補になったほか、ファイアークラッカー賞、世界幻想文学大賞を受賞。他の著書に『持続可能な魂の利用』『男の子になりたかった女の子になりたかった女の子』、エッセイに『自分で名付ける』など。最新の訳書にカレン・ラッセル『オレンジ色の世界』がある。
-
チョン・ソヨン (정 소연)
ソウル大学で社会福祉学と哲学を専攻。大学在学中、ストーリーを担当いたマンガ「宇宙流」が2005年の〈科学技術創作文芸〉公募で佳作を受賞し、作家としてのスタートを切った。
小説執筆と併行して英米のフェミニズムSF小説などの翻訳も手掛けている。2017年には他の作家とともに〈韓国SF作家連帯〉を設立し、初代代表を務めた。
また、社会的弱者の人権を守る弁護士としても活動中。著書に短編集『となりのヨンヒさん』(吉川凪 訳/集英社)、エッセイ集『#発言する女性として生きるということ』(李聖和 訳/クオン)。
関連書籍
新着コンテンツ
-
インタビュー・対談2025年07月08日
 インタビュー・対談2025年07月08日
インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」
著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。
-
お知らせ2025年07月04日
 お知らせ2025年07月04日
お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!
演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。
-
インタビュー・対談2025年07月04日
 インタビュー・対談2025年07月04日
インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」
ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は
窪美澄
2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日青の純度
篠田節子
煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日情熱
桜木柴乃
直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。