
今いちばん会いたい人に、作家が直撃インタビュー! 職人、役者、ミュージシャン、アスリート……さまざまな分野の方々に、作家の洞察力が切り込みます。ひと味違ったインタビューをお楽しみください。
第7回 永井玲衣さん(哲学研究者)が、最果タヒさん(詩人)に会いに行く
2023年04月10日
雑誌「青春と読書」の連載エッセイ「問いはかくれている」で、流行語に隠された問いの考察を展開する哲学研究者の永井玲衣さん。
今回会ってみたいと願ったのは、自著の『水中の哲学者たち』に帯文を寄せてくれた詩人の最果タヒさん。
詩人の言葉に最も心惹かれるという永井さんが、言葉と速度の関係や、詩の言葉と日常で不意に口からまろび出る鮮烈な言葉との違いなど、最果さんとともに言葉の深遠さに迫りました。
撮影/江原隆司 構成/綿貫あかね (2023年2月14日 オンラインにて収録)

人が言葉を使っているのではなく、言葉が喋(しゃべ)り始める
永井 最果さん、私の著書『水中の哲学者たち』に帯文を寄せていただき、ありがとうございます。「もしかして。あなたがそこにいることはこんなにも美しいと、伝えるのが、哲学ですか?」と本に言葉の宛先を向けてくださり、とても嬉しかったです。今回初めてお話しするのが楽しみでした。
最果 ありがとうございます。最初、この本のテーマが「話すということ」で、私は人と話すのが非常に苦手なので大丈夫かなと思いました。でもすごく新鮮に読めたし、人と話すのは面白いことなのかもと思えました。だから今回の対談は伏線が回収されたような気持ちです。
永井 私も対話の本を書いておきながら、話すのが苦手。他者がわからなくて哲学の方向に向かいましたが、最果さんも他者がわからずに、ある種拒絶しながらも他者を希求していくような言葉を重ねられている。言葉を提起していくときに、わからない他者とどう関わるのかを問われている気がしました。最果さんが詩を作るとき、あるいは言葉を書くとき、他者は目の前にどのような形で表れているのでしょうか。
最果 詩を書いていて意図しない方向に言葉が向いた瞬間に、その言葉に他者が触った跡のようなものが見える気がするときがあります。その際に誰かが確かにこの世界にいるんだって実感できるんです。昔からその瞬間がとても好きで、それがあるから他者と話さなくても平気でした。詩を書くようになったのもそのためだと思います。言葉って一つの固定された意味があるようで、本当は人によってどう捉えてるのかかなりばらつきがあるんです。永井さんの連載エッセイ「問いはかくれている」で、めしテロの回がありましたよね。あれは人が言葉を触って、蓄積された意味がどんどん変わる話だと読み取れました。めしテロという言葉は3年前より今のほうが使いたくないと思う人が多い。それは、テロという言葉を使うときの感覚が変わったからだと思います。言葉の周りにまとわりついているものがあって、それが変化している。私は言葉を書くときそのまとわりついているものに触れることができる気がして、その鮮やかさがとても好きなんです。
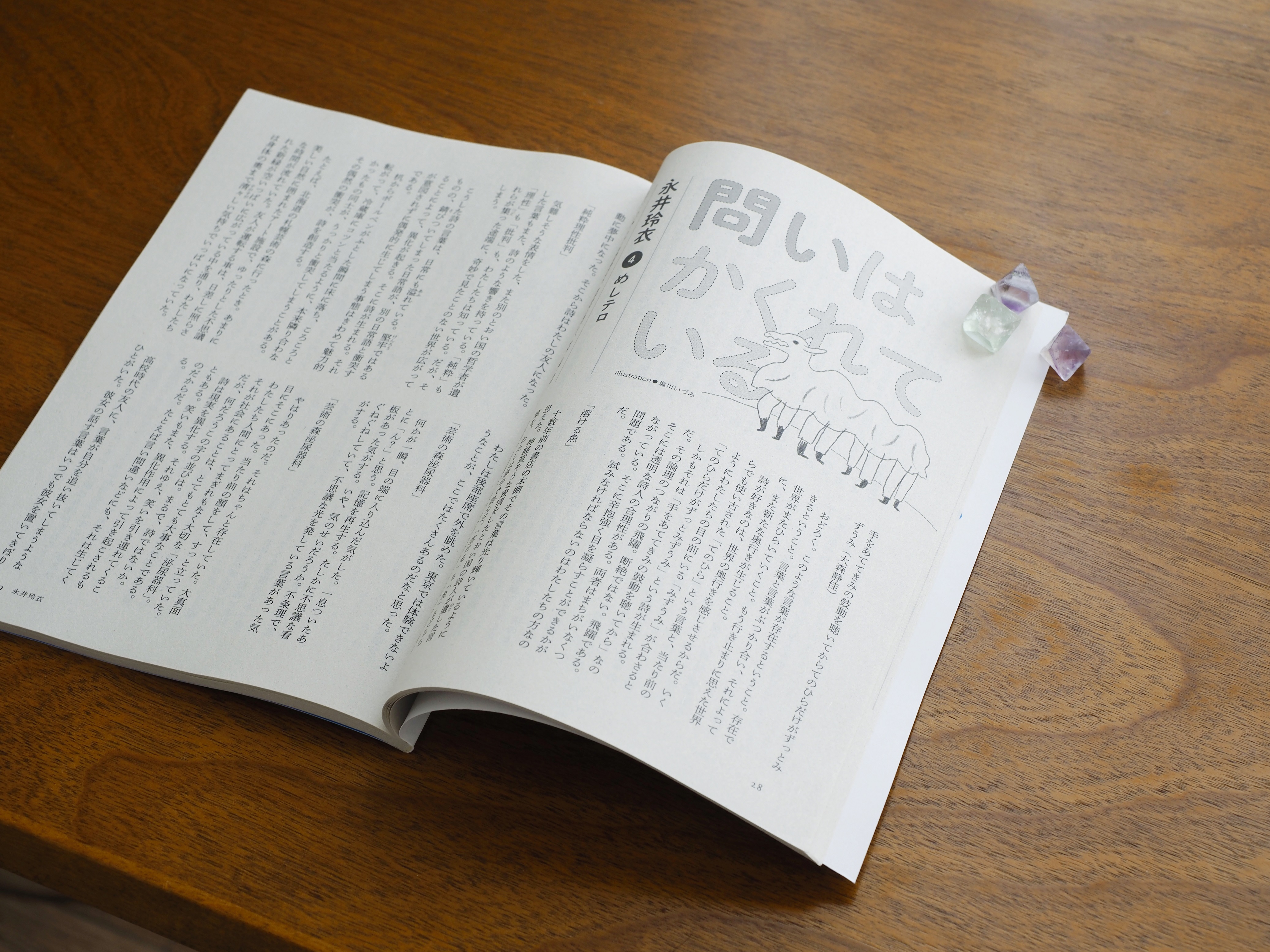
永井 哲学対話(日常で感じる問いについて、互いに聴き合いながら考えを深める時間)という場を開いていますが、今最果さんが言われたような、言葉をみんなでざらざらと触ってみて、その感覚のあまりのばらばらさに驚きます。驚くからこそ確かめていくあの瞬間が好きです。対話が進んでいくと、参加している人がわけのわからないことを喋り始めて、言葉の方に引っ張られていく。私というものが自由自在に言葉を使っているのではなく、言葉が喋っているというか、その場でぐねぐねと言葉がうねって、その周りにまとわりついている不思議な手触りみたいなものがどんどん見えてくる、という変な時間が好ましい。だから哲学書よりも詩の本をよく手に取るし、自分はいわゆる「研究者」ではないなと思ってしまうんです。
最果 すごくわかります。言葉がどこかへ飛んでいって、自分でも今何を言っているんだろう、となる瞬間。10代の頃からそれが繰り返される時間や場が欲しかったけれど、身近には一つもなかったから詩人になったように思います。ただ、当時すでにインターネットがあったから、私はそこで言葉を書くことができて、そして詩を書くようになっていきました。インターネットは現実と違って、人の顔色を見て語られる言葉が当時はほとんどなかったんです。書く人自身が言葉を自分が納得できるまで探し続けられるし、その探し続ける過程が言葉として残されている。私はそれが好きでネットで言葉を書くようになりました。ノートに一人で書くよりも、ネットは誰かが読むかもしれないという気配があってそれもよかったのだと思います。無数の人が触れて、意味が人によって違っている言葉の曖昧さを感じ取りながら書くことができました。その不安定さによって自分が言葉に振り回されて、思いもしない言葉にたどりつくことがある。だから、喋っている本人が一番何を言っているかわからないという話はとてもよく理解できます。人と普通に話していると、どうしても相手が望む言葉を探してそれを言うことが正解だと思ってしまう。でもそうではなく自分自身が話したい言葉を探そうとする時って、言葉が自分の想定外のところに連れて行ってくれることがあるんですよね。私は小説や漫画を読んでいると、こんな会話文はないなと思うときがあるんですが……。
永井 私もあります。
最果 一つの場のために、会話が無駄なく互いにちゃんと理解しあってそつなく進むことなんて滅多にないと思うんですが、そういうことが物語の中ではよく起きて。そのたびにぞわぞわしていました。私にはどうしてもできないことだから。小説を書くとき、そういうにせものにしか思えない会話をなくしたらどうなるかって思ってやってみたこともあります。会話はもっと不完全で困難で、ろくに成立しないものだって思うんです。
言葉の世界に一気に連れて行かれ、意味は後からやってくる
永井 あるとき、高校一年生の男の子が「僕は真っすぐ死にたい」と言ったんです。私はそういう言葉を聞くと保存しておきたくなる。もんどりうった、わけがわからない、でも取り替えのきかない言葉がぼろぼろ出始める瞬間や場は本当に面白い。でも詩のような言葉や変な言葉は、自分一人だけではいきなり出てこなくて、他者がいるから引き出されるんです。場によって語らされるとも言える。そういう意味で私は対話の場を信頼しています。最果さんが、言葉をインターネットの中で無から作ったというよりも、流れの中で引き出されたというようなことを言われて、そうかと腑(ふ)に落ちました。対面に他者がいなくても他者の中の言葉を最果さんも見つけていったのかなと。
最果 そうですね。言葉を使っている時点で、書いた人は誰かが読む可能性を考えているはずです。他人と自分との間に言葉があって、それを互いが使っているので、使おうとする時点で向こう側に何かがいるのは察知した上で書いている。詩を書いて、その都度誰かの反応が欲しいわけではなく、意外とそこは閉じていて、誰がなんと言おうと私はこれが完成だと思ったら完成、という頑固な部分も持ちながら、でも言葉を使う限り、この世界に他人がいることは強く認識している。リアルなコミュニケーションは望まずにいられるこの距離が私にはちょうどいいのです。ぼーっとしているけれど、誰かが行き交っている、その気配だけがわかる感覚の中にいられるのが、私にとって言葉を書く楽しさなのかなと思います。
永井さんは哲学対話をしていて、言葉が人の範疇から超える瞬間があると思うんですが、自分がそうなっていると思うことがありますか?
永井 言葉に連れて行かれることはしょっちゅうありますね。対話の場を作っているのは言葉が立ち現れるのを見たいからだし、それを書ける機会があるからこそ続けられていると思います。「僕は真っすぐ死にたい」という、詩のような言葉が出てきたときに保存しておきたい。そういう謎の焦燥感があるから、対話の場に来ている気がします。哲学をすること自体もそうですが、私が言葉を使っている、私がいいと思って書く、というのではなく、書いている最中に言葉がやってくるというか、問いが落ちてくる。受け身なんです。だから考えざるを得なくなる。その場ではさらっと流れていった言葉が、数ヶ月後に突然発芽することもあります。書くことは遅い行為なのですが、その分、言葉が育つのを待てる面白さがあります。私は言葉が育つのを待ちながら書くので、とても遅いんです。
最果さんが詩を書くとき、言葉を作るときの速度はいかがでしょうか。
最果 詩を書くスピードはものすごく速いです。最初に何を書くかは一切決めません。でも、上澄みのところから出てくる何かを、金魚掬(すく)いのようにパッと掬い、それを1行目にして言葉にできるだけ任せてその次の言葉を書いていきます。以前は、それで最後まで走り抜けたら完成、というような作り方をしていました。1行目の言葉をうまく説明しようとしたり、うまくまとめようとしたりすると完成しなくなるので、言葉の上澄みをそのままこぼさないように走り抜けられるといいなと思っています。だから速くないとできないのかも。我に返ったらだめ。でも、書き始めの一文字が来るのは遅いんです。タイミングもありますし……。だから数ヶ月後に発芽するというのもよくわかります。
永井 たしかに意味を引き込まないままに、言葉が自分を追い抜いてくれるように書く感覚もありますね。私は詩を読むのがすごく速いんです。お酒は飲みませんが、寝る前に強いお酒を飲む感覚で詩や短歌を読む。最果さんの詩を一編、ガッとあおって、言葉の変な感じにぐっときたまま眠りにつく。『死んでしまう系のぼくらに』にも衝撃を受けましたし、とりわけ最近の詩集『不死身のつもりの流れ星』は、そのタイトルの時点でもうやられてしまいました。

最果 ありがとうございます。
永井 言葉の世界に一気に連れて行かれる瞬間に惹かれるから、詩を読むのがやめられない。そういうとき、意味は常に後からやってくるんです。
詩や短歌は、言葉という楽器を使っている音楽
永井 最果さんが詩人になるきっかけは何だったのでしょう。
最果 高校時代に詩の投稿サイトに投稿していたとき、人から「『現代詩手帖』に投稿してみるといいよ」と言われて、書店に思潮社の「現代詩文庫」シリーズを読みに行ったんです。そこで吉増剛造(よしますごうぞう)さんの「燃える」という詩に「今夜、きみ/スポーツ・カーに乗って/流星を正面から/顔に刺青できるか、きみは!」という一文があって、超かっこいい! と思ったんです。何を言っているか全然わからないけど、かっこいいことだけがわかる。現代詩ってどんなものなんだろうって知りたくて本屋に行ったのに、現代詩がなんなのかはわからないままただ痺(しび)れて帰ってきました。それから現代詩が好きになったように思いますし、私にとっての「詩」はいまだにあの時の感覚が教えてくれる気がします。詩人になったとすればこの時でしょうか。
永井 私は寺山修司(てらやましゅうじ)が好きで、以前彼が「血は立ったまま眠っている」と書いているのを、「うわー、すごい」と周りに言ったら、「え、どういう意味?」と言われて、そうだ、意味というものがあった、と思い出したことがありました。あまりのスピードで読んでしまうので、流れを確認しないままに、その言葉が頭にどかんときてしまい、それ以外の文脈を忘れていることが結構あります。言葉にやられるのが好きだからだと思いますが、その言葉の何にぐっときているんだろう。ぐっとくるというのは何なのでしょうね。
最果 たとえば、ジャズでピアノがかっこよかったときに、誰も「どういう意味?」とは聞きませんよね。私は、詩や短歌は言葉という楽器を使っている音楽だと思っています。急に転調したり違った音が鳴ったりしたときに、ものすごくかっこいいというのを言葉でやっている感覚です。この言葉はこういう文脈で書かれていてその意味がとても素敵という楽しみ方よりは、人の根深いところにある強度を信頼し切って、そこだけを目掛けて言葉を投げる、そんな表現がすごく好きです。書いた本人も、意図がわからないくらいの集中力で仕上げた文章ってこの世界にいくつもあって、それを読んだ瞬間にぐっときます。そして私はそれが「詩」だと思っています。できるだけ言葉を言葉だと思わずに書いていきたいと思っています。
永井 たった1行でもいいから、言葉が言葉ではない方法で表れているとか、詩のような言葉が1フレーズでも見られれば、すべて満足してしまうんですよね。対話の場でもそうです。哲学対話では最初に問い出しといって、参加者に普段変だと感じていることを問いの形にしてもらうのですが、ある小学生が「宇宙はどこ。」と紙に書いていました。何を言おうとしているのかわからない。でも伝わるんですよね。宇宙はどこまであるのかという問いなのか、宇宙はどこにあるのかという叫びなのか、彼の混乱が問いに表れている。
哲学対話の場では、こういうわけのわからないものこそが醍醐味(だいごみ)。私はその1フレーズを聞けただけでぐっときて数週間はやっていける、そのくらいの愛着があるんです。それがなぜぐっとくるのかはわからないのですが、言葉はしぶとくて、すぐに理解させない。そのしぶとさみたいなものに世界の奥行きが見える。自分が10代の頃は「こんなもんだ」って思ってしまうとか、行き止まりだと感じられることがとても苦しかった。でも、ふと出てしまう詩的な言葉に相対したとき、まだ世界には厚みがあって、逆説的に希望になる感覚がありました。
詩も哲学も対話も、いつまでも終わらせられない
永井 私が先ほどから話している、偶然生まれてしまうような詩の言葉、言った本人が意図していないような仕方で出てくる奇妙な言葉があります。一方で、寺山修司や宮沢賢治(みやざわけんじ)が探求した先にある練り上げた詩の言葉が存在する。これらは違うものなのでしょうか。
最果さんは、詩を作るときに出てくる言葉と、偶発的に出てきてしまう詩のような言葉は、どう違うと思われますか?
最果 寺山修司も宮沢賢治も探究はしているけれど、書く1秒前に今から傑作を書くぞとは考えていないでしょうね。練り上げていてもそこには偶発的な何かが必ずあると思う。本人の計画から外れた何かが。
私の場合は、詩を作ると決めて書き始めると、本当に退屈な文章が始まってしまいます。だから別のことを考えながら、たとえば行列に並んでいるときとかに作り始めると、意外と集中して、いいものができた気がするときがあります。言葉を書いている人たちは、書き終わると作品の良し悪しを自分で判断して編集者に渡さなくてはなりません。
練り上げられた言葉と偶発的な言葉に違いがあるとしたら、その良し悪しを見極める目が育っているかが大きい気がします。それと、偶然言葉がやってくる時を、どれだけ前のめりに待っているか、も違うのかも。ペンを持ちながら、自分の中に閉じこもらず、自分の外からくるものをずっと待つのは視界を360度に開いて集中するようなことで、とても神経をすり減らしますから。そうやって詩の言葉が、自分の想定外のところで完成した瞬間に気づくことが、書くことと同じくらい大切な仕事なのかなと思います。
永井 哲学対話をやっていると、どう問いを出しているのですか、と聞かれることがありますが、感覚としては問いがやってくるのを待っている、というのに近い。そのときに思い出すのは友達が飼っている猫の話。すごく用心深い猫で、私は撫(な)でたいのですが、猫は関心を向けられるのが嫌いです。だから、こちらはまったく興味がないふりをして、あぐらをかいてぼーっとしている。すると時間が経つと寄って来て、あぐらの上に乗ってくれるんです。自分が問いを出したり言葉を書いたりするときは、その猫のことを思い出します。
いい問いを作ろう、いい言葉を書こうとするとすごくつまらなくなる。だからこっちに来るまでは見ないようにして、ひたすら待つ構えをする。詩人たちが不意に出てしまう言葉をちゃんとつかまえておけるのは、待つ構えが違うのかもしれませんね。書いている詩を終わらせて完成させるのはすごい決断だと思いますが、それは詩人の大切な仕事であり、経験が効く場なんだなと思いました。
最果 私もよく、その猫の例のような書き方をしますが、最初から猫が来ると思って書いていないんですよね。待つ姿勢がいい加減だったら来ないけれど、とてもいい待ち方をしたときにすとんと落ちる。だから私の中では猫が来た瞬間が完成です。
永井 私の場合は、文章を書いているときに気づいたら終わっています。自分で書いているのに、映画が急に終わるみたいに、あ、終わったって。その瞬間に書いたものが圧倒的に他者になる。哲学対話もいつ終わるのかは大きな問いで、本当には終われない。だから時間で区切っていて、どんなに盛り上がっていても時間が来たら終わります。でもそれぞれの人の内側では哲学も対話も続いていきます。数年後に、あのとき言っていたのはこういうことだったんだ、と不意に思い出すこともある。終われない宿命を引き受けるために、その場では徹底してパツンと終わることをやっている気がしています。だから対話はある意味、詩とは違って完成しません。その違いも面白いです。
最果 本当は詩も終わらせられないんだと思います。それを無理やり終わらせるのが、さっきの寺山修司のように強度の高い言葉。そういう、人が書くものを超えてしまった言葉みたいなものが出ると、終わるしかなくなって終われるのかなぁと思います。対話が終わらせられないのは、結局みんなの話をまとめるような結論が存在し得ないからでしょうね。詩も、そこまで書いてきたものを引き受けた言葉では終わらないと私は思います。全てを解決する言葉では終わらないです。ただ、それでも自分のそうしたぐるぐるした思考を飛び越えてしまったような錯覚を詩はくれて、それが詩の終わりなのかもって思う。終わらせられないのはきっと同じなんでしょうね。哲学対話が時間の区切りの代わりに、「それではお時間なので」と終わるのがいいですよね。詩には、そうした言葉がないからこそ、そのたびに別の「終わりではない終わりの言葉」を探しているのかもしれません。
永井 「それでは、お時間ですので終わります」で終わる詩も、いつか読んでみたいですね。


プロフィール
-
永井 玲衣 (ながい・れい)
学校や企業、自治体で哲学対話を続け、ファシリテーターを務める。哲学エッセイの執筆も行い、2021年に初の単行本『水中の哲学者たち』を上梓。現在「青春と読書」で「問いはかくれている」を連載中。音楽家の坂本龍一とGotch主催のムーブメント「D2021」などでも活動している。詩と植物園と念入りな散歩が好き。
-
最果 タヒ (さいはて・たひ)
2008年『グッドモーニング』で中原中也賞を、15年『死んでしまう系のぼくらに』で現代詩花椿賞を受賞。『夜空はいつでも最高密度の青色だ』は17年に石井裕也監督により映画化された。ほか、詩集に『夜景座生まれ』、『恋人たちはせーので光る』、『天国と、とてつもない暇』など、エッセイ集に『百人一首という感情』、『「好き」の因数分解』など、小説に『星か獣になる季節』、『十代に共感する奴はみんな嘘つき』などがある。
関連書籍
新着コンテンツ
-
新刊案内2024年07月26日
 新刊案内2024年07月26日
新刊案内2024年07月26日地面師たち ファイナル・ベッツ
新庄耕
不動産詐欺の組織犯罪の闇に迫る、新時代のクライムノベル『地面師たち』の待望の続編!!
-
インタビュー・対談2024年07月26日
 インタビュー・対談2024年07月26日
インタビュー・対談2024年07月26日新庄耕「釧路がシンガポールになる、というあり得なさで「いける!」と」
今夏Netflixでドラマシリーズ化された前作と、その待望の続編である本作への思いを著者に伺いました。
-
インタビュー・対談2024年07月19日
 インタビュー・対談2024年07月19日
インタビュー・対談2024年07月19日青波杏「「語れない」をテーマに描く、女性同士の繫がりと植民地の歴史」
現代の台湾に生きる女性二人が、古い日記に隠された真実を探る物語。謎と日常、過去の歴史と現在が交わる中で見えてくるものとは。
-
インタビュー・対談2024年07月19日
 インタビュー・対談2024年07月19日
インタビュー・対談2024年07月19日ファン・ボルム「休めない社会だからこそ、休む人たちの物語を描きたいと思った」
本屋大賞翻訳小説部門第1位に輝き、ロングセラーを続けている本作への思いを、著者のファン・ボルムさんに伺いました。
-
お知らせ2024年07月17日
 お知らせ2024年07月17日
お知らせ2024年07月17日小説すばる8月号、好評発売中です!
奥田英朗さん「家」シリーズの待望の新作読切を始めとした大特集のテーマは”家族”。新川帆立さん、遠田潤子さんの対談も必読です!
-
連載2024年07月12日
 連載2024年07月12日
連載2024年07月12日【ネガティブ読書案内】
第32回 浅倉秋成さん
「ポジティブ思考が羨ましくて仕方がない時」





