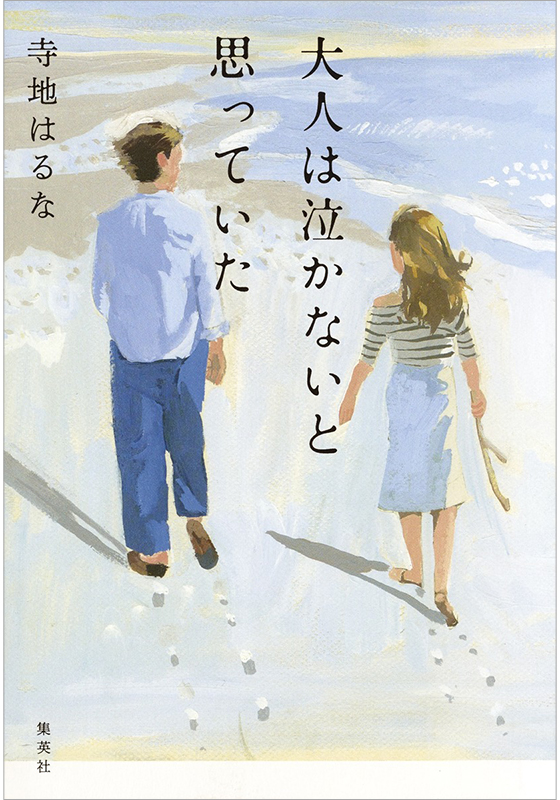作家・寺地はるなさんによるエッセイ連載。食べて眠って働いて……日々をやりくりしている全ての人に贈る、毎日がちょっと愉しく、ちょっと愛おしくなる生活エッセイです。
第7回:お茶の淹れかたを教えてくれた人
2025年01月24日
小説だったかエッセイだったかまるで思い出せないのだが、誰かの本に「出かける前にお茶を一杯飲む」という描写があって、ハァー! 私もこういう余裕のある人になりてぇもんだなあ! といたく感動し、憧れた。
私はどんなに楽しみな外出の場合でもなぜかギリギリまで準備を先延ばしにする癖があり、いつも家を出る十五分前ぐらいになってからあわてて着替えたり化粧をしはじめたりする。お茶一杯の余裕を持ちたい。来年の目標はそれにしよう。
また、こちらははっきりと記憶しているのだが、先日読んだ砂村かいりさんの『マリアージュ・ブラン』という小説には、外出をして帰ってきた主人公がまずお茶を淹れる、という場面があった。それもまたよいなあ、素敵だなあ、と思った。いったいどんだけお茶飲むことに憧れとんねんという話である。いや、余裕が欲しいんだわ、そういう心の余裕が。
私がふだんお茶を淹れるタイミングといったらそれはもう断然、原稿を書きはじめる前である。そういう時はたいてい脳がとっ散らかっているので、コーヒーを淹れたあとに数行書いて「あ、喉渇いた」と思い、また台所に行って紅茶を淹れて戻ってきたら「あれ? コーヒーが、ある……? どうして……?」とひとりで混乱したりしている。自分がコーヒーを淹れた記憶が皆無で、並行世界にワープしてきちゃったのかなとすら思う。
コーヒーも紅茶も、その他のお茶も大好きなのだが、とくにこだわりはない。というか、あまり味の違いがわからないのでなんでもおいしく飲めてしまう。こういう味の違いのわからない人間を「馬鹿舌」と表現する人がいるが、私はなんでもおいしくいただけるほうがだんぜん幸せだと思うので、自分のことは「恵まれし舌」の持ち主だと思っている。「舌」は「タン」と読んでほしい。メグマレシタン。隠れキリシタンみたいな語感だ。
そんな恵まれし舌である私の家の近くに、コーヒー豆の販売店ができた。一度行ってみたいと思っているのだが、店主ひとりでやっている店らしく(ガラス張りなのでよく見える)、いつも接客をしていて忙しそうだ。なかなか入ることができない。結果的に、買いもしないのに毎日のぞきにいく不審な人物と化している。
生まれ育った家ではコーヒーや紅茶を飲む習慣がなかった。おもに緑茶を飲んでいた。こたつテーブルの上に卓上ポットと急須、茶筒が常にセットされていて、飲みたい人はそれを自分で淹れるというシステムだった。だから子どもの頃から自分でお茶を淹れていたが、正しい淹れかたを知ったのは二十歳を過ぎてからだった。
二十歳から二十四歳までのあいだ勤めていた会社にはパートタイマーとして働く女性が数名いて、お茶の葉の適量もお湯の温度も、その人たちからひとつずつ教わった。
なにも知らない私に、彼女たちはとても親切だった。電話応対のしかたもお礼状の書きかたも、ぜんぶその人たちから教わった。私の無知さにあきれることもなく(内心ではあきれていたのかもしれないがそんな態度はいっさい見せず)、根気よく説明してくれた。
あまり人と話すのが得意ではなく、そのことを気にしている私に「あなたは仕事の手を抜かない。ずるいこともしない」「そのままでだいじょうぶ」と言ってくれたのも彼女たちだった。
たった三年間だったが、その時教わったことやほめてもらったことは、今自分が小説の仕事をする上での基本姿勢になっている。私には突出した才能もセンスも教養もない。でもせめてまじめにこつこつやっていこうと心にきめて、現在に至る。
プロフィール
-
寺地 はるな (てらち・はるな)
1977年佐賀県生まれ、大阪府在住。2014年『ビオレタ』でポプラ社小説新人賞を受賞しデビュー。2021年『水を縫う』で河合隼雄物語賞受賞、2023年『川のほとりに立つ者は』で本屋大賞9位入賞、2024年『ほたるいしマジカルランド』で大阪ほんま本大賞受賞。『大人は泣かないと思っていた』『こまどりたちが歌うなら』『いつか月夜』『雫』など著書多数。
関連書籍
新着コンテンツ
-
インタビュー・対談2025年08月22日
 インタビュー・対談2025年08月22日
インタビュー・対談2025年08月22日森晶麿「その一言が謎を呼ぶ 日常生活から生まれるミステリー」
街に落ちている様々な一言を自由律俳句、通称〈野良句〉に見立ててその謎を解いていくという、俳句ミステリーの魅力に迫る。
-
インタビュー・対談2025年08月20日
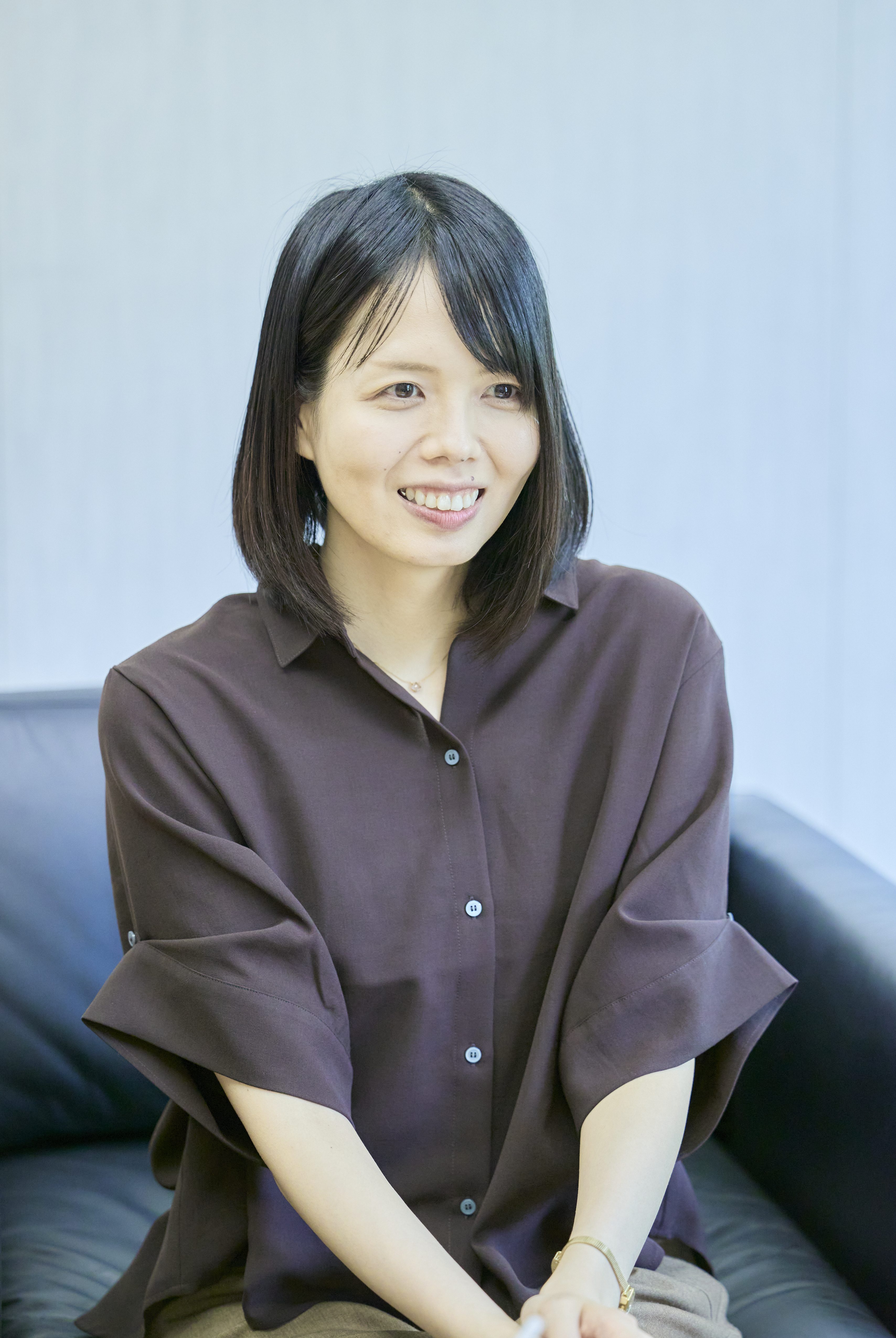 インタビュー・対談2025年08月20日
インタビュー・対談2025年08月20日渡辺 優「人によって性への感覚がちょっとずつ違うということを書きたかった」
ヘテロセクシュアルの恋愛が王道とされる社会に馴染めない女性が主人公の本作。著者の中に蓄積されていた違和感とは。
-
インタビュー・対談2025年08月18日
 インタビュー・対談2025年08月18日
インタビュー・対談2025年08月18日篠田節子×高橋明也「自分が立てたコンセプトに押し潰されず、歳を取るに従って自由度が増していく」
篠田節子さんと長きにわたる親交があり、美術史家で東京都美術館館長の高橋明也さんをお招きし、最新作についてたっぷり語っていただきました。
-
お知らせ2025年08月16日
 お知らせ2025年08月16日
お知らせ2025年08月16日小説すばる9月号、好評発売中です!
待望の新連載は、京極夏彦さんと月村了衛さんの二本立て! 篠田節子さん、渡辺優さんの新刊刊行記念対談も必読!
-
インタビュー・対談2025年08月16日
 インタビュー・対談2025年08月16日
インタビュー・対談2025年08月16日渡辺 優×齋藤明里(女優/読書系YouTube「ほんタメ」MC)「世の中は恋愛至上主義なのか?」
渡辺優さんの作品を愛読している読書系YouTube「ほんタメ」MCの女優・齋藤明里さんと、最新作について語っていただきました。
-
連載2025年08月15日
 連載2025年08月15日
連載2025年08月15日【ネガティブ読書案内】
第45回 川上和人さん
無人島でピンチに陥った時