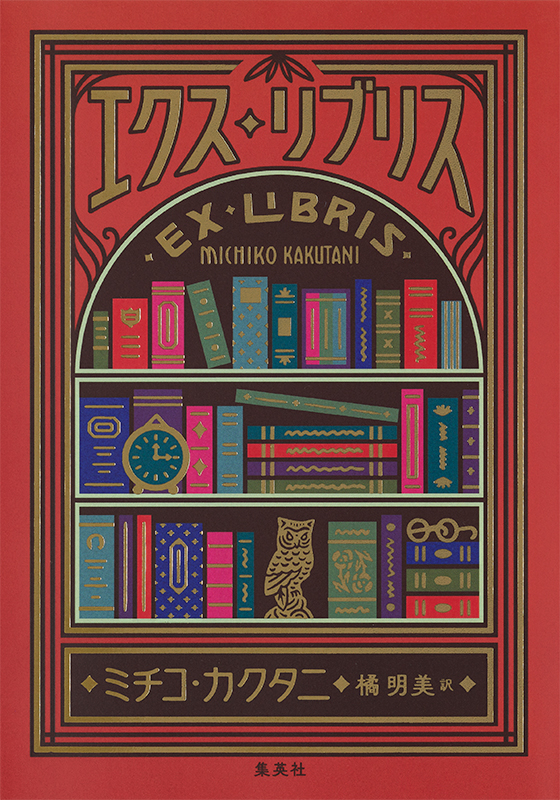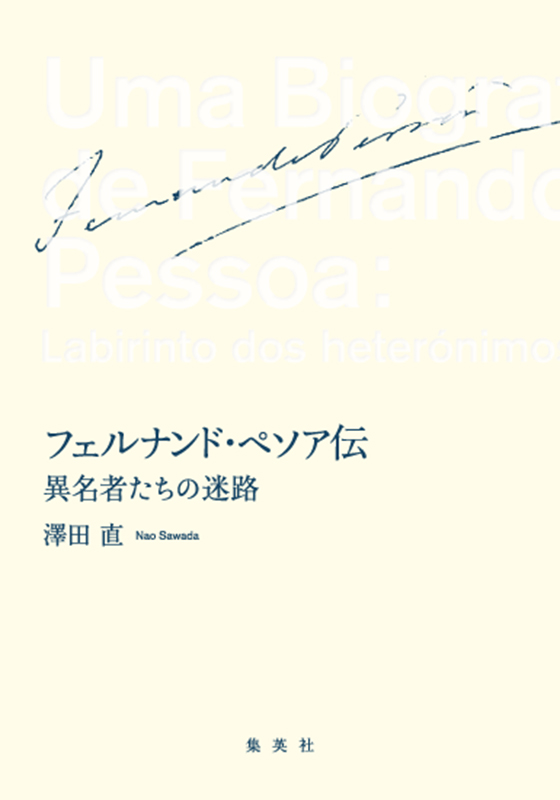内容紹介
【ゴンクール賞受賞作】
なぜ人間は、作家は、“書く”のか。根源ともいえる欲望の迷宮を恐ろしいほどの気迫で綴る、衝撃の傑作小説!
セネガル出身、パリに暮らす駆け出しの作家ジェガーヌには、気になる同郷の作家がいた。
1938年、デビュー作『人でなしの迷宮』でセンセーションを巻き起こし、「黒いランボー」とまで呼ばれた作家T・C・エリマン。しかしその直後、作品は回収騒ぎとなり、版元の出版社も廃業、ほぼ忘れ去られた存在となっていた。
そんなある日『人でなしの迷宮』を奇跡的に手に入れ、内容に感銘を受けたジェガーヌは、エリマン自身について調べはじめる。
様々な人の口から導き出されるエリマンの姿とは。時代の潮流に翻弄される黒人作家の懊悩、そして作家にとって “書く”という宿命は一体何なのか。
フランスで60万部を突破、40か国で版権が取得された、2021年ゴンクール賞受賞の傑作。
プロフィール
-
モアメド・ムブガル・サール (Mohamed Mbougar Sarr)
1990年セネガルのダカールに生まれ、パリの社会科学高等研究院(EHESS)で学ぶ。現在はフランスのボーヴェ在住。
2014年に中篇小説『La Cale(直訳:船倉)』でステファヌ・エセル賞を受賞し、2015年『Terre ceinte(直訳:包囲された土地)』で長篇デビュー、アマドゥ・クルマ文学賞とメティス小説大賞を受賞した。2017年『Silence du choeur(直訳:コーラスの沈黙)』でサン=マロ市主催の世界文学賞を受賞。2021年、4作目にあたる本書はフランスの4大文学賞(ゴンクール賞、ルノードー賞、フェミナ賞、メディシス賞)すべてにノミネートされ、ゴンクール賞を受賞した。
邦訳作品に『純粋な人間たち』(平野暁人訳、英治出版、2022年。原書は2018年)がある。 -
野崎 歓 (のざき・かん)
1959年新潟県生まれ。フランス文学者、翻訳家、エッセイスト。放送大学教養学部教授、東京大学名誉教授。2006年に『赤ちゃん教育』(青土社)で講談社エッセイ賞、2011年に『異邦の香り――ネルヴァル『東方紀行』論』(講談社)で読売文学賞、2019年に『水の匂いがするようだ――井伏鱒二のほうへ』(集英社)で角川財団学芸賞受賞。ほか『無垢の歌――大江健三郎と子供たちの物語』(生きのびるブックス)など著書多数。
訳書に、ジャン=フィリップ・トゥーサン『浴室』『ムッシュー』『カメラ』『ためらい』(以上集英社文庫)、サン=テグジュペリ『ちいさな王子』、スタンダール『赤と黒』(以上光文社古典新訳文庫)、ボリス・ヴィアン『北京の秋』(河出書房新社)、ミシェル・ウエルベック『素粒子』『地図と領土』(以上ちくま文庫)、同『滅ぼす』(共訳、河出書房新社)など多数。
書評
人種や性別、時空を超えて錯綜する、多声の織りなす物語
鴻巣友季子
二〇二一年のゴンクール賞受賞作『人類の深奥に秘められた記憶』が日本語で全姿を現わした。予想を上回る圧倒的傑作である。まだ九月とはいえ、間違いなく本年の翻訳文学ベストの一冊だ。
T・C・エリマンというセネガル出身の幻の作家を追い求めることで、書くという行為と人間の深奥にある本性を探求する物語だ。エリマンは第一次大戦中の一九一五年にセネガルの村に生まれ、パリの大学に学び、『人でなしの迷宮』という「血にまみれた一人の王」の暴虐きわまる所業を綴った小説を二十三歳で発表した伝説の作家。「黒いランボー」の異名を与えられ、フランス文学界の話題をさらったものの、セネガルのある民族の神話、西洋古典、現代文学に至るまで数多のテクストを「剽窃」していたと指弾され、文学シーンから姿を消した。これらの批判にはそれ自体でたらめなものもあったが、エリマンはなぜか沈黙を貫く。
物語の背景には、第一次大戦、第二次大戦をはじめとする数々の戦争がある。アルゼンチンではクーデターにより軍事政権が樹立され、二十一世紀にはセネガルでデモと蜂起の時代がつづく。ここに本作の語り手も巻き込まれていく。
エリマンが注目されたのは、剽窃という事件性もさることながら、アフリカ人であったことも大きい。ここで、本作がモデルとしたフランス文学界の出来事を紹介しておいたほうがいいだろう。訳者解説に詳しく記されているが、巻頭には「ヤンボ・ウオロゲムのために」という献辞が掲げられている。ウオロゲムはマリ(当時はフランス領スーダン)に生まれ、デビュー小説『暴力の義務』(邦訳は岡谷公二)が絶賛されて、ルノードー賞まで受賞した実在の作家である。
『暴力の義務』はアフリカの架空国家「ナケム」を舞台に、サイフ(王)の「暴力の哲学」の残忍な実践を余すところなく描いた衝撃作だ。アフリカ人による驚異の文学と称揚されたのち、グレアム・グリーン『ここは戦場だ』や、アンドレ・シュヴァルツ=バルト『最後の正しい人』などから盗用していると批判され、本は回収されて、作者も文学界から姿を消したという。『人類の深奥に秘められた記憶』に登場するエリマンと『人でなしの迷宮』も同様の道を辿るのだ。
しかしその経緯を語り伝える本作の手法はじつに複雑だ。案内役はジェガーヌ・ラチール・ファイというセネガル出身の若い作家。パリの大学を卒業したのち、アルジェリアの革命に参加するフォトジャーナリストの恋人に去られ、『空虚の解剖』なる小説を発表するが、七十九部しか売れず、それでもある批評家が「ル・モンド」に書評を寄せたことで、期待のアフリカ人作家となりおおせる。
彼が高校生の時から追い求めていたのが、T・C・エリマンだった。その幻の書を探しあぐねているうちに、六十近いアナーキーな大作家シガ・Dと知り合う。彼女を尊敬しているというわりにそのバストに欲情してしまうジェガーヌ。重要なのはこの女性作家が『人でなしの迷宮』を一冊所有しており、本作の主な語り手の座を乗っ取る仕儀になることだ。彼女の登場でこの小説はどんどん語りの入れ子構造を深めていく。ナラティヴが複層し輻輳していくテクストの迷宮をぜひ堪能いただきたい。
若いジェガーヌは語り手としてはある意味で“やわい”。しかしそれゆえに、とくに「第二の書」以降、語りの座を様々な話者へと譲り渡し抱擁する力をもつ。かくして、彼をいちばん大枠の語り手として、その中にシガ・Dによる大量の打ち明け話があり、さらにその中に彼女と年の離れた父ウセイヌの臨終の告白、シガ・Dがブリジッド・ボレームという女性評論家から聞いたエリマン失踪にまつわる調査内容、ボレームの著書の引用、さらにボレームによるエリマンの出版人の一人テレーズ・ヤコブへのインタビュー、シガ・Dを支援していたハイチの女性詩人による回想などが錯綜することになる。ある人物の談話の只中に、それを語り伝えている第二の話者の声や、それを聴いているジェガーヌの声までが折々に侵入し、読者は多声の織りなす物語のいかに「深奥」に自分がいるか気づいてはっとさせられるだろう。
さらに、章の間に挟まる「第〇の伝記素」という、語りの位相の違う“幕間”がスリリングで、ここでは死者をふくめ物語の枠外のだれかが語っているようだ。こうしてエリマンの著書は次々と人にとり憑く。一体この作家は表舞台から去ってなにをしていたのか?
エリマンは評論家たちの「読み」の脆弱さに憤り、その罪に絶望していた。作者が本当にアフリカ人であるか否かや、剽窃というスキャンダラスな面ばかりに囚われ、作品の真の意図を見抜こうとしなかったからだ。作中でボルヘスの『「ドン・キホーテ」の著者、ピエール・メナール』が言及されるのは自然なことだろう。あらゆる文字の組み合わせで表せる文章は理論的には有限であり、すべての本はすでに書かれているのかもしれない。その文字の大海から比類ない文字列=「物語」が発見され、『人でなしの迷宮』および『人類の深奥に秘められた記憶』と名づけられた。それは偶然に見えて一つの強靭な運命だったのだ。
こうのす・ゆきこ●翻訳家、文芸評論家
「青春と読書」2023年11月号転載
アフリカを描くのにもはや「マジック・リアリズム」は不要だ
柳原孝敦
『人類の深奥に秘められた記憶』はとにかくめっぽう面白いから、四の五の言わずに読んでいただきたい。これだけ面白い小説については、いつまでも語りたくなる。ここで与えられたわずかな紙幅ではとても足りないのだ。それならばひと言、読めと言うしかない。それが私の言えるすべてだ。……が、さすがにそれでは許されまい。作品の面白みを削いでしまう危険を冒して、精一杯紹介してみよう。
主人公兼語り手「ぼく」ことジェガーヌ・ラチール・ファイはセネガルからパリに出て勉強したが、学位取得の道を放棄して作家となり、一冊だけ小説『空虚の解剖』を出版した人物だ。その点で作者モアメド・ムブガル・サールの分身と言える。そんな「ぼく」は、一方でセネガルでの士官学校時代に文学史の教科書で読んだ同郷の作家T・C・エリマンのことが気になっている。一九三八年、パリで『人でなしの迷宮』という小説を発表して評判を呼び、「黒いランボー」と称されもした人物だ。しかしほどなく作品は剽窃だと指弾され、本が回収されるという憂き目に遭い、姿を消した。いわば幻の小説を書いた幻の作家だ。
若いアフリカ出身の作家仲間たちの誰も知らないその作家の作品を、しかし、「ぼく」は同郷のヴェテラン女性作家シガ・Dから借りることができ、ルームメイト(ゴンブローヴィッチの翻訳者)や仲間たちとも情報を共有して作家と作品について調査を重ねるが、多くの謎が残るばかりだ。
シガ・Dとの約束に従い、彼女のいるアムステルダムに会いに行った「ぼく」は、彼女が知る限りのエリマンとその作品についての来歴を教えられる。実はエリマンはシガ・Dの年の離れた従兄、もしくは異母兄にあたる人物であり、パリの名門高校で学んでいたころに知り合った友人の経営する出版社から『人でなしの迷宮』を出版した。エリマンは「文学とは剽窃のたわむれ」であることを自覚し「深いオリジナリティをもつ本だけれど、すでに存在している本を足し合わせたものでもある」この作品を、編集者の意図に逆らって敢えて出版したのだった。そしてそれが剽窃との誹りを受け、スキャンダルの種になってしまう。その後彼はヨーロッパ各地を放浪し、さらにはアルゼンチンに渡ってゴンブローヴィッチやエルネスト・サバトとつき合っていたらしい。誰かを探してこの南米の都市に辿り着いたのだという。が、そこから先の足取りはシガ・Dも知らない。ただ、一度、パリでそれらしい人物と遭遇したかもしれないのだが。
そうした話を聞いた「ぼく」はエリマンが故郷に戻ったのではないかと思い、セネガルに戻る。そこは民衆暴動前夜の緊張感に包まれていた……
このようにストーリーをまとめても、この小説の魅力を伝えるにはいかにも不充分だ。「ぼく」の語りのみならず伝聞と二重の伝聞、エリマンの編集者へのインタヴューとその成立の経緯についての伝聞、作家のブエノスアイレスでの同棲相手で、後にシガ・Dと愛し合い、若い彼女を援助しもしたハイチ出身の女性詩人の話、そして「伝記素」と記される出所の確かでない情報(その出所は最後にわかるのだが、それは言わないでおこう)の数々など多様な次元の語りによって、シガ・D、彼女の父親でエリマンの叔父もしくは父親にあたる人物とエリマンの母、エリマンの本を出版した友人にして出版社社主ふたりなど、幻の作家に関わる複数の人物のそれぞれに濃密な人生が紡がれ、圧倒されるばかりだ。
幻の作家(詩人)に関わった複数の人生というと、チリ生まれの作家ロベルト・ボラーニョを思い出さないではいられない。『野生の探偵たち』に『2666』だ……という言い方はいかにも倒錯的で、実は『人類の深奥に秘められた記憶』というタイトルは当のボラーニョ『野生の探偵たち』の一節から取られたものだし、その一節は小説冒頭のエピグラフに明示されてもいる。そしておそらく、だからこそ私(『野生の探偵たち』翻訳者代表)が今、この書評を書いているのだろう。幻の詩人を探したことが原因で放浪を続けることになったふたりの詩人の足跡を、複数の関係者へのインタヴューによってたどるボラーニョの小説では、追われる立場に転じた詩人のうちのひとりが、ヨーロッパに暮らした後にランボーよろしくアフリカに消えたのだった。そのアフリカ大陸から、ヨーロッパを経て南米(ボラーニョの出生地チリの隣国アルゼンチン)で消息を絶った幻の作家を描く『人類の深奥に秘められた記憶』は、ボラーニョへの応答以外のなにものでもあるまい。
かつてガブリエル・ガルシア=マルケス『百年の孤独』の作風が「マジック・リアリズム」の名の下に第三世界の現実を描く参考にされ、多くの作家に影響を与えた。そんな「マジック・リアリズム」が単に幽霊を描くための口実に過ぎなくなって久しい今、何ら「マジック(魔術)」を用いなかったボラーニョがアフリカを描くための霊感源となっているのである。いつまでもラテンアメリカに「マジック・リアリズム」を求める風潮にうんざりしている私は、その意味でも本作に溜飲が下がる思いだ(もっとも、厳密に言うと『人類の深奥に秘められた記憶』には一種の「マジック」が出てくることは出てくる。『百年の孤独』を想起させる細部もある)。
「ぼく」の作家仲間のコンゴ人ムジンブワはエリマンを「植民地主義の最も完成された、そして最も悲劇的な産物」であり「おれたちがそうなるべきではないのに、徐々にそうなりつつある者」と評した。彼はアフリカ人作家に「おまえに固有の形式を発見しろ」と警告しているのだと。「剽窃のたわむれ」たるエリマンの作品にも似た『人類の深奥に秘められた記憶』によってモアメド・ムブガル・サールは、確かに「固有の形式」を見出したようだ。
「すばる」2023年12月号転載
新着コンテンツ
-
インタビュー・対談2025年07月08日
 インタビュー・対談2025年07月08日
インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」
著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。
-
お知らせ2025年07月04日
 お知らせ2025年07月04日
お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!
演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。
-
インタビュー・対談2025年07月04日
 インタビュー・対談2025年07月04日
インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」
ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は
窪美澄
2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日青の純度
篠田節子
煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日情熱
桜木柴乃
直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。