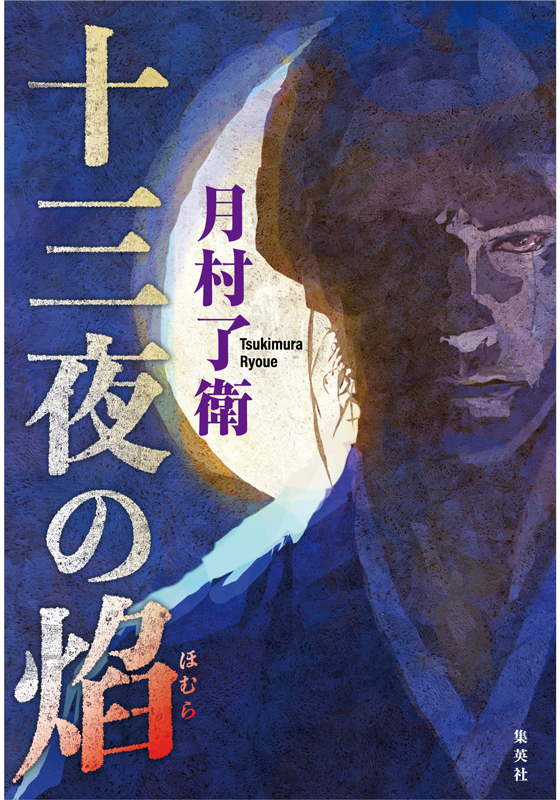内容紹介
竹千代は今に天下を掌中に入れおるぞ――。
室町幕府の権威が低下し、各地で戦乱が巻き起こっていた激動の時代。
松平家が城を構える三河、周辺国である尾張、遠江、美濃、駿河、信濃らが絡む東海地方の覇権争いは熾烈を極めていた。
そんな争いのなかで、織田家ついで今川家の質物として囚われていた松平家の竹千代――後の徳川家康。
数奇な運命を辿った幼少期から天下人へ。
直木賞候補『まいまいつぶろ』の著者が、天下統一を果たした男を鮮やかに浮かび上がらせる十の物語。
プロフィール
-
村木 嵐 (むらき・らん)
1967年、京都府生まれ。京都大学法学部卒業。会社勤務を経て、95年より司馬遼太郎家の家事手伝いとなり、後に司馬夫人である福田みどり氏の個人秘書を務める。2010年『マルガリータ』で第17回松本清張賞受賞、23年『まいまいつぶろ』が第12回日本歴史時代作家協会賞作品賞、第13回本屋が選ぶ時代小説大賞を受賞し、第170回直木賞候補作品となった。他の著書に『阿茶』『まいまいつぶろ 御庭番耳目抄』『またうど』など。
インタビュー
エッセイ
理不尽の向こうには
村木 嵐
家族でも恋人でもないが、家族より恋人より大切な人を、何年も看病していたことがある。
はじめは私の周りには大勢の仲間がいて、私たちは皆で協力し合っていた。だが入院が長引くとそんな暮らしも徐々に変わり、仲間は一人減り二人減り、最後は私とOさんだけになった。そのときのことを思い出すと、私は今も理不尽さに怒髪天を衝き、自分の不甲斐なさに涙が落ちる。
辛い毎日を送っていたあの頃、私はぼんやりと病室の高い窓から下を眺めては、鳥居忠吉のことばかり考えていた。
忠吉は徳川家康の譜代の家臣で、家康の祖父のときから三代にわたって忠節を尽くした三河侍だ。家康が関ヶ原に向かうとき、伏見城に敵を引きつけて十数日も戦い抜いた鳥居元忠の父でもあり、一族には他にもたくさん命を落とした者がいる。
戦国期に弱小国に生まれた家康が早くに父を亡くし、人質として辛酸を嘗めたことはよく知られている。そのあいだ家臣たちは家康の成長を待ち、辛抱のいくさを重ねたが、その留守を預かる家臣団の要が忠吉だった。
世は戦国。向かうところ敵なしの今川義元が横死を遂げ、信玄を擁する武田家も滅び、織田信長までが謀反に斃れた。裏切り、寝返り、騙しに謀殺と、何があってもおかしくなかった時代に、忠吉は最後までただひたすら家康大事を貫いた。
だが忠吉は家康の人となりについては、人質に出されるまでの幼少期しか知らなかった。忠吉には忠義も律儀も、義理も人情もあっただろうが、なぜ年端もいかない家康にそこまで入れ込み、買いかぶることができたのだろう。
家康の祖父のとき、徳川家は破竹の勢いで周辺諸国を征圧していた。だが祖父が家臣に討たれると一気に勢力を失い、父は城さえも乗っ取られて流浪の日々を送ることになった。
どうにか城には戻ったものの嫡男の家康を人質に出さざるを得ず、そのさなか、またも家臣のせいで父は死に、家康は敵国に取り残された。
子供家康も悲惨だったが、主を失った家中がどれほど騒然とし、疑心暗鬼になったかは想像に難くない。それを忠吉は必死で宥め、家康が帰るまで家臣を導いた。
とはいえその日々の中で忠吉の周囲からは朋輩が一人去り、二人去り、これでもかというほど徳川家は衰退していった。私はといえば、そんな忠吉にただ自分の小さな日常を重ね合わせ、勝手に感情移入していた。
そうして私なりに奮闘していた日々の終わりかた、ついにOさんが去ると言い出した。私はまさに目の前が真っ暗になった。
ああきっと、忠吉もこんな絶望を感じただろう。それなのになぜ忠吉は、何を思って堪えることができたのか。
一人で涙を拭っていたある夜、精一杯の強がりの、必死で踏ん張る忠吉の声が聞こえてきた。
――きっといつか朔日に、家康公は天下一の城にお入りになるわ。誰に見えずとも、儂の目にはそのお姿がはっきりと浮かんでおるゆえな。
家康が八月朔日に江戸城に入ったことは、今もその日を祝日とする形で残っている。天下分け目に向かう家康は、伏見城で元忠と一晩語り明かし、のちにその地で将軍宣下を受けた。元忠の孫があわや改易というときは、父祖の功績のゆえにと格別に免れてもいる。
どれも忠吉の死後のことだが、生前の忠吉にはこれらを知っていたとしか思えないふしがある。
そんなことを思いながら書いた忠吉の話が十篇になり、『いつかの朔日』と題をつけた。だがなかなか刊行の機会が巡ってこず、作者としては少し悩ましくもあった。
ただこの本のことは、書いていた当時のあのひりひりした感覚に、もう蓋をしろと何かに言われているような気もしていた。
だが理不尽の向こうには、いつか穏やかに思い返せる日が待っている。懸命にそう言い聞かせていたときからちょうど十年が経って、『いつかの朔日』は本になった。
十年前のあのとき、去ると言ったOさんに私は手紙を書いた。それは『いつかの朔日』で忠吉がしたのと全く逆のことだったが、Oさんは思い直して残ってくれた。そしてそのときから私とOさんは、二十の年の差を超えて真の戦友になった。
Oさんのおかげで私はあの日々を乗り越えることができた。だが忠吉はそれをせず、乗り越えた。
忠吉にそんなことができたのは、雲のあわいに何かを見ていたからではないかとずっと思ってきた。『いつかの朔日』で私が書きたかったのは、その忠吉が雲のあわいに見続けたものだった。
「青春と読書」2024年12月号転載
新着コンテンツ
-
インタビュー・対談2025年07月08日
 インタビュー・対談2025年07月08日
インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」
著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。
-
お知らせ2025年07月04日
 お知らせ2025年07月04日
お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!
演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。
-
インタビュー・対談2025年07月04日
 インタビュー・対談2025年07月04日
インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」
ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は
窪美澄
2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日青の純度
篠田節子
煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日情熱
桜木柴乃
直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。