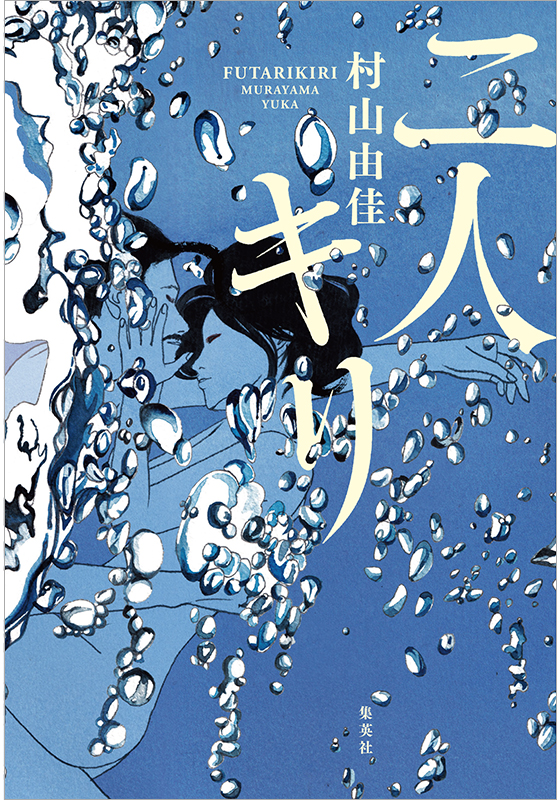内容紹介
感涙の動物病院ストーリー、誕生!
信州の美しい木立の中に佇む「エルザ動物クリニック」。
獣医師としては凄腕だけれど、ぶっきらぼうで抜けている院長の北川梓、頼れるベテラン看護士の柳沢雅美と萩原絵里香、受付と事務を担う真田深雪。4人のスタッフが力を合わせ、日々運び込まれるペットや野生動物の治療を懸命に続けている。
瀕死の野良の子猫を見捨てられず、クリニックに飛び込んできた建築職人の青年・土屋。高齢犬ロビンの介護に悩む、自身も重い病を抱えた久栄。歪んだ結婚生活に苦しむ里沙を見守り続けてきたインコのタロウ……。
それぞれの人生と共にある、かけがえのない命をいかに救い、いかに看取るのか。生きとし生けるすべての命への愛しさがあふれる物語。
プロフィール
-
村山 由佳 (むらやま・ゆか)
1964年東京都生まれ。立教大学文学部卒。会社勤務などを経て作家デビュー。1993年『天使の卵――エンジェルス・エッグ』で小説すばる新人賞、2003年『星々の舟』で直木賞、2009年『ダブル・ファンタジー』で中央公論文芸賞、柴田錬三郎賞、島清恋愛文学賞、2021年『風よ あらしよ』で吉川英治文学賞を受賞。エッセイ『命とられるわけじゃない』『記憶の歳時記』、小説『二人キリ』『PRIZEープライズー』など著書多数。

インタビュー
村山由佳「動物のことは噓偽りなく書ける。それが私の強みだと気づきました」
書評
訪ねてみたくなる動物病院はこちらです
三浦天紗子
愛猫家で無類の動物好きとして知られる村山由佳さん。最愛の猫もみじの思い出と看取りを描いた『猫がいなけりゃ息もできない』を始め、猫エッセイは多く手がけているが、実は動物との交流をメインテーマに書いた小説は少ない。そこにきて、近年は、女性解放活動家・伊藤野枝の評伝小説『風よ あらしよ』、昭和史に残る毒婦・阿部定を証言からあぶり出すフィクション『二人キリ』、承認欲求と自己実現の焰を秘めた作家の闘いと業界のリアルを描いた『PRIZE』など、重くパワフルな作品が続いた後だ。そんな村山さんが真正面から書いた動物ものと聞けば、きっとハートフルな作品だろうという期待はあったが、『しっぽのカルテ』は筆者のぬるい想像を軽々と超えてきた。血の通った生き物がそばにいる喜びと幸福感。そうした村山さんらしい目線を土台にしながら、その大切な存在をどう慈しむのか、いつか来る別れをどう受け入れるのか。人間と動物との最良の共生を考える命の賛歌だった。
「エルザ動物クリニック」(以下、「エルザ」)は、数千坪にも及ぶ信州の森の中に佇む。女性獣医師の北川梓がこのクリニックを含む一帯を所有しており、一年と少し前に隣町の〈刈泉町〉から移転してきた。さらに、柳沢雅美という独身の看護師、萩原絵里香という既婚で息子をひとり持つ看護師、事務と受付を担う真田深雪の四人が力を合わせ、必死に治療に当たっている。五つの章からなる物語は、土屋高志という青年が、古家から救い出した瀕死の子猫を「エルザ」に診せに来たことから動き出す。
各章で必ず問われているのは、有限な命との向き合い方だ。第一章では、見殺しにしても誰にも咎められない瀕死の生き物(捨て猫や事故に遭った犬)を助けようとするか、助けきる自信がないなら見捨てるのかが迫られる。理想の相手としたはずの結婚生活に息苦しさを覚えるようになった里沙と、おしゃべり上手なオキナインコのタロウとの絆を描いた第三章では、ペットが天命を全うするまで飼いきる責任について考えさせる。小学校で飼われているウサギを可愛いと思えなかった被虐待児の草太が、ウサギの境遇に少しずつ自分を重ね合わせていく変化が印象的な第四章では、生き物を飼う上での避妊手術やその生き物にとってよりよい環境でケアする大切さを訴えてくる。第五章では、雄大でときに残酷なモンゴルの遊牧民の暮らしの一端が描かれ、少女時代の梓が〈命の円環〉について深く考えたエピソードに揺さぶられる。
いちばん考えさせられたのは、第二章。自身も心臓病を抱える新井久栄の苦悩だ。愛犬のロビンが股関節の脱臼と老化による変形性脊椎症で寝たきりになる可能性を院長から告げられ、安楽死という選択について考え始める。痛みで苦しむことがわかっているペットにどんな治療をするか、どこまで延命させるか。それは愛するペットのみならず、大切な誰かがいる人にとっても刺さる問いだと思う。
同時に、自分が病気や事故で痛みやつらさの渦中にいても、飼い主や信頼する人間をいたわることを忘れない健気な動物たちの姿も描かれる。交通事故で右側の前肢と後肢を失い、それでも立とうとする中型犬〈チャーちゃん〉。里沙や自分を乱暴に扱う里沙の夫の指を嚙んで一矢報いるタロウ。ひたすら久栄を慰めようとする元保護犬のロビン。これこそが本書の白眉だろう。
本書を読んでいて頭が下がるのは、獣医師や動物看護師、あるいは動物愛護や保護に関わる人々の献身と努力、優しさだ。体のしくみや病気について人間以上にわからないことが多く、まして動物はモノ言わぬ存在だ。犬、猫、インコなど種を問わず、「うちのが急にぐったりして」「きのうから何も食べなくなって」等々、駆け込んできた飼い主の説明と患畜(病気にかかり、獣医の治療を受けている動物をこう呼ぶらしい)の様子だけで、どこが悪いのかつらいのかを察してあげられるのがまずすごい。だが、本当はそうした動物医療や愛護のプロたちも治療に確信を持っているわけではないのかもしれない。それでも、できることをする。その献身に圧倒される。
凄腕なのにちょっととぼけた雰囲気がある院長が魅力的だ。前職の人間関係で傷ついた深雪も、プロフェッショナルな雅美や絵里香の刺激を受けて成長していく。土屋は「エルザ」の外構工事を請け負った職人で、「エルザ」スタッフとの信頼を深め、黒一点の存在として活躍する。最後のページをめくったときに感じたのは「まだ終わってもらっては困る」ということだ。まだまだ彼女たちについて知りたいし、ペットたちの愛らしさに癒やされたい。シリーズとして続いていくことを切に願う。
新着コンテンツ
-
インタビュー・対談2026年02月26日
 インタビュー・対談2026年02月26日
インタビュー・対談2026年02月26日江國香織「ただのノスタルジーではない、今を生きるはみ出し者たちの物語」
かつて、元公民館の建物「ピンクの家」で共同生活をしていた家族を描いた今作。実際に存在した建物と、“ムーミン谷”とは?
-
インタビュー・対談2026年02月26日
 インタビュー・対談2026年02月26日
インタビュー・対談2026年02月26日平石さなぎ「“美しい負けざま”を描きたい」
小説すばる新人賞受賞作が抄録掲載から話題となっている著者の平石さなぎさんに、作品に込めた思いとここに至る道のりを聞きました
-
新刊案内2026年02月26日
 新刊案内2026年02月26日
新刊案内2026年02月26日ギアをあげて、風を鳴らして
平石さなぎ
【第38回小説すばる新人賞受賞作】小学四年生の吉沢癒知は、宗教団体「荻堂創流会」の中で創父の生まれ変わりとして信徒から崇拝されており…。
-
新刊案内2026年02月26日
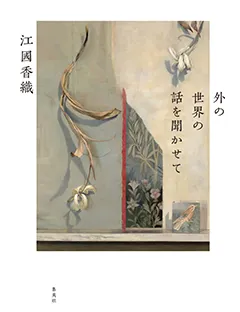 新刊案内2026年02月26日
新刊案内2026年02月26日外の世界の話を聞かせて
江国香織
時間と場所を超えて重なり、織り上げられてゆく人の生に静かに耳を傾ける、珠玉の群像劇。
-
インタビュー・対談2026年02月24日
 インタビュー・対談2026年02月24日
インタビュー・対談2026年02月24日辻村深月×平石さなぎ「人の心を打つメソッドはない」
小説すばる新人賞受賞者平石さんと、その筆力を高く評価された選考委員の辻村深月さんに、受賞作とその執筆の背景について語っていただきました。
-
インタビュー・対談2026年02月19日
 インタビュー・対談2026年02月19日
インタビュー・対談2026年02月19日奥泉光×更地郊「他人に合わせるなんてことはできない。自分が読んで面白いと思うものを書く」
選考会で評価が真っ二つに割れた、すばる文学賞受賞作の著者の更地郊さんと選考委員の奥泉光さん。新人と大先輩の初対談が実現した。