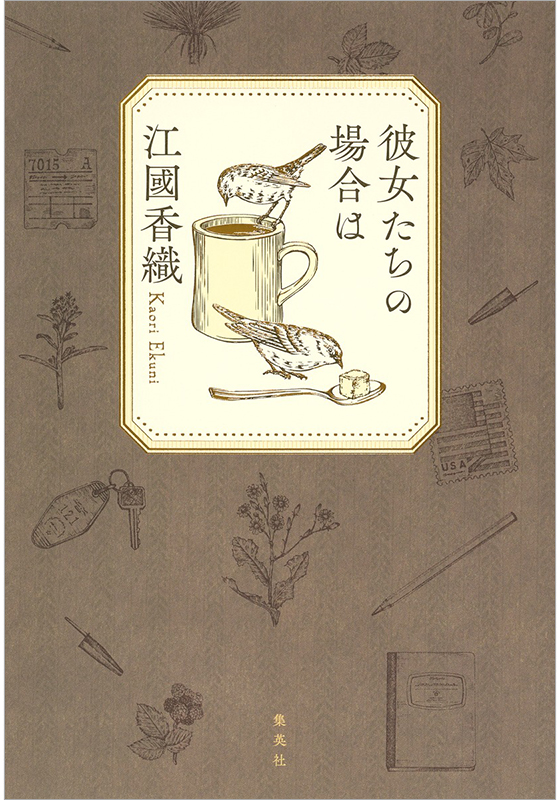プロフィール
-
小佐野 彈 (おさの・だん)
1983年東京都生まれ。2007年慶應義塾大学経済学部卒業。大学院進学後に台湾にて起業。台湾台北市在住。2017年「無垢な日本で」で第60回短歌研究新人賞受賞。2018年、第一歌集『メタリック』刊行。2019年第12回「(池田晶子記念)わたくし、つまりNobody賞」、第63回現代歌人協会賞受賞。
『車軸』刊行記念インタビュー
文芸分野が「カミングアウト」すれば、言葉はもっと豊かになっていく
中学二年生で短歌に出会い、作歌を続けてきた小佐野彈さん。2017年に「無垢な日本で」で「短歌研究新人賞」を受賞。翌年出版した第一歌集『メタリック』は、才能のきらめきと、出自、セクシャリティなどが相まって、瞬く間に話題となりました。そしてこの度、初の小説『車軸』が発売されます。裕福な家に生まれたゆえの屈折したアイデンティティや、己のセクシャリティに悩みながら、自分らしい性愛のかたちを求めていく若者たちの姿が鮮烈な中編です。本作の刊行にあたって、小佐野さんに、この作品にかけた思いなどを語っていただきました。
聞き手・構成=三浦天紗子/撮影=HAL KUZUYA
「青春と読書」2019年6月号掲載

ヘテロセクシャルな女性視点を多用したわけ
──『車軸』の刊行、おめでとうございます。ひりひりしていて切実で、息苦しいような気持ちで一気に読みました。物語は、岩手の県会議員を代々務めている裕福な家柄を嫌悪する真奈美が、同じく富裕な親を持つ台湾出身のアイリーンの紹介で、ホストクラブにデビューするところから始まります。真奈美はその日に出会ったばかりの、ゲイで資産家一族出身の潤に惹かれ、その昂りゆえに潤のお気に入りであるホストの聖也を、自分でも指名するようになりますね。
そうですね。実は真奈美にはモデルがいるんですよ。
── それは興味深いです。この小説は、真奈美、潤、聖也のいびつな三角関係の行方を追っていくわけですが、視点人物として真奈美が多くの部分を占めています。彼女は女性で、ヘテロ(異性愛者)ですよね。小佐野さんご自身から、遠いキャラクターをメインの語り手に据えたのはなぜですか。
企業グループを経営している一族という生い立ちやオープンリーゲイであることなど、確かに潤は僕自身のバックボーンと近いんですよね。なので、自分の気持ちを潤に託すのはちょっと生々しすぎる気がしたんです。一方、真奈美は、抱えているコンプレックスは僕と似ている。あとでもう少し詳しく説明しますが、僕の中のある種の憧れを具現化している。でも性は違う。そういう人物の方が自分を投影しやすい気がしました。真奈美にモデルがいると言っても、その女性は「事実は小説より奇なり」を生きていたような人で、真奈美のキャラクターは実際より盛らずに、抑えめに書いたくらいです。その分、実在の彼女と真奈美がいい具合に乖離し、余白になった部分を僕のリアルな心情やコンプレックスで埋めていけたので、このスタイルで書いてよかったなと書き上がって思いました。
あと、たぶんもう一つ、真奈美視点を選んだ理由があって。僕はデビュー時からかなり同性愛を強く押し出した作品を発表しています。『メタリック』の帯には〈オープンリーゲイとして〉と書かれています。ゲイであることは僕の属性の一つにすぎないんですが、そういうふうに語られてきたし、これからもそうだろうと思う。だから、語り手を潤にしたら、LGBT小説みたいに見られないかという危機感もあったのかもしれません。また、僕の中にもたぶん、ヘテロの女性の主観というものを書いておかなければ、この先もセクシャルマイノリティの視点でしか書けない作家になってしまうのではないかという恐れがありました。それが悪いことだとは思わないけれど、僕は一人の歌人にすぎないし、一人の新人小説家にすぎないのだから、単純に、いろいろやってみたいんです。だったら、ヘテロセクシャルの女性の立場から書いてみるのは、小説執筆のスタートとしていいんじゃないかと考えました。
── 新人の作品は、著者自身のよく知っている世界、著者自身が語りやすい立場で書かれることが多いので、そういうスタイルを採らなかったという意味でも目を引きました。
それは僕が小説ではなく短歌からデビューしているからかもしれません。いまの日本の文芸において短歌はどこか軽んじられているような気がして、歌人はそういう場面によく出くわすことがあります。僕だけじゃなく、短歌の世界ではすごく名の知られた歌人でも、です。無意識なのでしょうが、「短歌≠文学」というか、「文学=小説」という・小説帝国主義・がはびこっているような空気を感じるんですね。
そんな空気に対抗して、意識的に短歌的感覚を持って小説を書くということを、『車軸』でやってみようではないかと思ったんです。それで、少なくとも時系列なり視点人物なりが、不規則に変わってしまう形にしてみた。だから真奈美の視点がメインになっているけれど、視点は潤にも聖也にもなるし、性描写においては神の視点です。近代以降の小説の手法としては超ルール違反だと思いますね。
翻って、日本の古来の文学や芸能の伝統を見れば、僕は能が好きなんですけれども、たとえば世阿弥の能楽では語り部的な役がいつのまにか替わっていたりするのはふつうです。演者がセリフを言いながらくるっと舞台を一周したら、場所や時間が変わっていることもある。地謡の人たちの謡の内容がシテ(主役)の気持ちになったり、シテ方がしゃべっているのがワキ(脇役)の話だったり。『伊勢物語』や『源氏物語』なども、時空や語り手が不意に変わってわかりにくいところがありますが、僕はああいう曖昧さが、和歌や古典文学の面白い部分だなとも思っているんですよね。
血をめぐる、アイデンティティとコンプレックス
──真奈美、潤、聖也の関係は、複雑で危うく、それだけに無二とも言えます。真奈美と潤は、聖也をはさんでライバルのようでもあり、同志のようでもあり、実際、二人は頻繁に食事をしたりお茶を飲むような仲良しになるんですよね。ただ、性的には、〈ノンケだけど、男相手でもマクラしてくれる〉聖也を介さなければつながれないというねじれもある。この三角関係に込めた意味はなんでしょうか。
一つは、キリスト教的な三位一体のイメージですね。三人の中で、おそらくもっとも強い情念を抱いているのが真奈美で、それは潤に対する恋心です。一方、潤の真奈美への気持ちは憧憬、いや崇拝に近いかもしれません。そして、二人が聖也に対して求めているのは性的な快楽、性愛だけです。けれど三者が一つになることで大きな意味が生まれるというか。僕の中では、聖也やアイリーンは天使なんですね。あくまでも二人を導く存在にすぎない。
さらに言うならもう一つ、プロテスタントの古典的寓話、バニヤンの『天路歴程』も、この小説の一つのモデルにはなっているのかなと。僕が『車軸』で書いたのは、『天路歴程』のキリスト者が人生における困難や葛藤をくぐり抜けて「天の都」にたどり着くまでの道のりのようなものです。そう考えると、堕落が真奈美にとっては天の都への道だという、逆説的な、あるいは撞着的なものだとも言えるわけで、そうした宗教文学的な感じを、世俗の恋愛に重ねてみたかったのかもしれません。
── 潤と真奈美はともに、血のアイデンティティに強いコンプレックスを持っています。それが「本物/偽物」という感覚への拘泥になっているんですが、あれは小佐野さんご自身も感じたことがあるんでしょうか。
常々それはあります。ただ、真奈美と潤が探し求めている「本物」ってすごく薄っぺらいものですよね。明治以降に生まれた勲功華族なんて超ハイパー成り上がりなわけで、それを本物と言うのなら、近衛家や九条家とかの五摂家や、西園寺家とかの公家の血筋はなんなんだ、と。僕自身も小佐野という家に生まれて、そしてセクシャルマイノリティで。その軛から逃れていくことに憧れがあるのかもしれないです。それを真奈美と潤の二人に負ってもらったところはあります。真奈美にとっては、親のお金を遣い尽くしていくことが、自分を縛っている鎖を一つひとつ外していく作業なんですね。そうすることで彼女は自由に、よりまっさらな存在になっていく。
僕は短歌出身で、短歌はノンフィクションとして受け取られやすいところがあるので、一見すると潤が僕にかなり近い人物に思われやすい。けれども、僕の感覚としては真奈美の方がはるかに僕に近いし、同時に僕の理想の権化でもあるんです。真奈美は自分の生家を偽物だと断じ、世間の価値観という鎧を脱ぎ捨てていくじゃないですか。社会的に見たら堕落しているように見える人間の方がはるかに自由で美しかったり、より崇高なものに変わったりすることがある。それは一つの真実かもしれないと思っているんです、書いていて、真奈美のことがどこかうらやましく、むしろさわやかだとさえ感じました。僕は自分のコンプレックスや自分の中の不協和音をどう消していくかを、真奈美に託したように思います。
越境し合うことで、言葉の世界は豊かになる
── 『車軸』は、小佐野さんにとって初めての小説になるわけですが、書く前に、プロットは決めましたか。
いえ。実は一稿目は九日間で書いたんです。手書きだったので簡単には戻って書き直せない。たいてい自宅の麻雀卓の上で猛然と筆を進めていたので、自分でも書いていたときの記憶があまりないくらいです。
── 昼夜問わず書くような状況だったと。
僕はそもそも昼夜問わない生活をしていますが(笑)、あのときは常に原稿用紙を持ち歩いていました。それこそ友達のバーで、酒をやめたのでウーロン茶を飲んでいるときもいきなり「いま書かねば」という衝動が湧いてきたりして、結末まで一気でした。というか、書き終わりの瞬間が直感的にわかりました。僕を小説の世界へ導いてくれた林真理子さんから教わったことですが、「手書きで小説を書くいいところは、頭と手が直結してることで、だから勝手に登場人物もしゃべりだすし、勝手に物語が展開していく。手が疲れたら止まるから、そこで『了』と書いてよし」と。言われた通りのやり方で執筆してみたら『車軸』ができた。それで正しかったと思います。
僕たち歌人は、基本、ノリで詠むというか。ノリというのは語弊があるけれど、街を歩いているとき、電車に乗っているとき、あるいはまさに駅の改札を通り抜けた瞬間、コンビニでお茶を選んだ瞬間に、フッと初句が浮かぶってあるんです。そうやって五・七・五・七・七の最初の五が生まれると、それにつられて続く言葉がバーッと出てくる。それを携帯のメモ機能に打ち込む。そんな日常を、たぶん歌人はみな結構やっていると思います。僕の場合、小説もそれに近い感じでした。短歌のおかげでそういう書き方ができた。と言うより、そういう書き方しかできなかったですね。
──ところで、小佐野さんは中学生くらいから歌を詠んできたんですよね。ということは、独学なんですか。
はい。最初は自分のセクシャリティなどにとまどっていたころで、俵万智さんの『チョコレート革命』を手に取ったのがきっかけでした。あとがきに、短歌について「心の真実を届ける手紙でありたい。だから真実のための噓はとことんつく」というようなことが書かれてあり、真実には「こころ」というルビがついていました。「歌だったら、堂々とこころの“ほんとう”のために噓をついていいんだ!」と救われた気持ちになったんです。次の日から、僕の国語のノートは五・七・五・七・七で埋め尽くされていきました。詠むのは、自分の真実(ほんとう)を見つけるため。それこそ人に見せるものじゃなくって、本当に自分のためだけのものだったんです。
ですから、新人賞にもまったく応募しなかった。ごくたまに、学内誌に無難な作品を載せるくらいでした。三十歳のときに、短歌の評論と俳人をやっている慶應幼稚舎からの同級生からちゃんとやった方がいいとすすめられ、「かばん」という歌人集団に入りました。穂村弘さんや東直子さんもいるここは、他の結社と違って、添削が一切ない。失敗作だろうがなんだろうが、自分の出した作品はそのまま載るんです。非常に自由な集団だけど、その分、ひたすら自分で研鑽していくしかないんです。
ただ、その歌壇の同人たちが、ある意味、先生になってくれましたし、歌論や『万葉集』などの古典も読むようになりました。短歌は、真似から始まるんです。好きな歌に倣っているとだんだん上手くなってくる。数をこなすのも大事です。ですから、一年で千首詠む。自分に課しているノルマはそんな感じです。実際、最高記録は一年で三千六百首以上詠んだときですが、新人賞をいただいたのはその年です。量が質に転化するというのは歌の場合必ずあって、たぶん小説もそうなんじゃないかなと思っています。
── 小説という表現の方法を手に入れたことで、新しい扉が開いたような感じでしょうか。
われわれ短歌の世界には「純粋読者」がいない。短歌を・読む人・はほぼ・詠む人・なんですね。なので、純粋読者を得ていくことには興味があります。さっきも申し上げた通り、小説は近代以降の文芸の中で特権的な地位を得ていますが、その特権の中で内向きになっているようにも見えます。僕は博士課程まで経済学を学んだ経済学者のたまごだったんですけれども、「戦争を起こさず平和を維持しながらみんなが豊かになっていくにはどうしたらいいのか?」という問いの答えは、経済学の一つの常識としては「貿易をすること」なんですね。互いの成果物、互いの利益を分け合うということ。
僕たちゲイの世界ではよく言う「カミングアウト」の語源はカミング・アウト・オブ・ザ・クローゼット、「クローゼットから出る」という自動詞ですね。それと同様に今後、歌人もなんというか、クローゼットから出ていって小説やエッセイ、あるいは自由詩を書くべきだと思うんですね。逆に、小説の人には、ぜひ俳句や短歌の定型詩の世界にきてみてもらいたい。それこそ川上未映子さんは詩と小説という世界を行き来している人ですし、東直子さんは歌と小説ですね。
そうやって、いわゆるカテゴリーをもっと越えていけばいいのではないかと。ちょっと偉そうなことを言わせていただくと、カミング・アウト・オブ・ザ・クローゼットをそれぞれの文芸分野がしていけば、つまりそれぞれの成果物の特産品というか良い部分を貿易していけば、国民は豊かになっていく。その国民とはイコール「言葉」で、言葉はもっと豊かになっていくと思う。
なにぶん小説に関しては、僕はまだ不勉強ですが、知らないからこそ、小説の作法と呼ばれるようなもののルール破りをやらせてもらえてしまう。短歌は形式が重要で、どうしても動かしがたい韻律や定型という軛があるわけですが、一方で軛があるからこそより自由になれる部分もある。小説も歌人が書くのなら、免罪符みたいなものをいただいているようにも思えて、『車軸』もそのつもりで自由に書いた部分があります。これからもそういう越境を楽しむ気持ちで、短歌も小説も書いていきたいですね。
新着コンテンツ
-
新刊案内2024年07月26日
 新刊案内2024年07月26日
新刊案内2024年07月26日地面師たち ファイナル・ベッツ
新庄耕
不動産詐欺の組織犯罪の闇に迫る、新時代のクライムノベル『地面師たち』の待望の続編!!
-
インタビュー・対談2024年07月26日
 インタビュー・対談2024年07月26日
インタビュー・対談2024年07月26日新庄耕「釧路がシンガポールになる、というあり得なさで「いける!」と」
今夏Netflixでドラマシリーズ化された前作と、その待望の続編である本作への思いを著者に伺いました。
-
インタビュー・対談2024年07月19日
 インタビュー・対談2024年07月19日
インタビュー・対談2024年07月19日青波杏「「語れない」をテーマに描く、女性同士の繫がりと植民地の歴史」
現代の台湾に生きる女性二人が、古い日記に隠された真実を探る物語。謎と日常、過去の歴史と現在が交わる中で見えてくるものとは。
-
インタビュー・対談2024年07月19日
 インタビュー・対談2024年07月19日
インタビュー・対談2024年07月19日ファン・ボルム「休めない社会だからこそ、休む人たちの物語を描きたいと思った」
本屋大賞翻訳小説部門第1位に輝き、ロングセラーを続けている本作への思いを、著者のファン・ボルムさんに伺いました。
-
お知らせ2024年07月17日
 お知らせ2024年07月17日
お知らせ2024年07月17日小説すばる8月号、好評発売中です!
奥田英朗さん「家」シリーズの待望の新作読切を始めとした大特集のテーマは”家族”。新川帆立さん、遠田潤子さんの対談も必読です!
-
連載2024年07月12日
 連載2024年07月12日
連載2024年07月12日【ネガティブ読書案内】
第32回 浅倉秋成さん
「ポジティブ思考が羨ましくて仕方がない時」