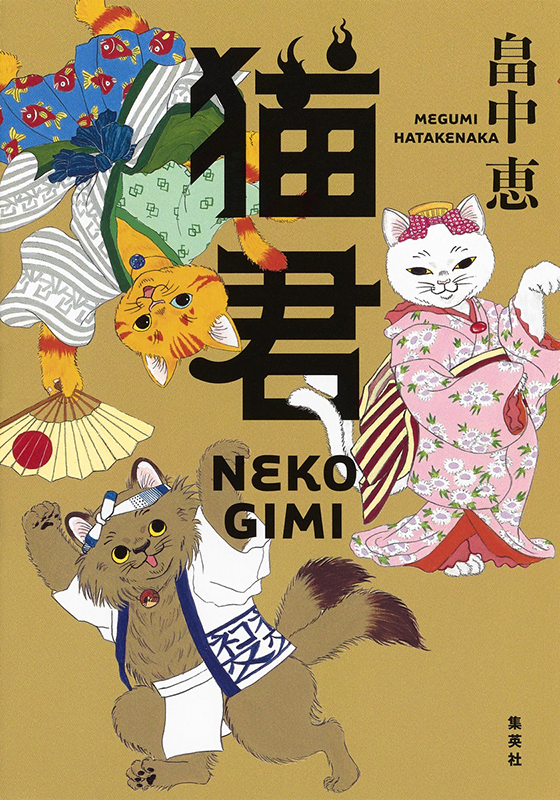内容紹介
【第164回直木賞受賞!】
「谷根千」と呼ばれ、東京の散策スポットとして知られる台東区の谷中、文京区の根津、千駄木エリア。
西條奈加さんの新作は、その一つ、千駄木周辺が舞台となる時代小説です。
江戸、千駄木町の一角に流れる「心淋し川(うらさびしがわ)」。その小さく淀んだ川のどん詰まりに建ち並ぶ、古びた長屋に暮らす人々が物語の主人公です。
青物卸の大隅屋六兵衛は、一つの長屋に不美人な妾を四人も囲っている。その一人、一番年嵩で先行きに不安を覚えていたおりきは、六兵衛が持ち込んだ張方をながめているうち、悪戯心から小刀で仏像を彫りだして……(「閨仏(ねやぼとけ)」)。
裏長屋で飯屋を営む与吾蔵は、仕入れ帰りに立ち寄る根津権現で、小さな唄声を聞く。かつて、荒れた日々を過ごしていた与吾蔵が手酷く捨ててしまった女がよく口にしていた、珍しい唄だった。唄声の主は小さな女の子供。思わず声をかけた与吾蔵だったが――(「はじめましょ」)ほか、全六話を収録。
生きる喜びと生きる哀しみが織りなす、感動の時代連作。
ぜひ一話ずつじっくりと味わってください。
プロフィール
-
西條 奈加 (さいじょう・なか)
1964年北海道生まれ。2005年『金春屋ゴメス』で日本ファンタジーノベル大賞を受賞しデビュー。2012年『涅槃の雪』で中山義秀文学賞、2015年『まるまるの毬』で吉川英治文学新人賞を受賞。時代小説から現代小説まで幅広く手がける。近著に『亥子ころころ』『せき越えぬ』『わかれ縁』などがある。
心淋し川
その川は止まったまま、流れることがない。
たぶん溜め込んだ塵芥が、重過ぎるためだ。十九のちほには、そう思えた。
岸辺の杭に身を寄せる藁屑や落葉は、夏を迎えて腐りはじめている。梅雨には川底から呻くような臭いが立つ。
杭の一本に、赤い布の切れ端が張りついていて、それがいまの自分の姿に重なった。
ちほはここで生まれ、ここに育った。
「やっぱり人ってのは死に際になると、生国に帰りたいと願うものなのかねえ」
今年の初め、昭三じいさんの葬式から帰った母のきんが、そんなことを口にした。
風邪がもとでひと月ほど寝込み、そのまま枕が上がることなく静かに逝ったが、
「ああ、帰りてえなあ……もういっぺんだけ、霞ヶ浦が見てえなあ」
それだけは床の中で、くり返し呟いていたという。
「じいさんの生国は常陸でね、霞ヶ浦の北辺りにある村の出だそうだよ」
故郷が遠くにあれば、恋しく思うものだろうか?
いや、そんなことはない。あたしはここを出たら、二度と戻りたくなぞない。
川沿いの狭い町にも、この家にも、ちほは心底嫌気がさしていた。
父の荻蔵は、いつもどおり貧乏徳利を抱いたまま、くだを巻いていて、ちほは仕立物に気をとられているふりをする。誰も返事なぞしないのに、母のおしゃべりは絶え間なく続き、ただその日に蓄えた些細な事々を、吐き出してしまわなければ気が済まないのだ。
四年前まで、相槌を打つのは姉の役目だった。姉のていは、鮨売りをしていた男と一緒になって、浅草で所帯をもった。
「ていもとんだ貧乏くじを引いたもんさね。多少見目がいいってだけで、ころりと参っちまって。だいたい鮨売りってのは、格好がいなせなだけに粋に見えるからね。親にも内緒で子供なんぞ拵えちまうから、罰が当たったんだよ。博奕好きってのは、いちばん手に負えないからねえ。稼ぎをみいんなすっちまって、ていの針仕事だけで賄っている有様だもの。そのうち子供を抱えて、実家に戻りたいなんて泣きを入れてきたって、面倒なんて見きれやしないよ」
母の愚痴めいた悲嘆は油のごとくたらたらと留まるところを知らず、これなら別に川岸の棒杭相手でも構わないようにも思える。言ったところで何の甲斐もないことを、どうして母はこぼし続けるのか、ちほにはわからない。
吐き出す母はすっきりするのだろうが、毎日毎日きかされるこっちはたまらない。どうして耳には目蓋のように、塞ぐものがないのだろう。そんなことを考えながら、ちくちくと針だけを動かすことで紛らわせる。
「うっせえな! いい加減、だまらねえか! ていの話なら、こちとら百遍はきかされて飽き飽きしてんだ」
酒に赤らんだ顔を、苛立ちでさらに朱に染めて、父が怒鳴りつける。これもまた、まるで芝居のひと幕のように、変わらずにくり返される。
不機嫌そうに常に仏頂面を崩さず、吞んでいるときだけはやたらと威勢がいい。ただし酒が抜けず仕事に出られぬ日も多く、どの仕事も長続きしない。いまは根津門前町の風呂屋、『柿の湯』で釡焚きをしているが、いつお払い箱になってもおかしくない。
母とちほの針仕事で家計を支えているのは、姉の家とまるで同じだった。
そして毎日の陳腐な芝居も、判で押したように同じ顚末を辿る。
「ちほが嫁に行ったら、寂しくなるねえ。頼むから、おまえは近くに嫁いでおくれよ」それこそご免だと、腹の中だけで言い返す。
「ていもたまには、顔を見せればいいのにねえ。清太ももう五歳だろ、可愛い盛りじゃないか。亭主もわざわざ、根津から浅草に鞍替えすることもないのにねえ」
鮨売りは、仕出屋から売り物を仕入れる。根津で売り歩いていたために、姉は亭主と出会ったのだが、嫁いで半年で子供が生まれ、さらに半年が過ぎると、特に理由もなく仕入れ先を浅草の仕出屋へと変えた。
おそらく言い出したのは、姉ではないか? この町とこの家から少しでも離れるために、姉が望んだことではなかろうか?
「ちほがいなくなったら、父ちゃんとふたりきり。寂しくなるねえ」
昨日が巻き戻ったみたいに、母は同じことをくり返す。
姉に続いて、糸車のようなこの家を出ることが、いまのちほにとっては、たったひとつのよすがだった。
【書評】ささやかな人の営みを描く、滋味溢れる連作
評者:大矢博子(書評家・文芸評論家)
半村良の『どぶどろ』を思い出した。社会の底辺で暮らす人々を、どぶの泥に喩えた名作時代小説である。ただし本書はどぶではなく、淀んで濁った川だ。
舞台は江戸。千駄木の淀んだ川沿いに建てられた貧乏長屋に暮らす人々の営みが、連作の形で描かれる。
長屋といっても、打ち捨てられた空き地に勝手に小屋を建てて住んでいるというのが実情だ。住民は訳ありばかり。暮らし向きが楽な者はひとりもいない。
働かない父を抱えた娘が、恋人と一緒に今の生活から抜け出ることを夢見る表題作。四人の妾が住む家で、お呼びのかからない最年長の女が思わぬ生き方を見つける「閨仏」。行き場のない板前が死んだ兄貴分のあとを継いで四文飯屋を切り盛りする「はじめましょ」。体の不自由な息子の世話が生きがいになっている母の歪みが恐ろしい「冬虫夏草」。同じ岡場所から異なる道を進んだふたりの女性の対比で読ませる「明けぬ里」。そして最終話「灰の男」は、この長屋の差配人の物語だ。
同じ場末に流れてきた人々だが、それぞれに抱えているものが違う。興味深いのは、不遇な状況にありながらも一発逆転を狙うのではなく、この場所でやりなおそうとする姿を描いている点だ。
出ていく機会があったのに、とどまることを選んだ主人公がいる。たまたま就いた仕事にやりがいを感じる者もいる。他人を妬むこともあるけれど、だからといってそれは現在の否定ではない。今の境遇でできること、今の境遇だからできることを、彼らは見つけていく。
確かに淀んだ川は汚いし、匂う。だがそんな町を指してある人物はこう言う。
「生き直すには、悪くねえ土地でさ」
なぜか。人の営みがあるからだ。ささやかな喜びと悲しみが詰まっているからだ。淀んだように見えても、中で懸命に蠢いているのがわかるからだ。
その集大成が最終話である。差配人がずっと抱えていた心の淀みが浄化される様子は、実に胸に染みる。
西條版どぶどろ、滋味溢れる連作だ。
(初出:「青春と読書」2020年9月号)
「人間のありようは、時代時代でそこまで変わらないんじゃないかと思います」作家・西條奈加インタビュー
新着コンテンツ
-
インタビュー・対談2025年07月08日
 インタビュー・対談2025年07月08日
インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」
著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。
-
お知らせ2025年07月04日
 お知らせ2025年07月04日
お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!
演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。
-
インタビュー・対談2025年07月04日
 インタビュー・対談2025年07月04日
インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」
ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は
窪美澄
2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日青の純度
篠田節子
煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日情熱
桜木柴乃
直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。