
時間がないけど読書がしたい!
そんなあなたのための、スキマ時間で楽しめるネット上の小さな本屋さん。
スキマブックス、開店します。
「殺し屋たちの怪談会」 第三回
平山夢明
【60分で読める】【小説】
平山夢明氏の本格新作、いよいよ始動。殺し屋たちが持つ「怪談」があなたを恐怖に誘う――――。
2025年11月21日
4
チャフの譚
ソフティーが具合が悪いと云って俺のやってるモーテルに転がり込んできたのが三年ほど前の事だった。兄弟とは云ってもこの業界にはよくある腹違いって奴で俺と似ている処なんか一ミリもありゃしなかった。奴にこの稼業に引きずり込まれたのは俺の手癖のせいだったよ。俺には昔っからおふくろをはじめ、他人様の金に手を付ける癖があったんだ。
あれは吐き気がするほどの猛暑が続いた日だった。フロントでピザを喰っていると『よお』って声がしたんだ。ソフティーだった。瞬きするだけでも汗が噴き出すような陽気なのに黒いタートルネックを着てやがってマスクにパナマ帽を深々被ってさ。何かの変装なのか? って云ったら、えらく怖い目で睨みやがって。俺はすぐにいつも博打用に空けている部屋に案内したんだ。うちのモーテルは常連しか来ないし、全員、ゴロツキのフダ付きの因業成金だ。だからソフティーも安全だと思って躯を躱しに来たんだろうと俺は思った。部屋に案内してから晩飯でも行くかい? って訊くと呼ぶまで来るなってんだ。久闊を叙する余裕もねえのかよって云ったら、奴はけっけっけって笑って『おまえ、いつの間にそんなシャレオツな御輪を鳴らすようになったんだよ』って云うからモーテル稼業は基本が待ちだ。その間に辞書を読んでるのさって云ったら随分、笑ってやがった。
でもその時、俺は杖を突いた奴の足がヘンテコな具合に捻じれたのに気づいたんだ。それは一瞬で戻ったからてっきり目の錯覚だと思ったけどね。あっちがこっちになってるような妙なグネ方だったよ。それから二時間ほどしてフロントに電話がかかってきた。卵サンドと濃いコーヒーを持って来いという話だった。
持っていった。手癖は悪いが俺は料理は巧い。
部屋に入ると奴は案内したときのまんまの恰好で壁によりかかっていたんだ。
『どうして服を脱がないんだ』
『そのつもりだったんだが、どうやらそういうわけには行かなくなっちまった。
『わかんねえな……ただ脱ぎゃいいだろう』
『まあ……順を追ってゆっくりやるさ。何せ、こともないんだから俺にはもう慌てふためくこともないんだからな』
『ソフティー。あんたそんなに痩せてたっけ? 腹もそうだが、胸の辺りまでが随分落ち窪んで見えるぜ。なんかの病気なのか?』
奴は返事をせず、俺の運んだやつをやり始めた。
『おまえの卵サンドは相変わらず美味いな。黄身がベトつかず、しっかり塩が利いていて甘みを引き立ててる。なによりも日向っぽい香りがするし、珈琲の苦みがその甘みを適度に弱めて胃にもたれない』
『厭に褒めるじゃないか』
『実はおまえに話しておきたいことができた。そんなにはかからない。陽がすっかり暮れる頃には終わるネタだ。ただ話の途中でこの部屋を出るのはなしだ。中座せず、最後までキチンと聞いてくれ』
俺は奴がまたぞろ軽口を叩いて担ごうとしてるんじゃねえかと思ったが、奴の目は真剣だった。
『……わかった。そしたら、ちょっと細々した用を済ませてくるから待っててくれ』
『その前におまえに土産がある。スーツケースを開けてみろ』
俺は奴が顎をしゃくり気に指したケースに取り付いて開け、目を丸くした。
『すげぇ! エシレじゃないか! しかも、こんなにたくさん!』
『店の在庫を総ざらいしてきた。それをつまみに話を聴くなら負担は少なかろう』
『勿論だよ! ありがてえ! 嬉しいぜ!』
今はこんな風になっちまってるけど、当時の俺はこの三倍は体重があった。理由は過食なんだが、特に俺はバターに目がなくてな、なかでもエシレの奴隷みたいになってた。ところがこいつはなかなかの高級品でバカスカ喰うわけにはいかなかったんだがソフティーはそれを銀の延べ棒みたくスーツケースに詰め込んで来やがった。
俺は早速、そいつを自室の冷蔵庫に詰め込んで、パンやらスナックやら珈琲やらを事務所からたんまり運んだんだ。
それからあれやりこれやりし、ほくほく顔で戻ったんだが、ソフティーを見た途端、ちょっとした違和感に面食らった。今度、奴はベッド脇の肘掛けに座っていたんだが、潰れているように見えたんだ。よくあるだろ説教喰らった悪餓鬼が腰をズラして座る形、椅子に座ると云うよりもズッてるみたいな感じ、フライパンから掬った目玉焼きだよ。ソフティーのはそれをもっと酷くした感じだった。椅子に座ると云うより沈んでいる。極端に云やぁ、椅子に呑まれないように必死で肘掛けを掴んでいるように見えた。
『なあ……なんだか随分、具合が悪いように見えるぜ。なんなら医者を呼んでやっても良い。闇医者で口の堅いのがいるんだ』
『気にするな。そういうことじゃないんだ……これは』
『そうかい。でも俺にとっちゃあんたは大事な御仁だ。気に障ったら勘弁な』
『まあ、いい。おまえも座ると良いぜ』
俺も促されるままにベッドに尻を落ち着けたよ。
『……話っていうのはな……』
『うん』
俺はその時の奴の顔を今でも覚えているよ。ちょっとゾッとしたんだ。何故って、指一本触れてもないのに奴の瞼がだらんと下がったからさ――まるで〈あっかんべぇ〉をするようにな。
ソフティーは少し前まで住んでいた下宿の話を始めた。奴は自分で仕事の分量を決めていた。腕が良いから依頼はたくさんあったんだが報酬に目が眩むようなことはなかった。何かちょっと殺しっていうのを普通のビジネスのように考えていた処があったんだな。厭、確かに他の殺し屋でも仕事だっていう奴はいるけれど、ソフティーのとは根本的に違う。
奴は単純に真っ正面から自分のやっている事はコンビニ経営やタクシーの運転手、サラリーマンと同等だと考えていた。だから住処も豪勢なマンションなんかじゃなく、ただ普通のアパートに住むのを当たり前としていた。博打も女もドラッグにも手を出さず、仕事のない時は朝から晩まで図書館を巡ったり、映画を観て過ごすのがあいつの唯一の娯楽だったんだ。一度、金をそんなに使わないで死んだらどうするんだ? って訊いたら全額ユニセフに寄付すると云ってやがった。
奴は本気でそうするつもりだったんだろう。とにかく並みの殺し屋とは毛色が変わっていた。奴は仕事をひとつかふたつ終える度に塒を変えるんだが、最新の下宿にはネズミがいたんだそうだ。鼠と云っても本物じゃなくて三つか四つの女の子なんだけどな。その子は両親と婆さんの四人で外国から渡ってきたんだが親父が博打狂いでね。エスニック料理屋でコックをしていたのが、そこの常連の女と仲良くなって蒸発ちまった。
かみさんも暫くは辛抱してパートの掃除婦やらスナックの店員をしてたらしいんだが、そのうち彼女も店の客とつるんで消えたんだと。残ったのは鯣のようなスカーフを巻いた婆さんと幼稚園に行くか行かないかのチビだけになっちまった。
たぶんソフティーが興味を抱いたのは、ふたりがカタコトの日本語しか話せなかったからだ。でなきゃ危険だからな。婆さんは料理が上手だったそうだ。ソフティーが材料を買い込んで戻るとそれは素晴らしい如何にも手料理、家庭の味ってやつに変身する。
それで奴も多少は娑婆っ気が付いたのか、しばしば買い込んでは飯を作らせる。向こうは向こうで日々の食事代は出るし、その頃にはソフティーもチビや婆さんに多少の土産や小遣いも渡すようになっていたから互いにwinwinの関係になっていたんだな。
チビの部屋はソフティーの部屋の下の階にあった。だから互いのプライバシーは守られていたんだが、やっぱり餓鬼は餓鬼なんだな。チビは寂しさからかソフティーに懐いてきた。奴が部屋で寛いでいたり、婆さんの飯ができるまで時間を潰していたりすると部屋に来るようになったんだ。で、ソフティーも、これが俺が話を聞いて本当に耳を疑ったんだが、よせば良いのにチビが読みそうな絵本の類いを買って置いとくようになったんだ。
勿論、部屋に仕事の匂いがするようなものは一切、置かなかった。万万万が一、警察に踏み込まれた時、そんなものが身近にあったら一発だからな。
――あるたったひとつの例外を除いて、ソフティーは自分が殺し屋だってことを完全に隠せていたのさ。
『或る日、俺が帰宅すると本が動いていたんだ。本ってのは表紙こそ偽装用に聖書と印刷した紙が貼ってあるんだが要は箱なんだ。
そいつを本棚にしまっていた。他の本と一緒にな』
『何がしまってあるんだい』
『奇蹟さ』
『キセキ?』
『ああ……俺が今迄、何度も危ない瞬間を掻い潜りながら綱渡りを続けてこられた力がそこには入っていたんだ。おまえも噂で聞いたことがあるだろう……偽神の剣だ。まあ、剣とは云ってもナイフに近い短刀なんだが、ありとあるゆる悪党どもの血と命を吸い続け、邪悪さが強化されたという穢れの逸品だ。それがしまってあった。俺は仕事に向かう前に必ずそれで躯を刺し、血を流すことにしている。それによってザンメルのカを体内に取り込めると信じているからだし、現にそうなっていた』
『そんなものよく手に入ったもんだな』
『リヴーさ。奴の個人的な仕事を引き受けた見返りにな。謂わば下賜されたのよ、ふふふ』
ソフティーはにんまりと笑ったよ。カーテンの隙間から背中越しに外の光が差し込んで躯全体がふわふわ黴たカステラのように見えたっけ。実際、そんな臭いもするような気がした。無論、その時はまだ本当の事態には気がついてなかったんだが……。
チチ……そのチビの名前なんだけど。ソフティーの奴、チチにカマ掛けたんだ『このなかに偽物の本があるけれど、どれか当てたら玩具を買ってやる』って。チチは三度『ほんと? ほんとにほんと?』って訊いたんだ。よっぽど玩具が欲しかったんだな。
婆さんひとりの稼ぎじゃ、顎と枕を養うのが精一杯だ。 玩具なんて夢のまた夢だ。だからチチは書棚に向かって掌を向けると目をつぶったんだそうだ。餓鬼がやりそうなことさ。超能力だかなんだかで感得できたような子どもなりの〈芝居〉をしたんだな。
そして少ししてから、あの聖書を指したんだと。それで終わりさ。チチはその部屋から生きて出ることはなかった。その場でソフティーが屠っちまったんだ。
『本人は何にも気づかずに逝った。奴の頸骨は鰺の小骨ほどの抵抗もなかった。目を開けて、凝っと俺を見つめたまま。唇が最期に放った〈あ〉っていう形のまま逝っちまった。俺が首に手を伸べたのを玩具をくれる為だとでも信じてたんだな』
『あんた、餓鬼は殺さない主義だった』
『ああ』
『それがなんで』
『ふむ……まあ其処なんだよ。其処なのさチャフ。葉巻持ってないか? 悪いが火はおまえが点けてくれ、指がどうもな。悪いな……サンキュ。そうなんだよ。俺は最悪の体験を自ら拵えちまったんだ。でもな、そうするより他なかった』
『なぜ』
『チビは聖域だ。俺だけじゃなく世間的にも、この宇宙的にも餓鬼ってのは尊いもんだ。奴らの悪さなんて大人のすることに比べたら蝶の鼻毛ほどの罪にもならねえ。そういうもんさ餓鬼ってのは。だがな、だからこそ、強いんだ。俺たちみたいな外道稼業からすりゃ勿論のこと。俺らが依り代にしているものだって、あんなものに近づかれたら木っ端微塵さ』
『ザンメルのことを云ってるのか』
『ああ、そうよ。俺はまだ引退する気はなかった。稼業を安心して続けていくにはザンメルの力が要る。だがな、そんな外道の神様に聖なる餓鬼が触れちまったとなるとどうなる?』
『触ったかどうかまではわからんだろう』
『それは俺も気づいていた。だから俺は本を最初に確認したとき、真っ先に調べたのさ。それこそ祈るようにな……触れてないでくれって……』
『触ってたんだな』
『……刃先の丁度、反りが急に始まる所に小さな丸いぽっちが付いていたよ。迷路のような模様の丸みがな』
『ああ……』
『胃の辺りがズンッと重くなって気分が悪くなった……だが、もう仕方がなかったんだ。俺はザンメルにカを再び取り戻させる為、完全に彼岸に渡る前のチビの心臓に突き立て、血を吸わせなくちゃならなかったんだ』
ソフティは沈んでいるように見えたな。心からさ。あいつは仕事には筋をとことん通す男だった。それが自らの拠り処を壊されてしまった上、餓鬼殺しはしないという掟を破っちまった。チチの躯は奴が持っている穴に埋めたそうだ。あんたらも知っての通り、この稼業の人間はみんな、いざという時の為に自分の穴を山に持っているからな。ソフティーも、奴の言葉で云うならばキチンとチチをそこに埋葬したらしい。
それから奴は警察を待った。当然、チチが居なくなったことに気づいた婆さんが泣きつくはずだからな。事情聴取や身元の確認なんかは奴にとっちゃ朝飯前だ。目を閉じていても運転できるぐらい完璧に策は講じてあった。勿論、部屋には殺しの痕跡なんかは一ミリも残っちゃいない。
ところが翌日になっても、三日を過ぎても何も起きなかった。確かにチチの姿はパズルのピースが欠けたみたいに、その界隈から消えていたんだが、周囲の奴らは疎か警察も動いていなかった。理由は婆さんがチチがいなくなったのは出て行った父親が一緒に暮らすと連れて行ったからだと近所の奴らに話していたからなんだ。
面食らったのはソフティーさ。餓鬼の身に何が起こったのか自分が一番よく知ってるんだからな。何か仕掛けがあるはずだと警戒を解かずにいたソフティーが日帰り出張から戻った態で、手土産片手に挨拶しに行くと婆さんは明日、帰国すると告げたらしい。
『偽の土産を受け取った婆さんはニコニコしてな。噂どおりチチは父親が連れてったと云った。なんだかその穏やかな顔を見ていると、まるで俺のしたことがまるっきりの妄想で、婆さんの云ってることが真実みたいな気がしてきたぜ。本当に奇妙な感じだった』
『もしかすると、婆さんも手のかかる餓鬼がいなくなってホッとしていたんじゃないのか』
『だとすれば話は簡単なんだがな。婆さんは後で茶を入れるからまた来てくれと云ったのさ。これが最後になるから飲みに来てくれと。俺は行くと云った。飯を喰う為じゃない。婆さんの腹の底をもう一度、探る為だ』
婆さんの部屋に行ったソフティーは面食らったそうだ。中はがらんどうでテレビも家具もベッドも全て売り払うか同郷の人間に分けてしまったらしい。空っぽの水槽さ。真ん中に四角い木箱があってその上にチャイを入れたポットとカップが置いてあった。ソフティーは注がれたチャイを呑む振りをしてわざと零して、大袈裟に謝った。
毒入りの可能性があるから当然のことさ。婆さんは入れ直すと云ったんだが、それを押し止めてソフティーは本当にチチは父親が連れて行ったのか? と訊いたのさ。
すると婆さんは、それには答えず、
〈森へ……〉と、ソフティーの頬に触れたらしい。
『森へ? どういう意味だ』
『ふふふ。婆さんはそれだけポツリと云うと電気が切れちまった』
『切れちまった?』
『ああ。両手をだらりと脇に垂らすと、その場にへたりこんじまったんだ。後は何度、声をかけてもうんともすんとも返事をしない。だから俺は部屋に戻った。 翌朝、様子を見に行くと婆さんは消えていた』
それからソフティーは流石に気分を変えようと柄にもなくリゾートなんぞに出かけると、そこで貯めた金を切り崩して過ごしていたんだな。ところが三日目に奴は躯が妙に重いのに気づいた。ホテルの廊下を歩いていて転倒したんだが奴はこの稼業に入ってから不意に転倒
したことなんてなかったんだ。そう断言していた。〈自分から転がる以外、俺は転んだことなんか一度もない〉って。俺なんかはしょっちゅう転んだり、ぶつけたりしてるもんだから、そういうことは誰にでもあるんじゃないかと云ったんだが奴はそれが〈はじまり〉だった
と云うんだ。
『それから段々、躯が重くなるのを感じた。少しずつだが変化は早かった。一日単位の変化じゃない。一時間、厭、分単位で変化は進んでいたんだろう。それも弛むことなくな……俺は次第にベッドから起き上がるのにも困難を感じ始めた。医者は嫌いだった。ホテルの医務室で薬は貰ったが後は気力だ。またそうしなければこの稼業はオシマイだ。正直な処、俺は自分に起きていることを知りたくもあり、知りたくもなかった。ところがある時、珈琲を呑もうとコップを持ち上げた途端、うっかり手が滑ってな、部屋の床に落としちまったんだ。しっかり掴んでいたつもりだったが、右手を見ると指があらぬ方向に曲がっていた。まるで爪の付いたバナナの皮のようだったぜ。それに掌もクレープみたいにタルンタルンになってやがった。餓鬼の頃以来だな、あれほど魂消たのは……』
『どうして』
『痛みは無いんだ。それに暫く眺めていると花が萎むように、あべこべを向いていた指がまとまって元通りになった。もう一度、指を動かすと手の甲で親指と小指がくっつきやがった。それも重なってな。他の指もいくらでも曲がるのさ。俺は莫迦みたいに暫く自分の指を曲げて遊んでいたんだ。が、そのうち躯の他の部分がどうなっているのか気になり、足の指でも試してみた。同じだった。手指ほど曲がるわけじゃないが、甲の方にぴったり引っ付くほどに倒れる。それにな、そんなことに熱中しているうちに肘がおかしなことになってきているのに気づいた。指を曲げている右肘が内側に曲がってたんだ。俺はいきなり噴き出しちまった。なんだかとてつもない莫迦げたことが起きているんだからな。鏡の前に立つと俺は躯を強く捻ってみた。するとどうだ。腹は皮がねじれて、まるで絞った雑巾みたいに俺は一回転して正面を向くことができたのさ』
『なんでそんなことになったんだよ』
『まあ、慌てるな。その時点じゃまだ俺はそんなに困っていたわけじゃない。ただ躯がふわふわして力が入りづらいのと重いものを持つのに気合いが必要になっただけでな。本当に何とかしなくちゃと思ったのはその先さ』
『何があったんだ』
『カジノのポーカー台で少しばっかり勝っていた処に淑女が来たんだ。五万で一晩と云うから、そんな端金ならと俺はOKした。少しは気晴らしもしたかったしな。女は若作りをして三十代だと嘯いていたが所謂、全身どんぶり整形のサイボーグでな。香水越しの体臭は四十路五十路たっぷりって処だった。だが俺は別に奴に営業させる気はなかったから金は払うから話し相手になれと云ったよ。奴は喜んで、それこそ古い話を随分と聴かせてくれた。ドラッグと酒、女はしこたま呑んで、上機嫌だし、俺も少しは飲った。それからふたりでベッドに入った。ままごとみたいなセックスをし、いつのまにか寝込んでしまった。その時、腕枕というか、女を抱えるような恰好で寝ちまったんだな。暫くすると何かが鳴ってる気配で俺は夢から浮上しだした。目を開けると寝たまま女が叫んでやがったんだ。俺と女は同じ方向を向いていた。そこには豪華なドレッサーがあって大きな鏡が載っていた。ベッドが丁度、映るのさ。そこへ、口を押っ広げて悲鳴を上げている女が居た。そしてその顔の下に俺が居たんだ。どういうことかわかるか? 女の顔の重みで俺の顔は潰れていたのさ。ビニール製の人形みたいにな。身の回りのものを掴むと、女は出走馬のような勢いで廊下に飛び出してったよ。ふふふ。ひとり残された俺はベッドに身を起こすと顔に触れた。凹みは現実だった。遊園地なんかにある歪んだ鏡そのままに凹んでいたんだ。俺は立ち上がってバスルームで確認することにした。右の爪先が毛足の長いカーペットに引っかかって踵まで丸まったのを感じたが、俺は気にしなかった。俺は鏡のなかに自分を材料に作った〈ぐい呑み〉を見た。右目は凹みの中になって鏡には映っていない。凹んだのは額から鼻に斜めに線を引いた部分で左目だけがぎょろついていた。俺は凹みの中に手を入れてみた。すると奇妙なことに井戸のなかから覗くように自分の手が近づくのを〈右目〉が見たんだ。全く、奇妙な光景だったぜ。俺は右耳と頬を摘まんで、なんとか凹んだ部分を戻した』
『流石に医者に行ったんだろうな』
『厭……医者は信用ならんし、そもそも嫌いだ。代わりに調べた。腕っこきの奴らを三人雇ってな。思い当たる節を片っ端、根刮ぎ。予想外に銭はかかったが。それでも徐々にわかってきたのさ』
『わかってきた? なにが』
『婆さんさ。ふふふっ。魂消たことに、ご同業だったのさ』
『なんだと?』
『金で殺しを請け負うのよ。尤もやり方は全く別だがな。奴らの一族は所謂、呪術師だったんだ。婆さんが俺の頬に触れたときに〈森へ〉と云ったと話したろう。あれは〈森へ〉じゃなく、正確には〈mollescet〉と云ったのさ。ラテン語だ』
『それはどういう意味なんだ?』
『ふふふ……はははは……全く、お笑いだ。俺がソフティーと渾名されているのは、稼業を始めた当初、女が寄ってくるほど面が甘ったるいって意味だったが……。婆さんが云ったのも同じことよ。モレシェってのは〈柔らか〉になれって事だったんだ。その言葉通りになっちまってるんだ』
『医者には……』
『莫迦なことを繰り返すな。俺に必要なのは医者よりシャーマンだ。だが、この呪いを解ける奴は見つかりっこないし、そもそも止めることはできても元に戻せる筈はない』
『じゃあ、どうするつもりなんだ』
『死ぬのさ。当たり前じゃないか……こんな形で何ができる。やがて俺は海月のようにベロベロになっておしまいさ。覚悟はできている。ただそれをおまえに見届けて貰いたい』
『……俺に』
『そうさ。それで賭場や酒場のジョークにして語り継ぐんだ。こんな奴がいたんだってな。都市伝説っぽくて良いだろう。おまえは嘘つき呼ばわりされるだろうがな』
趣味の悪い話だったが奴は本気だ。それから俺は死ぬまで面倒を見ることにした。三日もするとひとりで歩くことはできなくなっていた。厭、ふたりでも無理だった。なにしろ躯全体がぶよぶよしていて介助しようにも文字通り〈掴み処〉がないんだ。例えば躯を起こそうと背中に手を回しても、持ち上げた処だけしか上がらない。腹や胸、首までがゼリーのように、たわわに揺れて、てんでばらばらになっちまうんだ。正確には〈垂れる〉って感じがぴったりだ。奴は日がな一日、ベッドで〈拡がってる〉しかなかった。そして日がな一日、『ミツバチのささやき』とか『グッドフェローズ』とか『バタリアン』とかのDVDを繰り返し見ていたよ。終いには指がぺこぺこでリモコンも押せなくなったんでオート再生にしてやった。飯は喰わなくなっていった。歯も歯茎から浮いて吐き出しちまって。奴はそれをベッドサイドに並べていた。マックシェイクのバニラばっかり呑んでたな。ハンバーガーも好きだったんで食わせていたけれどピクルスどころか肉のパティも歯茎で噛み切れず上顎が凹むと云って止めた。フライドポテトはもっと前に諦めた。案外、あれは固いんだな。その頃になると本当の意味で人間ぽさが無くなっていった。肌色の大きな海月か、水を入れた風船みたいな状態だったんだ。不思議なことに全然、痛がってはいなかった。一度、ソフティーが真面目な顔をして、自分の状況について語ったことがある。
奴は〈使命だ〉と云ったんだ。何のことだかわからなかったけど、あいつは俺がわかろうが、わかるまいが全く関係ないといった風情で鼠の小便のシミがあちこちに浮いた天井を睨んで呟いた、〈使命だ〉ってな。
もうその頃には、どう見ても人の顔が印刷してある大型のシートか、もっと妙な云い方をすりゃあ人型に抜いた大きなトーストのようになっていたな。表面はぬらぬらしてバターを塗ったようになって広々、ベッドに拡がっていた。もう食事も取らなかったな。奴は凝っと冬眠を待つ蛙のように死を待つ態勢に入っていたんだ。
一週間ほど、奴はこっちが何かを問いかけても応答しなかった。死んでいるのかとベッドを覗くと、うっすら目を開け〈まだ死んじゃいないぜ〉という風にふっと嗤う。なんだ生きているのかと、こっちは黙って頷き、それから部屋を出る。この繰り返しさ。
ところがある日、部屋に入るとベッドに大きなシミだけ残して奴の姿がなかったんだ。
俺は面食らっちまってさ。驚いた拍子に屁をしたんだ。そしたら頭の上から薄ら笑いがした。見上げると奴が天井に貼り付いていた。肌色の蜘蛛の巣みたいに伸びきってな。
『おどかすなよ。おまえ、自力でそんなとこまで行ったのか』
『ああ。今朝から嘘のように気分が良くなってな。何か動けそうな気がしたから試してみた。ここまでできるようになるまで一時間もかからなかったぜ』
奴はそう云うとまた天井からダラーッと牛の涎みたいに垂れ下がり、ベッドに戻った。それからまた俺に天井に貼り付くやつを見せてくれたんだ。驚いたことに水中の蛸みたいに素早かった。一瞬でベッドから天井、壁から壁にビュッとロケットみたいに貼り付く。どうなってるのか訊いたけど、本人にもよく判らないようだった。それから奴は腹が減ったと云いだして俺に蜂蜜を買ってこさせると塗れと云ったんだ。そうさ、もう口から栄養を取る必要は無いんだって。ただ躯の表面に刷毛で塗ってやるだけで奴は大満足だったよ。味はよく分からないが、すごく落ち着くんだそうだ。
それから三日ほど経つと今度は本当にいなくなっちまった。天井裏から排水溝まで覗いたんだが蛻の殻だった。まるで狐につままれたような気持ちになったけど捜索願を出すこともできないから放っておいたんだ。そしたら十日ほどしてまたベッドの上にいたんだ。部屋の壁が泥で汚れていて酷い臭いがした。
『どこ行ってたんだよ。臭いな。なんの臭いだ』
『殺しだ』
『え?』
『婆だ。絞め殺してやった』
『婆? おまえに呪いを掛けたあの婆さんか?』
『そうだ。あいつ国に帰ると云いながら近所の仲間の処に残ってやがった。 やはり妙な婆だったぜ。俺を見ても眉ひとつ動かさなかった。ただ〈来たか〉とだけ。まるで俺がやってくるのを待っていたかのような感じで。何の抵抗もせず、餓鬼同様、アッという間に死にやがった。手応えのない詰まらない殺しだが、俺には意味がある』
『よく居場所がわかったもんだ。どうやったんだ。第一、どうやって出た。おまえはドアノブも回せないじゃないか』
『浴室の排水溝を使ったのさ。ある晩、あそこから声が聞こえたんだ。 人間の声じゃなかったけどな。俺には言葉の意味が理解できた。 あそこの店には残飯がたっぷりあるとか、コンビニの裏は野良猫が棲み着いていてヤバイとか……』
『なんだそりゃ』
『鼠の世間話だよ。俺はそれを聴きに行ったんだ。排水溝を使ってな。それから少しして試しに婆さんの居場所を訊いてみた。そしたらたちどころに教えてくれたよ。奴らのネットワークは大したもんだ。街のありとあらゆる事を奴らは知っている』
『おまえ……やっぱり、オツムがいかれちまったんじゃないのか?』
『そうかもしれん。だがな俺はおまえと組んでひとつやらかすことにしたんだよ』
『なにをだ?』
それからさ、俺とソフティーでリヴーを通さず内職を始めたのは。方法は簡単だった。仕事は奴が仕込む。俺が依頼人に直接会って『あんたが消したい人間を消そう』と持ちかける。相手は怪しむがソフティーが入手した確度の高い情報を伝えれば相手は俺が本物の殺し屋だと信じる。金額はソフティーが決めていた。話が決まれば、後は俺が奴を箱に入れて標的のいる場所に最も近い所まで運ぶ。箱から出た奴は下水道や排水溝に潜り込む。俺は予め決めておいた回収場所で待機。奴が戻ってくるとまた箱に詰め戻す。これだけだ。仕事が済むと依頼人には報酬を記入した小切手を枕元に置いておくように云う。朝になって依頼人は自分の寝室から小切手が消えているのに気づく。それだけで奴らは俺たちを裏切ろうという気はなくなる。
確かに今迄にない行動を俺たちは取り始めたな。体調がよくないとか気が変わったとか、あんたらの仕事をキャンセルすることが増えたからな。だけど俺もまさかソフティーがリヴーの仕事を横取りしてるなんて夢にも思わなかった。だけど冷静に考えたらそれしかないんだよな。あんな躯で新規のルート開拓なんてできないし、俺だってそっちの方面は素人同然なんだから。ソフティーにとっちゃリヴーと衝突するのを覚悟の上でやるしかなかったんだろう。でも仕事のペースはのんびりしたもんでひと月に一件か二件が関の山だった。別に大金持ちになろうなんて気はなかったし、金はシンドイ仕事をしなくて済む程度にあれば充分だったんだ。
ところがある夜、奇妙なことが起きたんだ。 仕事を終えてモーテルに戻り、箱に入ったソフティーをベッドの上に開けた時、声がした。
『――どうしようもない』
俺もソフティも全く無防備だったんで度肝を抜かれたよ。俺なんて腰かけようとして椅子からずり落ちたぐらいだ。
浴室のドアの前で、ひとりの男が椅子に座っていた。猟師のようながっしりした体格で顔中を固い髭が覆っていた。一瞬でゴムのように伸びたソフティーは男の顔に貼り付こうとしたな。でもダメだったんだ。男が手を振るとソフティーはぺしゃんと床に叩き付けられて、そのまま力が抜けてしまったようにへなへなになってしまったんだ。 それと躯全体が薄青い光で覆われ、失神したみたいになっていた。
男は素手でソフティーを掴んで床からベッドに放り投げた。ソフティーの顔が泣いているように見えた。ふたりとも殺されると思った。リヴーが放った殺し屋だと思ったんだ。ところがそうじゃなかった。男はまた椅子にドッカと座り直し、大きな革のジャケットの懐からパイプを取り出して火を点け始めたんだ。 沈黙が続いた、誰も喋らなかった。俺も椅子に座り直すのが精一杯だった。何か男の存在そのものに打ちのめされていた。それぐらい男は部屋中を圧倒していたんだ。パイプから煙を二、三発吐いた処で男はまた口を開いた。『どうしようもないな』
だから俺は『あんたは誰だ? 何がどうしようもないんだ?』って訊いたよ。そしたらあいつはベッドのソフティーを指差して首を振った。『救いようのない莫迦だ』それからまた沈黙。煙だけが部屋のなかに充満していった。やがてソフティーが『何が望みだ』 と云うと男はまたジャケットを探り、小さな石のついたネックレスを取り出した。『これはおまえが殺し、秘かに埋めたと思っている娘のものだ。我が部族に伝わる方法で正式に作成された。全ての邪なものを祓い、良き生を約束する守りだ。おまえが俺に触れることができなかったのも』男は自分の首に掛かっている同じような石のペンダントを見せたよ。『これのせいだ。おまえらの信じるものとは別の法則がこの宇宙にはある。我が部族はその法則を尊ぶ』
あんたが娘の父親なのかと尋ねると男は首を振った。『両親という概念は子どもを孤立させる。我々はそのような考え方はしない。子どもは皆のものだ。また大人は子ども全部のものだ』。ソフティーが「用件を云え』と苛ついた声を上げた。男はペンダントをソフティーの側に放った。『それはおまえのものだ。あの子がおまえにと作ったのだ。おまえは大切にする義務がある。その守りは女子が一生に一度しか創れない神聖なものだ。娘はおまえのことを本当に好いていた。あの子はおまえが幸せで良い人生を送ることを願った。どんなにおまえが邪悪な人間か見通せず……』
石に触れた途端、ソフティーから苦悶の声が上がった。見ると奴の体の一部から煙が上がっていた。『娘が死んでも石の効力は衰えていない。下衆にキャビアとはこのことだな』男は立ち上がった。痛みを堪えながらソフティーが訊いたよ。『何故、俺に渡す? 復讐なのか?』って。すると男はいきなり盛大に咳き込み始めた。が、そいつは咳じゃなかった。奴は嗤ったんだ。俺たちがそれに気づくのは少し経ってからだった。 そいつは真顔に戻って唇についた涎を拭うと『やれやれ』と、また首を振った。『全く救いようがないな』って。それからこう続けたよ。『復讐とは良心が創り出す糞だ。婆は哀しみのあまり一族の戒めを忘れ、おまえを呪詛した。故に婆はおまえの復讐を受け入れた。彼女は自ら戒律を破った己を潔く屠らせたのだ』
それから男は部屋を出ようとした。奴はまるで目に見えない城壁を纏っているようで俺たちは全く手出しができなかった。が、奴は掴んだドアノブを一度、捻って、止めた。
それから独り言のようにソフティーに向かって云ったのさ。
『ひとつだけ訊く。なぜ全く無害な娘を殺したのだ』
『あいつは黙って俺の大切な守り刀に触れたからだ』
『なぜ、それがわかる』
『刃先に指紋が残っていた。俺はいつもそれを鏡のように磨き上げていたんだ』
『貴様は無様なほど無知だ。また救いようがないほど愚かだ。それは娘の指紋ではない』
『なぜだ』
『……我が部族には男は九歳、女は七歳まで死兆に囚われぬよう薬草によって指紋を消す伝統がある。娘もそれを施されていた。おまえが見たのはおまえか、或いは別の人物の指紋だ……莫迦め』
5
チャフはそこまで話すと一旦、咳き込んだ。
――暫しの沈黙。
「それで?」と、おれ。
チャフは少し考えてから「それだけさ……」と云った。
「ハ」マンズが頓狂な声を出すと手を叩いた。「それじゃあ餓鬼を殺したのも、テメエが躯をくにゃらせたのも何の意味もねえじゃねえか? 餓鬼の方こそ良いとばっちりだぜ。救いようのねえおっちょこちょい野郎だな。てめえの兄貴ってのは」
「そういうことじゃないんだ。男の云うことに間違いがなければ餓鬼に指紋はないんだ」
「じゃあ、別の誰かが付けたんだろう。ソフティーのいない間に部屋に忍び込んだりして」
「それは不可能だ。現役の頃の奴にそんな隙はない。万が一、そんなことがあったとしたら何故、そいつはザンメルを盗まなかったんだ? わざわざ命を懸けて侵入して空手で帰る必然は?」
おれが訊いた。
「結論を聞こう」
「ソフティーは指紋はなかったんだと云った。指紋はなかった……が、指紋はあったんだ」
「はあ?」 マンズが声をあげた。
「心がそう見させたんだ」
「錯覚だと? あいつが? ソフティーが?」
「ソフティーは、チチと婆さんと付き合ううちに化石のように自分の意識の深層の白亜紀以前にまで埋めたつもりのものが知らず知らずに発掘されてしまったんだなと俺に云ったよ。そしてそれが自分の危機に繋がることを察知した無意識が自己防衛として彼に幻視を送ったんだ」
「莫迦こけ」マンズが鼻で嗤う。「寝言は寝て云え」
おれはそれを無視して訊いた。
「だが指紋が本物ならば拭き取るまでは残っていたはずだ」
チャフは首を振った。
「ナイフは即座にチチの為に使われた。血を拭ってしまえば指紋があったかどうかはわからんよ」
マンズは立ち上がるとチャフの前で腕組みをして立った。
「間抜けな弟に頓馬の兄貴とくらあ。自分で墓穴を掘ってりゃ世話ねえや。さあ、てめえもそんな兄貴に何時迄も義理立てするなんて阿呆なことは止しにして、さっさと塒を白状ったらどうだ? そしたら少しは楽に死なせてやるよ。それともそんなに命が惜しいか?」
「命が惜しいわけじゃないが…」
チャフは後ろ手に縛られたままマンズに顔を向け、皮肉気な表情を浮かべた。
「産み落とした我が子を踏み殺したくなるほど唾棄された莫迦に殺されるのは、ちょっと」
チャフの言葉にマンズの顔が文字通りドス黒くなった。
「何が云いたいんだテメエ」
「おまえの詰まらない与太話で耳が腐ったと云ったんだよ。ビンタはおまえの餓鬼なんかこの世の中にひり出したくはなかったのさ」
マンズが何処からか手袋を取り出し、右手に填めた。埋め込まれた剃刀の刃が天井の灯りでキラキラと反射した。
「チャフ、あまり興奮させん方が良い。マンズは今でこそ道具屋だが、この業界に入った当初は拷問方を希望としていたんだ。素人時代から手の付けられない嗜虐性向なんだぞ」
「ガス、もう遅いぜ。俺はもうギンギンにスイッチが入っちまったよ」
マンズの唇の端から涎が糸を引いて胸元に落ちた。股間が膨らんでいたのでおれは目を逸らした。醜いモノは嫌いだった。
ビッと皮を裂く音がすると手袋の動きに連れて剃刀がチャフの顔の上に赤く深い谷間を刻んでいった。下手な隈取りのようなものが残った。
「その厚い面の皮を剥いでやる」
「おい。マンズ、いいのか? おまえはチャフからソフティーの居場所を聞き出すんだろ?」
「頭の皮を剥いだぐらいじゃすぐに死にゃしない。半日は保つさ。その間に四川を喰わせてやろうと思うんだ。剥ぎたての肉の上に花椒をたっぷり使った麻辣汁を塗り込んでやる。それから顔中に針鼠のように釘を刺してから電気を流してやるんだ」
興味なさげに聞いていたチャフが云った。「……マンズ」
「なんだ……もう命乞いは無駄だぞ。もうおまえの兄貴のことなんかどうだって良いんだ」
「やけに臭いが顔に付いている穴は公衆便所か? おまえを相手にする風俗嬢に同情するよ」
その瞬間、マンズの剃刀手袋が確実にチャフの喉前――つまり、気管と食道部に走るのが見えた。仰け反りだした頭部によって切断面が大きく口を開けた。血が滝のように白い喉を奔り落ちる。脊髄が自重で折れる音が響いた。チャフの首は後頭部の皮で繋がったまま半分、落ちかかっていた。
「莫迦野郎……」マンズがそう云った途端、なにか起こった。
おれがハッとしたのはチャフの食道丸出しの首から何かが射出されたからだった。
それは巨大な自動傘のようにマンズの眼前で拡がると、その上半身を覆った。
被せられたマンズは、くるくるとその場で無目的に回転し、逃げ出すように移動した。が、その動きは躯に火が回った者のように緩慢で、椅子や今はいないチャフや、壁にぶつかるだけだった。マンズは袋のように奴を包んでいるものを内側から引き剥がそうと両手で万歳するようにしたり、シャドーボクシングのように動かしていたが、やがてその動きも小さくなり、バタリと倒れ込むと痙攣的になっていく。
間違いなくマンズを包んでいるのは――ソフティーだった。
「そんな処に隠れていたとはな」おれはチャフの抜け殻に目を遣った。「見つかるわけがない」
ソフティーはまだマンズから手を抜けないのか軽く『うふふふ』と嗤って返事をするだけだった。やがてドスドスとマンズが床を蹴り出した、が、その動きもやがてゼンマイ仕掛けの人形のようにゆっくりとなり、一、二、一、二と数えられるように間遠になった。
ソフティーは全体が白っぽい飴のように変化していた。
「さっき、笑ったように思えたが、口が利けるのか」
『ああ。どうもそのようだ……久しぶりだな。ガス』
「二年ぶりか」
『四年だ。ディズニーの裏で密告屋を屠って以来だろう』
「ああ……そうだった。もうそんなになるかな。あの頃のおまえはハンサムボーイだったのにな」
『墓穴を掘ったんだ。仕方がない。ちょっと、こいつしぶといな』
時折、まだマンズはソフティーの中で暴れるように痙攣した。
「まだ時間はかかりそうか?」
『厭、直だ。いつもならもっと早く始末できるんだが……こいつはワザとゆっくり窒息させてる』
「苦しめるためにか?」
「ああ。そんな感じだ。ビンタはこいつが大嫌いだったんだ。こいつは彼女が金に困っているとニタニタ笑いながら擦り寄っては淫売をさせていたんだ。口が臭くて、おまけに穴を開けた避妊具を使いたがる。ロシアンルーレットだとかなんだとか屁理屈つけてな」
「サイテーだな、おい」
「その通りさ」
おれたちが話していると動きを止めていたマンズが盛大に屁をひった。
「今のは?」
「死んだよ。これは断末屁だな」
そう云うとソフティーはマンズを放し、マンズはずるりと床に拡がった。
その時、呻き声を上げたので、おれは〈どうかしたのか〉と訊いた。
「痛いのさ」と奴は呻いた。
「完全にとろけちまったんだろうな。なのに神経だけはびんびんしてる。俺は外皮がないと生きていけない躯になっちまったんだ」
「それでチャフに潜り込み、栄養を取っていたんだな。それで奴がガンジーになった理由がわかったぜ」
「胃も腸も内臓がどうなってるのか、知るよしもねえが。俺は口は使えないんだ。皮膚から直に栄養を取るようになってる。外に出ていて俺が喰えるものはひとつしかないんだ」
「なんだ?」
「チャフに寄生する以前、下水を随分と這いずり回っちまったせいだと思うが……糞さ。人、鼠、犬、猫……糞なら何でも良いんだ。躯が温まってホッとする。昔なら考えられんことだが、今はなんとかそれでしのげるようになった」
「獲得形質ってやつか?」
「たぶんな」
「おれは今つくづくおまえの立場じゃなくて良かったと思うな。それはとんでもない呪いだよ」
おれが云い終わるとソフティーの形が微妙に変化したのに気づいた。てっぺんにある顔が明らかにおれを狙っていた。
「ひとつ質問がある」 おれは一歩下がった。
「おまえは次の宿主を決めているのか? それとも暫くは下水で鼠の糞を喰って暮らすつもりか?」
「まさか。早く暖かくて湿った場所でぬくぬくしたくて、うずうずしてるよ」
「だろうな……」
「ガス。俺は一度、おまえになってみたかった」
「なぜ」
「リヴーの近くにいられるからさ。奴はおまえ以外を容易に近づけない。おまえを乗っ取って奴に近づき、奴を喰いたい」
「なぜ」
「別に深い意味はない。ただ不可触な奴の鼻を明かしたいだけさ」
「おれに寄生するとおれを思いのままに動かせるんだな」
「そうさ。普段は自由にしてやるが、使いたいときは脳を奪取する」
「となると随分、間抜けな話だな。易々とマンズに捕まって拷問されるとは」
「マンズはしつこい。いつかは屠らなきゃならん相手だった。チャフはそろそろ残り滓状態だった。 乗り換え時期だったのさ」
「おまえはマンズに乗り換えるつもりだったのか」
「厭、おまえだよ、ガス」
「何故、おれがここに来るとわかった」
「ふふふ。云っただろう俺には人間にはわ らない情報網があるってよ」
ソフティーがずるりとおれに迫った。
「やるのか?」
「息が苦しくなって口を開けた瞬間に潜り込ませて貰うよ。 痛くはない……筈だ」
おれはポケットのなかの女物の護身用小型ピストルを握り直した――全く、リヴーには畏れ入る。
身構えたソフティーにおれはその銃を向けた。
「ふふふ。ガス、残念だが俺に銃は効かない。なんでも伸びて受け止めちまうからな。それに使うにしてもマグナムか対物ライフルにしろ」
「おれもそう云ったんだがリヴーがどうしてもこれを使えと云うんだ」
「リヴーが?」
「そうさ。おまえはきっとこいつが気に入るってな」
「どういう意味だ?」
「弾が違うんだよ……ここから射出されるのは、おまえがホテルに残していった歯を加工したものさ。謂わば、おまえの躯の一部でおまえを撃つということだ。それもおまえが唯一、融合できなかったものでな」
ソフティーの全身が白っぽく変化した――青褪めたのだろう。
おれは構えた。
「よせ」
そう云った途端、ソフティーは今迄見たこともない速さで戸口に跳んだ。
おれは追ったが出口のドアが見えた処で銃を下ろした。
――ダムが立っていた。悲鳴を上げようと丸く開けた口のまま、そしてその奥にソフティーの一部が滑り込むのが見えた。
「鍵はかかっていなかったのか」
二秒ほど遅れて女の声が返ってきた。
「そのようだ」
――全くマンズって奴は――と、おれとダムは声を合わせた。
そして、どちらともなく薄く笑った。
「ガス、おまえを乗っ取る必要がなくなった。それでも屠り合うというなら 俺はやる」
おれは腕時計を確認した。
「残業になるな······おれは残業が嫌いだ」
細い皺々の手が伸ばされた。「じゃあ、仲直り。握手しましょ」ダムの声だった。
おれはそれを握りかえし、ドアから出て行くダムの背に云った。
「次に会うときは屠り合いになるぞ」
ダムは振り返らず、ひらひらと手を振って去った。
おれは地下室に戻り、空っぽの袋のようになったチャフと驚いたような顔のまま斃っているマンズの前を過ぎるとテーブルの卵を回収した。
携帯が鳴った――リヴーの声がした。
『……初回にしては上出来だったな、ガス。この調子だ。今日は休んで次の指示を待て』
おれは無言で頷くとリヴーより先に通話を終わらせた。
「まだやるのかよ……」
傍らの木の箱に腰かけるとおれは煙草を取りだし、吸った。
灰は掌に落とす――柔らかな熱が心地よい。死体があるが、室内は静かだ。通りは腐ったまま動かない。妙に気がざわざわした仕事の後、おれは自分をこうすることが多い。でないと脱いだ靴下になったような気分で歩かなくちゃならない。それは危険だ。
と、また電話。
いつものように名乗らずにいると掠れた声がした。
『ガス……おまえ、ヤバいぞ』
人を使ってバッグや小物を作っているプレハブだった。奴はポン中だったが気の良い奴でおれはたまに金を恵んだり、飯を喰わせたりしていた。
「なにが……」
『ノイの奴らが血眼になって捜してる。街から出ろ!』
「どうして」
おれの問いに大きな舌打ちと呻き声が続いた。
「公開処刑に掛けられたんだよ! 賞金首だ!』
今度はおれが呆気に取られる番だった。
「なぜ」
『リヴーを殺ったろ! なんでそんなことしたんだ! あんなに信頼されていたのに!』
おれは咄嗟に【冗談だろ】と茶化そうとして止めた。
プレハブにそんな機知も趣味もない。こいつの世界には整数しかない。曖昧さや暗喩といった小数点の世界にいない。
ということは、おれはいま半ば死んだことになる。
ありとあるゆる金のために人殺しをしたい奴らがおれを猟犬のように追っているのだ。
『また連絡する』
プレハブの返事が来る前におれは通話を切り、立ち上がると外に出た。
――リヴーは殺された。
死ぬはずのないような男が死んだ。
殺したのはおれだという。が、それは嘘だ。
ならばおれが直前に会話した相手は誰だ。
――あれは紛れもなくリヴーだ。
それだけは確実だ。
voll-Softy end
プロフィール
-
平山 夢明 (ひらやま・ゆめあき)
1961年神奈川県生まれ。94年に『異常快楽殺人』、続いて長編小説『SINKER―沈むもの』『メルキオールの惨劇』を発表し、高い評価を得る。2006年「独白するユニバーサル横メルカトル」で第59回日本推理作家協会賞短編部門を受賞。同名の短編集は07年版「このミステリーがすごい!」の国内第一位に選ばれる。09年に刊行した『ダイナー』で第28回日本冒険小説協会大賞と第13回大藪春彦賞を受賞。『ミサイルマン』『他人事』『暗くて静かでロックな娘』『デブを捨てに』など、著書多数。
新着コンテンツ
-
連載2026年03月13日
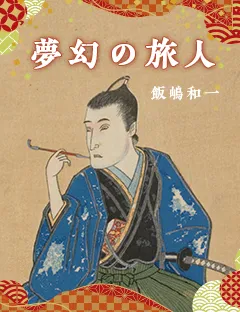 連載2026年03月13日
連載2026年03月13日夢幻の旅人
飯嶋和一
平賀源内の生涯を描く歴史大長篇。
-
インタビュー・対談2026年03月12日
 インタビュー・対談2026年03月12日
インタビュー・対談2026年03月12日トークイベント 永井玲衣×後藤正文「いまことばとは」
永井玲衣さんと後藤正文さんが言葉を通して今を考えるトークイベント「いまことばとは」の様子を再構成してお届けします。
-
お知らせ2026年03月06日
 お知らせ2026年03月06日
お知らせ2026年03月06日すばる4月号、好評発売中です!
特集のテーマは「道をゆく」。椎名誠さん×高田晃太郎さんの対談、駒田隼也さんの紀行ほか、小説、エッセイなど一挙16本立てです。
-
インタビュー・対談2026年03月06日
 インタビュー・対談2026年03月06日
インタビュー・対談2026年03月06日椎名 誠×高田晃太郎「自由に人は生きられる」
最新刊は逃避行がテーマの椎名誠さん。ロバを相棒に旅をしている高田晃太郎さんをお相手に、おふたりのこれまでの旅を振り返っていただきました。
-
新刊案内2026年03月05日
 新刊案内2026年03月05日
新刊案内2026年03月05日たったひとつの雪のかけら
ウン・ヒギョン 訳/オ・ヨンア
韓国を代表する作家のひとりウン・ヒギョンが、生きる孤独と哀しみ、そして人と人の一瞬の邂逅を描く、6篇の珠玉の短編集。
-
新刊案内2026年03月05日
 新刊案内2026年03月05日
新刊案内2026年03月05日劇場という名の星座
小川洋子
劇場を愛し、劇場を作り上げてきた人々の密やかな祈りがきらめく豊饒な短編集。

