
内容紹介
ここは生と死の「狭間の世界」。
あなたと私、二人だけの。
目覚めると、世界に二人きりとなっていたサチとワタル。二人の部屋はいびつにくっつき、誰もいない街は静まり返っていた。
そして不意に現れた管理人を自称する女に、ここは生と死の「狭間の世界」だと告げられる。二人の肉体は、今まさに死を迎えようとしている、と――。
そのまま「完全なる死」を迎えるはずだった二人だが、奇跡的に現実世界へ戻るチャンスが訪れる。
残酷な選択とともに。
私は、俺は、何のために、誰のために生きるのか。
生きることを真摯に見つめるエモーショナルな長編小説。
プロフィール
-
行成 薫 (ゆきなり・かおる)
1979年生まれ。宮城県仙台市出身。東北学院大学教養学部卒業。2012年「名も無き世界のエンドロール」(「マチルダ」改題)で第25回小説すばる新人賞を受賞。本作は21年に岩田剛典と新田真剣佑の共演で映画化された。同年『本日のメニューは。』で第2回宮崎本大賞を受賞。著書に『僕らだって扉くらい開けられる』『彩無き世界のノスタルジア』『稲荷町グルメロード』『立ち上がれ、何度でも』などがある。
【書評】 敷かれたレールをぶっ壊す勇気はなくても
評者・藤田香織(書評家、エッセイスト)
たとえば。やおら突然、誰かに「何のために生きているのですか?」と問われたら、あなたはどう応じるだろうか。
叶えたい夢がある。やりがいのある仕事がある。守りたい家族がいる。そんなふうに明確な答えを持っている人は、果たして今の世の中にどれくらいの割合で存在しているのだろう。
本書の主人公のひとりであるサチ(久遠幸)は、作中でこう口にする。「毎日、同じような日が来て、毎日同じようなことをして、それって私、生きてる意味あるのかなって思っちゃって。明日もまた同じ世界にいるなら、いっそのこと、もう死んじゃってもいいんじゃないかって」。
どうしようもない絶望を抱え「死にたい」わけじゃない。でも「生きている意味」がわからない。この気持ちを「わかる」と思う人は、実は案外、多いのではないだろうか。
物語は、サチがある朝、自宅のリビングで見知らぬ男と出会う場面から始まる。単なる習慣で発した「おはよう」の言葉に、思いがけず返ってきた聞きなれぬ声の「おはよう」。恐る恐る「どちら様でしょうか?」と聞けばワタル(伊達恒)と名乗った男は「そもそも」「ここはどこなんだろう」と問い返してきた。
となると、記憶喪失かタイムスリップかと想像しがちだが、読み進めていくとそうした展開ではないことが判ってくる。サチが両親と暮らす都心のタワーマンションの自宅と、ワタルがひとり暮らしをしていた築二十五年、家賃六万五千円のアパートの部屋が、突然融合してしまったという謎の状況。外へ出てみればふたり以外の人影はまったく見あたらない。街の様子もめちゃくちゃに変わっていた。住宅地のなかにいきなり高層ビルが生えている。とはいえ、隕石が落ちてきたとか爆撃を受けて崩壊したという雰囲気でもない。この状況は一体、どういうことなのか─―。
時空が歪んだ明らかに異常な世界に置かれたふたりの様子を〈狭間の世界〉として描きながら、合間にサチとワタルがそこへ至るまでの状況が、周囲の人々の視点によって語られていく。美容師をしているワタルの顧客、長患いで働けない夫を介護しながら働く母親、行きつけの焼き鳥屋の主人、勤務しているヘアサロンのオーナー。サチがコネ入社であることを知っている勤務先の先輩、過干渉な専業主婦の母親、お嬢様学校時代からの親友、勤務先の女性上司。やがて、ふたりを繋ぐ人物も現れ、少しずつ〈狭間の世界〉に至った経緯が見えてくる。
そうした周囲の人物の証言から明らかになるのは、ふたりが生きてきた足跡だ。生活に困窮している実家のために仕送りを続け、人も羨む天性の才能をもつ上に厭わぬ努力を重ねトップスタイリストへと駆け上がったワタル。何不自由なく育ち、父親が顧問弁護士を務める一流企業に入社し、与えられること、保護されることにジレンマを感じながらも動けずにいるサチ。それぞれが置かれた環境は、まったく異なるにもかかわらず、ふたりは共に自分は敷かれたレールの上を走っている、と感じていた。
でも、だけど。〈狭間の世界〉には、ふたりしかいない。判断や決断に口を出してくる者はいない。〈この世界には、こうすればいいよとレールを敷いてくれる人なんか誰もいない。俺もサチも、最初から正解なんかない問題の答えを、自分たちで出さなければならなかった〉。
詳細は控えるが、〈狭間の世界〉は「生」と「死」の狭間であり、ふたりがつきつけられる「問題」もまた、「生」と「死」に直結する。
自分は何のために生きるのか。生きることには、どんな意味があるというのか。重いテーマの物語だ。「残酷な話」だ。周囲の人々が語るサチとワタルの姿も、立場が違えば見えているものも異なり、やるせなさや切なさや虚しさが、幾度となくこみあげてくる。
けれど、まるで息つぎを促すように、著者ならではのフッと読者の頬を緩ます表現が随所にあり、そのたびに、沈みかけていた気持ちが浮上するのだ。デビュー作『名も無き世界のエンドロール』から変わらぬこの文章のリズムは、行成薫の大きな特長だとつくづく思う。
「生きてると、面倒なこともあるけどよ。腹さえ膨れれば、頭が動く。頭が動けば、体も動く」「人生には、レールなんてないんだからな」「俺は、命が平等だとは思わない派」ぐっとくる言葉はやっぱり数えきれない。鶏ガラスープのチキンカレー。美人管理人と美人女医。魅惑の〈カロリー高い! 味濃い! 量多い!〉。何気ない表現にニヤニヤしてしまう。そして幾重の意味をもつ「明日、世界がこのままだったら」。巧いなぁ。
私は、こんな小説を読むために、生きているのかもしれない。
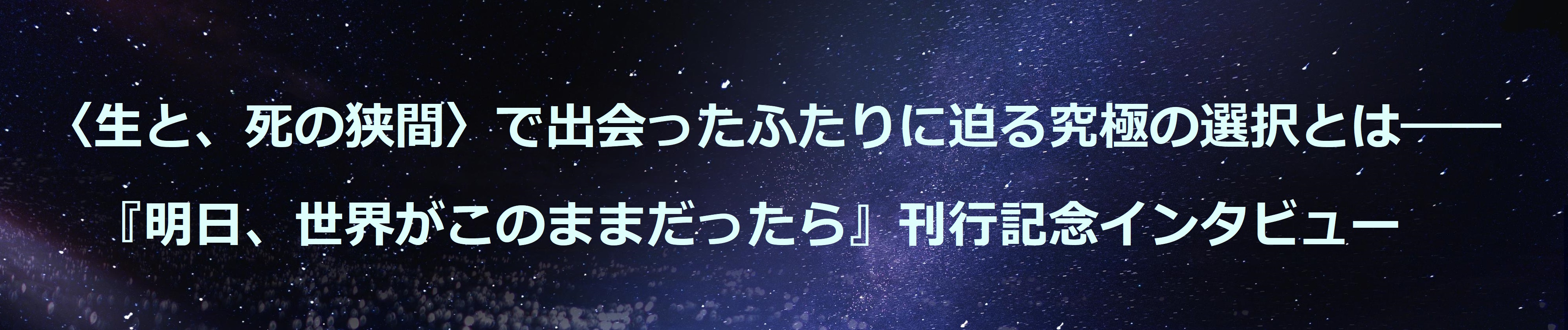
新着コンテンツ
-
インタビュー・対談2024年04月20日
 インタビュー・対談2024年04月20日
インタビュー・対談2024年04月20日青羽 悠「大学生活を送りながら書いた、 リアルタイムな京都、大学、青春小説」
一人の青年の大学四年間を描いた青春小説。大学生活とは? 大人になることとは?
-
お知らせ2024年04月17日
 お知らせ2024年04月17日
お知らせ2024年04月17日小説すばる5月号、好評発売中です!
注目は赤神諒さんと宇佐美まことさんの2大新連載! 本多孝好さん初の警察小説の短期集中連載も必読。
-
連載2024年04月15日
 連載2024年04月15日
連載2024年04月15日【ネガティブ読書案内】
第29回 インベカヲリ★さん
「常識に汚染されそうになった時」
-
お知らせ2024年04月10日
 お知らせ2024年04月10日
お知らせ2024年04月10日『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』が2024年本屋大賞翻訳小説部門第1位を受賞!
『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』(ファン・ボルム 著 牧野美加 訳)が2024年本屋大賞翻訳小説部門第1位に決定しました!
-
お知らせ2024年04月06日
 お知らせ2024年04月06日
お知らせ2024年04月06日すばる5月号、好評発売中です!
注目は松田青子さんの新連載と山内マリコさんの連作小説! キム・ソヨンさん×文月悠光さん、桜庭一樹さん×かが屋のお二人の対談も必読!
-
新刊案内2024年04月05日
 新刊案内2024年04月05日
新刊案内2024年04月05日22歳の扉
青羽悠
小説すばる新人賞、史上最年少受賞から8年! 二十代前半の「不変」と「今」が詰まった圧倒的青春小説!




