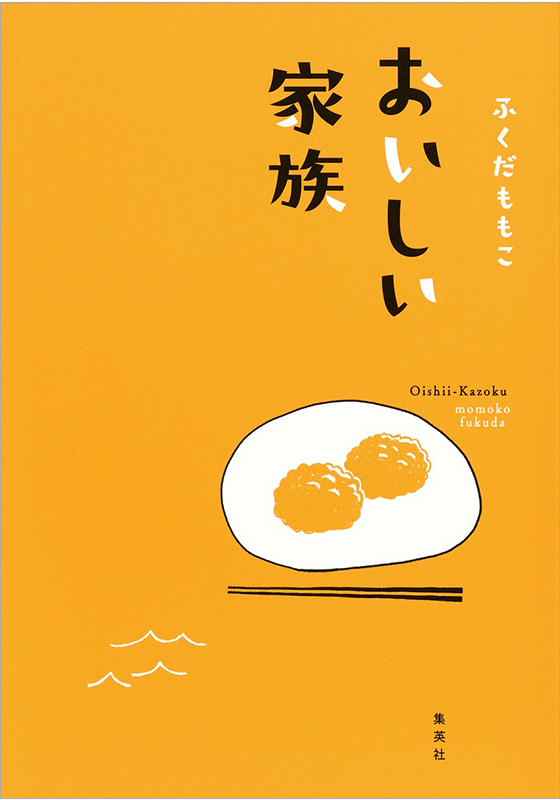プロフィール
-
木崎 みつ子 (きざき・みつこ)
1990年大阪府生まれ。大学を卒業し、現在は校正業に携わる。『コンジュジ』で、第44回すばる文学賞を受賞。
震撼の声、続々…!
とんでもない才能。
サバイブの果てに辿り着く、
こんなに悲しく美しいラストシーンをわたしは他に知らない。
深く、胸を打たれた。
この小説が見せてくれたもの、ずっとわたしの宝物です。
――川上未映子氏(作家)
最初は愉快だが、そのうち悪夢から脱け出せなくなる。
これほどまでに、主人公に同情し、共感した作品は珍しい。
――桐野夏生氏(作家)
現実には行くこともさわることもできない場所から、
束の間でも光が射して誰かの腕をつかむことをこの小説は書く。
本書が希有なのは、その腕をつかむ側の弱さやそのことへの幻滅を、
勇気をもって描いていることだ。
――津村記久子氏(作家)
木崎みつ子×川上未映子
『コンジュジ』刊行記念対談
すばる文学賞
受賞記念エッセイ
コンジュジの「コン」のアクセントは、コンタクトと同じです
モノ作りをする人々にとって、どんな子ども時代を過ごしたかということは重要なのだろうか。
私は物心がついたのもつい最近なので、自分がどういう子どもだったのかあまり覚えていない。というか、どういう子どもなのか自分でも把握しておらず、家庭訪問の際には先生が帰ってから「なんて言ってた?」と母親に聞いていた(別に普通のことだろうけど)。
そんな私でも鮮明に覚えているエピソードが二つある。一つ目は幼稚園の頃の話だ。お絵描きの時間、女の子の友達に「ねえ、なんでケッコンしたいの?」と聞いてみたことがある。その子がいつもドレス姿の自分の隣に、タキシードを着た背の高い男の子の絵を描いていたからだ。すると友達はすぐに答えてくれた。ウェディングドレスが着たいからだと。
その後の友達との会話で、自分が何と言ったのか覚えていない。おそらく返す言葉もなく、へらへら笑って場を取り繕ったのだと思う。「わたしは着たいとおもわない」と正直に言えなかったのは、その子が浮かべていた大人顔負けの自信に満ちた顔から、一人の幼稚園児の夢以上の大きなものを見てしまったからかもしれない。
この頃からドレスも白無垢も着こなせる自信がなかった。とはいえ、芋ジャージで結婚式に出ていいとしても同じことだ。花嫁衣裳の問題ではない。
二つ目は、小学校中学年の頃の話だ。誰かの家におじゃまして、数人でディズニー映画を観ていた。私はアニメ作品にうとかったけれど、知力・体力・正義心を兼ね備えたヒロインが、鍛え上げた男性陣を凌駕する展開が爽快で、大興奮しながら鑑賞した。
ヒロインが王子様からのプロポーズに応じる場面で物語が幕を閉じたとき、自分が何故「結婚」に悲しみのような感情を抱いていたのかがわかった。「はい、これがハッピーエンド!」と言われているような気がするからだ。「人の数だけ幸せがある」と学校で言われたときも別に希望を抱かなかったけれど、ひっそりと落ち込んだ。
違和感の正体を突き止めたところで、生活自体は何も変わらない。バカな自分も、この件が友達とのケンカの種にならないことは直感していた。
高校生になり、好きな人ができても結婚を意識することはなかった(ふられたし)。
さすがに自分も二十代になれば、結婚する未来が見えてくるような気がした。現実として迫ってくる感じはあったし、結婚していく友人たちがまぶしくも見えた。だから、二十四歳になったとき『コンジュジ』(ポルトガル語で配偶者の意味)というタイトルの小説を書こうと思った。
結局作中で主人公に結婚はさせなかったけれど、近頃は「愛」をテーマにしても恋愛の話を書かない人が増えてきた気がするので、あまり怒られずに済みそうだ(多分)。それでも誰かに甘えたいときはある。永遠を信じないのに形のないものにこそ期待をしたくなるし、夢だって見ていたい。自分の中にあるそういう気持ちを書いていった。
これからについても考えたい。
作家というのは自己表現ができる珍しい職業だけれど、おもしろく書かないと成り立たないものだと思っている。作家を志す若い方たちは、才気にあふれ、時流に合った作品を(少なくとも自分よりは)軽々と生み出すのだろう。今から考えるだけで「トッシ寄りは時代に取り残されるねん」と、皮肉屋のうちのばあちゃんみたいにしんみりしてしまう(旗色が悪くなると耳が遠くて聞こえないふりをするのをやめろ)。
それと自分が「作者の手から離れた瞬間に、作品は読者のものになる」と思える人間ではないのも不安要素だ。
作家の東山彰良さんが『流』で直木賞を受賞された際、記者会見で「小説は作者がどう読んでほしいというのは重要ではなく、読み手が自分のこととして読めるのが最良」というようなことをおっしゃっていて、作家の鑑のような方だと思った。スタンスさえも芸術的だと感動した。私なんて書き手と読み手の中身が似ていればいいのにと、無謀なことを願ってしまう。読者の方は「共感者」などではなく「お客さん」なのだと、心しておかないといけない。
家のトイレに飾っている御木幽石さんの万年カレンダーのかわいいお地蔵さまに、毎日元気をもらっていたこと。ビートルズの好きな曲をリピート再生しながらラストシーンを考えたこと。生きているのがくだらないと思う日も、小説を書いている時間は気の置けない友人と会話をするときのように安らげること。本当は色々と書きたいことがあるのに、文字数オーバーだ。
気弱なくせにひねくれ者だった子どもが、大人になって小説を書き、晴れがましい文学賞をいただいた。結局自分の中身は四〜五歳の頃から何も変わっていないけれど、この経験はとんぷくのように今後も活かしていけると思う。
(「青春と読書」2021年1月号より転載)
新着コンテンツ
-
新刊案内2024年07月26日
 新刊案内2024年07月26日
新刊案内2024年07月26日地面師たち ファイナル・ベッツ
新庄耕
不動産詐欺の組織犯罪の闇に迫る、新時代のクライムノベル『地面師たち』の待望の続編!!
-
インタビュー・対談2024年07月26日
 インタビュー・対談2024年07月26日
インタビュー・対談2024年07月26日新庄耕「釧路がシンガポールになる、というあり得なさで「いける!」と」
今夏Netflixでドラマシリーズ化された前作と、その待望の続編である本作への思いを著者に伺いました。
-
インタビュー・対談2024年07月19日
 インタビュー・対談2024年07月19日
インタビュー・対談2024年07月19日青波杏「「語れない」をテーマに描く、女性同士の繫がりと植民地の歴史」
現代の台湾に生きる女性二人が、古い日記に隠された真実を探る物語。謎と日常、過去の歴史と現在が交わる中で見えてくるものとは。
-
インタビュー・対談2024年07月19日
 インタビュー・対談2024年07月19日
インタビュー・対談2024年07月19日ファン・ボルム「休めない社会だからこそ、休む人たちの物語を描きたいと思った」
本屋大賞翻訳小説部門第1位に輝き、ロングセラーを続けている本作への思いを、著者のファン・ボルムさんに伺いました。
-
お知らせ2024年07月17日
 お知らせ2024年07月17日
お知らせ2024年07月17日小説すばる8月号、好評発売中です!
奥田英朗さん「家」シリーズの待望の新作読切を始めとした大特集のテーマは”家族”。新川帆立さん、遠田潤子さんの対談も必読です!
-
連載2024年07月12日
 連載2024年07月12日
連載2024年07月12日【ネガティブ読書案内】
第32回 浅倉秋成さん
「ポジティブ思考が羨ましくて仕方がない時」