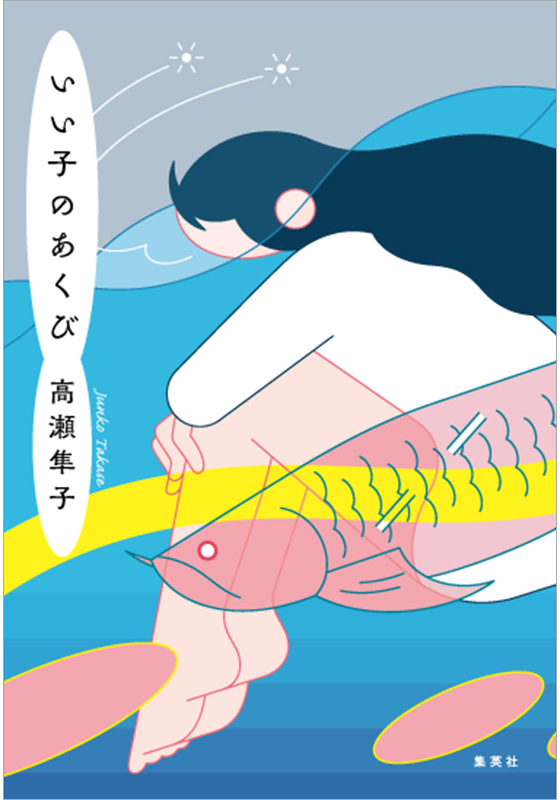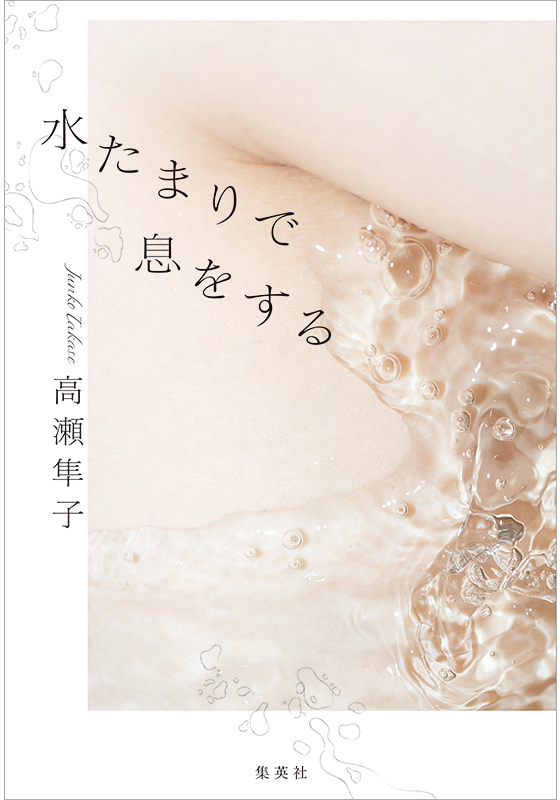内容紹介
【第74回芸術選奨文部科学新人賞受賞!】
芥川賞受賞第一作。
公私共にわたしは「いい子」。人よりもすこし先に気づくタイプ。わざとやってるんじゃなくて、いいことも、にこにこしちゃうのも、しちゃうから、しちゃうだけ。でも、歩きスマホをしてぶつかってくる人を除けてあげ続けるのは、なぜいつもわたしだけ?「割りに合わなさ」を訴える女性を描いた表題作(「いい子のあくび」)。郷里の友人が結婚することになったので式に出て欲しいという。祝福したい気持ちは本当だけど、わたしは結婚式が嫌いだ。バージンロードを父親の腕に手を添えて歩き、その先に待つ新郎に引き渡される新婦の姿を見て「物」みたいだと思ったから。「じんしんばいばい」と感じたから。友人には欠席の真意を伝えられずにいて……結婚の形式、幸せとは何かを問う(「末永い幸せ」)ほか、社会に適応しつつも、常に違和感を抱えて生きる人たちへ贈る全3話。
プロフィール
-

高瀬 隼子 (たかせ・じゅんこ)
1988年愛媛県生まれ。東京都在住。立命館大学文学部卒業。「犬のかたちをしているもの」で第43回すばる文学賞を受賞。「水たまりで息をする」が第165回芥川賞候補に。『おいしいごはんが食べられますように』で第167回芥川賞を受賞。著書に『犬のかたちをしているもの』『水たまりで息をする』『おいしいごはんが食べられますように』がある。
インタビュー
対談
書評
逸脱する“わたし”たちへの許し
年森瑛
高瀬隼子は「割に合わない」という感情を書き続けてきた作家だ。
こんなことはおかしいのに、こんなことはおかしいと言えない世界がむかつく。決まりを破る人のことを私ばかりが許さなくてはならないのは不公平だ。語り手たちは鬱屈を抱え、疲弊している。その割に合わなさを生み出しているのは職場の労働環境でもあり、東京という土地がもたらす忙しなさでもあり、社会が頑迷に手放そうとしない男女格差でもある。語り手たちは傷ついていても、目の前の相手が自分より傷ついているような顔をしているから、または許されると確信しているような顔でいるから我慢して口を閉ざす。我慢して、我慢して、でももう限界が、糸が切れてしまうから、どうか“わたし”を許してほしい、怒り悲しむことを、投げ出すことを、“わたし”が“わたし”から逸脱することを許してほしいと祈っている。高瀬隼子の小説は、語り手と同じようにこの世界のどこかで両の手のひらを合わせている“わたし”たちに許しを与える。
表題作『いい子のあくび』の語り手は、よく人にぶつかられる女性である。語り手がそのことを彼氏に伝えると反応はこうである。〈信じられないという顔をして、実際に疑っているような声色で「おれ、ぶつかられたことないよ」と言った。〉高身長で恰幅がよい彼氏のことはみんな気にかけてよけていくのだ。語り手は思う。〈なんだわたしやっぱりこいつならいいやって選別されてぶつかられてたんだな、と今更のように気付いたのだった。分かっていたけど、分かっていないことにしていたような。それで、わたしもよけるのを止めにした。よけない人のぶんをよけないことにした。〉
そうして物語は〈ぶつかったる。〉という語り手の激情で幕を上げる。一車線だけの狭い道、語り手の前からは、自転車のハンドルにひじをついて両手にもったスマホを眺める男子中学生が左右に揺れながらゆっくり近付いてきている。語り手は中学生に気付かないふりをしてまっすぐに歩く。そしてぶつかられる――ところまでは語り手の予定通りだったが、衝突の反動によって中学生は自転車ごと倒れ、やってきた車にぶつかられてしまう。幸い、自動車が急ブレーキを踏んだおかげで中学生は軽いすり傷で済んだ。少しでも何かが違っていれば死人が出ていたかもしれない結果だが、語り手のはらわたで燃え盛る炎は消えなかった。〈中学生は息が止まったように静かにしている。静かにしていればいいと思っているのかもしれない。子どもの時ってそうしていたら大人が助けてくれることが多いから。(中略)ねえ、黙ってても許してあげないよ。〉そのまま中学生が立ち去ろうとするのを呼び止めて、語り手は謝罪を引き出させる。〈わたしは「いいよ」と言ってあげる。/許しを与える。〉もう彼女は決めたのだ。まるで語り手が存在しないかのようにスマホを見ながら向かってくる人に気をまわしてよけて、仕方がないなあと許すのをやめると。謝罪を促し、許しは「与える」ことにしたのだ。自分ばかりが施してやるのは割に合わないから。
『お供え』の語り手は〈同僚の陰口をたたく間、わたしたちはぐっと、なんというか正確に、親しくなれているような気がする。〉と思いながら、後輩Aの話を聞いている。Aの隣に座る同僚は、デスクに置いたフィギュアにお菓子をお供えしているそうだ。かつて教育係としてかわいがっていたAから謙虚さが失われつつあることを憎らしく思う日々の中で、お供えをする人は増えていき、ある日Aがお供えをしている場面に遭遇する。
『末永い幸せ』の語り手は結婚式が苦手である。新婦が父親から新郎へと物のように引き渡されるバージンロード、女性が家事を担うことを前提としたファーストバイト、新婦だけが両親への感謝の手紙を読み上げること等々、恒例の演出が気持ち悪くて仕方がないのだ。地元の友人の結婚式への参列を頼まれた語り手は、友人の幸せを願う気持ちはあるが、結婚式のせいで心の底から「おめでとう」と言えなくなってしまうからと欠席を申し出る。そして当日、語り手が不在のまま、式が始まる。
語り手たちは皆、不快感を言葉で示すことができない。歩きスマホにも、侮るような態度の後輩にも注意できない。「結婚式なんて気持ち悪いからやめようよ」と友人に言うこともない。語り手たちの違和感は、たかがそれくらいで、とか、考えすぎ、とか言われるようなことだから。問題に対して憤っている自分のほうが非常識と窘められかねないから。だから誰も何も言わない。ただ祈る。どうか“わたし”に気付いて、“わたし”の声が届きますように。
多くの人がもっと「重要」な、めらめらと燃え盛る大きな炎を見上げて心配しているあいだに、そこからバチンと一度きりの音を立てて飛び出した火花が河原の平べったい石ころに落ちた、それに高瀬隼子は気付いている。消えないように手のひらで覆って、吹き付ける風や踏みつぶす人から守っている。火花はいつしか大きくなって、踏みにじろうとする誰かを退ける苛烈さをもつ一方で、“わたし”たちには犬みたいにやわらかく光って見える。
読み始めた当初の私は、書評の仕事なわけだし必要そうなところにマーカー引きながら読もう、と右手の中指から小指で蛍光ペンを挟み、同じ手の親指と人差し指でページの端をつまんでめくっていた。それがいつの間にかペンを置いてめくり続けていた。自分の執筆途中の小説のことを何度も思い出した。早く書かなきゃと思った。早く、早く私も書きたい。酒もコーヒーもおいしいごはんも間に挟まなくていいから、わたしはあなたの話が聞きたい、わたしたちは、「“わたし”と“わたし”たち」は共にありたいと、祈り、小声で告げるような小説を、私も書きたい。
「すばる」2023年8月号転載
新着コンテンツ
-
新刊案内2024年07月26日
 新刊案内2024年07月26日
新刊案内2024年07月26日地面師たち ファイナル・ベッツ
新庄耕
不動産詐欺の組織犯罪の闇に迫る、新時代のクライムノベル『地面師たち』の待望の続編!!
-
インタビュー・対談2024年07月26日
 インタビュー・対談2024年07月26日
インタビュー・対談2024年07月26日新庄耕「釧路がシンガポールになる、というあり得なさで「いける!」と」
今夏Netflixでドラマシリーズ化された前作と、その待望の続編である本作への思いを著者に伺いました。
-
インタビュー・対談2024年07月19日
 インタビュー・対談2024年07月19日
インタビュー・対談2024年07月19日青波杏「「語れない」をテーマに描く、女性同士の繫がりと植民地の歴史」
現代の台湾に生きる女性二人が、古い日記に隠された真実を探る物語。謎と日常、過去の歴史と現在が交わる中で見えてくるものとは。
-
インタビュー・対談2024年07月19日
 インタビュー・対談2024年07月19日
インタビュー・対談2024年07月19日ファン・ボルム「休めない社会だからこそ、休む人たちの物語を描きたいと思った」
本屋大賞翻訳小説部門第1位に輝き、ロングセラーを続けている本作への思いを、著者のファン・ボルムさんに伺いました。
-
お知らせ2024年07月17日
 お知らせ2024年07月17日
お知らせ2024年07月17日小説すばる8月号、好評発売中です!
奥田英朗さん「家」シリーズの待望の新作読切を始めとした大特集のテーマは”家族”。新川帆立さん、遠田潤子さんの対談も必読です!
-
連載2024年07月12日
 連載2024年07月12日
連載2024年07月12日【ネガティブ読書案内】
第32回 浅倉秋成さん
「ポジティブ思考が羨ましくて仕方がない時」