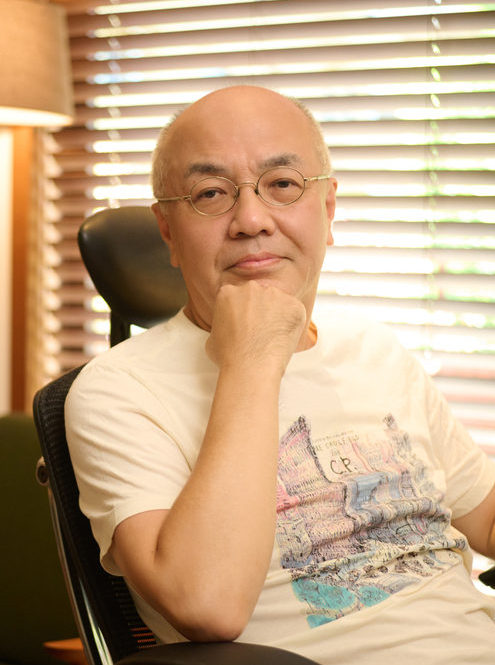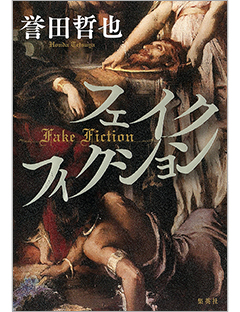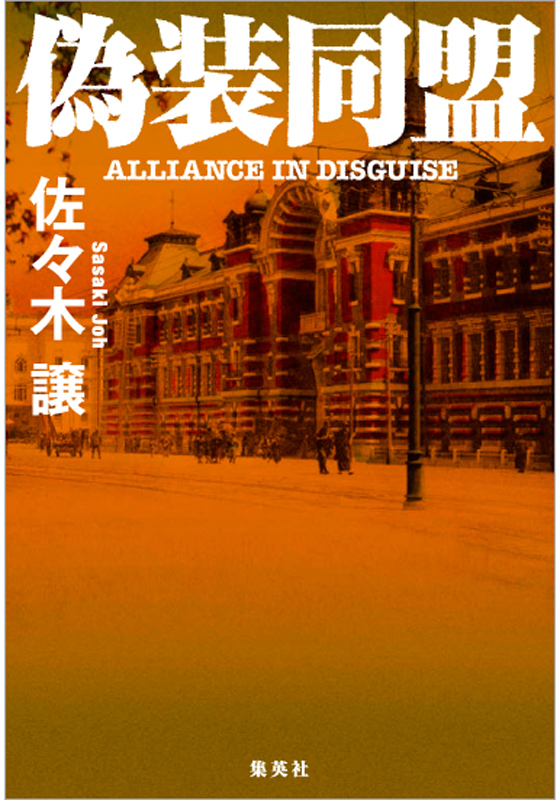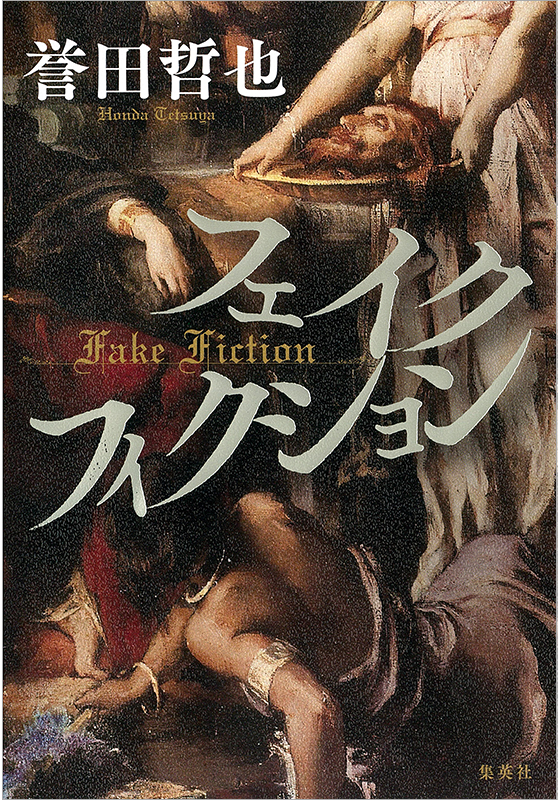内容紹介
真実を見抜き、罪を償わせる。
たった、それだけ。それだけのことが、なぜこんなにも難しい――?
マンションの一室で発生したある殺人事件の現場に向かった、県警捜査一課の和泉。
そこで出会った女性警官・瀬良の第一印象は、簡単に言えば「最悪」だった。
しかし、上の命令で瀬良とタッグを組み殺人事件を捜査することになり、
和泉は彼女の類稀な観察力を知ることになる。
二人の懸命な捜査により、事件のかたちが徐々に輪郭を帯びていくが、
待ち受けていたのは「正しい刑罰」の在り方を問う、予想外の真相だった――。
和泉と瀬良が立ち向かった最初の事件「イージー・ケース」ほか、
事件に関する証言を頑なに拒み続ける容疑者の謎を追う「ノー・リプライ」、
解決の糸口が見えない誘拐事件を描く書き下ろし中編「ホワイト・ポートレイト」を収録。
心揺さぶる結末に息を呑む、圧巻の傑作警察ミステリー!
プロフィール
-

本多 孝好 (ほんだ・たかよし)
1971年東京都生まれ。慶應義塾大学卒業。94年「眠りの海」で第16回小説推理新人賞受賞。99年、受賞作を収録した短篇集『MISSING』で単行本デビュー。2003年『MOMENT』、04年『FINE DAYS』で2年連続吉川英治文学新人賞候補。05年『真夜中の五分前』で第132回直木賞候補、10年『WILL』で第23回山本周五郎賞候補。他に『MEMORY』『ストレイヤーズ・クロニクル ACT 1~3』『チェーン・ポイズン』『at home』『君の隣に』『dele 1~3』『アフター・サイレンス』『こぼれ落ちる欠片のために』など著書多数。
インタビュー
本多孝好「書き進めるうちに感じた、自分なりの警察小説への手応え」
書評
欠片を見落とさない、著者初の警察小説
吉田伸子
本書は本多さん初の警察小説だ。へ? 本多さんって、前も警察小説書いてなかったっけ? と思ったのは私だけではないだろう(確認しました。初、です)。
なぜそんなふうに思ったのかというと、恐らくは二〇二一年に刊行された『アフター・サイレンス』が頭にあったからだと思う。犯罪被害者の家族と加害者の家族を描くことで、「罪と罰」を照射したこの作品は、読み手の心にも、罪とは? そして、罰とは? という深い問いかけを残した。その問いへの答えを、私自身はまだ見出せていない。現実で起こる悲惨な事件を目にした時は、どうしてこんなことが起きてしまったのか、と思いを巡らせることはあるものの、そこまでだ。
なので、本書を読んだ時に真っ先に思ったのは、そうか、本多さんは、『アフター・サイレンス』の問いかけを、きっとずっと持ち続け、事あるごとに考え続けていたのだな、ということだった。そこに、本多孝好という作家の誠実さを私は感じたし、それこそが、私の、本多さんの物語に対する信頼なのだな、と思った。ちなみに、本書には、『アフター・サイレンス』に登場した仲上刑事も出てきます。
本書は、三編の中編からなる連作集だ。物語の主人公は和泉光輝。県警本部の捜査一課強行犯二係に所属する若手刑事だ。彼が臨場する二度目の殺人事件を描いた「イージー・ケース」で、本書は幕を開ける。宮地班に属する和泉は桜井奈那巡査部長とコンビを組み、現場周辺での聞き込み、いわゆる「地取り」に強さを発揮していた。妊娠を機に宮地班を離れることになったナナさんの代わりに、光輝の“相棒”となったのは、中山署刑事課、瀬良朝陽巡査だった。
この朝陽、光輝いわく「顔立ちが整いすぎていて、年齢がわかりにくい」というレベル。ところが、朝陽の容姿がいい意味で度外れたレベルだとしたら、彼女のコミュニケーション能力は、「警察官としての力量云々以前の問題です。人間としておかしいです」「挨拶すらない。こんばんはも、初めましても、お疲れ様もないんですよ」と、光輝が班長に訴えるほど、これまた度外れて低い。
対する光輝は、コミュニケーション能力は際立っているものの、その容姿はといえば、実の姉から「これ以上、つまんなくできない顔。モブ中のモブ。モブモブ」と評されるほど、驚くほど特徴のない顔立ちだ。光輝自身、「集合写真では、俺自身が俺を探すのに苦労する」。
そう、光輝と朝陽は容姿もコミュニケーション能力も正反対なのだ。このでこぼこなコンビ(しかも男女!)を設定したあたりが、本書のミソ。加えて、そんな二人に「人が怖い」という共通項があることが、更なるミソだ。
最初のうちは朝陽のコミュ障っぷりにドン引きしていた光輝だったが、コンビを組むうち、朝陽が優秀な刑事であることに気が付く。自分が見落としてしまうようなことにも、朝陽の意識は向けられるのだ(その優れた能力から、交番巡査だった時に、ひと月の間に職務質問で違法薬物所持者、窃盗常習犯、銃器不法所持者を立て続けに捕まえたことがあり、「職質の女神」と噂されていたことを、光輝は後に知る)。
収録されている三編で描かれているのは、二つの殺人事件と、小五男児の行方不明事件(「ホワイト・ポートレイト」)だ。殺人事件は、一つは親に暴力を振るわれ、担当介護職員を殺した男(「イージー・ケース」)と、いわゆる痴情のもつれから年下の恋人を殺した女(「ノー・リプライ」)、の二件。こうやって書いてしまうと、ありふれた事件のように思える。事実、現実社会で報道されたとしても、ひととき目を留めはするけれど、それだけだ。けれど、本書で描かれているのはその事件の背後にあるもの――その事件に至るまでの、表には出てこない“真実”、そもそも何故、事件は起こったのか――だ。その背後こそが、タイトルにもなっている「欠片」たちなのだ。誰もが見落としてしまうようなその欠片に目を向けるのが朝陽で、彼女が感じとったものを事件の解決に繋げていくのが光輝だ。
いいコンビだな、この二人。読みながらそう思う。二人が抱える「人が怖い」という思いが、表面的な“事実”だけで事件を捉えるのではなく、“真実”を見ようとすることに生かされている、というのが物語のなかで効いている。
とりわけ、読後も印象に残るのは、「ノー・リプライ」のなかで、朝陽が問う、それは真実ですか? 正義ですか? という言葉だ。それは、「イージー・ケース」で光輝と同じ班の刑事・都倉が言った「俺たちの仕事は捕まえたやつの罪を最大化することだよ」という言葉に対する問いかけでもあるからだ。
光輝と朝陽が「人が怖い」と思う理由はちらりと描かれてはいるが、その辺りのことももっと深く読みたいな、と思う。というわけで、続編、ぜひお願いします!
「小説すばる」2024年12月号転載
新着コンテンツ
-
新刊案内2025年06月26日
 新刊案内2025年06月26日
新刊案内2025年06月26日筏までの距離
水原涼
デビュー作で芥川賞候補に挙がった著者が贈る、わたしとあなたの8つの物語。
-
インタビュー・対談2025年06月20日
 インタビュー・対談2025年06月20日
インタビュー・対談2025年06月20日宇山佳佑×檜山沙耶(フリーアナウンサー)「風が吹くたび、物語が生まれる」
ウェザーニューズで気象キャスターとして活躍し、その後も活動の幅を広げる檜山沙耶さんと作品、風、お天気について語っていただきました。
-
お知らせ2025年06月17日
 お知らせ2025年06月17日
お知らせ2025年06月17日小説すばる7月号、好評発売中です!
新連載はいずれも小説すばる新人賞出身の佐藤雫さん、神尾水無子さんの2本立て!
-
お知らせ2025年06月17日
 お知らせ2025年06月17日
お知らせ2025年06月17日本日開店、「スキマブックス」!!
文芸ステーションに新しい読みもののコーナー「スキマブックス」がオープンしました!
-
スキマブックス2025年06月17日
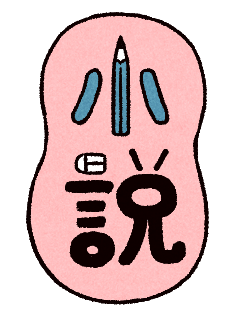 スキマブックス2025年06月17日
スキマブックス2025年06月17日今度こそ許すまじ春野菜といんげん豆の冷製スープ事件
結城真一郎
彼氏が浮気をしているのではないかと疑った大学生は、「あるレストラン」に浮気調査を依頼するが――。
-
インタビュー・対談2025年06月17日
 インタビュー・対談2025年06月17日
インタビュー・対談2025年06月17日堂場瞬一「日本政治の未来をフィクションで問う」
堂場瞬一さんの通算195冊目の作品にして、実験的政治小説第二弾『ポピュリズム』の世界観を語ってもらった。