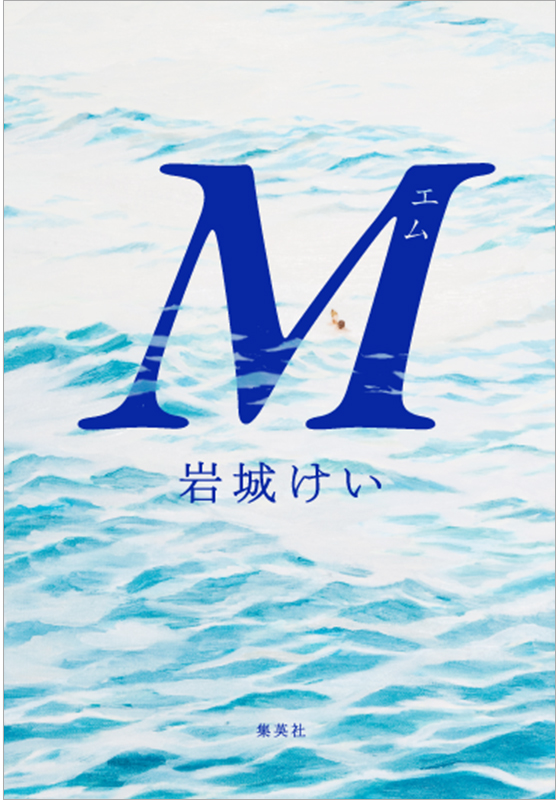内容紹介
【第74回芸術選奨文部科学大臣賞受賞!】
あれから何年経ったのだろう。あれって、いつから? どのできごとから?
日本を襲った二つの大地震。未知の病原体の出現。誰にも流れたはずの、あの月日――。別々の場所で暮らす男女三人の日常を描き、蓄積した時間を見つめる、著者の最新長編小説。
プロフィール
-
柴崎 友香 (しばさき・ともか)
1973年、大阪府生まれ、東京都在住。大阪府立大学卒業。1999年「レッド、イエロー、オレンジ、オレンジ、ブルー」が文藝別冊に掲載されデビュー。2007年『その街の今は』で芸術選奨文部科学大臣新人賞、織田作之助賞、咲くやこの花賞を受賞。2010年『寝ても覚めても』で野間文芸新人賞、2014年『春の庭』で芥川賞を受賞。その他に『パノララ』『千の扉』『百年と一日』ほか、エッセイに『よう知らんけど日記』など、著書多数。
対談
書評
絶えない
一穂ミチ
絶え間なさ、に泣きたいような気持ちになった。どうしてなのか、うまく説明できない。柴崎友香の小説を読むと、いつもこういう、滲んだ曇り空みたいな胸苦しさを覚える。単純な喜怒哀楽や、今まで経験してきた「あの時の感じ」に当てはめようとしてもうまくいかない。どんなに目を凝らしても、虹や夕焼け空のグラデーションの境目を見つけられないのに似ている。色がつく前の感情を未分化のまま手繰り寄せられるざわめき。
二〇二〇年からのコロナ禍に生きる三人の男女の日常が、縷々と綴られていく。滋賀で暮らすパート主婦の石原優子、東京で料理人として働く小坂圭太郎、同じく東京在住の女性カメラマン、柳本れい。読み進めながら、緊急事態宣言や休業要請、東京オリンピックの延期などといった、あの特殊な状況下での出来事が自分の中で既に「昔の話」になっていることに驚いた。つらく苦しかったはずなのに、懐かしささえ覚えながらページを捲る。忘れない、忘れられるわけがない、と思っていても、この瞬間にも過ぎていく「今」がわたしたちを押し流してしまう。でも、「終わったこと」「なかったこと」にはならないし、記憶は薄れても残っている。
彼らは三者三様に血肉を持った生活者で、劇的な事件が起こってエッジが立つ瞬間をドラマチックに切り取られたりしない。混迷の中でも働き、子どもと遊び、人と会い、食べ、眠る。そんな「非日常の日常」から、東日本大震災や阪神・淡路大震災、あるいは家族をめぐるそれぞれの痛みがふと浮かび上がる。本当に「忘れられないこと」には節目も時効もなく、「忘れられないこと」のほうから不意に訪れてくる。それでも、流れは止まらない。
ラストの数ページ、今までミクロだった視点がふわっと浮き上がり、気づけばわたしは巨大な模様を俯瞰していた。それは雨上がりのくもの巣みたいにか細く光り、あちこちに水滴の球をくっつけてどこまでも広がっている。
始まりの前の続き、続きの後の始まりを見下ろし、あの中のどこかにわたしもいる、と思った。こんな景色を見せてくれてありがとう、と思った。
いちほ・みち●作家
「青春と読書」2023年12月号転載
“終わらなさ”のなかで
瀧井朝世
「始まりと続き」と「続きと始まり」という表現では受ける印象が違う。前者は、何かが始まってそれが続いていくイメージ、後者は、何かが続いているなかでまた新たな何かが始まる、というイメージだ。読みながらそう実感させるのが、柴崎友香の新作長篇『続きと始まり』である。
二〇二〇年三月から二〇二二年二月まで、別々の場所で暮らす男女三人の日常がひと月おきに交互に語られていく。と説明するとコロナ禍の期間の人々の生活が描かれた作品のように思えるが、そうではない。これまで続いてきた彼らの人生、あるいは彼らの生まれる前から続いてきた時間が本作には詰まっている。
視点人物は滋賀県に住む三十代後半の石原優子、東京に住む三十三歳の小坂圭太郎、同じく東京に住む四十六歳の柳本れい。優子は大阪出身で、一時期は東京のデザイン事務所に勤めていたが今は滋賀県で暮らしている。家族は夫と七歳の娘、三歳の息子で、仕事は衣料雑貨や日用品を通信販売する会社にパート勤務だ。圭太郎は妻と四歳の娘と暮らし、料理人として居酒屋で働いていたが、緊急事態宣言で店が夜の営業を止めたため、物語の始まりでは休業状態だ。柳本れいはフリーランスのカメラマン。さまざまな媒体で仕事をこなす一方、知人のヘアメイクが始めた郊外の木造家屋の写真館も手伝っている。
彼らの仕事先や実家との関係性なども実に細やかに描かれ、三人だけでなく周囲の人々の性格や人生模様も伝わってきて、三人を「始まり」として相関図が「続いて」いく印象だ。
みな、仕事でも日常生活でもなにかしらコロナ禍の影響を受けており、読み進めるうちにこちらも、あの時期の記憶がくすぐられる(「まんぼう」という略語を久々に思い出した)。ただし、コロナ禍で人々の生活が一変したのは確かだが、それまでのすべてがリセットされたわけではない。これまでの人生の続きの中に、コロナ禍という状況が加わったのである。感染症の影響による変化とはまた異なる生活の起伏も描かれ、混沌とした彼らの日常が浮かび上がっていく。このあたりは著者の真骨頂。
時折三人の胸を去来するのは阪神・淡路大震災や東日本大震災の記憶。被災者ではなくとも、その時の状況やその時に抱いた感情、葛藤は消え去ったわけではなく、心の奥底に潜んでいる。それだけではなく、昔の苦い思い出や後悔、なんとなくひっかかっていた光景や誰かの言動なども、ふと彼/彼女らの心に表出する。忘れられないこと、忘れているようで心の奥底に刻まれていたこと、経験自体は忘れたかもしれないけれどその影響が残されているもの。そうしたものが蓄積されて、今のその人は形作られているのである。新たに始まったものが生活の中心になり、過去の出来事は遠くなったとしても、よくも悪くもどうしようもない“終わらなさ”のなかで人は生きているのだ。
三人それぞれ、親との間になにかしらの齟齬が生じているのも印象に残る。圭太郎の両親が無神経な言葉で妻の貴美子に第二子、しかも男子を望む場面などは象徴的だ。現実でも、親からの前時代的な価値観の押しつけが“続いている”ことは多いだろう。また、優子が、ずっと嫌だと感じていた両親の物言いを無意識のうちに口走っている場面は、子供もまた親の考えを内面化し持続させてしまっている表れだ。ただし、そのことに気づいてはっとする様子から、彼女の中に「そうした物言いはよくない」という基準が生まれていると分かる。ほかにも、女性の人格や生き方を軽んじる風潮や、外国人差別に関するエピソードなども盛り込まれ、変わったようで続いている世間の人々の意識が描かれる一方、登場人物がそれらを自覚する姿からは、新しい意識が“始まっている”と感じさせる。
異なる場所で異なる生活を送る彼らだが、実は共通点がある。それはポーランドの詩人、ヴィスワヴァ・シンボルスカの詩集『終わりと始まり』を持っていることだ。作中に引用される詩は、どれもが本作に繫がる象徴的な内容である。「おや」と思わせるのは、三人ともこの詩集を知ったきっかけがとあるイベントだったと語っている点。「彼らはいっとき、同じ空間にいたのでは」と読者には分かるが、もちろん三人は互いのことは憶えていない。だが、その詩集の言葉に巡り合った経験と影響は、三人それぞれの中で続いている。
引用されるシンボルスカの詩はどれもが心に響くが、なかでも突き刺さるのは、〈戦争が終わるたびに/誰かが後片付けをしなければならない/物事がひとりでに/片づいてくれるわけではないのだから〉だった。後片付けが必要なのは戦争だけではないだろう。震災やコロナ禍がもたらしたもの、これまでの世代が残してきた、人を抑圧する価値観や偏見、差別。その後片付けは、自分も担うべきものだろう。
れいが写真に魅せられたきっかけについて考える箇所がある。〈周りの世界が、目に見えるものすべてが、光と影で塗り変わっていくような、色彩が湧き出すような経験だった。〉〈過去の一瞬に存在して消えてしまった光がレンズを通して別の時間に残される、その驚異というか謎のようなものは仕事として何千回、何万回とシャッターを切っても、れいの中に変わらずに存在していた〉。これは小説にも通じる感覚ではないだろうか。過去の一瞬を言葉を通して残し、その謎のようなものを提示し続けているのが、柴崎友香が書く小説だ。
いつかの一瞬が今に繫がり、今がこの先のいつかに繫がっていくことを、しみじみ実感させる本作。登場人物たちがシンボルスカの言葉を胸に刻みこんだように、読み手の心に刻まれるに違いない言葉がたくさん詰まった一冊である。
「すばる」2024年1月号転載
新着コンテンツ
-
インタビュー・対談2024年04月26日
 インタビュー・対談2024年04月26日
インタビュー・対談2024年04月26日千早茜「十人十色の「傷痕」を描いた物語」
短篇ならではの切れ味を持った十篇、それぞれにこめた思いとは。
-
インタビュー・対談2024年04月26日
 インタビュー・対談2024年04月26日
インタビュー・対談2024年04月26日小路幸也「愛って何だろうね。何歳になってもわからないよ」
大人気シリーズの『東京バンドワゴン』も第十九弾。今回のテーマ「LOVE」を、ホームドラマでどう料理するか。その苦心と覚悟とは。
-
新刊案内2024年04月26日
 新刊案内2024年04月26日
新刊案内2024年04月26日キャント・バイ・ミー・ラブ 東京バンドワゴン
小路幸也
愛を歌って生きていく。いつにも増して「LOVE」にあふれた大人気シリーズ第19弾!
-
新刊案内2024年04月26日
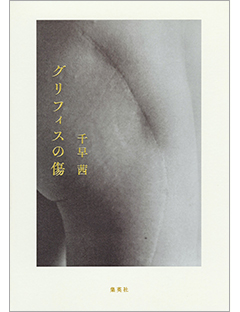 新刊案内2024年04月26日
新刊案内2024年04月26日グリフィスの傷
千早茜
からだは傷みを忘れない――「傷」をめぐる10の物語を通して「癒える」とは何かを問いかける、切々とした疼きとふくよかな余韻に満ちた短編小説集。
-
インタビュー・対談2024年04月20日
 インタビュー・対談2024年04月20日
インタビュー・対談2024年04月20日青羽 悠「大学生活を送りながら書いた、 リアルタイムな京都、大学、青春小説」
一人の青年の大学四年間を描いた青春小説。大学生活とは? 大人になることとは?
-
お知らせ2024年04月17日
 お知らせ2024年04月17日
お知らせ2024年04月17日小説すばる5月号、好評発売中です!
注目は赤神諒さんと宇佐美まことさんの2大新連載! 本多孝好さん初の警察小説の短期集中連載も必読。