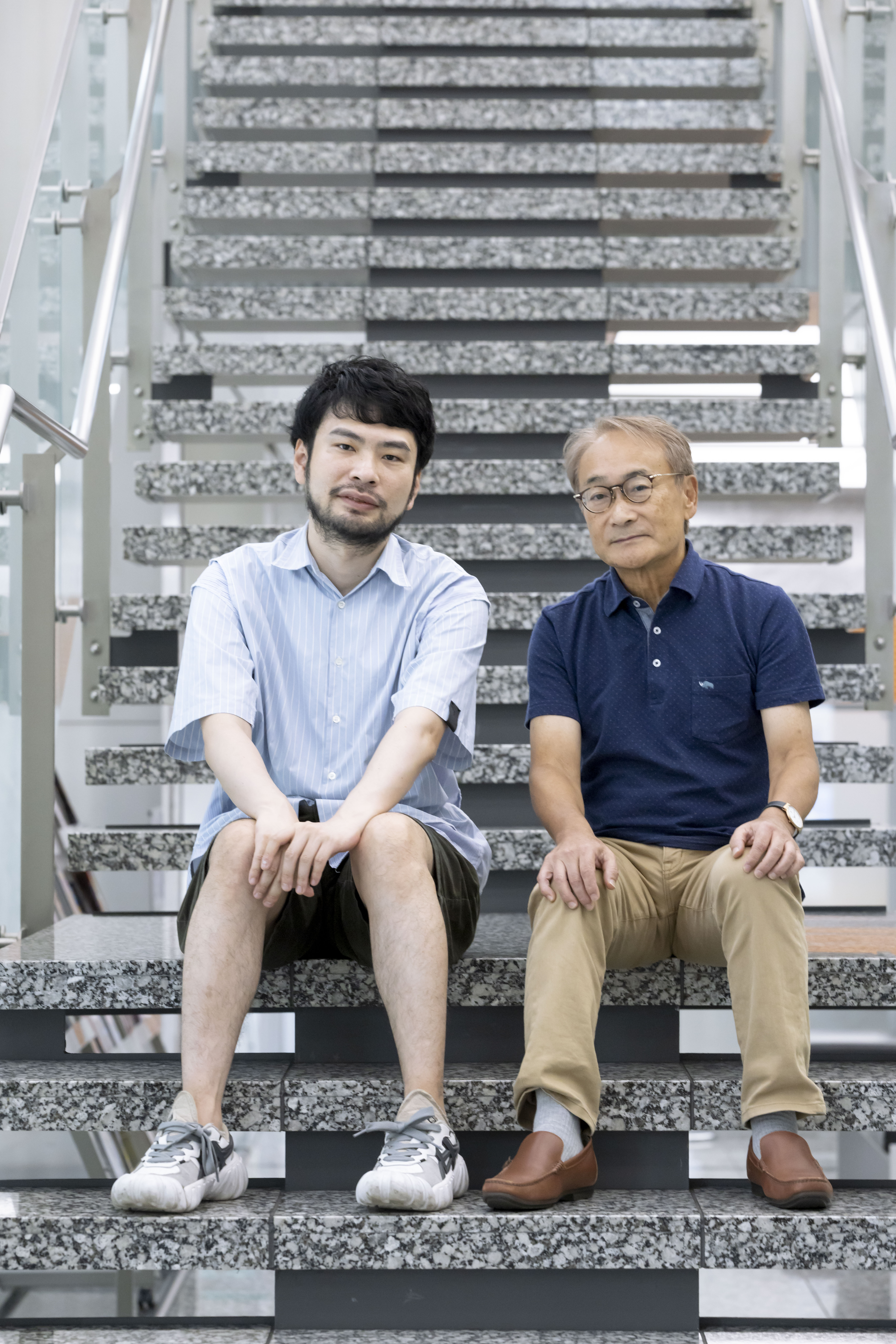内容紹介
昭和のあの頃、百万人の少女たちを夢中にさせた漫画雑誌があった!
1969年、人類が月面着陸をした年に出版社に就職した辰巳牧子は、経理補助として「週刊デイジー」「別冊デイジー」編集部で働き始める。
親分肌の川名編集長が率いる「週デ」は、漫画班・活版班・グラフ班に分かれて編集部員一同、日々忙しく動き回り、「別デ」を率いる小柳編集長は、才能あふれる若い漫画家たちを見出し、次々にデビューさせていた。
いつかは男性編集者に並んで漫画を担当したいと願う西口克子や香月美紀、少女漫画という縁のない世界に放り込まれ戸惑う綿貫誠治、暇さえあれば雀荘で麻雀ばかりしている武部俊彦……。
女性漫画家たちがその若き才能を爆発させ、全国の少女たちが夢中になって読んだ“百万部時代”。編集部で働くひとりひとりの希望と挫折、喜びと苦しみに光をあて、時代の熱を描き出す大河長編!
プロフィール
-
大島 真寿美 (おおしま・ますみ)
1962年愛知県生まれ。1991年「宙の家」が第15回すばる文学賞最終候補作となる。1992年「春の手品師」で第74回文學界新人賞を受賞しデビュー。2012年『ピエタ』で第9回本屋大賞第3位入賞。2019年『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』で第161回直木賞受賞。『それでも彼女は歩きつづける』『空に牡丹』『結 妹背山婦女庭訓 波模様』『たとえば、葡萄』ほか著書多数。
読書ガイド
あらすじや著者直筆メッセージなど盛りだくさんのスペシャルペーパー『別冊 うまれたての星』をお楽しみください☆


インタビュー
大島真寿美「少女漫画編集部という宇宙、ジグザグした形の星をまるごと描きたかった」
書評
星の欠片はいまも輝く
増田のぞみ
1969年、物語はアポロ11号が月面に着陸したその年から始まる。当時、100万人の少女たちを夢中にさせた『週刊デイジー』と『別冊デイジー』。本書は、編集部で働くひとりひとりに光を当て、それぞれが抱える葛藤や苦悩と未来への希望を細部まで描き出している。集英社の『週刊マーガレット』『別冊マーガレット』をモデルに、直木賞作家の大島真寿美が当時の編集者や漫画家などの関係者に丁寧に取材を重ねたうえで書かれた労作だ。
日本の漫画の特徴のひとつとして、漫画家と編集者が密接に関わる制作過程があげられる。編集者は作品のテーマや表現の内容に深く関わり、作家とともに二人三脚で作品を作り上げていく。資料集めや必要な物品の買い出し、引っ越しの手伝いなどの生活面でのサポートはもちろん、精神面でも寄り添い、励ましながら漫画家を支える伴走者となる。
にもかかわらず、この時代の漫画編集者については、本書の小柳編集長のモデルとなっている小長井信昌氏による『わたしの少女マンガ史』(西田書店、2011年)に唯一まとめられているくらいで、まだ珍しかった女性の編集者が当時の編集部でどのように働いていたかを知る機会はほとんどなかった。本書では編集部で働く5人以上の女性が登場し、それぞれの仕事内容を詳しく知ることができる。漫画史としても貴重な資料だ。
しかも、この女性たちは同じ出版社で働いていても、置かれている状況や抱える葛藤が大きく異なる。
高卒で出版社に就職し、編集部の経理補助としてひとり制服を着て働く辰巳牧子は、自由な服装で潑溂と働く編集部員たちをまぶしく見ている。女性の編集部員の中で最も若く懸賞ページや読者のページなどを担当している西口克子は、女性の編集者が漫画班に配属されないことに納得できず、なんとか漫画の担当を持てないかと機会をうかがっている。一方、大学を出てから嘱託として編集部に潜り込み、グラフ班で芸能記事などを担当している香月美紀は、ファッションもおしゃれで「漫画の目利き」だが、正社員ではなく個別契約の嘱託職員であるため立場は不安定で孤独だ。
克子と美紀は男性の編集者よりも漫画が「わかる」。何としても漫画班として漫画の担当をしたいと望んでいるが、女性というだけで補助的な作業しかさせてもらえず、その立場が悔しい。その高い壁に苦しむ二人が『週刊デイジー』の100万部突破を記念したパーティー会場の外で涙をこぼす場面では、こちらまで苦しくなり胸が詰まった。
美紀の一回り上で、最も早くから唯一の正社員の女性として編集部で働いてきた藤原修子は、自分たちが「いつも戦っていた」ことに気づき、新しい世代の少女漫画の登場に「少女漫画とはわたしたちの物語であったのか」と語る。本書には男性ばかりの環境の中で「同じ席に座らせてもらえない」女性の編集者たちがいかに壁と向き合い、悔しい思いをしながらどのように歩みを進めてきたのか、その戦いの軌跡が示されている。
一方、本書には男性の編集者たちの置かれた状況も詳しく書かれる。少女漫画の良し悪しが「どうにもよくわからない」と自信をなくす綿貫誠治、女性の漫画家とのコミュニケーションに苦労しつつ、ヒット作を担当する同僚に焦りや嫉妬を抱く武部俊彦など、男性の編集者たちの複雑な思いにも共感できる。
さらに、牧子の姪として登場する小学生の千秋とその友達の浅沼さんなど、おそらく作者の大島真寿美と同じ生まれ年と思われる当時の小学生の読者たちが、少女漫画をいかに夢中になって読んでいたのかも鮮やかに描き出される。
あくまでも架空の名称として提示されているものの、モデルになる作家や作品はおよそ推測ができるため、「誕生!」(大島弓子)、「美人はいかが?」(忠津陽子)、「聖ロザリンド」(わたなべまさこ)、「ベルサイユのばら」(池田理代子)などの舞台裏を知ることができるのも楽しい。
とくに本書の終盤、「ベルサイユのばら」と思しき歴史長編の連載が佳境を迎えた1973年の読者たちの熱狂ぶりと最終回を読む登場人物たちの姿が心に残る。「編集者や編集部が雑誌を作っていると思ったら大間違いで、コントロールしているのはじつは読者の女の子たちなのだ」と修子が語るように、時代の変化をリードしていたのは100万部、150万部を支えた熱心な読者たちだったのだ。
それから半世紀以上が経った現在でも、「うまれたての星」として「デイジー星」が残した星の欠片は、まだ読者たちの胸に輝きを放ち続けている。本書を読むことで当時の熱狂を追体験する読者の胸にも星の欠片が飛び散り、それぞれの場所で歩みを進めるための熱い灯になるのではないかと期待している。
新着コンテンツ
-
インタビュー・対談2026年02月17日
 インタビュー・対談2026年02月17日
インタビュー・対談2026年02月17日北方謙三×美村里江(俳優)「海が紡ぐ物語」
『チンギス紀』の文庫解説でも北方作品について熱く語ってくださった俳優・美村里江さんが読み解く『森羅記』の魅力とは――?
-
インタビュー・対談2026年02月17日
 インタビュー・対談2026年02月17日
インタビュー・対談2026年02月17日連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」 北方謙三×織田裕二(俳優)「小説と映像、唯一無二の表現」
待望のドラマ化を記念して、原作者・北方謙三さんと主演・織田裕二さんに小説と映像、表現者としての醍醐味を語り合っていただきました。
-
お知らせ2026年02月17日
 お知らせ2026年02月17日
お知らせ2026年02月17日小説すばる3月号、好評発売中です!
平石さなぎさんの読切や村山由佳さんの新連載など小すば新人賞出身作家の作品が目白押し。北方謙三さんと織田裕二さん、美村里江さんとの対談2本も。
-
連載2026年02月16日
 連載2026年02月16日
連載2026年02月16日【ネガティブ読書案内】
第51回 古賀及子さん
ふられた時
-
インタビュー・対談2026年02月06日
 インタビュー・対談2026年02月06日
インタビュー・対談2026年02月06日ピンク地底人3号×鳥山まこと「言葉と物語が立ち上がるまで」
選考委員も「好対照」と評した作品で第47回野間文芸新人賞を同時受賞したお二人。贈賞式から間もない高揚感のままに、語り合っていただきました。
-
お知らせ2026年02月06日
 お知らせ2026年02月06日
お知らせ2026年02月06日すばる3月号、好評発売中です!
新作小説は上田岳弘さん、古川真人さん、佐倉ユミさん、三角みづ紀さんの4本立て。ピンク地底人3号さんと鳥山まことさんの対談もお見逃しなく。