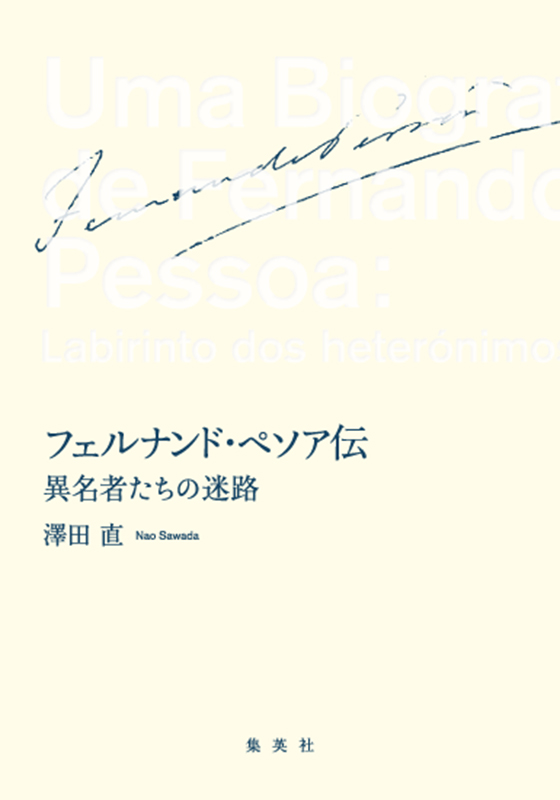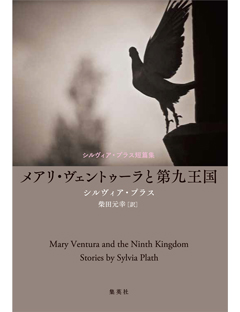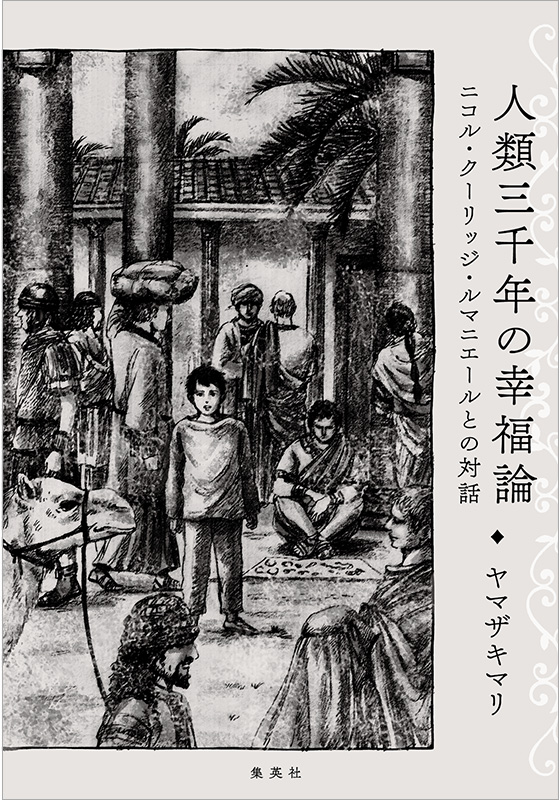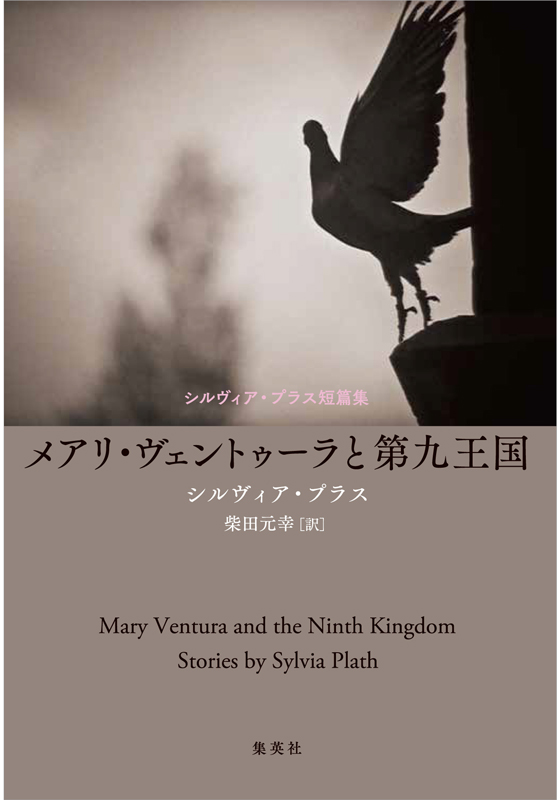『フェルナンド・ペソア伝 異名者たちの迷路』刊行記念対談 澤田直×山本貴光「人はなぜペソアに惹かれるのか」
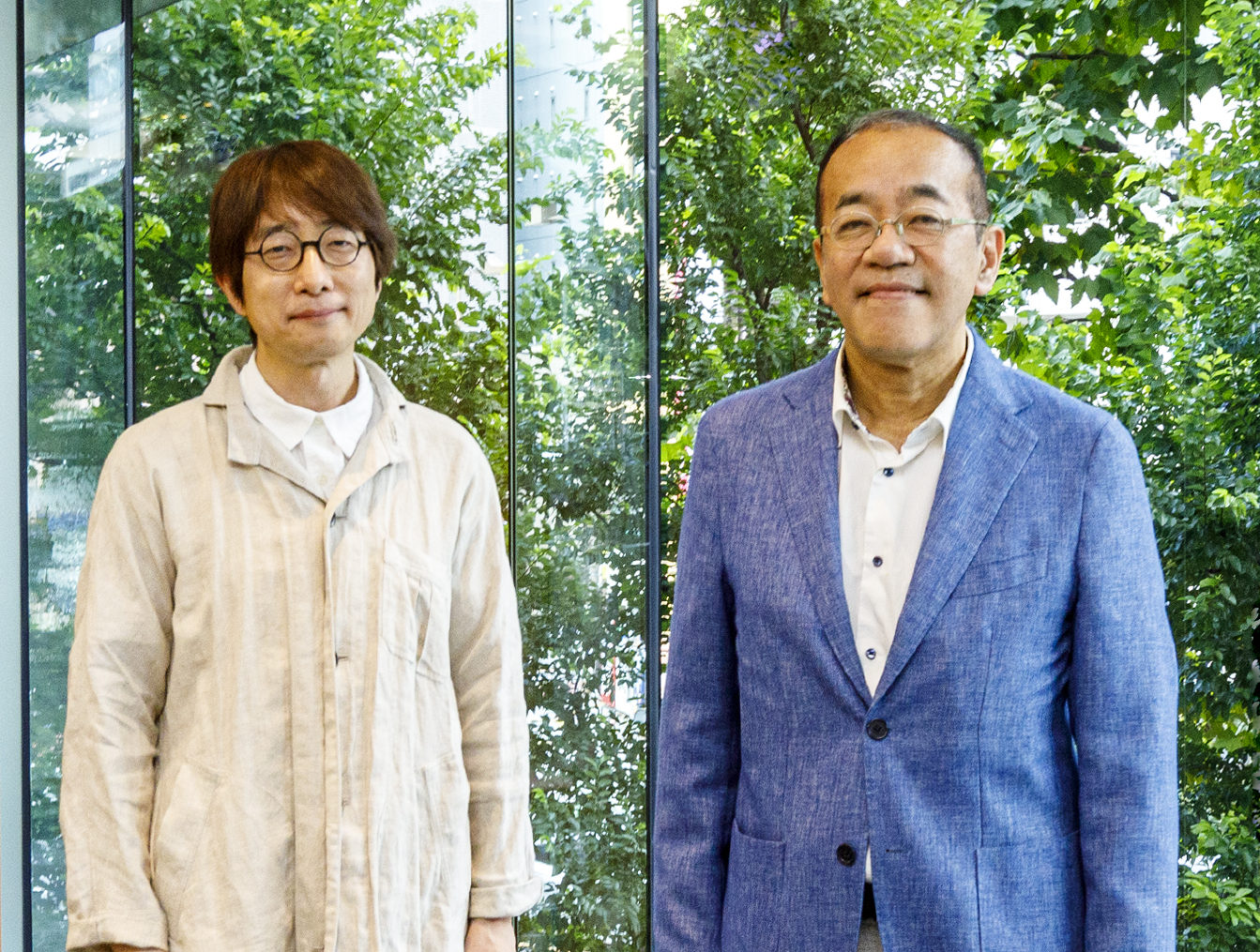
ポルトガルの国民的詩人フェルナンド・ペソア。自分とは人格の異なる人物を何人も創造し、書き分けたその多面的な作品は、タブッキ、ボルヘス、ヴェンダースなど多くの芸術家を魅了し、詩群誕生一世紀に及ぶ今日ますます輝きを増している。
長年ペソア作品を日本で紹介してきた澤田直氏がこのほど『フェルナンド・ペソア伝 異名者たちの迷路』を上梓したことを機に、自身もペソアに深く魅せられてきた文筆家でゲーム作家の山本貴光氏が、その創造世界について著者の澤田氏と語り合った。
構成/長瀬海 撮影/中野義樹
出会い
山本 ペソアが書いたものとはじめて出会って以来、ずっと大好きで繰り返し読んできました。澤田さんが「すばる」でペソア伝の連載を始めたときは本当に嬉しくて、毎号真っ先に読んでいました。今回、本のかたちになって欣喜雀躍しています。とはいえ、私はペソア研究者でもなければ、文学の研究者でさえありません。今日は一人の愛読者という立場でお話を伺わせてください。
澤田 ありがとうございます。山本さんが『不安の書 増補版』(高橋都彦訳、彩流社)の刊行イベントのために書かれた十六ページにも及ぶ配布資料を読めば、どれほどお好きなのかよくわかります。「異名者」とは何かだけでなく、ペソアの蔵書について、さらには「ペソアを楽しむためのミニガイドブック」まで、至れり尽くせりのものです。山本さんがペソアに出会ったのはいつでしたか?
山本 最初の出会いとなると少し曖昧なのですが、おそらくジル・ドゥルーズの本で触れたのがきっかけだったと思います。三十年ほど前でしょうか。彩流社から出ている『ポルトガルの海』を手にとって、もっと読んでみたいと思うようになりました。なかでも決定的だったのが、澤田さんの編訳による『ペソア詩集』(思潮社)です。これを読んで、今回のペソア伝で澤田さんも書かれていますが、なぜか自分のことが書いてあるような気がしたんですね。
どうしてそんなふうに思うのかといえば、やはりペソアの人間の見方でしょうか。彼の詩には、一人の人間が一人ではないという感覚、一人の人間のなかに複数のキャラクターが存在し得るという感じが強く響いています。自分をペソアと比べるのは不遜な気もしますけれど、私も一つの固定したアイデンティティという見方に違和感を覚えていたので、それでもいいんだと勝手に励まされました。高校では理系を選んだけど文系にも興味を持ち続けたり、大学を出たあとでゲームクリエイターの仕事をしばらくやって、現在は大学で哲学を教えていたり。本も互いに関係のなさそうなものを書いたりしているせいか、ときどき「同姓同名の別人がいるのかと思った」と言われたりします(笑)。そんなこともあって、自己紹介をしてくださいと言われると困るんですね。自分のなかに複数のものがあるのに、「要するに何者ですか」と一つにアイデンティファイするように期待されても困るなあと。
だからでしょうか。ペソアの言葉に触れて、この詩は自分が書いたんじゃないかと思うほど響いた。澤田さんが編訳された『ペソア詩集』はそのきっかけとなった一冊で、思い入れがあります。この詩集を読んでからというもの、ともかくペソアと名のつくものを見かけたら読む。あるいは、原語でも読みたいからポルトガル語の勉強をする、といったことをしてきました。と言っても、すんなり理解できたりはしないのですが。
澤田 そのお話は僕の体験とよく似ていて、とても共感できます。本のなかにも書いたのですが、僕は一九八五年からフランスの大学院で哲学の修士課程に入学しました。その年の夏にパリである本に出会いました。それが、ちょうど同年三月から五月にかけてポンピドゥー・センターでペソアの没後五十年を記念して行われた展覧会のカタログ風の書籍だったんです。
展覧会そのものは見逃したわけですが、この本を読んで、衝撃を受けました。まず、執筆陣として並んでいるのが、ボルヘスだったり、タブッキだったりするわけです。彼らが、ペソアという未だ世に知られざる詩人がいるのだが、これが実にすごいということを書いていて、そこを糸口に、ペソアの持っている不思議な世界に引き込まれました。ペソアという人の最大の特徴は、彼が「異名者」と呼ぶ、自分とはまったく人格の異なる人物を何人も創造し、彼らが独立して作品を書いたことにあります。「偽名」とも「筆名」とも違う「異名」というものが最初はよくわからなかったのですが、強い磁力を感じました。一人でありながら多面的であるなんて、果たして可能なのだろうか。そう思いながら、作品を手に取ってみたんです。折しも、フランスではペソアの作品の翻訳が少しずつ刊行されているところで、アルベルト・カエイロ、リカルド・レイス、アルヴァロ・デ・カンポスという主要な三人の異名詩人の詩だけでなく、どのようにして異名者が誕生したのか、その過程を説明する手紙なども読むことができました。仏訳のいくつかはバイリンガル版で、そのおかげでポルトガル語の原文にも触れることができたんです。フランス語とはかなり違うけれど、他のロマンス語も学んだ人間からするとまるっきり歯が立たないわけではない。そんなわけで、たまたま当時叔父が駐在でリスボンにいたので遊びに行き、原書を買い込んだりしました。そこからすっかりペソアに入れ込んで、一九八六年には同人誌にペソア論を書きました。
山本 なんという同人誌ですか?
澤田 『水色の卵』というかわいい名前の雑誌です。中西夏之さんのイラストを使わせてもらっていたり、小沼純一さんが寄稿していたり、あと、デビュー前の中島京子さんがペンネームで書いていたりする、立派な同人誌だったんですよ。そこに最初のペソア論を書いたんですが、今回、書庫をひっくりかえして取り出してみたら、論のタイトルが「異名者たちの迷路」(笑)。
山本 四十年越しに同じタイトルをつけることになったんですね!(笑)
澤田 そうなんです。まるで進歩していないことが判明しました。当時から哲学と文学の狭間にあるものについて考えていたので、詩人でありながら哲学的な作品を書くペソアには一気に惹きつけられました。それが最初の出会いでしたね。

「異名者」の背景
山本 澤田さんの御本の感想に入る前に、少し補助線を引かせてください。先日、科学史研究者の伊藤憲二さんが『励起――仁科芳雄と日本の現代物理学』(みすず書房)という本を刊行されました。二巻本の浩瀚な仁科芳雄伝です。仁科芳雄は二十世紀前半に活躍した物理学者で、時代的にもペソアと重なります。それだけじゃなくて、伊藤さんによると、普通は理論物理学者として理解される仁科芳雄が、実に様々な広い関心の持ち主だったようです。
同書の冒頭で仁科の言葉が引かれています。「環境は人を創り、人は環境を創る」という言葉です。伊藤さんもまた、環境と人のインタラクションのなかでこの評伝を書くと宣言していて、つまり、一人の人物の偉人伝として綴っていく旧来のスタイルではなくて、自然環境や社会環境のなかで仁科芳雄という人物がどうなっていったのかを書いておられます。人間関係や知的なバックグラウンドも含めて、ネットワークのなかの仁科を記述するわけです。これは、言うは易しですけれど、実際に書くのはとても大変なはずです。伊藤さんの本と澤田さんの『フェルナンド・ペソア伝』を同時期に読んで、改めて環境と人の関係に目を向ける重要性を教えられました。
澤田 ありがとうございます。ペソアの人生そのものは波乱万丈でもなく、大きなドラマがあるわけでもなく、むしろ単調な日々です。当時のポルトガルは、国王や元首が暗殺され、クーデターが頻発するという騒乱の時代ですから、亡命、逮捕、投獄などがあってもおかしくないのですが、そういったこととは無縁にひっそりと暮らしました。ですから、彼個人の人生だけを書いても面白みがないし、ペソアのすごさもわからない。彼の作品の素晴らしさは、外界のすべてがペソアという特殊な光学装置で変化して見える内部世界にあるからです。そこで、編集者と話し合って決めた最初の方針に、ペソアの言葉をなるべくたくさん入れる、というものがありました。
山本 そうでしたか。対比のために少し触れると、澤田さんのペソア伝の少し前に、ペソアの翻訳者でもあるリチャード・ゼニスが英語で一千ページを超えるペソアの伝記を出しましたね。これもありがたい労作ですが、贅沢を言えばちょっと細かすぎる印象を受けました。辞典のように読むにはいいんだけど、ペソアがどういう生涯を送ったのか、どんな社会で生きたのかとなると、なかなか頭に入ってこなかったりします。その点、澤田さんの評伝はバランス感覚が絶妙でした。
いまおっしゃったように、今回の『フェルナンド・ペソア伝』は編年体で書くだけでなく、ペソアが書いた詩や書簡やメモがたくさん引かれているので、ペソアのアンソロジーとしても読めて、これもうれしい点の一つです。そうしたペソアの言葉を引用しながら、彼が生きた環境もしっかり書き込まれている。ペソアと周りの人々が織りなすネットワーク、さらに社会や政治のことを近景、中景、遠景に置きながら、彼の生涯が記述されているので、ポルトガルの歴史に詳しくなくても、ペソアがどのような状況のなかで作品を書いていたのかが無理なく理解できます。
それに加えて、ペソアの複数性の扱い方も素晴らしいと感じました。先ほどのお話にもあったように、ペソアはいくつもの自分を持つ作家でした。読者としては、そんな作家をどう記述するのかが気になるところです。「ペソアはこういう人だ」とまとめ過ぎても、その複数性を取り逃してしまいます。澤田さんの評伝はそのバランスも見事でした。さらに驚いたのは、そんな複雑な作家を複雑なままに提示しているのに、ミステリを読むように読めてしまうことです。ストーリーの枠組みに嵌めて書いているわけではないのに、最後まで面白く読めて、得難い読書体験をしました。
澤田 そうおっしゃってくださって嬉しいです。僕としては単なる編年体の連記にしたくはなかった理由は他にもあって、彼が創造した「異名者」の世界の背景を明らかにしたかった。なぜペソアは異名者などという迂回路を通して、作品を書く必要があったのか。それについて、謎解きのような考察を少し入れようと思いました。その際に、たとえば、ペソアの仮面性について論じるときには、オスカー・ワイルド、ヴァレリー・ラルボーといった文学者やニーチェやキルケゴールなどの哲学者を引き合いに出して論じる、ということをしました。ただ、これらのいわば批評的な部分は小難しすぎる気もしていて、僕自身としてはその辺りに自信が持てませんでした。今の山本さんのご感想を伺って胸をなで下ろしているところです(笑)。
ゼニスの本は素晴らしい本で、細かい事実をたくさん書いてくれてありがたいのですが、一般読者からすると情報の洪水に流されてしまいかねない気がします。そうした細かい情報をどう取捨選択すればよいかというのは難しい点でした。そこで、僕自身がポルトガルの歴史や社会の専門家ではないので、ある意味、学びながら読者の方に理解してもらえるような記述をすればよいかなと考えました。一つひとつの固有名詞も、日本の読者には馴染みがないものばかりだから丁寧に説明することを心がけて。そういう意味ではペソアの入門書として読まれてほしいです。
山本 本文中で何度か、話が込み入ったところに行きそうになると、ここではこれくらい理解しておけば十分だろう、と切り上げていらっしゃいますよね。情報の遠近感というか、グーっと行けるところまで行くんじゃなくて、ここまでわかれば大丈夫というところで引く。その書き方が読者としては頼もしいガイドだと感じます。
澤田 本当はオタク的に細かいところを書いていく方が楽しいんですけどね(笑)。
山本 わかります(笑)。次はぜひ澤田さんには、容赦しない版のペソア論を書いてほしいと思います。
ペソアと漱石
山本 先ほど仁科芳雄の話をしましたが、もう一人、今回の評伝を読んで思い浮かべた同時代人がいました。夏目漱石です。漱石はご存じの通り、政府から英語の研究をするように命じられてロンドンに留学するんですが、それを無視して「リテラチュア」の研究をするわけですね。彼にしてみたら、それは未知の概念で、漢語でいう「文学」とイコールにして良いのかがわからない。大学の授業に出て、いろいろ聞いてみるもののピンとこない。それで本屋でいろんな分野の本を買い漁って、下宿に立て籠もってそれを読みまくる。自分で道を切り開く構えです。これはあとで伺えればと思うのですが、多方面に関心を向けたペソアと重なって見えます。
では、漱石がどういう落とし前をつけたかというと、古今東西のあらゆる文学を一般化しようとした。帰国後に東京帝国大学で「ジェネラル・コンセプション・オブ・リテラチャー」という文学論講義をやっています。当時の文学とは何かという議論では、社会の問題が書かれていないとダメだとか、人間の生き様を表現していなければいけない、なんてことが言われていた。でも、漱石はそういう捉え方では狭すぎて、同時代の局地でしか通用しないのではないかと考え、文学の一般理論を構築しようとした。そのとき土台にしたのが当時の最新科学である心理学でした。文学という営みを成り立たせている人間の意識や精神という基盤まで戻って捉え直そうというわけです。そこでもっぱら参照されたのは、ウイリアム・ジェイムズ流の意識観で、つまり意識とは川の流れのようなもので、次々と注意の焦点が移り変わってゆくというモデルでした。人はひとつのことにぐっと集中することもあるけれど、たいていは外からくる知覚や自分の中で生じるいろんな変化に次々と気をとられながら生きている。その移ろう内容を漱石は例の「F+f」(認識と情緒)として捉えたのでした。
ペソアも生きた十九世紀末から二十世紀にかけて、西洋では人間の心理への関心が高まっていましたね。無意識に目を向けるフロイトの精神分析しかり、「事象そのものへ」といい、意識の働きを探究したフッサールの現象学しかり。心理学の「意識の流れ」しかり。意識とは次々と移り変わるものだという書き方は、ヴァージニア・ウルフが得意としたものですが、ペソアを読んだあとに「意識の流れ」と呼ばれる文学を読むと、そこにあるのは何か単一の意識のように見えてくる。その点、ペソアはさらにラディカルで、意識がマルチプルというか、千々に乱れた状態を素直に認めて受け入れている。ペソアは同時代の心理学が前提としていた人間の意識の根っこにある単一性を認めていない気がして、それが百年以上の月日が経っても彼の作品が色褪せない理由なのかなと思います。漱石も意識の流れや個人主義について考えながら、個人というユニットそれ自体に疑いを持っていた。その視点を突き詰めると、ペソアのような考えに通じる気がしたのでした。
澤田 いやぁ、とても面白い捉え方ですね。刺激的な批評をありがとうございます。まさに漱石があの時代に生きた矛盾を、ペソア自身も抱えていたんだと私も思います。ペソアは、母親が外交官と再婚した関係で、継父が赴任する南アフリカのダーバンで八歳から十七歳までを過ごし、そこで英国風の教育を受けるのです。漱石の留学とは違うけれど、生まれ育った南欧のカトリック文化圏から引き離され、植民地というバイアスがかかったイギリス文化のなかで思春期の人格形成を行うのです。もちろん、親はポルトガル人ですし、家庭ではポルトガル文化との接点もあったのでしょうが、学校ではまったく違う世界があった。そこには大きなギャップがあって、彼のなかにはそれが唯一という考え方、単線的な価値観の基準はなかったと思います。
青年期、リスボンに単身帰国するわけですが、いま風に言えば帰国子女的な感じで、周囲から浮いていたのではないでしょうか。たとえば、彼が詩人として活動していた頃、ヨーロッパでは第一次世界大戦が起き、それと前後して多くの芸術潮流が起こります。友人たちの目はこぞってパリの方に向いているのに、ペソアの関心はむしろロンドンです。むろん、未来派などに共鳴し、アルヴァロ・デ・カンポス名義ではそういった作品も書いていますが、リカルド・レイス名義の詩には、ギリシャやローマの古典が重要な要素になっています。彼のうちにあるこのような多様な関心が、様々な異名を生み出したことの背景にあるかと思うのです。誰しも自分のなかに矛盾した要素を抱え持つわけですが、ペソアはそれらをヘーゲル的にアウフヘーベンするのではなく、むしろばらばらなものを積極的に拡散し、乱反射させていく。ペソアは人間の意識を捉える上で、そういう戦略を取ったんだと私は思います。たとえば山本さんが例として挙げたフッサールの現象学に似た考えをするのが、見える世界は見えるがままだとする自然詩人のアルベルト・カエイロという異名者なわけですが、ペソア自身の世界観は必ずしもそうではなくて、見える世界の背後にある隠れた世界を追求します。一方で、カンポスの人格になると、突然、機械文明が全面的に展開するという次第で、まるで片付けができない子供部屋のような光景がペソアという多数詩人のうちにある。一人のなかにある複数の自分をそのまま引き受けているわけです。
だからペソアに関しては、ビルドゥングス・ロマンのような、成長していく人格ではなく、むしろ分人主義的な捉え方をしたほうがわかりやすいと思います。垂直方向に展開していくのではなくて、水平方向に移動変化していくのです。本人は、「私は進化するのではなく、旅をするのです」と説明しています。ペソアは作品が完成する前に関心が別のものへと移っていってしまう癖があるために未完の作品を多く残したんですが、その理由もそこにあるのではないでしょうか。ペソアのなかにはポルトガル最大の詩人カモンイスが書いた叙事詩『ウズ・ルジアダス』のような趣きがあると思えば、一方で、コスモポリタンを意識している部分もある。どっちかではなく、両方あってもいいんだよね、と引き受けている。そこがやっぱり面白くて、科学を信奉しながらもお正月には初詣に行ったりする、我々、現代の日本人の共感を呼ぶのかもしれません。
山本 ごたまぜでも平然としている。ところで、漱石の前任者のラフカディオ・ハーンは学生たちに向けた最後の授業で、文学にもその時々の流行があって、古典的なものと前衛的なものの間を揺れ動いているのだ、と説いています。どちらか一方だけではなく、両方を見ておかなければダメだ、というわけです。ペソアの意識や関心は、そういうリニアな展開ではなく、古典的な趣味だったり前衛に近づこうとする趣向だったりが並行していますね。
つまり、あれかこれか、ではなく、あれもこれも、なんですね。あれとこれにそれぞれキャラを配分すれば、異名者になる。現代のコンピューターのOSを連想します。OSはいくつものアプリケーションを同時に動かせるので、一見、マルチタスクを実現しているように見えます。でも、その実、CPUの稼働時間を細かく分けて、断片化している。ワードを動かして、ブラウザを動かして、メーラーを動かしてと、ぐるぐる超高速回転しながら断片を渡り歩いている。ペソアはそれに近くて、今はカンポスでも、別のときにはカエイロになる。そういう意味では、同時並行ではなく、疑似並行とでも言いましょうか。
澤田 そうした意識や関心の複数性は彼が遺した蔵書を見てもわかりますね。あと、本のなかにも書いたのですが、ペソアは実務には不得手で、何度も小さな会社を立ち上げてはすぐに失敗しちゃうんですが、政治や商業の理論的なことには詳しい人でもあり、それについて書いた論文もなかなか面白いのです。考えれば考えるほど、不思議な人です。
蔵書という思想
山本 今、蔵書のお話が出ましたが、ペソアの蔵書は記念館に収められていて、同館のウェブサイトで目録が公開されていますね。以前、その蔵書を自分でリスト化して、言語やジャンルで分けて一覧にしてみました。母語のポルトガル語だけでなく、英語、フランス語、それからローブ古典叢書という、古代ギリシャ語・ラテン語の古典作品に英語の対訳を付したものまである。
澤田さんにお聞きしたいのですが、ポルトガルに生まれ、イギリス文化に浸かりながら、これだけ多言語の本を読み、英語だけでなくフランス語でもものを考えたり書いたりするという経験はペソアにとってどういうものだったのでしょうか。たとえば、澤田さんご自身も日本語を第一言語としながら、先ほどお話しくださったように様々な言語に触れてこられましたよね。ご自身のなかで言語同士が相対化されたりするものでしょうか。
澤田 複数言語を生きるという問題は、今、文学を語る上で重要なテーマになっていると思います。ペソアには比べるべくもないのですが、僕自身はたまたまフランス人が作った学校に十二年間通っていたために、入学式や卒業式には日の丸と三色旗が並んで掲揚され、「ラ・マルセイエーズ」と「君が代」を斉唱するという奇妙な環境で成長しました。他の世界を知らないので、世の中そういうものだと思っていました(笑)。その後、フランスで勉強し、私生活でもフランス語を話す時間がかなり多いので、複数言語を生きる人間と言えるかもしれません。ただ、そういう人はいまかなり増えているのではないでしょうか。
ペソアに戻れば、やはり、南アフリカで英国風の教育を受けたことが大きかったと思います。古典文学に対する関心はそこで培われたはずですから。彼の場合、日常会話はポルトガル語で行われたのかもしれませんが、知的、かつ、理論的な思考は生涯にわたって英語がメインだったように思われます。当時、ポルトガルの上流階級の人たちはフランス語を喋る人が多く、作家たちもフランス語で作品を発表していました。そんななかで英語で書く作家は、同時代の人々にとっては違和感や異質感を感じさせたかもしれません。複数言語の問題は翻訳の問題とも関わることで、ペソアという人を考えるときに鍵になると思います。ちなみに、ペソアが生涯にわたって生活の糧としたのは商業翻訳の仕事でした。
山本 言語環境もものの見方を育むわけですね。ペソアの蔵書に含まれている言語関連の本の割合を調べてみると、英語がダントツです。私が検討した限りのことではありますが、六百八冊で全蔵書のほぼ半分。第二位がポルトガル語で、約二十五パーセントの三百七冊。フランス語は第三位でした。こんな風に母語ではない言語が蔵書に占める割合の最上位に来るのは面白いですよね。澤田さんがおっしゃったように、英語で知的にものを考える実践をしていたというのは、ここにも表れているのかもしれません。ペソアは学校で古典語も習ったのでしたね。
澤田 ラテン語は習っていましたね。
山本 そうですよね。そのつもりで蔵書を見ると、言語そのものにも関心があった様子も窺えます。語学関連では、ギリシャ語、ラテン語、英語、ポルトガル語の他にドイツ語、エスペラント語、ヒッタイト語、それからバントゥー語の書物まである。
澤田 すごいですよね。驚きます。
山本 私もそこまでとは、とびっくりしました。実際どこまで勉強して、どこまで読み書きできたのかはわかりませんが、少なくとも関心があったのは事実だと思います。他にも気になるのは、蔵書に理工系の本が並んでいるところ。ざっと見てみると、一番多いのは言語学、文献学、文学で六百六十八冊。数学、化学、応用化学、薬学、工学といった理工系が四十八冊。哲学、心理学が百七十四冊。文理がこれだけ分かれてしまった私たちの時代から考えると、詩人のペソアが理系的な知にこれほどの関心を持っていたことはとても興味深いです。
澤田 ええ。ペソアのなかに百科全書的な関心というのは紛れもなくあったと思います。世界を丸ごと、そっくりそのまま捉えたいというか。それは理解したいというのとも違う、不思議な欲望だったように思われます。一言で捉えたいと言っても、知的に、感覚的に、感情的に捉える方法があると思うのですが、ペソアはあらゆるレベルであらゆるものを捉えたいと思った。ですが、薬学や化学、工学にまで手を伸ばすというのは、なかなか面白いですよね。僕はそこまで精査して見ていなかったので、山本さんに教えてもらって、なるほどと思いました。
山本 私はペソアの関心の散らかりようが気になるのでした。蔵書といえば、今度復刊される山口昌男さんの『本の神話学[増補新版]』(中公文庫)に解説を書く機会があって再読しました。あの本で山口さんはヴァールブルク文庫を紹介しています。ヴァールブルク文庫というのは、銀行家の息子で美術史家になったアビ・ヴァールブルクが美術史の研究のために買い集めた書物や資料を収蔵したアーカイヴです。山口さんは、そこに注目して、書棚とはそれ自体が思想の表現なんだと強調している。つまり、どんな本をどんな風に集めて、どうやって並べているのか、それもまたその人の世界の見方、コスモロジーの表現なんだと言うわけです。山口さんがそのような文章を書いてから五十年近くが経ち、デジタル環境がこれだけ発達した時代になって、いっそう身に染みる指摘です。ある人が、本をどう集め、どう並べたのか。いつも目に入る物理環境としての書棚に思想の表現がある。その人が何に関心を持って、何を考えたのかの痕跡である蔵書って、その人物や時代について知りたい後世の者にとっても重要なアーカイヴなんですよね。

計画倒れの人
山本 これは澤田さんのご本を読んでいて、ちょっと笑ってしまったところなんですが、ペソアは計画を立てるのが本当に大好きですよね。子どもの頃からいろんな計画を立ててはそれが実現せずに終わっちゃう。
澤田 そうそう。ポルトガルの国立図書館のアーカイヴに多数のノートや手帖も残されているのですが、そのほとんどが、このような計画の箇条書きです。若いときからノートにたくさんやりたいことを書くんだけど、その半分も実現しない(笑)。計画だけで終わってしまう。でも、性懲りも無く、同じ計画をまた立てていく。
山本 つい自分を重ねてしまいますが、私も計画するのが大好きで、勝手に共感しています(笑)。もちろん計画を立てるだけでは現実は変わらない。でも、何か構想を練っているときって、ちょっとしかつめらしく言うと、現実を変えることへ向かう潜在性を計画している感じがするんですよね。それが何かの拍子で実現したなら、それによって世界がちょっと変化する。計画を考案している人の頭のなかにあるのは、そういう別のあり方への希望や期待でもあるわけですね。ペソアが計画好きだというのは、いい話だと思います。
澤田 そうですよね。ペソアは野望がかなり大きいんです。本人の生活とはかけ離れた、大規模な計画をいつも立てている。たとえばポルトガル文化を世界に普及することを目的とした「ポルトガル倶楽部」という大きな組織のプロジェクトもある。実現可能なちまちましたものではなくて、古典作品の叢書を受け持つ出版部門、正書法改革を担う言語部門、その他もろもろあって、ほとんど国家規模の事業のような計画で、びっくりします。誇大妄想というのとはちょっと違う、気宇壮大なところがあります。
山本 若い頃に、転がり込んできた遺産を使って自分の評論を刊行するための出版社を設立するでしょう。あの話を読んでバルザックのことを思い出しました。彼の場合は儲けのためだったかもしれないけれど。
澤田 鹿島茂さんの解説によると、バルザックは小説家がなぜ儲からないのかを考えた結果、出版社が搾取しているからだと思い至ったようです。それで、自分で出版社を立ち上げたんだけど、全然儲からない。今度は印刷所が搾取してるんじゃないかと考えて、印刷所を始めた。でも、事業はことごとく失敗し、借金まみれになり、それを返済するために次から次へと作品を書いた。印税をもらうことが結局は一番稼ぎが良かったというアイロニカルな結末です(笑)。ペソアの場合、実際にポルトガル語で刊行した詩集は『メンサージェン』だけでした。これが刊行された理由はいくつかありますが、大きかったのは賞金目当てだったことです。当時、独裁体制を確立したばかりのサラザールの国民広報局が国威発揚のために、公募の文学賞を開催するのです。ペソアの友人が企画に絡んでいたこともあって、ペソアは賞金目当てに応募しました。結果は次点に終わってしまうのですが。この文学賞がなければ、計画倒れのペソアのことですからこの詩集も完成しなかったかもしれません。
『メンサージェン』は、英語で言えばメッセージですが、建国神話を扱う詩集です。この詩集については今回の伝記のなかで一番書き切れなかった部分が多いです。ペソアにとって祖国とは何か、偏狭な愛国心とは異なるパトリオティズムとは何かという問題は複雑なものです。彼は当時の政治家たちが考えるようなポルトガル復興の動きには反対でした。でも、一方で、彼のなかにはポルトガル語は偉大な帝国的言語だという確信があるのです。そういう複雑な葛藤を抱えながら、建国の偉人たちを主題に、あたかもカモンイスに対抗するかのような詩集を編む。ストレートな詩もありますが、全体を捉えるのは難しい。いまだに僕にはあの詩集はわからない。その凄さが実感できないと言いますか。
山本 私もあの詩集はうまく読めなくて、なぜだろうと考えていたのですが、今回の評伝を読んで腑に落ちました。やはりポルトガルの歴史や政治的な状況を知悉していなければ、読み難いところがあるのですね。
澤田 唯一共感できるのが、セバスティアン王の神話のところですね。彼は見果てぬ夢を見て、無謀な戦争を起こし、ポルトガル凋落の原因を作ったダメ王様です。ところが、その彼が神話となり、いつかセバスティアン王が霧のなかからおぼろげな姿を現し、ポルトガルを復興するというメシア的な存在に、民衆の想像力のなかで変化する。そこに、ペソアはアンビバレンツなポルトガルの未来を読み取ります。ただ、この詩集はペソアがポルトガル語で刊行した唯一の作品なので、ペソアが気になった人が最初にこの本に手を伸ばすと……。
山本 そこで終わってしまう。
澤田 ええ。かといって『不穏の書』を読もうと思っても、最初から最後まで読むのがなかなか難しい。半―異名者ベルナルド・ソアレスが著者とされる『不穏の書』は、ペソアの散文作品のなかではダントツに面白いんですけれど、未完の草稿ですから、途中だれるところもあって、通読はむずかしい。そこで、これを訳出するときに、そのエッセンスだけを選び、他のアフォリズム的な言葉と併せて、『不穏の書、断章』という形で一冊にまとめてみたんです。この構成は今回の単行本でもお世話になった編集者の佐藤一郎さんの卓見でした。ペソアの作品のあらゆるところにキラキラ輝いている短い文章。そういう断片から入ればペソアの凄さがわかるのではないか、と。あれは、佐藤さんのそんな考えから生まれた本でもあるんです。
ペソア・ウイルスに感染すること
山本 『不穏の書、断章』は、はじめてペソアに触れる人にも親切な構成だと思います。私が教えている東工大は理系の学生が中心で、入学前は本を読んだことがないという人もたくさんいます。そんなみなさんに『不穏の書、断章』から「私と自己について」を紹介すると、授業のあとで「これは自分のことだと思いました」と感想を教えてくれる人が毎回います。自分事として詩に出会うわけです。あの本は、巻頭に置かれたペソアについての言葉や断章から、『不穏の書』のほうへ誘うという編集がとてもいいなと感じています。
そもそも『不穏の書』の場合、これが唯一というエディションはないんですよね。だから本を編む人がその配列を作ることになる。これは私が親しんでいることに重ねるなら、どこかカードゲームに似ていると思います。ペソアの詩を読むのは、カードゲームのデッキ(カードの組み合わせ)を作るのに近い。誰かが作ったデッキをそのまま受容する読者もいるけれど、深く入れ込むと、自分だけのデッキを編んでみたくなる。そういう風に読者を作り手の側に引き込んでしまう力を持っているのが、ペソアの詩なのではないかと思ったりもします。
澤田 まさにおっしゃる通りだと思います。完全に固定された完成した作品にはない、そういう可動性がペソアのテクストの魅力ですし、シャッフルして自分なりに並べ替えたときに、また違う風景が見えてくるというのもペソアならではですよね。
山本 『不穏の書』には、人間の心は風景みたいなものだし、天気のように入れ替わっていくものなんだということが書かれていますよね。そういう一つの精神状態を「断章」という形で固定はしているんだけれども、配列やボリュームはこれと定まっていないので、いくらでも並べ替えることができる。どういう順番で読むか、決まっていないわけですから。
澤田 それでいて、ペソアには一度、読む人のなかに入るとそこで増殖していく感じがあるんですよね。先ほどの学生さんのように、感染してしまうとなかなか抜け出せなくなる。だからこそ、文学だけでなく、映画、音楽、舞台芸術に携わるいろんな人たちが自分のペソアを作っていこうとなっています。ヴィム・ヴェンダース、マノエル・ド・オリヴェイラといった監督、アントニオ・タブッキ、ジョゼ・サラマーゴといった作家たちが、自分のペソアを造形していく。ペソアを読むことが終着点じゃなくて、出発点になっているのが面白い。私はこれをよく、ペソア・ウイルスに感染すると言っています。最近のご時世だと少し使いづらいのですが。
山本 本当にそうですね。ウイルスといえば、ウィリアム・バロウズが「言語ウイルス」という喩えをしていましたね。そもそも言語は自分で発明したものじゃない。どこかで誰かが作って使ってきたその集積を一旦受け入れて、自分の身体を明け渡す感じが私にはあります。言語ウイルスと共生することによって、考えや行動が変わるというか。そこにきて、さらにペソア・ウイルスに感染すると、手が勝手に動いたり、体がどこかに出かけていってしまうような感覚を覚えます。ペソア・ウイルスが頭のなかで動き始めて、何者かになる。澤田さんも評伝のなかで「ペソアの言葉を書き写すのは、なんだか少しだけペソアその人になったようで心地よい経験だ」と書かれていました。これは本当にそうだと思うし、なぜペソアだとそうなるのか、どこに秘密があるのか、不思議ですよね。
澤田 今、山本さんがおっしゃった言語の問題は重要で、ペソアを読むという経験はある意味では外国語を習得することに似ていると思うんです。英語を学習し始めると身振りが突然、大きくなったりするじゃないですか。あれと同じで、ペソアが入った瞬間に自分の行動が変わるというのは、異物を受け入れ、それに支配されることで、ドーパミンが溢れ出るからなのかもしれません。突然、ポルトガルに行きたくなったりしますしね。
山本 突然、仕事を辞めちゃったりするかもしれない(笑)。あるいは、明日できることは今日しなかったり。
澤田 でも、計画だけはたくさんある(笑)。
山本 そうそう、夢みがちになったりしてね(笑)。
オカルティズムとペソアの関係
澤田 最後にオカルティズムの話をさせてください。今回、伝記を書くうえで難しかったもう一つはオカルトの部分でした。彼のオカルティズムをどこまで本気で読まなければいけないかがわからなかったのですが、ペソアを理解するためにはオカルティズムは避けて通れません。彼はその手の本を多数読んでいただけでなく、ブラヴァツキーやベサントを翻訳出版しています。また、秘教的な詩も多数書いているし、そもそも『メンサージェン』という詩集が「隠れたるもの」を巡るメッセージなのです。ペソアはキリスト教を否定し、異教的な世界を再構築することを提唱しているわけですが、その一方で、オカルト的なものこそが世界の真理を教えてくれると確信に満ちた手紙も書いています。
山本 オカルティズムについての章で、アレイスター・クロウリーとの交流も書き込まれていますよね。あそこはとても愉快に読んだ一コマでした。先ほどお話に出たように、ペソアは同時代の科学にも関心があった。蔵書には相対性理論に関する本もあったりして。二十一世紀の現在から見ると、科学とオカルトは相容れない感じが強いかもしれませんが、二十世紀初頭は科学とオカルトは重なって見えるようなところがあったように思います。
少しペソアの文脈から外れますが、二十世紀のはじめ頃、特殊相対性理論が提示されて程なく、アインシュタインの先生の一人、ヘルマン・ミンコフスキーが「四次元」という概念で整理しました。三次元の空間に時間という一次元を加えてまとめて扱おうというわけです。それと前後して、シュルレアリスムや未来派など、前衛芸術の各方面で四次元という概念(ミンコフスキーの用法とは違う場合もありますが)に刺激を受けた作品が現れています。一枚の絵に時間的に連続した一連の動きを表現するような絵画は分かりやすい例でしょうか。四次元という科学の概念が、他の分野にも波及していたわけです。これは、神秘思想やオカルトにも親和性の高いアイディアだったと思います。
澤田 確かにそういう同時代性は重要ですね。ベルクソンだって神秘主義に強い関心を示していましたし、他にも二十世紀初めのフランス哲学では神秘主義がきわめてまじめに論じられていた時期があります。ペソアの場合は、神智学、グノーシス主義、薔薇十字思想など異端の思想全般に通底するものを真剣に考えていました。
山本 そうですよね。科学は基本的に繰り返し確認できる現象を相手にしますが、それで万事を説明できるわけではない。それ以外のことをどう理解できるか。百科全書的な関心を持っていたペソアが、オカルトにも興味を向けていたのは自然なことなのかもしれません。あと、個人的にもう一つ面白かったのは、ペソアの占星術好みです。異名者のホロスコープを描いたりしている。占星術の知は、ヨーロッパの文脈でいえば、少なくともルネッサンス以来、人々が地上と天空の出来事を照応させて考えていたことを明かすものだと思います。自分と結びついた天体が今どうなっているのかを見れば、その運命も読み解けるという発想がその基礎にありました。ということは、マクロコスモスのなかのミクロコスモスたる自分が連動して何か起きている、といった宇宙の見方を好んでいなければ、ホロスコープを描いたりしなかったと思うんですよね。
澤田 おっしゃる通りで、ペソアはそういう意味でも、近代的な自我とはまったく違う世界観を持っていました。近代的な自我の考えというのは、環境から遮断されてもそれだけで存在するものですよね。デカルトの哲学はまさにそのようなものでした。でも、ペソアはそういう風には考えない。あらゆるものが環境との関わりのなかで存在する。だから、自分や知人といった個人のホロスコープだけではなく、『オルフェウ』といった雑誌自体のホロスコープも作っていた。ペソアは一時期、職業的な占星術師になろうと考えていた時期もあるほどのめり込んでいて、異名者のなかにはラファエル・バルダヤという占星術師もいます。
山本 雑誌のホロスコープ! そう考えるとペソアって、彼が書いたものも含めて、エコロジカルだと思うんです。「自然を守ろう」という意味でのエコロジーではなく、その言葉を作ったエルンスト・ヘッケルの、あるいは、その意味をさらに拡張したフェリックス・ガタリの文脈におけるエコロジー。ガタリは、かつて環境問題が取り沙汰されたときに、多くの人は自然をどうにかしようと対症療法的に考えるけど、それだけでは駄目だと言いました。エコロジーは自然環境だけの問題ではない。我々は社会というエコロジーも作っているし、そのなかにいる個人の精神のエコロジーもある。だから、自然環境と、社会、それから個人の精神、少なくともこの三重のエコロジーで物事を見なくては地球環境の問題は解決できないのではないか、と考えたわけです。つまり、ここで言われているのは、複数の重なり合う関係をどう見るかという問題ですよね。それこそ仁科の言葉ではありませんが、環境のなかにいる私が環境を変える。その環境によって私が変わる。そこがどうもペソアに重なるような気がするんです。
澤田 まさにそうですね。だから、ペソアには多島海をモチーフとしたカリブ海の詩人・思想家エドゥアール・グリッサンが提唱した「〈関係〉の詩学」という考えに通じる部分があると思います。単一起源ではなく、複数のパースペクティヴに基づいて捉え、開かれたアイデンティティを考える。そういう意味では、ペソアって、ポストコロニアルだったり、複数言語だったりといった現在、世界文学が問題にしているような主題系を先取りしていた作家でもあるんですよね。
山本 それは今日のお話にもあった、彼が計画を最後まで完成させずに、断章をたくさん残したこととも関係すると思います。つまり、ストーリーが完全に固定されていると、その文脈で捉えなければならないのですが、ペソアの場合、文脈から離れてもなお、魅力を持ち続ける。接続可能性が高いとでも言いましょうか。そんなこともあってか、エコロジーを考えざるを得ない我々にとっても、そのまま使えてしまう遺産の山なんですね。
澤田 そうそう。だから逆に断片がまた生きてくるんです。一つのユニットとしてのペソアの世界はもちろんあるんだけど、でも、それは無数のピースからできあがっていて、それぞれの機能が一つじゃないから、それらをマルチに転換できるわけですよね。このピース、こっちに置いても繋がるじゃん、というのがペソアの面白いところです。逆にばらばらに分解しても読めてしまいますし。
山本 しかも作品を通して、他であること、変わり得ることを肯定している。受け取った側もそうでもありえるのか、と気づかされる。一つの不変的な個という息苦しさから解放してくれるというのかな。そういう作用があるのも魅力です。
澤田 だから現代風な言い方をすると、ダイバーシティを肯定するような懐の深さがあるから、息苦しさを感じている人たちにぜひ読んでほしいですね。なかなか話が尽きませんが、話がまとまらないというのも、ペソアらしくて良いかもしれません(笑)。
(2023・7・22 神保町にて)
「すばる」2023年10月号転載
プロフィール
-
澤田 直 (さわだ・なお)
1959年、東京生まれ。パリ第一大学大学院哲学科博士課程修了。現在、立教大学文学部教授(フランス文学)。
著書に『〈呼びかけ〉の経験:サルトルのモラル論』(人文書院)、『新・サルトル講義:未完の思想、実存から倫理へ』(平凡社)、『ジャン=リュック・ナンシー:分有のためのエチュード』(白水社)、『サルトルのプリズム:二十世紀フランス文学・思想論』(法政大学出版局)など。
訳書にフィリップ・フォレスト『洪水』(共訳、河出書房新社)、『シュレーディンガーの猫を追って』(共訳、河出書房新社)、
『夢、ゆきかひて』(共訳、白水社)、『荒木経惟つひのはてに』(共訳、白水社)、『さりながら』(白水社)、ミシェル・ウエルベック『ショーペンハウアーとともに』(国書刊行会)、J-P・サルトル『真理と実存』『言葉』(以上、人文書院)、『自由への道』全6巻(共訳、岩波書店)、『家の馬鹿息子:ギュスターヴ・フローベール論』4巻、5巻(共訳、人文書院)、フェルナンド・ペソア『新編 不穏の書、断章』(平凡社)、『ペソア詩集』(思潮社)などがある。 -
山本 貴光 (やまもと・たかみつ)
文筆家、ゲーム作家。1971年生まれ。著書に『マルジナリアでつかまえて』『「百学連環」を読む』『文学問題(F+f)+』、共著に『世界を変えた書物』『人文的、あまりに人文的』『高校生のためのゲームで考える人工知能』、訳書にサレン/ジマーマン『ルールズ・オブ・プレイ』などがある。
新着コンテンツ
-
新刊案内2024年07月26日
 新刊案内2024年07月26日
新刊案内2024年07月26日地面師たち ファイナル・ベッツ
新庄耕
不動産詐欺の組織犯罪の闇に迫る、新時代のクライムノベル『地面師たち』の待望の続編!!
-
インタビュー・対談2024年07月26日
 インタビュー・対談2024年07月26日
インタビュー・対談2024年07月26日新庄耕「釧路がシンガポールになる、というあり得なさで「いける!」と」
今夏Netflixでドラマシリーズ化された前作と、その待望の続編である本作への思いを著者に伺いました。
-
インタビュー・対談2024年07月19日
 インタビュー・対談2024年07月19日
インタビュー・対談2024年07月19日青波杏「「語れない」をテーマに描く、女性同士の繫がりと植民地の歴史」
現代の台湾に生きる女性二人が、古い日記に隠された真実を探る物語。謎と日常、過去の歴史と現在が交わる中で見えてくるものとは。
-
インタビュー・対談2024年07月19日
 インタビュー・対談2024年07月19日
インタビュー・対談2024年07月19日ファン・ボルム「休めない社会だからこそ、休む人たちの物語を描きたいと思った」
本屋大賞翻訳小説部門第1位に輝き、ロングセラーを続けている本作への思いを、著者のファン・ボルムさんに伺いました。
-
お知らせ2024年07月17日
 お知らせ2024年07月17日
お知らせ2024年07月17日小説すばる8月号、好評発売中です!
奥田英朗さん「家」シリーズの待望の新作読切を始めとした大特集のテーマは”家族”。新川帆立さん、遠田潤子さんの対談も必読です!
-
連載2024年07月12日
 連載2024年07月12日
連載2024年07月12日【ネガティブ読書案内】
第32回 浅倉秋成さん
「ポジティブ思考が羨ましくて仕方がない時」