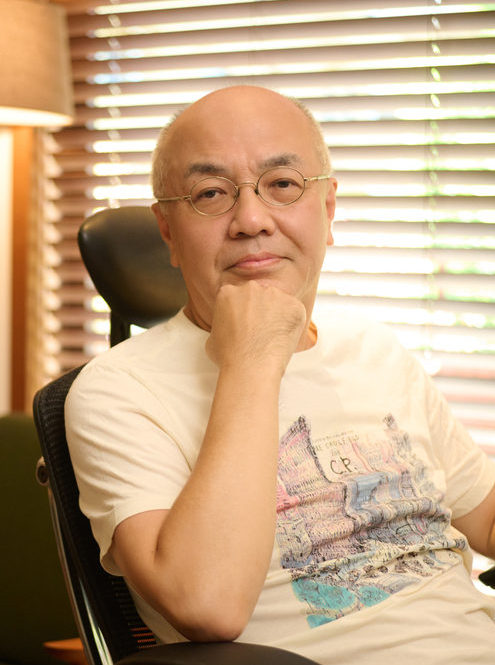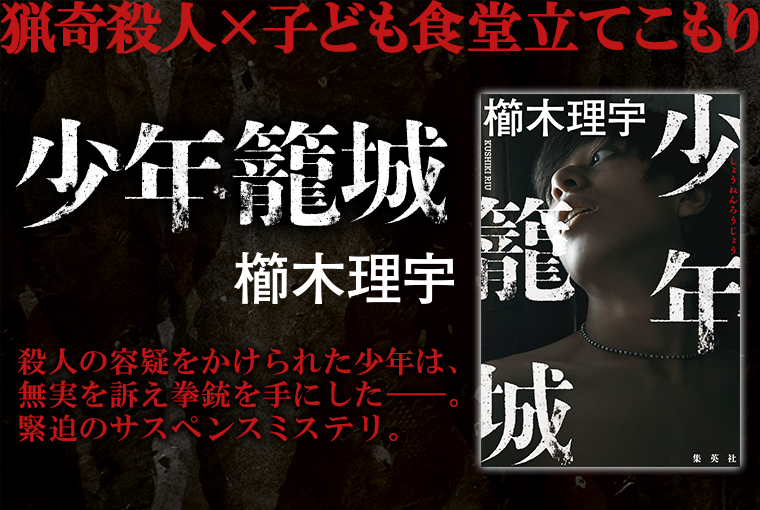
内容紹介
猟奇殺人×子ども食堂立てこもり
究極のサスペンスミステリ
地方の温泉街の河原で、子どもの惨殺遺体が発見された。
警察は、小児わいせつ事件を繰り返していた15歳の少年・当真への疑いを強める。
逃亡中の当真は警官の拳銃を強奪し、子分とともに子ども食堂に立てこもった。
自分は無実で、人質を殺されたくなければ、警察は真犯人を捕まえろという。
子ども食堂の店主・司は、人質の少年少女を守るために戦うことを誓うが――
当真は本当に無実なのか。他に殺人犯はいるのか。
さらに新たな遺体が発見され、暴走する当真は引き金に指をかける――
誰もが予想できない結末が待つサスペンスミステリ。
プロフィール
-
櫛木 理宇 (くしき・りう)
1972年新潟県生まれ。2012年『ホーンテッド・キャンパス』で第19回日本ホラー小説大賞読者賞を、同年『赤と白』で第25回小説すばる新人賞を受賞。
プロローグ
記憶の中の〝梨々子ちゃん〟は、いつまでも十一歳のままだ。
彼女との思い出は、たいてい柳楽家の書庫とセットになっている。ずらりと並ぶ本の背表紙。古紙の黴くささ。天窓の磨りガラスから斜めに射しこむ光の帯。その帯の中で降るように舞う、こまかな塵。
そんな書庫の壁にもたれて座り、いつも梨々子は本を読んでいた。
だが柳楽家の長男である司には、書庫など場所ふさぎで鬱陶しいだけだった。
「あんなのより、おれはゲーム専用の部屋がほしいよ」
「じゃあ司くん、立場を取っ替えて」
司が愚痴るたび、梨々子はそう反駁した。
「わたしが司くん家の子になるから、司くんはうちの子になりな。うちなら一日じゅうゲームしてようがテレビ観てようが、親はなんにも言わないよ」
「おー、いいね。取り替えようぜ」
応じながらも、「それはやだな」と胸中で司は思う。
司の家には父親しかいない。〝梨々子ちゃん〟には母親しかいない。お母さんがいることも、一日じゅうテレビを観ていられることも、確かにうらやましい。でもやっぱり〝梨々子ちゃん〟に成り替わりたいとは思わない。
――だって、〝梨々子ちゃん〟のうちは。
そんな司の心を悟ったか、梨々子がふんと鼻を鳴らし、ふたたび本をひらく。
かぼそい腕にはいくつもの青痣がある。火傷の痕があり、刃物でできたらしい古傷が走っている。
その日とくに目立っていたのは、左目をぐるりと囲む痣だった。治りかけの痣は紫に変わりつつあり、まわりはぞっとするような暗黄色でまだらに染まっていた。
――でも、傷のことだけじゃない。
家をほんとに〝取り替え〟たなら、きっと彼女はもうおれと遊ばない。
梨々子ちゃんのお目当ては、おれじゃなくこの書庫だ、と彼は信じていた。書庫が自分のものになれば、彼女が司と幾也に付きあう義理はなくなる。三角サッカーも、川遊びも、司たちのゲーム観戦もしなくなるだろう。
この書庫には父の蔵書だけでなく、死んだ母の愛書も並べてあった。『クラバート』『指輪物語』『赤毛のアン』『ジェーン・エア』『はてしない物語』『飛ぶ教室』『子どもだけの町』『ナルニア国ものがたり』……。どれも、梨々子のお気に入りだ。
「そんじゃあさ、おれの妹になるってのはどう?」
棚に寄りかかり、司はなるべくさりげない口調で言う。
「取り替えっこより、そのほうがいい。おまえがうちの食堂継いでくれよ」
「え、わたしが継いでいいの?」
梨々子の目が輝いた。
「もちろん。でも一生、他人のメシ作って生きてかなきゃいけないぜ」
「いいよ、そんなの全然いい。ていうか、それのなにがいやなのかわかんない」
むきになって言いかえす梨々子に、
「ああ違う違う、わかった。おまえ幾也とケッコンすりゃいいんだ」
と司は膝を打った。
「あいつん家はさ、姉ちゃんも本好きなんだぜ。それに幾也の親父さんは店やってねえもん。あいつとケッコンすれば本が読めて、食堂もやんないで済むじゃんか」
矢継ぎ早にそう言いつのる。なぜって、司は知っていた。
――幾也は、〝梨々子ちゃん〟が好きなんだ。
だからおれは協力してやらなきゃいけない。男の友情ってやつだ。男同士の絆は永遠だって、こないだ読んだ漫画に描いてあったからな。
「――司くんはさあ、きっと一生ケッコンできないね」
つまらなそうに梨々子が天窓を仰ぐ。
「は?」
「女心が全然わかんないもん。そんなんじゃ、一生無理だと思う」
「なに言ってっかわかんねえ」
司は首を振った。だが言葉とは裏腹に、なぜか胸がどきりとした。これ以上、この会話をつづけるのは危険な気がした。
「……おまえ、その本好きだよな」
話をそらすべく、梨々子が膝に広げた本を指さす。
松谷みよ子の『ふたりのイーダ』だ。これもまた、亡母の愛書であった。
司もすこし読んでみたことがある。だが怖くてすぐやめた。椅子のお化けが、女の子を捜して歩きまわる話なのだ。なんだか暗い雰囲気がしたし、気味が悪かった。
「それ、おまえにやるよ。持って帰れば?」
「なに言ってんの。駄目だよ、司くんの本じゃないでしょ」梨々子が眉をひそめる。「勝手にそんなこと言ったら駄目」
「そうか? じゃあ、期限なしで貸してやる」
「いいの?」
「うん。返すの、いつでもいいよ」
親父にはおれから言っとくから――。そう付けくわえた。
その瞬間、梨々子がどんな顔をしたのか司は覚えていない。
たぶん笑ったんだろう、と思う。嬉しそうに顔をくしゃっとさせて、目を細めて笑ったに違いない。しかし三十一歳になったいまでも、彼はその顔をどうしても思いだせない。
わかっているのは、その本が書庫に戻らなかった、という事実だけだ。
本と一緒に〝梨々子ちゃん〟は消えてしまった。
ある日、母親とともにいなくなった。
彼女たちが住んでいた部屋はからっぽのがらんどうになり、一箇月もすると、別の誰かが当たりまえのように住みはじめた。それ以来、司は彼女に会えていない。
司と幾也は、彼女を失ったのだ。たぶん永久に。
日に焼けて背表紙が薄れた『ふたりのイーダ』とともに。
第一章 端緒
1
夏休みが明けたとはいえ、まだまだ蝉の声はうるさかった。
エアコンを二十度設定で効かせても、厨房の中は暑い。火のついたコンロの前に立っているだけで、うなじにも背にもじんわり汗が湧いてくる。
固定電話の子機から響く声を、柳楽司は片耳で聞いた。
「だからな、おれは言ったんだよ。『いつまでも若いつもりなのは自分だけ。免許なんざ、さっさと返納しちまえ』って……」
子機から聞こえてくるのは、スピーカーフォンにした父の声だ。
父はこの『やぎら食堂』の先代店主である。五十五歳の誕生日を機に、店を息子に譲って田舎へ引っこんだのだ。
妻に先立たれた男三人――ほかに元古本屋の店主と、元喫茶店のマスター――で徒党を組み、いまは年寄りばかりの限界集落に住んでいる。古民家でちいさな畑を耕し、雨の日には大好きな本を読みふけるという、単調かつ優雅な暮らしだった。
「まったく田舎の年寄り連中には困ったもんさ。自損事故を起こしても、けろっとしてやがる。大怪我したらどうするんだって、何度も注意してるのに」
「そうは言っても、あの村で車なしじゃ暮らせないだろう」
鰯の梅干煮の火加減を見つつ、司は父に反論する。
「バスは一日二本きりなんだっけか? なら免許を手ばなせなくて当然だ。親父もあんまりお節介するなよ。しょせんよそ者なんだから、嫌われたら住みづらいぜ」
「いやあ、気ごころが知れてるからこそ、遠慮なくものが言えるのさ」
と父は軽くかわして、
「もし村八分にされたとしても、こっちは男三人で結束してるしな。最低限の暮らしは確保していける。ノープロブレムだ」
「はいはい。そりゃよかった」
「なにがはいはいだ、最後にものを言うのはやっぱり友情だぞ。……なあ、司」
父の声のトーンが変わる。
「というわけで、おまえもそろそろ幾也くんと仲なおりを――」
「だーかーら、何度言わせんだよ。おれはあいつと喧嘩なんかしちゃいないっての!」
司はぴしゃりと父を遮った。
「しょうもない雑談だけなら、もう切るぞ。おれは仕込みで忙しいの。じゃあな。つづきがあるならメールで送っといてくれ」
一方的に言い、切った。
子機を充電器に立てかけ、ふうと司は息を吐く。
――そう、喧嘩などしていない。
幼馴染みの三好幾也が、ただ店に食べに来なくなった。それだけだ。
理由はわかっている。所轄署の警察官である幾也は、去年の春に刑事課から異動して内勤になった。となれば外で食う機会が減るのは当然だろう。同時になぜか連絡も途切れたが、忙しいだけだ、と司は己に言い聞かせていた。
なのに父は無神経にも、
「幾也くんはまだ顔を出してくれんのか」
「喧嘩はよくないぞ。おまえから譲歩したらどうだ」
などと毎度ちくちく言ってくる。
――譲歩もなにも、その譲るもんの心あたりがないんだよ。
ひとりごちて、司はコンロの火を止めた。梅干煮の鍋から煮汁をひとすくいし、味を見る。
――うん、美味い。
さて次は豚汁の仕込みだ。
まずは牛蒡である。風味が失せるからあまり剥きたくないが、九月の牛蒡は旬とは言えない。ぶ厚い皮をピーラーで軽く剥き、ささがきにし、五分ほど水にさらしておく。
その間に、ほかの具材を刻む。この時季の白菜は高いから、キャベツで代用だ。キャベツは一口大、大根と人参は銀杏切りにする。
長葱も高くて手が出ないため、玉葱を使うことにした。だがあまり大量に入れると甘くなる。量を加減しつつ、半月切りにしていく。
『やぎら食堂』の定番メニューは、なんといってもこの豚汁である。
一年を通して、司は毎日必ず豚汁を仕込む。
ほかの定番といえばハンバーグ、竜田揚げ、豚の生姜焼き、鯖の味噌煮、ポテトサラダ、焼きそば、出汁巻き玉子といったところか。あとは客のリクエストを聞きつつ、旬の安い食材を使ってこしらえていく。
す、と入口の引き戸がわずかに開いた。
まだ開店時刻ではない。引き戸には『準備中』の札も下げてある。しかし薄く戸を開けて、誰かが半分顔を覗かせている。
司は目をすがめた。
十歳前後の女児であった。はじめて見る顔だ。
ベリーショートと言えるほど短く切った髪。色褪せたピンクのワンピース。服の中で、痩せた体が泳いでいる。どう見ても誰かのお下がりだった。
豚汁の具材をさっと炒め合わせながら、
「名前は?」と司は訊いた。
「……ココナ」
「どんな漢字かわかるか?」
「心に、えーと、菜……は、こういう字」
空中に指で字を書いてみせる。司はうなずいた。
「よし心菜、入って戸をぴったり閉めろ。冷房がもったいないからな。─店のことは、誰から聞いた?」
「えっと、『千扇』の番頭さん……。あと、和歌乃ちゃん」
なるほど、と司は納得した。温泉旅館『千扇』の番頭のしなびた顔と、和歌乃の猫目が脳裏に浮かぶ。
「和歌乃ならうちの大常連だぞ。仲いいのか」
「まあまあ」
「じゃあとっくに聞いてるだろうが、うちの料理は子どもに限り、なんでも百円だ。百円がないなら、別の支払い方法もある。割らずに皿を洗える子にはカツ丼。表を掃き掃除できる子は親子丼。客の皿を厨房に下げて、テーブルを拭ける子は玉子丼だ。さて、心菜はなにができる?」
「掃除できるよ」心菜は即答してから、
「あ……でも、玉子がいい。玉子丼」
おずおずと付けくわえた。
「そうか。掃除できるけど玉子丼、な」
鰹出汁を張った鍋に、司は豚汁の具材を順に放りこんだ。
「ちなみに鶏肉は嫌いか? 唐揚げとか、チキンナゲットとか食えないか」
「……ううん、好き」
「そっか。じゃあ初回サービスで鶏肉も入れてやろう。鶏肉入りの玉子丼だ。代わりにおまえは表の掃き掃除をする。これでいいな?」
「うん。いい」
心菜がうなずいた。強張っていた頬が、ようやくほっとゆるむ。
『やぎら食堂』では、この手のやりとりは珍しくない。店にはじめて来る子どものうち、約四割は「親子丼」という単語を知らない。なぜなら親子丼を作って食卓に出す親がおらず、本を読まないから語彙が乏しく、学校にも行っていないせいだ。
しかしながら、子どもはプライドの高い生き物である。「オヤコドンってなに?」と無知を認め、「テーブル拭きしかできない」と卑下するくらいなら、
「掃除できるよ! でも玉子丼が好きなの」
と強がってみせる。それが子どもというものだ。
「よし心菜。掃除はあと。食うのが先だ」
司はカウンター席を親指で指した。
「十分待てるか? もうちょっとで豚汁ができる。玉子丼はそのあとな」
「うん」心菜がストゥールを引いて座る。
玉 子に取った味噌を、司はゆっくりと煮汁で溶きのばした。味噌のいい香りが店じゅうに広がっていく。
心菜の喉が、ごくりと上下した。
親子丼を食べる心菜を横目に、司は厨房を出て引き戸を開けた。表に下げてある『準備中』の札を裏返し、『営業中』に替える。
二人目の客は、五分と経たず入ってきた。
「よう司ちゃん。カレーくれ。カレーライスの大盛りだ」
「残念だな。今日はカレーは仕込んでない」
「ちぇっ。相変わらずひでえ店だ」
そう顔をしかめるのは、道向こうの角に立つ『かなざわ内科医院』の院長である。とうに還暦を過ぎた頭は禿げあがり、磨いたように光っている。
「メニューの安定した店がいいなら、ファミレスに行きな」
「マジでひでえ店だ」
金沢院長は苦笑して、「じゃあなにがあるんだよ?」と訊く。
「『魚辰』に鰯のいいのがあったんで、梅干煮にした。あとは秋鰆の味噌煮。秋刀魚の塩焼き、もしくは刺身。鮭ならフライかな。肉は、新鮮なレバーが入ったからレバニラ。ニラ抜きの、もやしのみにもできるぜ」
「じゃあ最後のそれ」
院長が膝を打った。
「午後も往診するんだ。息がニラ臭くなっちゃまずい」
「どうせマスクするだろ」
司がそう応じたとき、引き戸が開いて三人目が入ってきた。
「おい司ちゃん、野菜くれ野菜。薄味でな。こないだの健診で、血圧が引っかかっちまってよ。女房がうるさくてたまらん」
「野菜より青魚がいいぞ」司は言った。
「今日のおすすめは鰯の梅干煮だが、いやなら秋刀魚にしなよ。それに小松菜のおひたしときんぴらの小鉢を付けて、肉すくなめの豚汁でどうだ」
「いいね。そいつでいく」
ぽんぽんとお互い遠慮なく言い合えるのは、全員がこの泥首温泉街の住民で、司が幼い頃からの顔馴染みだからだ。
磐垣市大字泥首は、県内有数の温泉街である。
硫黄を多く含む低張性弱アルカリ性高温泉で、源泉は約五十度。肩こり、リウマチ、皮膚病、婦人病、神経痛、軽度の高血圧に効くと言われる。メインストリートには一泊四千円台の安宿から、一泊五万超えのホテルまでがずらりと立ち並ぶ。
そんなメインストリートからバスで一区間離れた繁華街のはずれに、この『やぎら食堂』は建っていた。
ちまたに〝子ども食堂〟なる言葉が広まって久しい。だがそのはるか前から、腹を空かした子どもに食事を提供してきた店であった。
なぜなら泥首には、平日の日中に街をうろつく子どもが多い。その大半が、温泉旅館に住み込みで働くシングルマザーたちの子である。
店の常連たちもむろん、そのへんの事情はよく心得ていた。
「うちの店は子どもらを食わせてやんなきゃいけないんだ。そのぶん料金に上乗せするが、いやなら来るな」
と公言する司に、「無礼だ」などとは誰も言わない。
「教育によくないから、十九時以前に酒を頼む客はおことわり。その代わりアルコールを出す時間帯になれば、子どもは一人も入れない」
等々のルールに、双手を挙げて賛成している。司いわく「気のいいおっちゃんの群れ」が、この『やぎら食堂』の常連たちなのだ。
そんな客たちが店に押し寄せ、ほぼ満席となった頃。
「こんにちはぁ」
かん高い声とともに、引き戸が勢いよくひらいた。
「あーなんだ心菜、先に来てたんじゃん」
掃除道具入れから出てきた心菜に、先頭の少女がマスクを下げて笑う。厚めの前髪の下で、大きな猫目がきゅっと細まる。
「おう和歌乃、いつも客引きありがとうよ」
フライパンを振りつつ司は言った。
「おかげで新規の客が獲得できた」
「いいっていいって、気にしないで。店長とあたしの仲じゃん」
和歌乃はカウンターのストゥールを引いた。
しかし腰を下ろす前に、同じくカウンターに座る『千扇』の番頭にぺこりと頭を下げることは忘れない。和歌乃が後ろに引き連れた、芽愛と蓮斗も同様だ。
彼らの母親はみな、温泉旅館で住み込みの仲居をしている。和歌乃と芽愛の母が『千扇』、蓮斗の母が『ひさご屋』勤務という違いはあれど、番頭の前を素通りできぬ立場は同じであった。
今年で十五歳になる和歌乃は、同じ境遇の子どもたちのリーダー的存在だ。
芽愛は十二歳。蓮斗は九歳。どちらも和歌乃が数年前に、
「店長。この子らに食べさせてやってよ」
とこの店へ引っぱってきた〝上客〟である。
「和歌乃は実績があるから皿洗いな。一時間めいっぱい洗えよ。芽愛は皿を拭いて片づける係。蓮斗は洗面所の床をモップ掛けだ。で、今日はなにを食う?」
「唐揚げ!」
勢いよく蓮斗が手を挙げた。
「あたしは……なにか、ヘルシーで野菜多めのやつ」と和歌乃。
「じゃあレバニラか」
「ちょっとぉ! 乙女が昼間からニラなんか食べるわけないでしょ。もっとこう、サラダ的な感じにしてよ」
「はいはい。そんじゃおまえはキャベツのサラダに鰯の梅干煮で、血液さらさらになっとけ。芽愛は、いつものでいいな?」
芽愛が無言でうなずく。
小鍋に取り分けておいたぶんの豚汁に、司はかねて用意のスパイスを放りこんだ。
この小鍋には味噌を溶いておらず、代わりにホールトマトを一缶ぶちこんで煮詰めてある。スパイスはクミン、コリアンダー、ターメリック、そして市販のカレー粉だ。
じきに店内に、カレーの匂いが漂いはじめた。子どもが食べる甘口スパイスカレーの香りであった。
「おいおい、おれにさっき『カレーはない』って言わなかったか?」
さっそく金沢院長が抗議する。
司は片手を振ってあしらった。
「いい歳して大人げないこと言うなよ。しょうがないだろ」
――そう、しょうがない。
芽愛は偏食だ。なぜって彼女は八歳四箇月になるまで、食パンとレトルトカレーとスナック菓子のみで生きてきた。
暴力夫から逃げまわる過程で、芽愛の母親は心を病んだ。わが子の食事の支度まで手がまわらなかった。だから今も芽愛は、ほかの食べ物をほぼ受けつけない。この豚汁アレンジの、野菜たっぷりのカレーを食べるようになっただけでも大した進歩なのだ。
「いいから院長は黙って食えよ。文句ばっか言ってると、よけいハゲるぜ」
「まったくひでえ店だ」
金沢院長が三たび慨嘆して、「いい大学出てるくせして、司ちゃんはなんでそう口が悪りいかな」とぼやく。
「え、店長って大学出てんの?」
なぜか和歌乃が目をまるくした。
「なんだ、おれが大学出てちゃおかしいか」
「ううん。おかしくはないけど」
鰯の梅干煮を箸でつついて、上目づかいに言う。その横では蓮斗が、大口を開けて唐揚げを頬張っている。
「……あの頃は、店を継ぐ気はなかったんだ」
ぽつりと司は言った。
そうだ。大学受験した当時は、こんな片田舎の食堂の親爺で終わる気はなかった。
彼は福祉に携わる仕事をしたかった。とりわけ児童を対象とした福祉にだ。大学では社会福祉学を専攻し、児童心理学や心身健康科学を中心に学んだ。状況が許せば、ほんとうは院にまで進みたかった。
なぜ児童福祉を志したかと言えば、それは――。
「そうだ店長。これ返すね」
思いだしたように、和歌乃がバックパックから本を引っぱりだした。
店の本棚から貸し出していた、手塚治虫の『ブラック・ジャック』三巻である。
「あ、知ってる! それ怖えーんだぜ。気持ち悪りい絵がいっぱいなの」
口から飯粒を飛ばしながら蓮斗が言い、
「ちょっと、きったないなぁ。飲みこんでからしゃべんなよ」
芽愛が顔をしかめる。
その隣で金沢院長が、腹を擦りながら言った。
「おい司ちゃんよ。なんかデザートはねえのか」
「カスタードプリンなら蒸してある」
甘口カレーを味見し、塩で味をととのえて司は答えた。
「それ以外だと、今日出せるのはバナナシャーベットくらいかな。あとはそこらで売ってるバニラの棒アイスか、もらいもんのカステラしかない」
「んじゃカステラをくれ」
「あいよ」
応えて司は、『?月堂』のカステラを二きれ平皿に取った。斜めに薄く切ったバナナを添え、生クリームを絞り、チョコレートソースを幾重にも細くかけてから、ミントの葉をちょこんと挿す。
「たんと食え」
「おまえなぁ……。おれに出す皿を洒落てどうする。凝らなくていい方向に凝るんじゃねえよ」
文句を垂れつつも、金沢院長はカステラを嬉しそうに切り分けた。
2
その死体は、河原に転がっていた。
風のない日だった。地元住民が「小笹川」と呼ぶ川が、水面にペットボトルやビニールのごみを浮かせ、虹色の油膜をぬんめりと陽に弾かせている。
死体はうつろな目を見ひらき、晩夏の青空を仰ぐように大の字に倒れていた。
十歳前後の男児であった。
青のボタンダウンシャツにハーフパンツ。どちらも量販店の安物だ。食べこぼしの染みだらけで、全体に垢じみている。また袖も裾も短すぎる。
おそらく親が成長を無視し、何年も同じ服を着せつづけたに違いない。だがその安っぽいシャツとパンツを剥げば、誰もがきっと瞠目するだろう。
男児の下半身は、切創にまみれていた。
鋭利な刃物での創だ。×字を描く創は下腹部や太腿だけでなく、陰茎と睾丸にまで及んでいる。滅多切りであった。とくに睾丸の片方は、皮一枚でかろうじて繋がっている惨状だった。
そして創にまみれた鼠蹊部は、現在進行形でじわじわと暗緑色に変わりつつある。腸内細菌と外来菌による、腐敗の色であった。そのぞっとするような緑は、まだ顔までは達していない。代わりに顔面を這うのは、蛆だった。
鼻孔、耳孔、眼球などに産みつけられた蠅の卵が孵化したのだ。蛆はまだ二ミリ程度で、死体が捨てられたのが約半日前だと物語っている。今日も気温は三十度を超えた。蛆の成長も、当然ながら早かった。
創だらけの下半身とは対照的に、彼の上半身には三箇所しか創がない。しかしそのすべてが深い刺創であった。そのうち一創は右心室を、一創は太い動脈を傷つけ、彼の命を血液とともに流し去った。
眼球はとうに乾き、濁っていた。死後硬直は全身に達していた。また、舌の先端が切りとられてもいた。
パトカーのサイレンが近づいてくる。
あきらかに、この河原に向かっている。
男児の死体を発見した通行人が、十分ほど前に一一〇番通報したからだ。
通行人は初老の男性だった。いまは草むらで嘔吐している。男児が発する腐敗臭のせい、そして男児と同じ年ごろの孫がいるせいだった。肉体的にも精神的にも、ショックを受けていた。
その次に男児を目にしたのは、パトカーで到着した巡査と巡査長だ。通信指令室より無線連絡を受け、この河原に急行した交番勤務員である。
「こちら現場到着。ただいま、通報者を確認中――」
巡査長が無線で一報を入れる。
その間に、出動服をまとった機動捜査隊が到着した。
河原の脇にパトカーが集結しつつある。ルーフの上で、赤色警光灯を派手に回転させる。同時に野次馬も集まりはじめていた。
機動捜査隊員が、きびきびと現場をイエローテープで区切っていく。
野次馬は手に手にスマートフォンを掲げていた。男児の死体など写しようもない距離から、つま先立って背伸びし、腕を伸ばしてシャッターを切る。
やがて新たな捜査車両が二台、脇道に横づけされた。所轄署刑事課の捜査員と、鑑識係の車であった。
彼らが現場をカメラで撮影し、足跡を調べ、毛髪や繊維、血液などを採取する間にも、やはり男児はもの言わぬ死体として転がっていた。
3
「おーい、三好ぃ」
磐垣署警務課は留置管理係の島に、係長ののんきな声が響く。
「……はい?」
三好幾也はパソコンモニタから顔を上げた。
「なんですか、係長」
「あーあれだ。おまえも聞いとるだろ? 小笹川の河原で見つかったマル害。小学生くらいの子で、身元不明のやつ」
「はあ、まあ」
幾也の眉間に、われ知らず皺が寄る。しかし係長は彼の皺など頓着せず、
「うちの管轄区域だからな、当然ながら署内に捜査本部が立った。ついては警務課からも兵隊を派遣しろとよ。てなわけで、おまえ行ってくれ」
「なんでおれが」
「なんでってそりゃ、ほかに使えそうなやつがおらんもの」
しれっと係長は答えた。
「知ってるだろ。生活安全課も地域課も、目ぼしいやつはみんな塚本町の殺人に動員済みだ。となれば残りの課から、なんとか人員をかき集めにゃなるまいよ」
塚本町のコロシとは、先々月に発生した女性会社員殺人事件だ。この磐垣署から徒歩二分とかからぬアパートで、二十代の女性が絞殺されたのである。
目と鼻の先で起こった事件だけに、解決には磐垣署の面子がかかっている。捜査員をはじめ、署員の誰もが意気込んでいた。
――なのに解決せぬうち、別の死体が発見されてしまった。
人員が足らなくなって当たりまえだ。
地方の所轄署では、「年に二回捜査本部が立てば、それだけで年度予算を使いきる」と言われる。それほどに田舎の殺人事件は珍しい。現にこの磐垣署管内は、一昨年も去年も大きな事件はなかった。
――まだ九月だというのに、二件たてつづけか。
いやな当たり年だ。そう眉を曇らせる幾也を、係長が片手で拝んだ。
「なあ頼むよ。警務課から出せるのはおまえくらいなんだ。それに刑事課で長いことメシを食ったおまえなら、すぐに溶け込めるだろ」
「はあ……」
――だからこそ、行きたくないんですよ。
そう幾也は内心で反駁した。
確かに去年の春に異動するまで、幾也は刑事課強行犯係の捜査員だった。
この警務課留置管理係にやってきたのは、ひとえに異動願が通ったからだ。やる気を失い、ゴンゾウ化した捜査員など、刑事課にいる資格はない。
――そう思っていたのに。
幾也は深いため息をついた。
係長が片手拝みのポーズを崩さずに、
「県警本部からは、強行犯第四係が出張ってきなさるそうだ。捜査主任官には大迫警部が就く予定だとよ。おまえも知ってるだろ? 大迫課長補佐」と言う。
「はあ」
幾也はまたも生返事をした。
係長が苦笑して、
「そんな顔するなって。今回のマル害は年端もいかん子どもだぞ。どう見ても十歳前後だってのに、いまだ身元不明だ。行方不明者届も出されとらんし、各学校に問い合わせても『該当する児童はおりません』だった。あの殺されかたもたまらんが、親にすら捜してもらえんとはな。せめて犯人を挙げてやらにゃ、気の毒すぎるだろうよ」
「わかってます」
幾也は低く答えた。
被害者の情報は、すでに聞くともなしに耳に入れていた。身長百三十二センチの男児。ランドセル、記名ありの文具、名札、子ども用スマートフォンなど、IDつまり身分を証明する所持品いっさいなし。衣服にも記名なし。
死因は失血死。上半身に三箇所の刺創。下半身に無数の切創あり。
衣服は上下とも着用していたものの、ボタンが掛け違っていたり、肩の位置が不自然だったりと、死後に衣服を着せた疑いが濃いという。また、下着や肌着のたぐいは着けていなかった。
性的暴行の顕著な形跡あり。しかし遺体は漂白剤で洗われており、体液の検出は望めなかった。また、舌先が三センチほど切除されていた。
「……かわいそうだとは、もちろん思ってますよ」
「だろ? まあこう言っちゃなんだが、十中八九、泥首温泉まわりの子だしな。三好、確かおまえも泥首の生まれだろう?」
「ですね」
いやいやながら幾也は答えた。
正直、幾也自身も泥首の子だろうとは思っていた。行方不明者届が出ていない、就学の様子がない、サイズに合わない不潔な衣服となれば、条件は揃っている。
「おまえ、高校卒業まで泥首の実家に住んでたのか? やっぱりあれか。ガキの頃は、もっとヤバい場所だったか?」
「いえ、いまとたいして変わりません」
「そうかぁ? 生安課からたまに洩れ聞くが、三、四十年前なんてそりゃあもう――。あ、おまえはまだその頃生まれてねえか、ははは」
そっくりかえって笑う係長を、幾也は苦にがしく眺めた。
泥首温泉は、よくも悪くも〝昔ながらの温泉街〟だ。
従業員の流出入が激しく、どの旅館もつねに人手不足である。だから仲居を保証人なし、履歴書なしで雇い入れ、住み込みで長時間働かせてはばからない。
そんな仲居の大半が、行政を信じられず、頼れもせずにいる女たちだ。
子どもを抱えてDV夫から逃げた女。身寄りのないシングルマザー。借金で夜逃げしてきた一家の母親。はたまた親に虐待された家出娘。彼女たちにとっては、泥首温泉街そのものが巨大なシェルター的存在だった。
暴力や借金から逃げおおせるため、仲居たちはなるべく息を殺し、気配を消しながら日銭を稼ぐ。まずは〝生きる〟ことに精いっぱいで、わが子の教育や衛生状態は二の次、三の次になってしまう。
その結果、街には子どもたちが溢れる。学校に行けず行き場もない子どもたちが、日がな路地裏や飲み屋街をうろついては、食べ物をあさるのだ。
――ガキの頃は、不思議にも思わなかった。
幾也は奥歯をひそかに?みしめる。
――あの頃はよその世界を知らなかった。飢えた子や、洟汁で袖を光らせた子や、虱だらけの頭をした子がいることを、当たりまえだと思いこんでいた。
同い年なのに、学校に籍のない子がいた。通っていても来なくなる子や、いつの間にか転校した子が何人も、いや何十人もいた。
当たりまえではないと気づいたのは、小学五年生のときである。
一人のクラスメイトが消えたのだ。もう顔もろくに思いだせない、なのに存在と名前だけは、胸に焼きついているクラスメイトが。
「やぎら食堂……」
われ知らず、幾也の唇から言葉が洩れた。
「あ?」
係長が怪訝な顔をする。
「あ、いや」と幾也は手を振って、
「『やぎら食堂』に聞きこみに行けば、マル害の身元はすぐ割れるだろうと思ったんです。あそこは子どもたちの溜まり場ですから」
とごまかした。
「そりゃそうだな。だが心配せんでも、捜査がはじまりゃ捜査一係は真っ先にあそこへ向かうさ。そこまで無能じゃない」
「それはそうでしょうが」
「しっかし『やぎら食堂』かあ。久しく行ってねえな。知ってるか、三好? あそこの親子丼と野菜炒め定食は絶品だぞ。二代目は若いが、先代より腕がいい」
「はあ」
幾也は生返事をした。
係長に演説されるまでもない。幼馴染みの腕ならよく知っている。
司には料理のセンスがあった。とくに火加減と塩加減を見きわめる感覚が、飛びぬけている。大蒜を効かせ、ラードの風味を活かしただけの野菜炒めが、息を?むほど美味い。
――だが、もう二年近く食っていない。
とくに警務課に異動してからは、一度も『やぎら食堂』に足を運んでいなかった。
顔を合わせづらかった。いや正確に言えば、合わせる顔がないのだ。
ふたたびむっつり黙りこむ幾也に、
「おいおい、大丈夫だって。たぶん残業なんかさせないから」
と係長がピントはずれの言葉を投げてくる。
「いくら刑事課の出でも、いまが警務課なら炊き出しか雑用係にされるだけさ。ちゃんと夜には帰してもらえる。ここは、かるーい気持ちで行ってくれ」
なにが軽い気持ちだ。幾也は思わず係長を上目で睨んだ。
――地元で子どもが殺されたんだぞ。
それもあんな、残虐なやりかたで。
だが彼の口からこぼれたのは、やはり「はあ」の一言のみだった。
4
そして同日の午後三時半。
三好幾也はうだるような炎天下を、県警捜査一課の志波巡査部長とともに歩いていた。
「いやあ、なんも知りませんねえ」
ハーフパンツから脛毛をはみ出させた男が、アパートの扉に寄りかかって言う。
「リョウ? リョウって呼び名の子ども? そんなの、このへんには売るほどいますよ。リョウだのショウだのリュウだの、似たような名前のガキ……いや、男の子はさあ」
ハーフパンツに手を突っこみ、男があらぬ箇所をぼりぼりと掻く。
「ありがとうございました。ではなにか思いだされましたら、署までご連絡を」
幾也は型どおりの台詞を吐いた。同時に、叩きつける勢いで扉を閉められる。
手の甲で、幾也は汗を拭った。
「いまが警務課なら炊き出しか雑用係にされるだけさ」との係長の予言は、ものの見事にはずれた。
子ども殺しの特捜本部となれば、最低でも六十人規模、できれば八十人はほしい。署長は急いで、女性殺しの捜本から十五人を呼びもどした。
しかし県警本部からやって来た三十人に、応援要員を足してもまだ足りなかった。というわけで幾也のような〝出戻り〟すら、貴重な捜査要員とあいなったのだ。
『小笹川男児殺人死体遺棄事件特別捜査本部』の第一回捜査会議は、磐垣署一階の多目的室で午後二時からおこなわれた。
殺人事件ともなれば人員はたいてい捜査班、予備班、庶務班、鑑識班に割りふられる。そうして捜査班はさらに、地取り、敷鑑、証拠品に分けられる。
幾也は志波とともに地取り班に任命された。遺体発見現場を中心に周辺一帯を区分けし、不審な人物や車両、見慣れぬ残留物や遺失物がなかったか、住民に尋ねてまわる班である。
捜査班の編成後、刑事課強行犯係の係長――つまり幾也の元上司が、
「おい三好、頼んだぞ」
と幾也の肩を強く叩いた。
「おまえは使えるやつだと、捜査主任官に太鼓判を押しといたからな」
「はあ」
――なにが太鼓判だ。
幾也はひっそり唇を曲げた。
忌々しかった。元上司が、ではない。彼の見えすいた世辞を、どこかで嬉しく思ってしまう自分がいやだった。
捜査主任官が噂どおり大迫警部だったことも、志波と組まされたこともつらかった。幾也が刑事課だった頃、何度かともに捜査をした二人であった。
――いまのおれを、彼らに見せるのが恥ずかしい。
アパートの外付け階段を下り、幾也はアスファルトに立つ陽炎を眺めた。
結局はこうして、自己嫌悪にすべて回帰していく。しょせんは自分の問題なのだ。自分、自分、なにもかも自分だ。三十歳を過ぎてさえ、まるで成長できない。
――十一歳のあの頃から、進歩できていない。
「なあ、間瀬当真とかいうガキは、ここらじゃ有名なのか?」
ハンドタオルで額を拭いつつ、志波が小声で問うた。
四十代なかばのはずだが、引き締まった体躯のせいか、後ろ姿と横顔が若々しい。
「少年係の話じゃ、そのようです」
幾也も手で顔を扇いだ。
――間瀬当真。
第一発見者および、現場に集まった野次馬の口から洩れた名だ。『小笹川男児殺人死体遺棄事件特別捜査本部』の第一回捜査会議は、
「現場から、間瀬んとこの悪ガキが逃げていくのを見た」
「殺された子は確か、ここいらで『リョウ』とか呼ばれてた子だ」
との目撃証言を報告し、班編成を発表したのみで慌ただしく終わった。まだ解剖の結果が出ておらず、被害者の身元さえわからないからだ。夜九時からいま一度、各班の報告を受けての会議をひらく予定とされていた。
幾也はスマートフォンのメモ帳アプリをひらき、読みあげた。
「えー、生安課少年係の情報によれば、間瀬当真は満十五歳。本来であれば中学三年生です。また間瀬とともに目撃された渡辺慶太郎も、同年の生まれです」
〝本来であれば〟と付けたのは、当真たちが学校へ通っていないせいだ。後者にいたっては、学籍そのものが存在しない。
照会したところ、間瀬当真は小学一年生の三学期から登校をやめていた。
対する渡辺慶太郎のほうは、小学二年生のなかばから就学実績がない。県外の生まれ育ちで、転居後の住まいを行政が追えなくなったケースである。俗に言う〝居所不明児童〟であった。
「間瀬の身柄はまだ押さえていないんだよな? 親のほうはどうだ」
「そちらもまだです。間瀬当真に母親はなく、父親は泥首温泉街のストリップ小屋で呼び込みをしています。経営者の甥だそうで、不真面目でもクビになる心配はないようですね。交番員がアパートを訪ねたところ、不在でした」
「夜の商売なら、おねんね中かね。手を付けたストリッパーのアパートで、いまごろは高いびきってとこか」
「かもしれません」幾也はうなずいて、
「渡辺慶太郎のほうも、同じく父子のみの家庭です。母子家庭の多い泥首では少数派にあたりますから、それでつるむようになったかな。ただ間瀬と違い、渡辺は粗暴ではないようです。間瀬の金魚の糞というか舎弟というか、パシリですね。単独ならば、内気でおとなしい少年です」
「リーダーと舎弟コンビか。ありがちだな。一人一人はたいしたやつじゃなくても、二人になると途端に凶悪化する。互いが互いにいい恰好をしようとして、イキり合ううちエスカレートしていくんだ」
志波の半袖シャツから覗く上腕は、真っ黒に日焼けしていた。ところどころ皮がめくれ、赤?けになっている。
幾也はつづけた。
「間瀬当真はバタフライナイフを所持しており、いつも泥首の子どもたちに見せびらかしていたそうです。ただ遺体の刺創がバタフライナイフと一致するかは、まだ不明。司法解剖の結果待ちです」
「マル害の身元がわからんってのが痛いよな。死亡推定時刻は、昨夜なんだろう? 親が夜の商売で夕方に出勤したとしても、朝には帰るはずだ。帰宅してわが子の姿がないことを、ちったあおかしいと思わんものかね」
「そこはいろいろ理屈を付けて先送りしたんでしょう。友達の家に泊まったんだろう、朝メシを食いに行ったんだろうと、彼らお得意の〝だろうだろう〟でね」
つい口調に皮肉が滲む。
だが、いわれのない反感ではなかった。幼い頃からの、幾也自身の体験が言わせた台詞であった。
――親である彼らとて、社会の犠牲者だ。わかっている。
貧困も虐待も連鎖する。彼らのそのまた親がしたことが、繰りかえされているだけだ。事情を汲まずに上から責めたところで意味がない。わかっている。
――だが、どうしたって腹は立つんだ。
「温泉宿の従業員寮は、朝食のみ提供のところが多いんです。母親は昼夜にまかないが食えても、子どものぶんまではない。だから夜明けごろから、腹をすかして徘徊をはじめる子どもは珍しくありません」
幾也は、なるべく抑えた声で語った。
「つい三、四十年前までは、お菓子一袋や総菜パン一個で売春する子もいたそうですよ。『やぎら食堂』ができる前の話です」
「『やぎら食堂』か。そういや前に三好くんと組んだとき、連れてってもらったな」
ふっと志波が頬をほころばせる。
「店長が幼馴染みなんだっけか。いやあ、あそこの生姜焼きとポテトサラダは絶品だった。また食いたいと思っちゃいたが、結局ずっと行けずじまいだ」
「どうせ、これから向かいますよ」
さりげなく顔をそらし、幾也は言った。
「食堂に行きゃあ、マル害の身元はすぐ割れるでしょう。……泥首の子どもの三割弱が集まる店ですからね。夜の会議までに名前と素性が割れりゃ、こっちは大手を振って帰署できます」
5
皿を洗い終え、掃除を終えた和歌乃たちは「店長、またあとで来るね!」と言い置いて店を出て行った。
司はおざなりに片手を振り、
「夜七時までだぞ。酒を出す時間になったら入れないからな」
と念押しして送りだした。
町医者や商店街の店主たちも、昼休みを終えていっせいに出ていく。
――午後二時か。さて、ここからは大人タイムだな。
と言ってもメニューが変わるわけではない。変わるのは客層のほうだ。
この時刻あたりから店内は、スウェットにすっぴんの女性や、目やにをくっつけた無精髭の男性で埋まりはじめる。
明け方まで、温泉旅館まわりの歓楽街で働く者たちだった。女性はホステスやストリッパー、ピンクコンパニオン。そして男性はバーテンダーに黒服、もしくは女たちの情夫である。
彼らは店に長居しない。無駄口もほとんど利かない。丼ものや定食を無言で?きこみ、けだるそうに帰っていく。
しかしたまには例外もいて、
「店長! 焼きそばひとつね、紅生姜マシマシで。あと持ち帰り二人前もお願い。うちのガキどもったら、ここの焼きそばにバカハマり中でさぁ」
とカウンターから身を乗りだすのは、ピンクコンパニオンのユキであった。時計の針は四時にさしかかりつつある。
「おうおう、えらいな、ユキちゃん」
温泉饅頭屋のご隠居が野次を飛ばした。
「ちゃんとわが子のメシも考えてやってんだ。えらいえらい」
「あったりまえじゃん。ほかのやつらが考えなさすぎなんだよ。自分が産んだ子のごはん買って帰るだけで誉められんだから、変わった街だよねえ、ここ」
顔じゅうにタトゥーメイクを入れた〝ユキちゃん〟が、鼻でふんと笑う。
フライパンを振りながら司は笑った。
「まあそこは〝貧すれば鈍する〟ってやつだな。もしくは〝朱に交われば赤くなる〟」
「は? なにそれ」ユキが顔をしかめる。
「店長って、たまにわけわかんないこと言うよね。黙ってりゃいい男なのにさ」
「そうか。すまなかった」
司は素直に謝った。
「それよりお座敷の景気はどうだい。盛りかえしてきたか?」
「駄目だめ。全っ然駄目。そりゃコロナのせいもあるけどさ、不景気だとなにより客層が落ちるね。もう下品も下品。っていうかエグい。触りかたがエグいよ。あたしが言うなって話だけどさあ、なんか世の中、全体的におかしくなってない?」
「言えてるな」隠居が同意した。
「そういや聞いたか? 小笹川の河原で、子どもの死体が見つかったって」
「えっ知らない。なにそれ」
ユキが目を見張った。
司は焼きそばを盛りつけながら、「?だよ、?」と頭上のテレビを顎で指す。
「朝からずっと点けっぱなしだが、そんなニュースは一度も見てないぞ? ご隠居、趣味の悪りい?をつくな」
「いやいや、?じゃねえって。司ちゃんはそこで鍋振ってたから知らんだろうが、表じゃとっくに騒ぎになってんだ。朝の十時だか十一時に死体が見つかってさ。河原が野次馬だらけだったんだから」
「えー。子どもの死体って……」
ユキが満面に皺を寄せる。
「まさかここいらの子? やだぁ、うちのガキどもに『外出るな』って言わなくちゃ。やっぱ世の中おかしいよ。子どもなんか殺して、いったいなんになるっての」
「まったくだ。変なやつが増えたよな」
隠居が腕組みして唸る。
「うちの姪がデパートで働いとるんだがな、こんな話を聞いたよ。ほら、迷子案内のアナウンスってやつを最近聞かなくなったろう。あれはアナウンスを聞いた変質者が、親を名のって来るケースが増えてやめたんだそうだ。いまは対応マニュアルを作って〝マジックミラー越しに、子どもに顔を確認させてから引きわたすこと〟〝アルバイトは対応せず、警備員を必ず呼ぶこと〟を徹底させとるんだとよ。姪自身も体験したそうで、『アナウンスしたらほんとの親は来ずに、他人ばっかり四人も来た。迷子の子どもは一人だけなのに。気持ち悪いし、怖い』と愚痴ってたよ。あーあ、まったくいやな時代になったもんだ。昔は、子どもを狙う変態なんていなかったのにな」
「いや、そんなこたぁない」
司はかぶりを振った。
「変なのは昔からいたさ。おれだって、ガキの頃は知らんおっさんにしょっちゅう声をかけられた。『ねえぼく、お小遣いあげるから、おちんちん見せてくれない?』なんてな」
「そうそう。変態に一度も遭わずに育つ子のほうが珍しいよね」
ユキが大きくうなずく。
「あーヤバ。こんな話してたら、シャレ抜きでうちの子が心配になってきた。ねえ店長、やっぱあたしの焼きそばも持ち帰りにして。変態はともかく、人殺しがうろうろしてんのはヤッバいわ。ここらの警察は、まるっきり頼りになんないしさ」
――ポリさんだけじゃないさ。
食べかけの皿をユキから受けとり、司はひとりごちた。
そう、警察だけではない。子どもの死体が真実かデマかは知らないが、この泥首に飢えた子や無学な子が溢れているのは、まぎれもない事実だ。
だが住民のほとんどは見慣れて麻痺し、当の親たちでさえなんとも思っていない。ユキのような「子どもの食事を気にかける」程度の母親が誉められる街だ。
――本来なら、行政が乗りだすべきだ。
子ども食堂だってそうだ。民間ではなく行政が子どもを保護し、食べさせ、教育をほどこすのが近代国家というものだ。
だが「泥首の教育状況を改善しましょう」などと言いだす議員は、いままで一人もいなかった。
歴代の市長とて同じだ。噂では泥首温泉協会の会長が、多額の納税を盾に、市長たちに鼻薬を長年かがせてきたという。真偽はむろん不明だが、ありそうな話だと司は思っていた。困窮する母親たちを仲居として丸抱えし、十六時間以上働かせている旅館は、この泥首にひとつや二つではない。
「ほらよ、ユキちゃん」
司はフードパックに詰めた三人前の焼きそばを差しだした。
「それ持って、早く……」
帰ってやりな、と言いかけた声は、しかし喉の奥で消えた。
入口の引き戸が開いたからだ。
入ってきたのは、あきらかに店の空気にそぐわぬ二人組であった。
――幾也。
片割れは、幼馴染みの三好幾也だった。
司はもう一人の男に素早く目線をくれた。こちらも見た顔だ。何年か前に、やはり幾也が連れてきた客である。確か、そう、県警本部の捜査員だと聞いたような――。
「おう、幾ちゃんじゃないか」
饅頭屋の隠居が片手を上げた。だが幾也はそれを黙殺して、
「すみません。ちょっとお聞きしたいことが」
他人行儀な口調で言った。
「この店に来る男児の中に、〝リョウ〟という愛称で、十歳から十二歳の子はいませんか? 身長百三十二センチの?せ形。目は二重で色黒。虫歯の多い子です」
「あー……、そりゃ、何人かいるな」
わざと司は乱暴に答えた。「苗字は? なにリョウだ?」
「いえ。愛称が〝リョウ〟の男児を捜しているんです」
「つまり苗字はわからんってことだな。もしかしてそれが、死体で見つかったって噂の子か?」
「お答えできません」
幾也が無表情に答える。その視線は司から微妙にそれ、背後の壁を見据えていた。
さすがに司はむっとした。しかし顔には出さず、
「知っている限りで遼介が一人、亮太が一人いる。それと漢字違いのリョウが二人いるな。遼介と、さんずいの涼は昼に来た。こざとへんの陵と亮太は、今日はまだ見ていない」
「では間瀬当真と、渡辺慶太郎は? 見かけましたか」
「見てない。それに間瀬はうちに来たことがない。慶太郎は常連だったがな」
「だった? 過去形ですか」
「ここ半年はあまり顔を出さないんだ。たぶん、間瀬とつるむようになってからだろう」
そう答えてから、司は片目をすがめた。
「間瀬当真が容疑者なのか?」
「なぜそう思うんです」
問いかえしたのは県警捜査員のほうだった。司は肩をすくめた。
「そりゃ、誰だってそう考えるでしょ。間瀬当真は有名な悪ガキだ。子どもの死体が見つかった直後に、警察がやつを捜してるならほかの答えはあり得ない。一たす一は二みたいなもんです」
幾也よりくだけた態度の捜査員は「はあ」と苦笑して、
「どちらにしろ、捜査に関してはお答えできないんです。もし見かけたらご一報ください」
と名刺を差しだしてきた。
司は素直に受けとり、背後の冷蔵庫にマグネットで貼りつけた。幾也へと目を戻す。
「死体の身元さえわかってないのか? だったらあとで和歌乃たちが来るはずだから、あいつらに亮太と陵を捜すよう言っておくぞ?」
幾也は応えない。かまわず司はつづけた。
「捜させるにあたって、情報の切れっぱしでももらえりゃありがたいんだがな」
「捜査に関しては、なにも言えません」
抑揚のない声だ。やはり視線は合わないままだった。
「いやいや、ご協力ありがとうございました」
県警捜査員が割って入る。
「ではなにか思いだされましたら、ぜひ署までご連絡を」
そう念押しし、きびすを返して二人は店を出ていった。
引き戸が閉まる。
同時に隠居とユキが、ふうっと肺から絞りだすような長いため息をついた。
「なんだい幾ちゃん、ずいぶん気取ってやがんなあ」
「ほんとほんと。えっらそうにしちゃってさ。なーにが『ソーサに関しては言えません』だよ。だから言ったじゃん。ポリコなんて、どいつもこいつも糞ばっかなんだよ」
仁王立ちでユキが吐き捨てる。司はうなずいた。
「典型的な〝慇懃無礼〟ってやつだな」
「はあ? 店長ってば、またわけのわかんないこと言ってぇ」
焼きそばのフードパックを、ユキはカウンターに置きなおした。
「それよりトイレ貸してよ。ムカついたらもよおしてきちゃった。おまけに今日、あたし二日目なのよね」
「かまわんが、汚すなよ」
「あ、女子に向かってそういうこと言うー? 最悪。そんなんだから店長、いつまでも結婚できないんだよ!」
鼻息荒く言うと、ユキはトイレの方角へ足早に消えた。
6
その三十分前、磐垣署は泥首交番から、一台のミニパトが出動した。
ハンドルを握るのは今年二年目の巡査だ。助手席には交番長兼係長である、五十代の警部補が着いている。
今日の午前に立ちあがった『小笹川男児殺人死体遺棄事件特別捜査本部』より命を受けての出動であった。
むろん自動車警邏隊は出動済みで、すでに現場の半径五キロ以内を捜索中である。とはいえ土地勘は、地元交番の勤務員が絶対的に上だ。
彼らのマル対は─第一の捜索対象は、十五歳の少年二人だった。次いで優先順位が高いのが、被害者男児の身元調査である。
「えー、現時点でのマル害の情報は、おおよその年齢と体格、〝リョウ〟という呼び名の三点のみか」
交番長が言う。
近県はもちろん、本州以外からも該当する行方不明者届は確認できていない。
十歳やそこらの男児が無残な死体で見つかったというのに、親からの通報一本ない現状は、あきらかに異様であった。
「まずは、そうさな。リョウが付く名の男児を一人ずつ見つけて、リストから順に消していくか」
「子どもらの溜まり場というと、まずはゲーセンですかね」
ハンドルを握る巡査が答えた。
オンラインゲームの普及を受け、都会ではゲームセンターが続々と閉店しつつあるという。しかしここ泥首では、ゲームセンターは堂々の現役だ。なぜか人は温泉に来ると、レトロな雰囲気を楽しみたくなるものらしい。ひと昔前に流行った格闘ゲームやメダルゲームに、喜んで金を落としていく。
「あとはコンビニの駐車場、ショッピングセンター。それと『やぎら食堂』ですか」
「仲居の子が多いから、従業員寮のまわりも見にゃならんな」
「そしてマル対――、とりわけマル間の捜索ですね」
巡査はうなずいて言った。
マル間こと、間瀬当真のことならよく知っている。泥首交番に着任して以来、幾度となく補導し、職質してきた相手だ。
間瀬当真は背が高く、十五歳にしては体格がよかった。
右目が左目に比べて極端に細く、それが顔全体に酷薄な印象を与えている。色白で、唇ばかりが妙に赤い。虫歯とトルエンの常用により、前歯が二本ない。
十四になってすぐの頃、彼は傷害と恐喝で鑑別所送致となった。
規定どおりの四週間で帰ってきたものの、早々に強盗および傷害で再逮捕。今度こそ少年院送りが決まった。約三箇月を院で過ごし、退院したのが半年前である。
現在は保護司の監督下にあるはずだが、間瀬当真の素行が改まった様子はない。家裁調査官からの連絡もない。巡査としては少年係の署員と顔を見合わせ、
「いやあ、間瀬には困ったもんですな」
「まったく」
と嘆息し合うしかすべがなかった。
とくに最近の間瀬当真は色気づいており、厄介だった。年少の子どもにナイフを突きつけて体を触る、性的いたずらをはたらく等の訴えが十数件起きている。被害者のほぼ全員が、男児であった。
「遺体は――マル害は、性的暴行されていたんですよね?」
巡査はウィンカーを出し、右折レーンに入った。
「ああ、ひでえもんだったらしい。おまけに下半身は切り創だらけだそうだ」
「だったらやっぱり――」
間瀬の仕業かもしれませんね、との言葉を?み、巡査はハンドルを切って右折した。
「せめて、マル辺のほうを確保したいんですが」
と微妙に話題を変える。
「単独ならあの子は、おとなしくて扱いやすいですから」
マル辺こと渡辺慶太郎の顔を、巡査は脳裏に思い浮かべた。
こちらは間瀬当真とは対照的に、ひょろりと?せぎすだ。目も鼻もちいさく、印象の薄い顔である。代わりに顔じゅうのにきびと、大きな泣きぼくろばかりが目立つ。首が長く撫で肩なため、どこか動物のキリンを思わせる少年であった。
「お、子どもらがいたぞ」
交番長が窓の外を指した。
コンビニの駐車場だった。数人の子どもがたむろしている。巡査は再度ウィンカーを出し、駐車場にミニパトを停めた。
「おーい、ちょっといいか」
助手席側のドアを開け、交番長が声をかける。
慌てて立ちあがろうとする子どもたちを押しとどめ、
「いやいや、補導しようってんじゃないんだ。すこし話を聞きたいだけさ。きみたち、リョウって子を今日見かけたかい。十歳ちょっとの男の子なんだが」
「……リョウスケなら、お昼に『やぎら食堂』で会ったよ」
一人の男児が警戒心もあらわに答える。
「あとハシリョウがさっき、『すが田』の横で自販機の小銭拾ってた」
ハシリョウね、巡査は胸中でつぶやいた。フルネームは橋本リョウか橋田リョウといったところか。リョウがたくさんいるため、呼び分けているのだろう。
「ありがとうよ。日が暮れる前に帰るんだぞ」
交番長はミニパトのドアを閉めた。バックミラーに映る子どもたちの顔が、目に見えてほっとゆるむ。
「歯牙照会で、見つかってくれりゃいいんですがね」
巡査は低く言った。
遺体の歯型照会は、県警を通して歯科医師会に要請済みだ。身元さえ判明すれば、こんな気まずい聞き込みの手間もなくなる。
「まったくだ。しかしマル害の口腔は、ご多分に洩れず虫歯でぼろぼろだった。すくなくとも、ここ数年の治療痕はないとよ。もし親が〝夜逃げ組〟なら、県外から越してきた可能性も高い。乳歯の生え変わりもあるし、照会は手こずりそうだな。……おい、それより報告頼む」
「あ、はい」
交番長の言葉に、「そうでした。すみません」と巡査は肩の無線機に手をかけた。
肩がけの無線は『小笹川事件特捜本部』に、ミニパトの無線は通常どおり通信指令室に、あらかじめ周波数を合わせてある。
「泥首112から特捜」
「特捜です、どうぞ」
「報告一件願います。リョウスケ一名、本日の目撃あり。つづいて俗称ハシリョウなる子ども一名、目撃あり。繁華街へ確認に向かいます、どうぞ」
「特捜了解」
「泥首112了解。以上泥首112」
無線を切ってシートベルトを締め、巡査はシフトをDに入れた。コンビニの駐車場を出て、温泉饅頭屋『すが田』へ向かうべく左折する。
しかし五分と走らないうち、ミニパトのスピードは落ちた。
「おい、あれ見ろ」
「ええ」
気づいたのは、巡査と交番長とで同時だった。
前方を走る二人乗りの自転車である。?せぎすの少年がペダルを漕ぎ、その肩に体格のいい少年が手をかけての二人乗りであった。
――間瀬当真と、渡辺慶太郎だ。
今度は交番長が、自分の肩から無線マイクを取った。
「泥首112から特捜。報告一件願います。マル対を発見。マル間およびマル辺を発見。これよりバンカケに向かいます、どうぞ」
了解、の返事を聞くのもそこそこに、無線を切った。車内に一気に緊張が走る。
通常ならば「そこの自転車、停まりなさい」との警告を発するところだ。しかしそれはせず、巡査はミニパトのスピードを上げて自転車を追い越した。そして、行く手をふさぐようにして停めた。
渡辺慶太郎が急ブレーキをかけた。交番長が素早く降りる。自転車が斜めに停まり、後ろに乗っていた間瀬当真がアスファルトへ片足を付く。
自転車を降りて数歩たたらを踏むと、当真は交番長を睨みつけた。
交番長が、顔に愛想笑いを貼りつけて言う。
「おいおい、自転車の二人乗りは道路交通法五十七条違反だぞ。違反だってことくらい、きみらでも知ってるよな? ……ついでにちょっと質問させてくれや。その自転車、誰のだい?」
「おれのだよ」当真が即答した。
「ほう、きみの名前は?」
「関係ねえだろ」
「そうか、じゃあきみは?」
交番長が慶太郎へ目線を移す。「え、あ」とくぐもった声を出し、慶太郎は露骨に顔をそむけた。
少年たちが交番長に気を取られている隙に、
「防犯登録だけ、確認させてね」
ミニパトを降りた巡査は、自転車の後ろへまわった。防犯登録のシールを確認し、地域名と番号を手帳に素早くメモする。
「あ、おい」
気づいて目を怒らせた当真を、「大丈夫、大丈夫」と交番長がなだめた。
「きみたちの自転車だって確認さえとれりゃ、それで終わるんだから。ごねたら余計に長引くぞ? それはいやだろうが。さあ、名前は?」
茶番であった。泥首交番の勤務員が、間瀬当真の顔と姓名を知らないはずがない。その場の誰もが芝居だとわかっていた。
「こっちの子は答えたくないようだな」交番長が言い、慶太郎に再度顔を向ける。
「もういっぺん訊くぞ。きみの名前は?」
「あ、あの……、わた、な」
「おい!」
当真が怒鳴った。
空気が震えるような声だった。慶太郎がびくりと身をすくめ、肩を縮める。
一気に場が張りつめた。交番長がゆっくりと、当真に視線を戻す。
「――佐藤だ」
逃げられないと悟ってか、当真はふてくされた顔で吐き捨てた。
「ほう、佐藤ね。佐藤なにくん?」
「ハルキ」
「じゃあそっちのきみは? 渡辺なに?」
やはり答えたのは当真だった。「ケンジだよ」
「そうかい。渡辺ケンジくんね」
交番長が巡査に目くばせする。
巡査は早足でミニパトに戻り、無線機を取った。磐垣署の通信指令室へ?がる。まだるっこしいが、必要な手順は踏まねばならない。
「泥首112から磐垣。自転車一件願います。番号は……」
交番長と当真に目を配りながら、巡査はメモした登録番号を、わざと時間をかけて読みあげた。
肩越しに交番長の声が聞こえる。
「佐藤くん、いま登録番号を照会中だ。その間にポケットの中を見せてもらえんか」
「あぁ? なんでだよ」
「いいから、な? 見せてくれれば、すぐに終わるから」
「ヤに決まってんだろ。なんだよそれ、ふざけんな」
「いやいや、『ふざけんな』で済まされたんじゃ仕事にならんのだなあ。これで自転車の持ち主がきみらでないとわかって、ポケットも見せてもらえんとなれば、きみらは不審者を越えて参考人になる。となれば、磐垣署まで来てもらわにゃいかん」
「は? なに言ってんだ。馬鹿じゃねえの」
「いやいや、だからな、それがいやなら……」
巡査は登録番号を読み終えた。ただちに通信指令室から返答がある。
「磐垣了解。――登録者の住所、磐垣市大字泥首一二四二番地。姓名、須藤礼一。どうぞ」
やはり間瀬当真の自転車でも、渡辺慶太郎の自転車でもなかった。だよなあ、と巡査は含み笑う。彼らの所有物にしては、あの自転車は真新しくきれいすぎる。
「ざっけんな。……わかってんだぞ、てめえら警察のやることは、いつも……」
「だから、見せればすぐ済む……」
「さわんな、糞が。……てめえ、最初からおれを……」
ごねる当真の声を片耳で聞きながら、
「泥首112了解。以上泥首112」
と巡査は通信を切った。ともかく、これで彼らを署に引っぱる理由はできた。よしと小声でつぶやき、巡査が無線機をミニパトに戻した瞬間。
背後で悲鳴が起こった。
短く、鋭い悲鳴だった。
反射的に巡査は振りかえろうとした。だが遅かった。
ナイフの刃が、巡査の喉もとに突きつけられていた。
バタフライナイフだ。見覚えがある。ボールスペーサータイプで、そう、確か間瀬当真が以前所持していた――。
だがいま巡査の喉に刃を向けているのは、当真ではなかった。
「すみません」
震える声で言ったのは、渡辺慶太郎だった。その手もまた、音をたてんばかりに震えていた。
やめてくれ、と巡査は思った。
――そんなわななく手で、刃を、おれの喉に近づけないでくれ。
首すじに痛みが走った。
やはり刃が当たったらしい。だが自分の傷をうかがう余裕はなかった。彼は眼球を動かし、向こうの間瀬当真を見やった。
当真は道路にかがみこんでいた。いや違う、とすぐに悟る。
交番長が倒れている。当真が交番長の横にしゃがみこんでいる。その右手には、ミリタリーショップで買えるたぐいのハンティングナイフが握られていた。
地面を赤いものが流れている。
まさか、あれは血か。巡査は目を疑った。
喉がからからだ。一瞬にして舌が干上がっていた。声を上げたいのに、喉の奥で悲鳴は凝り、固く縮こまっていた。
――交番長が、刺されたのか。
交番勤務の警官は、基本的に防刃ベストを着けている。だが刃物を跳ねかえすほど強靱ではなく、完全に刃を防ぐことはできない。それに、むろん――。
――むろん首を狙われれば、おしまいだ。
交番長はどこを刺されたんだ。巡査は目を凝らした。
この角度からはうまく見えない。いや刺されたのではなく、首を裂かれたのかもしれない。血が流れつづけている。アスファルトが、見る間に染まっていく。
自分の視界がぼやけるのがわかった。鼻がつんとし、頬を熱いものが流れた。
「ごめんなさい」慶太郎がいま一度言った。
その声もまた、涙でふやけていた。
「だって、こうしないと、当真くんが……。ほんとうに、ごめんなさい」
7
長っ尻な饅頭屋の隠居が帰っていくのを見送って、司は引き戸の札を『準備中』に裏返した。
しかし数分後、戸はふたたび開いた。
入ってきたのは和歌乃であった。背後に蓮斗、芽愛、心菜を連れている。
「おい、まだ準備中だぞ」
「わかってるよぉ」和歌乃が口を尖らせた。
「夜の仕込み、手伝おうと思って来てやったんじゃん」
「殊勝な心がけだな。どういう魂胆だ?」
和歌乃が答える前に、肩をすくめたのは芽愛だった。
「だって外、めっちゃウザいんだよ。あっちこっち警察がうろついててさ」
「そうそう、家に帰れ帰れってうるせえの」
蓮斗もまるい頬をふくらませる。
「その家にいらんないから外にいんじゃんか。馬鹿だよなあ。あいつらってば、大人のくせに頭悪りいんじゃねえの」
泥首三大旅館のひとつと言われる『千扇』は、朝九時に従業員寮から子どもを追いだす。そして夕方五時まで完全に締めだしてしまう。理由は「中に誰かいると、光熱費がかかるから」である。
残る『ひさご屋』と『月見の宿』は多少マシで、午後三時に開錠し、病気の子ならば追いださない。こう比べれば、やはり『千扇』は因業さで群を抜いていた。
蓮斗がスイングドアを押し、厨房へ入ってくる。
「店長、おれ野菜の皮剥きする。その代わり剥き終わったら、七時までここで漫画読ませてよ。うるさくしないからさあ」
「わかった。じゃあそこの人参とじゃがいもを剥け。手ぇ洗ってからだぞ」
「あたし、玉葱切りたーい」芽愛が片手を挙げる。
「剥いたらみじん切りやらして」
「それはいいが、事件のこと、もうだいぶ噂になってるか?」
司は尋ねた。
「もっちろん。大人も子どもも、今日はその話ばっかしてるよ。小笹川の河原で、死体が見つかったんだってさ。でも殺されたのが誰かは、まだわかってないみたい」
「あたしらが顔見れば、すぐわかるかもだけど」と和歌乃。
「そのうち被害者の似顔絵でもできりゃ、それを持って聞き込みにまわるかもな。もしくはデジタル処理した画像か」
司は首をひねった。子ども相手にどれほどこの話題をつづけていいものか、切りあげどきに迷う。
心菜がおずおずと口をひらいて、
「ねえ、殺された子が誰かわかれば、犯人もすぐ捕まる?」と訊いた。
「まっさかあ、無理でしょ」
和歌乃と芽愛が異口同音に言った。
「無理無理。だって塚本町で女の人が殺されたアレも、まだ逮捕できてないじゃん。刑事ドラマみたいにはいかないんだって」
「あっちとは違う犯人っぽいよね。だって今回殺されたのって、男の子でしょ?」
「え、おれは女の子だって聞いた」
とピーラー片手に蓮斗が声を上げる。
「男の子だってば」
「あたしもそう聞いたよ」
「えー、でも……」と四人が口ぐちに言い合う。
どうやら情報が錯綜しているらしい、と司は思った。言い争う子どもたちを「おい、でかい声出すな」と仲裁する。
「それよりおまえら、怖くないのか。殺されたのはおまえらの友達かもしれないんだぞ。人殺しがこの近くを歩いてたんだぞ」
「え、うーん……」
和歌乃が額を掻く。
「なんか、ぴんとこないっていうかさぁ。殺されたのが、ほんとに知ってる子だったらあれだけど……。なんかまだ、よくわかんないんだ」
「うん。ほんと、ドラマかなんか観てる感じ」
芽愛が和歌乃と目を見交わし、うなずいた。
「怖いし、ヤバいのかもしんないけど、まだ全然『ふーん』って感じ」
「そうか」
司は首肯し、それ以上言うのをやめた。
確かに降って湧いたような大事件だ。どこか現実感がないのは司とて同じで、子どもたちはなおさらだろう。彼らは空想を好むが、かといって大人が期待するほど想像力豊かでもない。精神的に未熟なぶん、共感力は高くない。
――とくに、泥首の子はそうかもしれない。
声には出さず、司はそう口中でつぶやく。
ここの子たちは、突然の別れに慣れている。ある日友達が、親と夜逃げしていなくなる。その翌日には別の友達が、借金取りに追われて一家ごと消える。もしくは近隣の父親が泥酔して道端で寝入り、凍死体となって発見される。
死や失踪に関する感覚が鈍麻し、いつ誰がいなくなっても驚きもしない。むしろ〝人はいなくなるものだ〟〝それで当然だ〟と思っているふしさえある――。
と、己の考えに沈みつつあった司の耳に、
「殺したの、当真のやつみたいだよ」
ふとそんな言葉が届いた。
司は顔を上げた。物騒な言葉を吐いたのは和歌乃であった。細い腰に片手を当て、わけ知り顔で得々と話している。
「だってお巡りたち、みんな当真を捜してたもん。『リョウが付く名前の子を今日見かけたか。間瀬当真を見たか』って。でもまあ、あいつなら納得……」
慌てて司は「そういやあ」と割って入った。
「そういや、うちにも警察が聞き込みに来たぞ。和歌乃、おまえ顔が広いだろ? 昨日から見かけてない〝リョウ〟はいるか? もしいるなら、おれから警察に伝えておく」
「え、あ、えーと……。遼介は見たよね?」
いち早く心菜が反応した。
「見た見た。昼にいた」蓮斗が同意する。
「ハシリョウもどっかで見たよ」と芽愛。
「スガリョウは?」
「昨日の夜、パチ屋の前で見たな」
「そういえばセイリョウを見てな……」
遮るように、ばたん、と派手な音がした。
ピンクコンパニオンのユキだった。手を振ってしずくを切りながら、トイレの戸を閉めて悠々と出てくる。
まだいたのか、と司は内心で呆れた。あまりにもトイレが長いので、彼女がいたことすら忘れかけていた。
ユキは睫毛の角度をいじりつつ、
「うへぇ。あんたら、『千扇』とこの子じゃん」と眉根を寄せた。
「は? だったらなに」
和歌乃が臆さず応じる。
「なにじゃないよ。女将に言っときな。あたしはあんたの亭主なんかに色目使うほど、男に飢えちゃいないって。ふん、マジで頭おかしいよ、あのババア」
「おいおい、子どもにからむなよ」
司はユキを制した。
「焼きそば持って、早く帰ってやれ」
しかしユキはするりと厨房へ入りこみ、司にしなだれかかってきた。
「聞いてよ店長。あそこのババアってば、ほんと最悪なんだから。『千扇』からお呼びがかかんなくなって、どんだけあたしの実入りが減ったと思う? 『ひさご屋』は客層がお上品すぎるしさ。『月見』はグレードが一段落ちるし、『千扇』が一番ピンク目当ての客が多いってのに……」
「おい、包丁持ってんだぞ。くっつくな」
「そうだよ、やめなよみっともない」
和歌乃が目を怒らせて言った。
「だいたい、うちの女将はみんなにそうだよ。あたしの母さんだって、心菜の母さんだって疑われたんだからね。女将のヒスがおさまるまで『はいはい』って受け流してりゃいいだけ。なのに、あんたがうまく立ちまわれなかったんじゃん。そういうのって、ただのジコセキニンじゃない?」
「はあ? なにそれ。最近のガキって、マジで生意気」
「やめろって」
言いあう二人を制して、司はユキを厨房の外へ押しだした。
「ほら、子どもんとこに早く帰ってやれ。さっき警察から聞いただろ。人殺しがうろついてるかもしれないんだぞ」
「なんだよ。邪魔者扱いしやがってさ」
悪態をつきながらも、ユキは焼きそばの袋に手を伸ばした。フードパック入りの焼きそばは、すっかり冷めていた。
「店長、これレンジであっため……」
られるよね? と尋ねた語尾が消えた。
引き戸が開く音に、司は顔を上げた。
冷房の効いた店内に、熱を帯びた外気がむわっと吹きこむ。なのに一瞬、背すじが冷えた。空気が変わったのがわかった。
引き戸から半身を入れ、覗きこんでいるのは見慣れた顔だった。
「あれ、慶ちゃんじゃん」
芽愛が声を弾ませる。渡辺慶太郎だ。
しかし慶太郎は応えなかった。芽愛を見ようともしない。彼は店の外を振りかえり、掌を広げてみせた。次に指を一本立てる。
なんだ? 司は思った。掌を広げ、次いで指を一本。数字の六か。六─。
その瞬間、司の腕にさあっと鳥肌が立った。
和歌乃。芽愛。心菜。蓮斗。ユキ。そして自分。六人だ。
─外の誰かに、人数を伝えていやがる。
誰に、などと考えるまでもなかった。慶太郎に一番近い位置に─本棚の前にいる心菜へと目を移す。気をつけろ、と叫ぼうとした。
だが遅かった。
ものも言わず慶太郎が心菜を?むのと、黒い影が押し入るのは同時だった。
かたわらで、蓮斗が息を呑むのがわかった。司は咄嗟に蓮斗を背にかばいつつ、影の正体を見やった。
少年だった。
黒のTシャツに、同じく黒のデニム。どちらも擦りきれ、汗で色落ちしている。
背が高く骨太だ。体格がいい。右目が左目に比べて極端に細い。奇妙なほど赤い唇の合わせ目から、抜けた前歯の穴がぽっかりと黒く映る。
――間瀬、当真。
当真は和歌乃にナイフを突きつけていた。
ハンティングナイフだ。厚く太い刃がなめらかに湾曲している。喉を切り裂くのに、最適な曲線に見えた。
つづいて慶太郎も、おずおずとバタフライナイフを抜いた。心菜の喉に当てる。当真と違い、ひどくぎこちない仕草だ。それだけに危うかった。いつ間違えて刃を皮膚に当て、裂いてしまうかわからぬ不安定さがあった。
唐突に「ぱぁん」と鋭い音が響いた。
その場の全員が――当真ですら、身をすくめた。
ユキが焼きそばのフードパックを床に叩きつけた音だった。
その隙を突き、床を蹴ってユキは走った。慶太郎の脇をすり抜け、引き戸の向こうへと駆け去っていく。止める間もなかった。わずか数秒間の出来事であった。
「あ、あぁ、逃げた……」
慶太郎が、ため息のような声を洩らす。
「――に、逃げられたよ。当真くん」
にきびだらけの顔が、くしゃりと歪んだ。
「いいさ。どうせババアなんか人質にならねえ」
対照的に、当真は悠然としていた。和歌乃にナイフを突きつけたまま、唇を吊りあげて笑う。
「ババアが殺されたってテレビは騒がねえ。でもガキが死ねば、わんわん騒ぎやがるんだ。警察だってそれは知ってる。……ガキが四人いりゃ、充分だ」
司は目を凝らした。
当真が持っているあのナイフ。刃が汚れで曇って見えるが、あれはいったいなんの汚れだろう。まさか血曇り? いやそんな、まさか――。
当真は引き戸に手を伸ばし、中から施錠した。そしてナイフを左手に持ち替え、利き手を背中にまわしてなにかを抜いた。
一瞬後、司は己の目を疑った。
背にかばった蓮斗が、「ひっ」とちいさく叫ぶのが聞こえた。
「動くなよ。本物だぞ」
拳銃だった。見覚えのある吊り紐がぶら下がっている。
司の脳裏を、幼馴染みの幾也の顔がよぎった。そうだ、あれは幾也がまだ交番勤務員だった頃だ。制服の帯革に、必ず決まった装備を着けていた。警棒。手錠。そして吊り紐に?がった、ホルスター入りの拳銃――。
「間抜けなお巡りから、ぶん捕ってきたばっかのほやほやだぜ」
当真が得意げに笑う。
「おまえら、そこに一列に並べ。両手を出して上げろ。――いいか。たったいまからおまえらは、全員おれのもんだ」
(『少年籠城』より一部掲載)
インタビュー
書評
倫理を揺さぶる立てこもりスリラー
若林 踏
弱者が弱者を喰らう。そのような負の連鎖が続く地獄絵図を見せるために、『少年籠城』という小説は書かれたのかもしれない。
本書は『小説すばる』二〇二一年九月号から二〇二二年八月号にかけて連載された長編作品である。舞台となるのは泥首という地方の街だ。有数の温泉街として知られる泥首は、夫の暴力から逃れるために仲居として身を寄せる母親など、機能不全に陥った家族が多く住まう。なかには親からネグレクトを受けているため、食事が満足に取れない子どもも多いのだ。視点人物の一人である柳楽司は「やぎら食堂」という飲食店の店主で、彼はお腹を空かせた子どもに対して、簡単な手伝いなどを条件に美味くて栄養のある食事を提供する活動を行っていた。いわゆる“子ども食堂”だ。ある日、その「やぎら食堂」に少年二人が飛び込み、司や食事を取っていた子どもたち数人を人質に取って立てこもりを始める。少年のひとり、間瀬当真は地域内で起こった幼い子どもの惨殺事件の容疑者として追われている人物だ。十五歳の当真は小児わいせつ事件を繰り返していた過去があり、警察は当真に対して疑いの目を向けていた。だが当真自身は無実を主張し、真犯人を捕まえなければ人質を殺す、と警察を脅す。当真は「やぎら食堂」に入る直前に、職務質問をかけた警察官を負傷させ、拳銃を奪っていた。
当真が幼いながらも非道な振舞いを続けるなか、司は子どもたちを守るため懸命に助かる道を模索する。司はもともと国立大学で社会福祉学を専攻していた経歴があり、そこで学んだ知識も活かしながら、何とか当真を諭そうとする。理不尽な暴力に同じく力で対抗するのではなく、知性や心で相手と接し立ち向かおうとする構図が、まず読者を惹き込むはずだ。緊迫感に溢れた立てこもりの様子と並行して、本書では泥首内で発生した子どもの惨殺事件の捜査が描かれていく。もう一人の視点人物である三好幾也はある理由のため刑事課から刑務課へと異動した警察官で、同じく泥首で育った幼馴染の司に対して最近は距離をおいていた。だが、司が人質となったことを知った幾也は店内との連絡係を担当しつつ、殺人事件の捜査にも加わることになる。人質救出というリミットを課されながらも、警察陣は泥首内を歩き回り、証言を集めながら真実に近づこうとする。閉鎖空間を舞台にした手に汗握るスリラーの要素と、地道に事実を積み重ねていく警察小説の醍醐味が一度に味わえるようになっているのが、ミステリとしての本書の読みどころだろう。
立てこもりのパートと警察捜査のパートの双方で浮かび上がるのは、弱い者がさらに弱い者を生み出し搾取するという構造である。「やぎら食堂」に集まるような子どもたちは、親の貧困や虐待によって満足な生活を送ることが出来ない。だが、その親もまた、他者からの暴力などに晒されたことで社会の片隅に追いやられた被害者でもあるのだ。こうした社会的弱者が蟻地獄のような状況に嵌まり、次の世代へと負の影響が引き継がれてしまう構図が身近に潜んでいることを、作者はミステリの形式を通して描いているのだ。『虜囚の犬 元家裁調査官・白石洛』(角川ホラー文庫)の単行本刊行時、櫛木理宇は同作品のテーマが“絶対的な強者は存在するのか”であると述べていたが(ウェブサイト「本がすき。」掲載のインタビューより)、『少年籠城』では一つの共同体の姿を描くことによって同じテーマを浮かび上がらせている。泥首は格差が進み、負のスパイラルから抜け出せない弱者が増えた日本の縮図と捉えることも出来るだろう。閉鎖的な状況から社会全体を見渡すというダイナミックな視点も実は孕んだ小説なのだ。
櫛木理宇はシリアルキラーや猟奇犯罪など、常識人ならば目を背けたくなるようなものに敢えて踏み込むことによって、読者の中にある倫理観に揺さぶりをかけてくる作家である。本書では柳楽司という人物に読者が視点を委ねた時に、それは見えてくるはずだ。司が大学で社会福祉学を学んだのも「やぎら食堂」で子どもたちを支援するのも、根本には人間の善に対する信頼があるからだ。しかし、立てこもり事件の被害者となった司は、そうした自分の思いが揺さぶられる瞬間にたびたび遭遇する。そうした状況に陥ったとしても、人間は善なるものへの信頼を保つことが出来るのか。立てこもりの顚末や児童惨殺事件の真相に興味を惹かれつつ、その傍らで読者は善性について思いを巡らせることになるだろう。櫛木理宇は読者の倫理に刃を突き付ける。
わかばやし・ふみ ◆ 書評家。主にミステリ小説の書評、文庫解説を中心に活動。著書に『新世代ミステリ作家探訪』など。
「小説すばる」2023年6月号転載
全国の書店員の皆様からの推薦コメント
未来屋書店有松店 富田晴子さん
あまりに面白くて、好きすぎて、一気読み。
社会の暗黒面をこれでもかと詰め込みながらも、ミステリ的構成、緊迫感あふれるサスペンス、そしてヒューマニティが素晴らしい。
特級すぎる闇のエンターテインメント小説だ!
文苑堂書店富山豊田店 菓子涼子さん
貧困の問題を前面に出しながらも、ミステリー要素があり、読んでいてドキドキしました。
スピード感もあり、読みごたえたっぷりでした!! 文句なしで面白い!!!
文教堂書店新札幌DUO店 若木ひとえさん
「まさか、そこまでやらないだろう」だなんて甘い考えを捨てて読むといいと思います。
この本は必ずそこを超えてきます。
鹿島ブックセンター 八巻明日香さん
最初から最後まで張り詰めた緊張感のなか読みました。
大人たちが目をつぶり、蓋をしてきたことが続々と溢れ出てきて、無力さに打ちのめされるばかり。
けれど社会にはまだ良心も希望も残っている、と思わせてくれるラストが救いでした。
紀伊國屋書店福岡本店 宗岡敦子さん
生きづらい社会で懸命に生きる子ども達の心の声が、ページをめくるたびに聴こえてくるようでした。
胸の奥底に潜む孤独の闇が、光に変わっていくような物語。
最後のページを読み終えた後、爽やかな希望の風に包まれるようでした。
新着コンテンツ
-
インタビュー・対談2025年07月08日
 インタビュー・対談2025年07月08日
インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」
著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。
-
お知らせ2025年07月04日
 お知らせ2025年07月04日
お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!
演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。
-
インタビュー・対談2025年07月04日
 インタビュー・対談2025年07月04日
インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」
ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は
窪美澄
2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日青の純度
篠田節子
煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!
-
新刊案内2025年07月04日
 新刊案内2025年07月04日
新刊案内2025年07月04日情熱
桜木柴乃
直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。