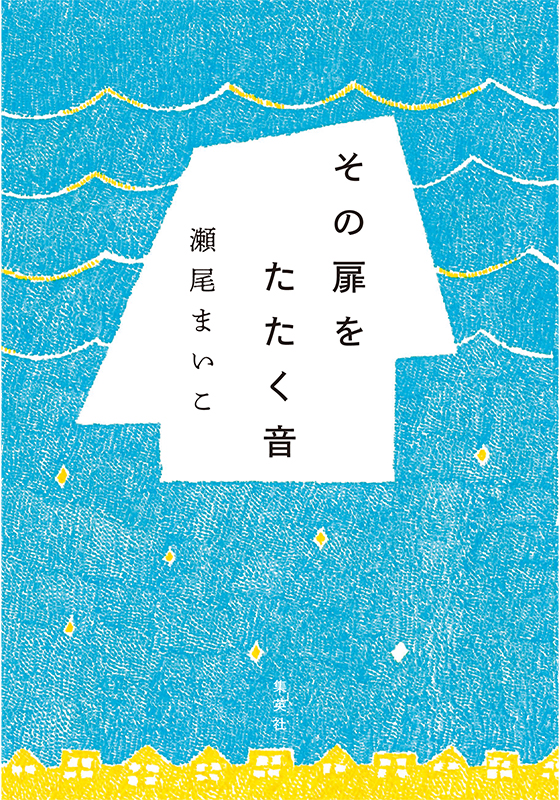作家・瀬尾まいこインタビュー「誰かと関わろうとする限り、素敵なことが待っていない人生なんか絶対にないので。私はそう信じています」
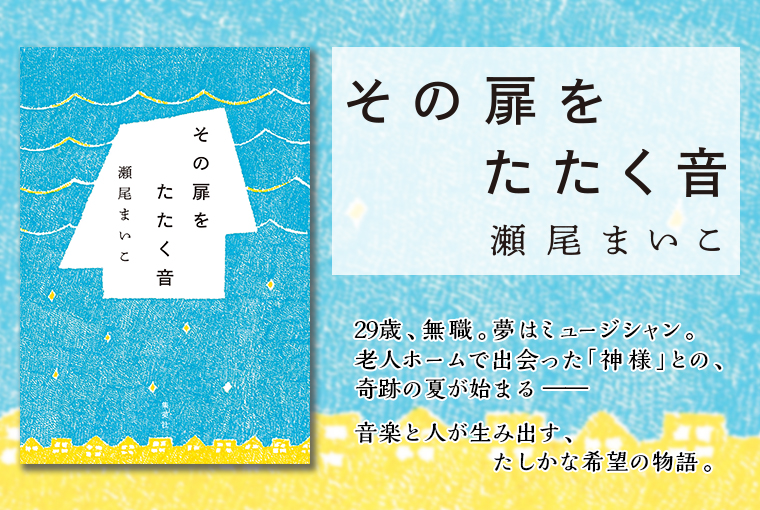
本屋大賞を受賞した『そして、バトンは渡された』をはじめ、家族や学校などを題材にハートフルな物語を数多く紡いできた瀬尾まいこさん。
新作『その扉をたたく音』の舞台は老人ホームの「そよかぜ荘」です。
人生のモラトリアムで焦燥するフリーター・宮路と、若くして人生を達観した介護士の渡部、そして人生の終幕が近づく入居者たちが、数々の名曲と共に奏でる「音楽×青春小説」。
作品に込められた願い、創作秘話などについてお聞きしました。
初出/「小説すばる」2021年3月号
モラトリアム青年と老人たち
──新刊『その扉をたたく音』は、29歳、無職の宮路が主人公です。ミュージシャンへの夢を捨てきれずに怠惰な日々を送る宮路が、余興演奏で訪れた老人ホーム「そよかぜ荘」で介護士・渡部の吹くサックスの音色に心を奪われるところから物語が始まります。単行本の帯にも引用されている「いた、天才が」という書き出しがとにかく印象的ですよね。
瀬尾 私、いつも書き出しを考えるのがすごく好きなんです。印象的な言葉が浮かんだ瞬間、自分でもワクワクするんですよね。どの作品も、舞台や登場人物のキャラクターを固めずに着手するので、書き出しが決まると、それに導かれるみたいに物語が動き始めるんです。
──ミュージシャン志望の主人公に用意された舞台が、ライブハウスやストリートではなくて老人ホームだというのが面白いですよね、意外性もあって。
瀬尾 以前、中学校で教師として働いていたので、老人ホームは交流会やボランティア、職場体験などでうかがう機会が多かったんです。だから割と情景が浮かびやすかったのかな。それに音楽を気軽に披露できる場所はどこかって考えたときに、老人ホームと路上くらいしか思いつかなくて。ただ、奈良の田舎に住んでいると、路上で歌う人を見かけることもないし彼らの気持ちについて考えたこともなかったので、知らない人の物語は書けないなぁと思って。
──老人ホームだけあって、登場人物も老若男女バラエティに富んでいて、個性派揃いですよね。そもそも宮路自身、大学卒業から7年間仕事もせず、かといって音楽に心底打ち込むこともできず、30歳の誕生日が5か月後に迫ってようやく焦りを募らせるという、なんというか、モラトリアムまっしぐらな青年で。
瀬尾 自分の殻に閉じこもっていたので、社会を知らないから成長もできず、結局大人にもなれていないんですよね。しかも、ぼんぼんなので、いまだに親から仕送りをもらいながら生活しているという。いいご身分ですね(笑)。
──一方の渡部は、堅実な介護士で入居者からの人望も厚く、若いのにどこか達観している部分もあって、ある意味、宮路とは対照的ですよね。
瀬尾 宮路と渡部を対比的に描こうとか、ことさらドライな人にしようと思ったわけではないんです。長く老人ホームに勤めて、これまでたくさんのお年寄りに接しながら介護に携わってきたので、面倒見がよくて現実的な考え方をするお兄さんは絶対いるだろうなぁと思って。
──宮路はそんな渡部のサックスプレイに心酔してホームに通いつめた挙げ句、前のめりにバンド結成まで持ち掛けてしまうわけですが、「音楽は思いを自分の演奏に乗せられるんだぜ」とか「老人ホームで演奏するんじゃなくて、もっと広い世界で」とか、言葉遣いだけは大物ミュージシャンみたいだなぁと(笑)。
瀬尾 ほんとそうですよね。「(ライブ会場の)地名叫ぶだけで観客はみんなキャーってなるんだから」とか(笑)。
──それに対する渡部のレスが「ぼくは地名を叫ぶことに喜びを見いだせそうにないです」と、超冷静で(笑)。宮路と渡部の絶妙にかみ合わないやり取りが、とにかく可笑しくて癖になります。
瀬尾 二人の掛け合いは、自分でも書きながら面白いなぁと思っていました。この物語はとにかく面白おかしく読んでもらいたいし、せっかく読んでもらうんだったら笑ってほしくて。
──一方、入居者である水木のばあさんから「ぼんくら」といじられ、おつかいまで頼まれるようになりますが、宮路も最初は億劫そうに応じていたのが、そのうち気の利いたアイテムを選んだり、世話焼きな一面を見せ始めるんですよね。同じく入居者の本庄のじいさんにウクレレを教えるようになったり、だんだん入居者たちの輪に溶けこみ始めて。
瀬尾 水木さんも、最初は「おつかいを頼むのにちょうどいいやつが来た」ぐらいに思ってたんでしょうけど、でも週に一度誰かが会いに来るのって、お年寄りからしたらすごく楽しみだと思うんですよね。それに、老人と会話するにあたっての速度とか、声の大きさとか、大事じゃないですか。そのへんのさじ加減が自然と身についている宮路には、一目置くようになったんじゃないかと思います。ほっとけない兄ちゃんっていうか。
「青春」を描くということ
──他者と触れ合うなかで宮路の心もゆっくりと動き出して、無風だった日常が少しずつ色づいていく様子が、読んでいて微笑ましかったです。
瀬尾 小説のなかで人と人との関わりを描いていると、いつもは「アットホームでほっこりあったかい物語を書いてるなぁ」と自覚するような瞬間があるんです。でも、今回はそれよりも「青春小説を書いてるなぁ」という手応えが強くて。
──青春小説ですか。
瀬尾 もちろん読者にはどう解釈していただいても構わないのですが、私自身は、ひとりの男性が殻を破ってどんどん世界に進んでいく様子を描いている感覚があったんですよね。
──瀬尾さんにとっての「青春」を言葉にするとしたらどんなものですか?
瀬尾 う~ん。いつも胸がギュ~ッと締め付けられるような感じっていうか。嬉しくて楽しくてハラハラドキドキしてたかと思えば、落ち込んでウジウジグズグズする。何をやってもうまくいかなくて、焦りもあるんだけど、とりあえず前に進んでかなきゃならない……そんな感じです。ただ、私自身に青春はなかったので、あくまで教師として働きながら生徒たちを通して感じた青春ですが(笑)。
──そんな青春の煌めきが、宮路には29歳にしてようやく訪れたわけですね。
瀬尾 でも、胸がギュ~ッと締め付けられるような経験は年齢関係ないというか、もちろん大人になればそういう機会は減るけど、私自身、小説を書いているときや子育てをしているときにそんな瞬間があるので、その揺れ動きがあれば、中学生だろうと30歳手前の男だろうと青春だし、青春小説になると思うんです。
──そこで老人ホームという舞台がまた意味を持ってきますね。ほのぼのとした交流だけではなく、人生の終わりが近づいた人々に訪れる現実とも宮路は自ずと向き合うことになり、心は動揺します。
瀬尾 お年寄りってぼけるし、死ぬんですよね。私の祖母も老人ホームに入って、その後亡くなりましたが、老人ホームが身近な人にとって、それは当たり前に起きることなんです。宮路は知らなかった現実を前に戸惑ったり傷ついたりしますが、それは特別なことではなくてあくまでも日常、現実なんだぞっていう気持ちは書きながらあったかもしれません。
──実際、そうした周囲の現実が、宮路にとっての現実に裂け目を入れていきますよね。このままじゃダメだ、でも何をどうしたらいいかわからない……という、宮路のジリジリとした焦燥感がリアリティをもって伝わってきたのですが、このあたり瀬尾さんご自身の経験も投影されていたりするのでしょうか?
瀬尾 どうでしょう。私が宮路と同じ29歳の頃って……そうか、教員採用試験に受かった年ですね。私、採用試験に10回も落ちてるんです。それまでは講師として働いていて、仕事がないときはバイトしてましたし、めちゃめちゃ焦燥感がありました。それに37歳で教師を辞めた直後も、社会からはみ出してしまったような感覚がありました。小説は書いてたけど、暖かい部屋でパソコンに向かっているだけで、無職と同じようなものだと思っていて。その後、結婚して子供が生まれて主婦が職業になったとも言えますが、ちゃんと社会の一員でいられてるのかなっていう思いは心のどこかにあった気がします。なので、そのあたりは無意識に投影されているかもしれません。
──その気持ちは今でも?
瀬尾 いえ。2年前に『そして、バトンは渡された』で本屋大賞をいただいたことで書店員さんとたくさんお会いする機会ができて、必死で本を売ってくれている姿を見ながら「小説を書くことは仕事じゃない」なんて言うのは無責任だなぁと思いました。いま書くことが楽しいのは、趣味ではなく、仕事だという意識でやっているからこそだと思うんです。小説家になりたいと思ったことは一度もなくて、教師を辞めたあと「人生、間違えたかな」とも思いましたが、書店員さんや読者からの感想やメッセージを読むと、人に喜んでもらいたいとか、わずかでも誰かの背中を押すことができればという気持ちは一緒で、教師の頃から本質は変わっていないんだなって思います。
偶然の音楽と動き出す人生
──今作は音楽が大切な要素として物語に熱さと彩りを添えていますね。瀬尾さんがここまで音楽をメインにした作品を書かれたのは初めてじゃないですか。
瀬尾 音楽ってすごいですよね! 音楽を聴くと、何もない状態から突然胸が震えたりするじゃないですか。それくらい音楽の力って大きい。でも、私自身は音楽に詳しいわけでも、そもそも今回、音楽を題材にしようと思ったわけでもないんです。書いているうちに、宮路も渡部も演奏するし、ホームでの演奏会も決まるし、「じゃあ、セットリスト決めなきゃ!」みたいな感覚で、どんどん登場する曲が増えていったんですよね。
──偶然だったんですか。
瀬尾 普段、音楽が鳴っていると集中できないので仕事中は絶対聴かないんですが、この物語だけは作品に登場する音楽をリピートしながら書きました。もともと好きな曲ばかりですけど、聴いていると、宮路や渡部が演奏する場面がすっとイメージできましたね。
──唱歌の『ふるさと』から、坂本九『上を向いて歩こう』やビートルズ『ヘイ・ジュード』といった超名曲、そしてアメリカのパンクバンド、グリーン・デイの『ウェイク・ミー・アップ・ホウェン・セプテンバー・エンズ』まで、幅広い選曲になっていますよね。中でも「セプテンバー・エンズ」は特に印象的な使われ方をしますが、もともと瀬尾さんの思い出の一曲だったりするんですか?
瀬尾 それが、違うんですよ。宮路なら老人が相手だろうと関係なく、洋楽を歌うだろうなと思いました。でも、有名な洋楽バンドっていうとオアシスとグリーン・デイくらいしか知らなくて。それでいろいろ聴いてみた中で「セプテンバー・エンズ」が一番引っかかったんです。ほんと、いい曲だなって。
──それも偶然でしたか! この曲はフロントマンのビリー・ジョー・アームストロングの父親を亡くした悲しみが綴られているそうですが、宮路の置かれた状況や心境とも完全にシンクロしているので、もともとお好きだったのかと……。
瀬尾 それはほんと、自分でも驚きました。宮路が30歳の誕生日を迎える11月まで、今の生活をちんたら続けているのは違うな、動き出すとしたらもう少し前だなと思っていたんです。それで、書き進めながらこの曲について調べて、自分で少し歌詞を訳してみたら、〈夏は終わる 無邪気なままではいられない 九月の終わりに起こしてほしい〉……って、えっ! これって宮路へのメッセージじゃない!? って、びっくりして。グリーン・デイがアメリカから宮路にエールを送ってくれていたんですね(笑)。
──最終的に宮路がそのエールをどう受け止めたか、ぜひ本編で確認していただきたいのですが、この物語を読むと、他者と関わることの意味を改めて身に染みて感じますね。
瀬尾 ひとりでいても人生は変わらないけど、誰かと関わることによって絶対に動き出す何かがありますよね。部屋に閉じこもっているときの宮路には実際何も起きなかったけど、関わる人が増えて、関わる時間が長く深くなったからこそ、素敵な何かが待っていた。誰かと関わろうとする限り、それが明日なのか10年後なのかはわからないけど、素敵なことが待っていない人生なんか絶対にないので。私はそう信じています。
──力強いですね。
瀬尾 でも何より、この物語は楽しく読んでもらうのが一番だと思って書いたので、読んでいただいた誰かの気持ちが、少しでも明るくなるなら幸いです。
──最後に……実はですね、瀬尾さんが『卵の緒』で坊っちゃん文学賞を受賞して作家になられたのが2001年なので、ちょうど今年が20年目なんですよ。
瀬尾 えっ、ほんとですか!? 考えたこともなかった。すごい、20年も書いてたんですね……って、そう言った途端、急に部屋に日光が射し込んできて、いま私、めっちゃ光が当たってます。祝い出しました、太陽が、20年を(笑)。そうか、じゃあ、20年目を記念する一冊になりましたね。でも、それを帯に書いたりしたら歳がバレて「年寄りが青春小説書いてキモい」とか言われるのでやめましょう(笑)。いっそ、女子高生の覆面小説家が書いたことにしましょうか?
──いえいえ、「瀬尾まいこ、20年目の青春小説」って、とても素敵ですよ。
瀬尾 でも、こうして書き続けていられるのも、ただただ楽しいからで。書かない生活は想像できないというか、書かないとやっていけない……あ、そんな内田裕也さんみたいなカッコいいことをいつも思ってるわけじゃないですよ!? でも、1週間書くなと言われたら、むずむずしそうな気はします(笑)。
──今後も、気持ちは「キープオン・ロックンロール」で書き続けてくださいね。
瀬尾 はい。楽しみながら頑張ります。
プロフィール
-
瀬尾 まいこ (せお・まいこ)
1974年大阪府生まれ。大谷女子大学国文科卒。
2001年「卵の緒」で坊っちゃん文学賞大賞を受賞し、翌年、同作を表題とする単行本でデビュー。2005年『幸福な食卓』で吉川英治文学新人賞、2008年『戸村飯店 青春100連発』で坪田譲治文学賞、2013年咲くやこの花賞、2019年『そして、バトンは渡された』で第16回本屋大賞を受賞する。
『おしまいのデート』『春、戻る』『ファミリーデイズ』『傑作はまだ』『夜明けのすべて』など著書多数。
新着コンテンツ
-
インタビュー・対談2024年04月20日
 インタビュー・対談2024年04月20日
インタビュー・対談2024年04月20日青羽 悠「大学生活を送りながら書いた、 リアルタイムな京都、大学、青春小説」
一人の青年の大学四年間を描いた青春小説。大学生活とは? 大人になることとは?
-
お知らせ2024年04月17日
 お知らせ2024年04月17日
お知らせ2024年04月17日小説すばる5月号、好評発売中です!
注目は赤神諒さんと宇佐美まことさんの2大新連載! 本多孝好さん初の警察小説の短期集中連載も必読。
-
連載2024年04月15日
 連載2024年04月15日
連載2024年04月15日【ネガティブ読書案内】
第29回 インベカヲリ★さん
「常識に汚染されそうになった時」
-
お知らせ2024年04月10日
 お知らせ2024年04月10日
お知らせ2024年04月10日『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』が2024年本屋大賞翻訳小説部門第1位を受賞!
『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』(ファン・ボルム 著 牧野美加 訳)が2024年本屋大賞翻訳小説部門第1位に決定しました!
-
お知らせ2024年04月06日
 お知らせ2024年04月06日
お知らせ2024年04月06日すばる5月号、好評発売中です!
注目は松田青子さんの新連載と山内マリコさんの連作小説! キム・ソヨンさん×文月悠光さん、桜庭一樹さん×かが屋のお二人の対談も必読!
-
新刊案内2024年04月05日
 新刊案内2024年04月05日
新刊案内2024年04月05日22歳の扉
青羽悠
小説すばる新人賞、史上最年少受賞から8年! 二十代前半の「不変」と「今」が詰まった圧倒的青春小説!