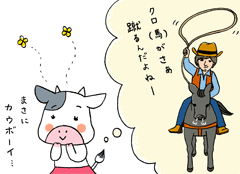嘘はつかずに、ひっかける
デザイナー・池田進吾(67)
森絵都さんの『カラフル』、角田光代さんの『対岸の彼女』、最近ではいしいしんじさんの『四とそれ以上の国』……。
これら話題作の装丁を手がけたのが、デザイナー・池田進吾さんだ。
パッと目を引きつつ、作品の内容をピタリと表現したデザインに、作家の信頼も厚い。
そんな池田さんに、上京秘話から仕事にかける思いまで、たっぷりとうかがいました!
(1)デザイナー・池田進吾の誕生
北海道から東京へ
北海道出身の池田さんは、高校卒業を機に上京した。
しかし、当時はデザイナーになるつもりは全くなかった。
内定していた会社は、アイスクリーム製造会社だった。

池田進吾(67)<いけだ・しんご(ロクナナ)>
1967年北海道生まれ。デザイナー。
ポスター、エディトリアル、書籍の装丁など、様々なデザインを手がける。装丁の仕事に、森絵都『ラン』、誉田哲也『武士道セブンティーン』など多数。

池田: 高校3年生になって就職活動をはじめたんです。先生と面談して、栃木のアイスクリーム工場に内定をもらいました。それを報告しようと思って東京に住んでいる親戚のおじさんに電話したら、「ダメだ。お前はデザイナーになれ!」と言われて……
--ずいぶん唐突に、断言されましたね(笑)。
池田: おじさんは東京でデザイン事務所を構えていたんですけど、僕が子供の頃に描いた絵を見たことがあって、それが面白い構図だったらしく、デザイナーに向いていると思ったみたいなんです。それに、北海道からいきなり独りで栃木県に出ていくのは可愛そうだと思ったんでしょうね。それから2年間、おじさんのところに下宿してデザイン専門学校に通いました。
--専門学校ではどういう勉強をしていたのですか?
池田: 商業デザイン科で、主に広告をつくっていました。学校はすごくつまらなかったですね。先生とうまくいかないこともあったし、ただ授業に出て、課題をこなしていただけでした。
--デザインの面白さに、その頃はまだ開眼していなかったのですね。
池田: 卒業した後も、最初に就職した会社は半年で辞めました。ビデオのパッケージデザインなどをやっている会社でしたが、僕の仕事はお使いでした。会社と写植屋を、毎日何回も往復したりしてね。
次に、広告デザインの会社に移って、版下をつくる作業をしていました。先輩たちが文字や絵を紙に貼り付けてレイアウトしたものを、印刷屋に渡す版下原稿に起すんです。結局、おおもとのデザインは代理店が作ってしまうので、物足りなさを感じていました。

愛用のカメラたち
K2での日々
そんな時、池田さんは二人の人物と出会う。
デザイン事務所「K2」の、黒田征太郎さんと長友啓典さんだ。
K2は、エディトリアル、ポスター、広告など、様々なデザインを手がけていた。
池田: 学生の頃、渋谷パルコの展覧会で、初めて黒田さんの絵を見ました。その絵の印象がすごく強烈で、ずっと欲しくて……就職してお金が貯まってから、黒田さんの事務所に買いに行ったんです。その後、事務所のマネージャーさんから電話がきて、黒田さんと会えることになり、黒田さんのアトリエで僕のデザインしたものを見てもらったんです。そこで、「今やっている仕事は面白い?」と訊かれました。「うち(K2)は、今より面白いと思うよ」と。そういうわけで、K2でアルバイトを始めました。22歳の時です。
--その時は、まだ別の会社の社員でもあったわけですよね。
池田: 朝9時から夕方6時まで東銀座の会社で働いて、それから六本木のK2で、終電までアルバイトをさせてもらいました。
--ものすごくハードな生活ですね……
池田: でも、すごく面白かったですね。K2は、仕事がたくさんあるし、スタッフも仕事に厳しかったです。
--その後、アルバイトから社員になったのですね。K2ではどんなお仕事を?
池田: 雑誌の仕事が多かったですね。最初は先輩の手伝いをしていて、徐々に自分でデザインをさせてもらえるようになりました。タイトルを忘れてしまったけど、一番初めの仕事は装丁だったと思います。
主に、角川書店の雑誌で「野生時代」や「月刊カドカワ」のデザインをしてました。「月刊カドカワ」では、永瀬正敏さんの連載で、僕がほとんどの撮影を担当してました。当時、永瀬さん主演の映画「私立探偵濱マイク」が流行ってたんですけど、僕が濱マイクになって永瀬さんを追跡するという企画でした。彼の婚約会見も、実は、最前列で写真を撮っていたんです。芸能レポーターがずらりと並んで、報道カメラマンがたくさんいて、そんな中、僕だけコンパクトカメラを構えて、「左に目線お願いしまーす!」なんて言ってましたね(笑)。
本当に、K2ではなんでもやらせてもらって勉強になりましたね。
大竹伸朗さんとの出会い、そして独立

次の転機は、30歳の時だった。
池田さんはK2を辞め、独立する。
決め手になったのは、アーティスト・大竹伸朗さんとの出会いだった。
池田: K2に入って2年くらいすると、どうしたら社長からデザインのOKが出るかだいたい分かってきました。仕事はどんどん来るし、朝まで仕事をするような毎日で、だんだん仕事をこなしているだけになっていきました。たまに、欲を出してちょっと変わったデザインのポスターにしてみると、黒田さんにビリビリと破られてしまうということもありました。破られることは嫌ではなかったけれど、前に進んでいかない気がしてきて、辛くなってきましたね。
--そんな息苦しさを抜け出すべく、独立を決意したのですか?
池田: 辞めたいというよりは、自分でやりたいと漠然と思っていただけで、きっかけが無かったんです。そんな時に、大竹伸朗さんと出会いました。大竹さんはもともとK2と親しくしていたみたいですね。ある時、一緒に飲みに行く機会があって、そこで「K2に何年いるの?」と訊かれました。8年だと答えたら、「もう、いいんじゃないの」と言われたんです。それで僕も素直に「もういいのかぁ」と思って、社長に辞めますと言いました。
驚くほど潔い決断だが、直感は間違っていなかったといえる。
その後、大竹さんとの付き合いは続き、
2006年には東京都現代美術館での大竹伸朗大回顧展「全景」の図録を池田さんがデザインするなど、話題となった。
出会うべくして出会った二人だったのだ。

(2)装丁
『カラフル』との出会い
デザイナーとして独立した池田さん。
現在では装丁家としてのイメージが強いが、独立当初は音楽や映画関係の仕事が多かった。
転機となったのは、森絵都さんの作品との出会いだ。
--文芸書の装丁を本格的に始めたきっかけは?
池田: 独立して最初に手がけたのは、又吉栄喜さんの『波の上のマリア』でした。これが「ダ・ヴィンチ」の装丁大賞「今月の大賞」に選ばれたんです。その後、森絵都さんの『カラフル』という作品に出会いました。この仕事の反響が大きかったですね。
--『波の上のマリア』は、タイトルを作り文字にしたり、装画もご自身で描かれたりと、最初のお仕事にして既に池田さんの装丁のエッセンスが詰まっていたように思います。
『カラフル』は今から10年前の作品ですが、当時のヤングアダルト(YA)小説にはない斬新なデザインで、話題になりました。私はちょうど読者の世代でしたが、あの頃のYA小説は、カバーが子どもっぽかったですよね。
池田: 『カラフル』は、僕のデザインした映画パンフレットが基になっているんです。理論社の編集者がそのパンフを持って、依頼に来てくれました。僕も気に入っているデザインだったし、カバーはほぼそのままの雰囲気にしたんです。
--装丁は評判になりましたし、本もかなり売れましたよね。そこから、装丁の仕事は増えましたか?

池田: 理論社の編集部が信用してくれたみたいで、その後、伊藤たかみさんや角田光代さんの装丁をさせてもらいました。そうやって増えていきましたね。
--伊藤さんの『ミカ×ミカ!』や、角田さんの『これからはあるくのだ』ですね。池田さんの装丁を書店でもたくさん目にしますが、今は、一年間に何冊くらいお仕事を請けているのですか?
池田: そんなに多くないです。年間30冊くらいだと思います。

嘘をつかない装丁
池田さんの装丁は、斬新だと評価されることも多い。
手書きのタイトルやノンブル(ページ数を示す文字)、目を引く色使いなどが新鮮だ。
どのようにして生み出されているのだろうか。
--文芸書の場合、どういうプロセスでデザインをされるのでしょうか。
池田: まず、装丁を考えながらゲラを読みます。これに一番、時間がかかります。1回読んで済むこともあるし、5回も6回も読むこともあります。デザイン案が出てくるまで、とにかくしつこく何度でも読みますね。
--池田さんは以前、「装丁は自分なりの感想文」と仰っていました。「感想文」を書くにあたり、こだわっていることはありますか?
池田: 作品の内容に対して、装丁が嘘をつかないようにしています。内容がすごく面白いものはそれに負けないくらいの装丁を作りたいと思うし、色んな人に読んでもらいたいから、書店でも何だか気になって、ひっかかって、手に取って、買ってもらえるようにと考えます。そして、読んだ後で「やっぱり買って良かった」と思ってほしいです。変に盛り上げようとしたり、作品を過大に解釈するようなことはしたくないですから。
池田さんは、決して新しさを狙っているわけではない。
作品の内容を、最もうまく表現する方法を選んでいるだけなのだ。
その誠実な姿勢から生まれるデザインは、私たちを「ひっかけ」、そして裏切らない。
(3)5つのキーワード
池田さんのデザインの秘密、そして素顔に迫る、5つのキーワードを並べてみよう。
「カバーと表紙」

白くてシンプルなカバー。外すと……

ベルベットの表紙が!
--カバーが良くても、外してみたら意外と普通の表紙だったということがよくあります。その点、池田さんの装丁は、カバーを外す時の楽しみがあるので好きです。例えば『カラフル』の単行本はシンプルな黄色いカバーですが、外すと可愛らしいタッチの教室のイラストが表紙になっています。『ショート・トリップ』の単行本は、白いカバーを外すと、なんとベルベットの生地に金色のロケットが飛んでいる! これには驚きました。
池田: カバーと表紙のデザインが同じだったりすると、ちょっとさびしくなったりしますね。
僕は、カバーで表現しきれないことを、表紙や別丁扉を使って伝えられれば良いと思っています。でも、書店で本を開いてみる人はいても、カバーを外して表紙を見ている人はそんなにいないかも知れないですね
--表紙の仕掛けは、買った後、あるいは読んだ後の楽しみですよね。得した気分になります。
池田: そういう驚きがあると、買って良かったと思います。その気持ちを大事にしたいですね。

「手書き文字」
--池田さんというと、手書き文字の印象が強いです。最近刊行された森絵都さんの『ラン』は、なんと463ページ分のノンブルが全て手書き! よく見ると「8」という字も「18」と「86」では微妙に違っていたりして、面白いです。
池田: 『ラン』は、森さんの希望で手書きにしたんです。『カラフル』の時に初めてノンブルを手書きしたんですけど、それが気に入ったみたいですね。
僕は、作品の内容に合っているフォントが無いと思ったら自分で作るんです。凝ったものにしようとか考えているわけではないんです。
--作品ごとに、違った感じの字が作れるのがすごいと思います。

もはや原型をとどめていない「麦」の字
池田: 例えば、『麦ふみクーツェ』のタイトルは手書きにしました。この「麦」という字を書いているうちに、だんだんもとの字がわからなくなってくるんです。麦だったらもっとタテ棒が生えててもいいかな、とか、もっと点があっても良いかな、とか……(写真参照)。タイトルの文字は僕にとっては絵の一部のようなものだから、字の原型をとどめなくなってしまうんです。絵の中にまた文字という絵があって、その組み合わせで「麦ふみクーツェ」を表現するという感覚ですね。だから、文字の形は作品ごとに違います。
始めに左手で書いてみてから形を決めることもあります。右手で書くとどうしても「文字を書いている」という前提ができてしまうけど、左手は不自由だから、変に崩れて面白い形ができたりするんです。

--いったん文字の枠を外してみるということですね。タイトルではなく、文字だけのページ、例えば目次などの文字はどうですか?
池田: 手書きでと頼まれたらやっぱり毎回違いますね。普通に「あ」と書くにしても、毎日違う字になります。右肩上がりの日もあるし、平べったくなる日もあるし、縦に伸びる日もある。自分の字の形は無いので、小説の内容次第で変わりますね。
「3つの椅子」

奥からデザイン、絵、文章の場所
--池田さんは、装画を描いたり、絵本の文章を書いたりと、多岐にわたるお仕事をされています。仕事の内容によって、3つの椅子を使い分けているそうですね。
池田: デザインをする場所、絵を描く場所、文章を書く場所があって、作り文字の場合、パソコンに取り込んで形を整えるのでデザインの場所で作業をします。でも、手書きのまま使おうとする時は、絵の場所でないと書けません。細かく切り替えて仕事をしています。
--ご自分で装画を描く作品と、そうでない作品がありますよね。
池田: どういう装丁にしたいのか考えながら原稿を読んでいる時、いくつかのイメージが頭に浮かんできて、それに合いそうで描けそうな時は、デザイナーの僕がイラストレーターの僕に依頼します。内容次第では最初の候補にも入りませんね。
--作品の内容を表現するために最良のものを選んだ結果、池田さんの絵になることもあるということですね。『屋久島ジュウソウ』や『これからはあるくのだ』では写真撮影もなさっていて、本当に多才だなぁと思います。

「カウボーイ」
--絵と文を手がけた絵本『TONY』は、カウボーイのトニーが主人公です。愛馬シルバーに乗って都会に行くトニーの物語は、池田さんの自伝でもあるとか?
池田: 実際、北海道で実家の近所の牧場でアルバイトをしていて、馬の世話をしていました。よく馬にバカにされてたなぁ。鞍を載せようとすると逃げられるんです。その度にニンジンをあげて、撫でて、「頼むよぉ~」とお願いするんです(笑)。
--馬への愛情をすごく感じます(笑)。その馬の名前が、シルバーですか?
池田: 名前はクロだったと思います。黒い馬で、道産子の足が太い農耕馬でした。
--今はもう馬には乗らないとのことですが、カウボーイはお好きですよね。事務所の入り口で、テンガロンハットを発見しました。
池田: 最近の芸人さんで面白いと思うのは、テレビ番組の「あらびき団」に出てくるハリウッドザコシショウとふとっちょカウボーイだし(笑)。
東銀座に勤めていた頃は、ウェスタンシャツを着て、テンガロンハットにウェスタンブーツで通勤していました。昼飯時の大通りを、小綺麗な会社員に混じってフリンジたっぷりの皮ジャケットを着て歩いていました。

北海道から、東京へ。
ひょんなことからデザインの世界に入った<元・カウボーイ>池田さんは、
編集者、作家からも信頼されるデザイナーとなった。
作品の内容に忠実に、自由な発想から生まれる装丁は、決して嘘をつかない。
これから、どんな作品を手がけ、どんな風に見せてくれるのだろう。
本屋さんの店頭でも、要チェックだ。
「池田さんって、最初は怖そうに見えるかも……」と先輩に言われ、ドキドキしながらお会いしました。けれど、そんな心配は無用でした。池田さんは、デザインだけでなくお話する時も嘘をつかない、飾らないのです。そんな率直な物言いが「怖そう」なのかもしれませんが、実は面白いこと好きで、愉快なお話もたくさんお持ちです。事務所には懐かしのオモチャがあちこちに置かれ、なかでも「キン肉マン」がお好きだとか。遊び心を忘れない、素敵なお兄さんなのでした。どうもありがとうございました!