佐々木俊尚2013.3.15
第3回横すべりするコンテンツ
日本で初めて上映禁止処分となった映画は、明治41年(1908)に公開された『仏国大革命 ルイ十六世の末路』というフランスの無声映画だ。
この上映禁止の顛末は、いまの映画の常識から考えるととほうもなくヘンで面白い。
『仏国大革命』が公開されたのは、日本で映画文化が少しずつ広がろうとしていた時期だった。
フランスのリュミエール兄弟が発明したシネマトグラフ映写機が輸入され、大阪の南地演舞場で国内初上映されたのは、明治30年。
日本オリジナルの映画が初めて制作されたのはその2年後の明治31年。この年に、今も現存している最古のフィルムである9代目市川團十郎、5代目尾上菊五郎主演の『紅葉狩』も撮られている。
最初の常設映画館である東京浅草・電気館がオープンしたのはさらに2年後の明治36年。だが国産映画を制作する態勢はととのっておらず、上映された映画の大半は輸入フィルムだった。
そしてこの時期にはすでに「弁士」「活弁」と後に呼ばれるようになる映画説明者が、スクリーンのそばに立って映画の内容を口頭で解説していた。
『もう一つの映画史 活弁の時代』(吉田智恵男、時事通信社)によれば、シネマトグラフ以前に日本に輸入されたキネトスコープが公開された際、機械の横に人が立って説明していたのがその発祥ではないかという。キネトスコープはシネマトグラフのようにスクリーンに投影されるのではなく、郵便ポストぐらいの大きさの箱にのぞき穴がついていて、ひとりずつのぞき込んで穴を通過するフィルムの映像を見る仕掛けである。発明王エジソンがつくったものだ。
このキネトスコープの横に立っていた解説者は、上田布袋軒という人だった。大阪の商家の生まれだったが、家業をつがずに遊芸の道に入り、義太夫語りになった。興行などの口上が得意で、その技を買われてキネトスコープの解説者を頼まれたらしい。そして義太夫語りが最初の映画説明者となったことが、その後の活動弁士の文化の方向性を規定していくことになる。ドラマチックかつ重厚に盛り上げる義太夫節はそれ自体が独立したひとつの芸術である。義太夫的な語りが無声映画と合体することによって、単体の映画コンテンツに弁士のコンテンツが組み合わされた二次コンテンツをうみだすきっかけとなったのだ。
映画の中身がチープでも、活弁が面白ければそれで観客は沸いてしまうなんていうことも起きた。人気のある弁士は映画スターのような扱いを受け、「あの弁士でなければこの映画は観たくない」など観客の側が弁士の質によって観る映画を決めていたほどだとも言われている。欧米では無声映画は楽団の演奏とともに上映するのが一般的で弁士は流行せず、活動弁士というのは日本だけの特異な上映法だった。
活弁として歴史上最も有名な徳川夢声は、著書『徳川夢声のくらがり二十年』(清流出版)で、『二〇三高地激戦』というひどい出来の映画をどうやってとある弁士が盛り上げたかを面白おかしく紹介している。
二〇三高地というのは当時勃発していた日露戦争の激戦地で、この映画は「戦争の実写」という触れ込みだった。しかし実際には、無人の野原も広がっていた新宿の戸山ケ原あたりで花火を爆発させて、兵士に扮した役者十数人がただでたらめに駆け回っているだけのものだったという。これを観客に見せるために、活弁はどうしたか。
「先ず、前説で客を脅かしちまうんだそうである。滔々数十分に亘って、ソモソモ日露戦争は、と満州問題から説き起し、逆のぼって日清戦争の由来、三国干渉のガシン・ショータンに悲憤の涙を流し、客を滅茶々々に興奮さしといて、
──さて、諸君! 此写真は、あらかじめ御断りして置きまするが、正真正銘の写真でアリマス。デアルカラ、そんじょそこらで映しておるイカサマ物と異り、あまり綺麗に写っておらんのでアル。また、見た目に華々しく勇しき戦争もアリマセン──何故かなれば、実戦は決して華々しく勇しきものではない、寧ろ凄惨なものであるからでアリマス。
てんで、大喝采のうちに、ボロボロの戸山ケ原が映り出す。
『諸君、この写真が、如何に命懸けで写されたかという証拠は、二〇三高地の頂上が、今御覧になれる事である。実写であるから、ホンの一寸しか映りませんぞ。その御積りで、私が注意したら、御見落しなく御覧を願います。それッ、只今ですぞ!』
と一段大きな気合をかけて、
『今ッ! いまッ! 見えます、濛々たる煙の中に──あッ見えました──あれあれ、あッ、もう見えません。』
とやるんだそうだ。一寸、近頃のスポーツの放送みたい。
すると観客は、目をパチパチして、
『おい君、見えたかい。』
『うん、俺は見たよ。微かにチラッとだけ見えた事は確かだ。』
『そうか、残念だなア。俺には何んにも見えなかった。』
と、頻りに残念がっているが、実のところ、初めッから何んにもないものなんだから、見えない方が確かだったんである」
活弁の語りというコンテンツが、一次コンテンツの映画のコンテキスト(文脈)になることによって、非常に面白い二次コンテンツに変化してしまう。これは、現代のニコニコ動画で行われている二次創作のありように非常に近い。
たとえばニコニコ動画には「ゲーム実況」という人気ジャンルがある。しゃべりながらゲームをプレイしている様子を記録したものだ。画面には、RPGやアクションなどのさまざまなゲームの画面。そこにゲームプレイヤーの雑談まじりの音声が被さっているだけである。
しかしこれが妙に面白い。たとえばホラーゲームの中で、暗い廊下を進んでいる時。何かが出そうな雰囲気だなあというところで、実況者は「うわ、やべえ。これやべえ。……うわっきた!」と怯えながらゲームをプレイする。何が面白いのかを説明するのはたいへん困難だが、ゲーム実況の面白さを「友達の家に行って、その友達がゲームやってるのを横でだらだら酒呑みながら見てるような感じ」と表現した人もいた。たしかにそのような感覚かもしれない。
ゲーム実況をテーマにしたマンガ『おとなりさん』(みなもと悠、『つもる話もあるけれど、とりあえずみんなゲーム実況みようぜ!』ハーヴェスト出版に所収)には、女性のゲーム実況者に淡い恋心を抱く青年の話が描かれている。
「おはようございます こんにちは こんばんは 初めましての方は初めまして音鳴(おとなり)です」
という実況者の声。青年はつぶやく。「マイナーゲームを中心としたゲームチョイス プレイ画面と共に流れてくる可愛らしい女性の声 そして一度実況をはじめたゲームはいかなる無理ゲーでも必ず最後までやり遂げる 女性らしさの中にかいま見える芯の強さ 僕は彼女の動画に夢中だった」
そしてある日、ニコニコ生放送のゲーム実況で音鳴が選んだゲームは、主人公の青年が子供時代にロープレメーカーというRPG制作ソフト(たぶん実在のソフト『RPGツクール』をイメージしているのだろう)でつくった「血塗られた堕天使」という恥ずかしいタイトルのゲームだった。
「僕のじゃねえか」「よせ やめろ 僕の厨二丸出しの黒歴史を」と恥ずかしさにもだえる青年。生放送を見ている視聴者たちは「つまんなそう」「タイトルからクソ」「これは見なくていいわ」「クソゲー確定」とさんざん罵倒しながらも、けっこう楽しんでいる……というストーリーだ。
その先は作品を読んでいただくこととして、ここでは元のゲームそのものよりも、そのゲームを実況する側にコンテンツの主体が移ってしまっているということに着目しておきたい。一次コンテンツに対する単なるコンテキストではなく、そのコンテキストが新たな二次コンテンツとして成立するということが起きている。そしてこのようなコンテキストからコンテンツへの転換という行為は、ニコニコ動画のような世界ではとくに珍しい話ではない。
これは映画における日本の活弁の立ち位置ときわめてよく似ている。元作品がクソゲーや戸山ケ原で花火を使って撮られたインチキ映画であっても、優秀なゲーム実況者や活弁は、駄作という一次コンテンツをうまく活用して秀逸な二次コンテンツを創作してしまうのだ。
一次コンテンツそのものを改変してしまうようなことも起きる。
それが冒頭に書いた、上映禁止作品『仏国大革命 ルイ十六世の末路』のケースだ。ルイ十六世はフランス革命が起きた当時の国王。王権が停止された後、革命政府によって王妃のマリー・アントワネットともどもギロチン台にかけられ、処刑された。この悲劇を映画化したものだ。
しかし社会主義が日本社会にも普及しつつあった明治末期のこの時代、革命を扇動し、権力への反抗を示唆するような映画は御法度だった。警視庁は「治安に妨害がある」と『仏国大革命』の上映を禁止してしまう。
このまま映画はお蔵入りになるはずだったが、配給会社はタダでは転ばなかった。なんとフィルムはそのままで、活弁のナレーションと映画タイトルを変更し、まったく別の映画として公開したのである。
新しいタイトルは『北米奇譚・巌窟王』。
フランス国王のルイ十六世と王妃マリー・アントワネットは、なんとアメリカ人の山賊夫婦ということにされた。奪ったカネで国王並みの豪華な生活を送っているという設定だ。そして革命を起こす民衆の映像は、山賊退治に押し寄せた市民の群れということになった。フィルムは変わらないので、活弁がそのように無理矢理説明したのである。
つまりはフランス革命の映画が、山賊退治の映画になってしまったのだった。
それで通ってしまうのもおおらかというかいい加減というか、明治時代というのはいまとはまったく異なる常識で動いていた時代だったのだろう。いずれにしても、明治時代における活弁というのはこのように、映画フィルムという一次コンテンツそのものをも根底から変えてしまうことのできるコンテキストだったといえる。
一方、黎明期の映画評論家たちからみれば活弁は実に気にくわない存在でもあった。彼らは映画フィルムそのものをまっすぐな目で批評しようと考えていたからだ。大正時代になって創刊された『キネマ旬報』などの映画雑誌の誌面では、活弁批判がさかんに行われたという。映画フィルムは純粋な芸術として単体で成立しているにもかかわらず、浪曲や義太夫のように説明する活弁がそれを大衆演劇的コンテンツに引きずり下ろしてしまっているというわけだ。
加藤幹郎氏の『映画館と観客の文化史』(中公新書)にはこう書かれている。「映画の内容よりも、むしろ弁士の優劣によって興行成績に差が出る場合が少なくなかった。それゆえ弁士がサイレント映画に付け加える説明は、『外国にあっては、作者と監督との二重創作であるが我が国へ来ては、それに説明[弁士]が加わり、三重創作となる』と言われるほどであった」
つまりは映画フィルムというコンテンツが、活弁によって完全に別のコンテンツへと置き換えられてしまうということだ。もしその映画に原作があるとすれば、
原作→映画→活弁による説明
という形でコンテンツは一次から二次、二次から三次へと生成されることになる。そして二次創作である映画がときに一次創作であるはずの原作を単なる素材としてしか扱わず、原作とは似ても似つかない内容になることがよくあるのと同じように、三次創作の活弁も二次創作の映画をまったく別のものにしてしまう。
それはゲーム実況者がゲームソフトを単なる生放送トークの素材としてしか扱わないのと同じように、活弁は映画フィルムを単なる素材として利用した新たなパフォーマンスアートだったという言い方もできるだろう。
ここでは、コンテンツとコンテキストの関係が逆転している。コンテキストは本来はコンテンツ(映画、ゲームソフト)の補完物でしかないはずなのに、補完物であるはずの活弁やゲーム実況がコンテンツの主体となり、コンテンツは素材におとしめられてしまうのだ。
これまで、映画や書籍のようなコンテンツは分解されないと考えていた。インターネット時代に入って、雑誌記事や新聞記事、動画などはマイクロコンテンツ化が進んでいる。たとえば新聞社の記事は、新聞社のウェブのトップページからたどっていって読む人は相対的に減っている。多くの人は、ツイッターやフェイスブックなどで記事が紹介されているのを見つけ、そこから記事への直接リンク(ディープリンク)を経由して読んでいる。それまでは40ページもある分厚い新聞ページの中のひとつの記事として読まれていたのが、ディープリンクによってひとつひとつの記事が分断されて読まれるようになっている。これがマイクロコンテンツ化だ。
しかし映画や小説のような書籍は、全体がひとつのまとまりになっている。村上春樹のベストセラー小説『1Q84』を、バラバラに一部の章だけを取り出して読もうと思う人はいないだろう。映画や小説はひとつの大きな船のようなもので、観客や読者はその船に乗せられ、作り手の意のままに時には大波に揺られ、時にはさざ波に気持ち良く身を任せながら、冒頭から終章まで運ばれていく。この「大きな船」がコンテンツの外殻であり、外殻はそうかんたんには破壊されない。非常に強固な外殻を持つコンテンツのパッケージなのである。
しかし活弁の事例を見ればわかるように、映画はマイクロコンテンツのように断片化されるようなかたちでは外殻は破壊されないが、しかし別の方法で外殻を突き破られ、コンテンツの中身そのものが影響され変容されるというようなことが起きる。これまで述べてきたように、コンテキストがコンテンツを変容させ、時にはコンテンツを単なる素材におとしこんでしまうようなことが起きるのだ。
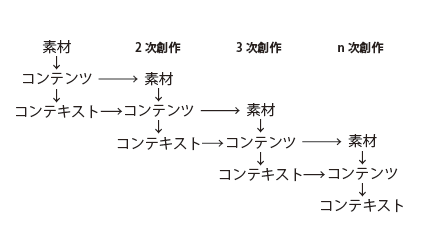
これを図示すると、上のような形になる。左から右に進むにつれて、コンテンツは変容していく。コンテンツは二次創作されると素材になり、コンテキストが新たなコンテンツになる。しかしさらに創作が進めば、せっかくコンテキストからコンテンツに成り上がったはずのものも、あっという間に素材に転落してしまう。
コンテキスト → コンテンツ → 素材
上記のようなプロセスが、永遠にくり返されるということになるのだ。そしてこのような構図は、いまインターネットのソーシャルメディアの世界では毎日のようにごく普通に起きていることだ。
2000年代の初めごろに『カンブリアン・ゲーム』というメディアアートのプロジェクトがあった。情報が情報を生み出し、多様化していく様子をゲームの形式でビジュアル化しようとしたものだ。安斎利洋と中村理恵子という二人のアーティストが手がけた。
最初にまず、「種」となる写真や絵が置かれる。参加者は、その種から自分自身の思いつきや連想でさまざまにイメージを広がらせていく。たとえば2005年春に行われたセッションでは、「町の瞳」と題された道路の上によく設置されているカーブミラーの写真が種となった。町の風景を映しているカーブミラーを「瞳」にひっかけている。
ある人は、カーブミラーの鏡を異世界への穴に見立て、穴の写真に「鏡の穴に吸い込まれる。」とタイトルをつけた。さらにそこから、公園の遊具をタイムトンネルに見立てた「地球を鏡にうつす」、そして塀の穴によって向こう側の景色が切り取られた写真「素敵な額縁」とイメージが広げられた。
また別の人は、カーブミラーのかたちを五円硬貨に見立て、五円玉と祝儀袋を重ねた「いいご縁がありますように。ゴールドカードになった。」というタイトル。
「種」のカーブミラーの写真が撮影された交差点角の光景からインスパイアされ、別の似たような交差点を撮影し、「この角まがってみたくなる」と題した人もいた。
このようにカンブリアン・ゲームは、種から次々とイメージが派生し、作品が増殖していく。最終的にそれらの全体像は枝分れの集大成となり、樹木のような形を作り出すのだ。
種の写真や絵が、受け手の側にどう見えるのかは、その人の受け止め方に任されている。カーブミラーが五円玉に見えるのか、それとも異世界への穴に見えるのか。別のカンブリアン・ゲームのセッションでは、品川駅の旅行パンフレット置き場を上から撮影した種に対して、ある人はそれが巣の幼鳥がいっせいに口を開けてえさをねだっている様子として認識し、そこから新たな枝分れを起こさせた。
ここではつねに、コンテキストがコンテンツになり、それが素材に最終的に転化して消えて行くというプロセスが行われている。「カーブミラーを異世界への穴として見る」というコンテキストが、「穴の写真」というコンテンツになり、それが次には単なる素材となって、「公園の遊具をタイムトンネルとして見る」というコンテキストにコンテンツの座を奪われていく。
カンブリアン・ゲームを主宰したアーティストの安斎利洋は、これを「星座作用」と呼んでいた。彼は『コミュナルなケータイ』(水越伸編著、岩波書店)でこう書いている。
「子どものころ眠る間際に天井の木目を見上げると、動物や老婆や花や車などそこに棲みつく無数の形が立ち上がっては消えた。その形は古人が見上げた星の配列にも棲んでいて、私たちがいまその目を装填して歩くと、世界は無数の星座として立ち上がってくる」
コンテキストというのは、つまりは「天井の木目」というコンテンツをどう読み解くのかという視座であり、そこに面白いかたちが見えてきた瞬間に、天井の木目は単なる素材となり、見えてきたかたちそのものが面白いコンテンツとして子供の頭の中に浮かび上がってくるということなのだ。
これはソーシャルメディアの世界で起きている言論空間そのものでもある。
ソーシャルメディアでは、書かれたブログやツイッター、フェイスブックのコメントという最初のコンテンツが投げ込まれると、それに対して他の人たちが反応し、賛同したり、あるいは批判したりと、さまざまなやりとりが相互に行われていく。そのコミュニケーションそのものが二次的なコンテンツとして消費されていくようになる。
つまりソーシャルメディアにおいてはコンテンツの本質は、単体の記事や書き込みやコメントそのものではなく、記事同士が影響し合う、その共鳴の中に存在しているということなのだ。
インターネットでは、無数の情報が広い海の中を漂っている。この海から偶然に拾い上げられた情報と情報の組み合わせが、「星座」となって見えてくる。その星座はまた別の星座と結びつき、そしてまた新しい別の星座として見えるようになる。そういう無限の繰り返しがおこなわれている。
星座作用の中で結びつけられる星と星、つまりコンテンツやコンテキストや素材は核融合のような反応を起こす。核融合によって原子核の外殻が破壊されるのと同じように、コンテンツの外殻は破壊され、他のコンテンツやコンテキストと融合してしまう。
コンテンツとコンテキストの衝突と融合。コンテンツは書き手が作るものであり、コンテンツをどう読むかというコンテキストは読み手が作るものだった。
そうであればコンテンツとコンテキストの衝突と融合というのは、書き手と読み手の衝突と融合ということでもある。実際、ソーシャルメディアの世界では書き手と読み手は分離されていない。書き手がときには読み手になり、読み手が書き手にまわる。
そしてこのような構図でコンテンツが生成されていくというのは、とても古い民族伝承の世界に実はよく似ている。人類に古くから伝わる民族伝承の世界では、読者と書き手がひとつのコンテンツをともに構築し、その中で無意識から引きずり出された物語を紡いでいく。そういう技法でつくられてきたからだ。
2007年にケータイ小説の大ブームがあった。ガラケーのウェブサイト上で書き手と読み手がひとつの掲示板に参加し、物語が書かれている途中から共有されていくという不思議なやりかたで書かれていたこのケータイ小説は、民族伝承に近い生成プロセスを持っていた。
本田透は『なぜケータイ小説は売れるのか』(ソフトバンク新書)でこう書いている。ケータイ小説は「文学ではなく、大衆芸能であり、大衆小説であり、物語である」「読者の自我を癒すための説話なのだ」「読者の無意味な生、閉塞した世界、不条理な不幸、それらに意味を与えてくれるものなのである」
近代以降の文学は、孤高の作家がみずからの内面と向き合い、その世界観を世に問うという行為だった。しかしケータイ小説では書き手も読み手も、自分たちがひとつの空間を共有していると信じ、その空間に寄り添うかたちで小説をコラボレーションによって完成させていた。文学が卓越した個人による営為であるのに対し、ケータイ小説は人々の集合知をメディア化したものだったのだ。
ケータイ小説の文体は当時「陳腐で、ステレオタイプ的なプロットばかり」と批判されていた。しかしこれは民族伝承であると考えれば不思議ではない。陳腐でステレオタイプなものこそが、地方の若い読者にとってはリアルだと感じられたからだ。
ケータイ小説でよく書かれていたのは、援助交際や思わぬ妊娠といったありがちな話ばかりで、文学だとこれは「陳腐」ということになってしまうけれども、ケータイ小説ではこうしたテーマが小説の空間とリアルの空間をつなぐブリッジのような役割を果たしていた。
もし作者がこのリアルな空間から外れ、自分固有の世界観に入り込んでいこうとすれば、読者の側は方向修正をしようとする。ケータイ小説の優秀な書き手は読者のそうした感覚を敏感に受け入れ、みずから軌道修正を行っていく。ケータイ小説作家は文学を追い求める孤高の個人ではなく、実はソーシャルメディアに依拠した集合的無意識の可視化装置のような役割を果たしていたのだと言える。
ケータイ小説では書き手と読み手は渾然一体となっており、コンテンツとコンテキストの境界線もあいまいになっている。つまりはコンテキストからコンテンツへ、さらに素材へというプロセスが不断に起きていたのだ。
これはインターネットのソーシャルメディアで起きている今の現実であり、そして同時に電子書籍の未来のありようでもある。
もともと書物というものの発生を考えてみれば、それは単なる「知のアーカイブ」でしかなかった。「知」というコンテンツそのものではなく、知のコンテンツを保存しておくための容器として考えられていたのだ。
では知のコンテンツとは一体何を指していったのかと言えば、「語られた言葉」「議論」がそうだった。ソクラテスが書物なんてしょせんは死んだ知にすぎず、本当の知というのは今ここで私とあなたが議論することにある、と語ったのは有名な話だ。だから彼は生涯本を書かなかった。
ひとりの世界観を描く書物というありようは、絶対ではないということだ。ヨーロッパでは19世紀になっても、「書いたものと語られたもののどちらが優れているのか」についてロマン派と百科全書派で論争が続いていたほどだった。
古代に「語られた言葉」によって物語が作られていた時代、物語は決まり文句や常套句によって構成されていた。もともとは民族伝承だったと言われるホメーロスの「オデュッセイアー」「イリーアス」は、語り手たちが多様なストーリーや場面に対応する決まり文句を習得しておくことによって、物語を的確かつ迅速にその場で構成することができたと言われている。つまり物語を丸暗記するのではなくて、決まり文句を駆使して口頭で構成していくという方法を採ったということだ。これは「どこかで聞いたようなエピソード」「どこかにいるような高校生」「どこかにあるようなシチュエーション」といったモジュールをつなぎ合わせ、その場その場でアドホックな物語をつむいでいくケータイ小説と構造的にはつながっているといえる。
口承から「書き文字」に移り、書かれた書籍が登場したことで、書き手は自分たちの集合的無意識を体現するのではなく、自分の内面を描くという方向に変わった。「話す」文化は相手がいなければ成立しないが、 「書く」文化は自分との対話であり、内面を取り出す作業だったからだ。そうやって書くことの内面化が自己意識を増幅させ、それが近代を生み出したともいえるのだ。
であるとすると、いま起きているソーシャルメディアの胎動は、再びわれわれの言葉に「自分の内面」だけでなく「人々の集合的無意識」を取り戻す道程となるのかもしれない。それは近代から古代の民族伝承への回帰であり、新たな書籍の概念を切りひらく可能性を秘めているのだ。
![[メディア論] 100年後の「本」 佐々木俊尚 紙の書籍を模倣するだけの電子書籍は、まだ新しいメディアとは言えない。
メディアとしての書物を原理的に問い直し、
新たな「本」の未来像を提起する本格評論。](../common/image/title.gif)